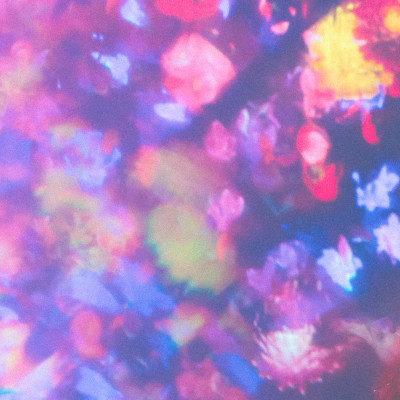
これをよすがとする 十話
扉をゆっくり開けるとその先は暗がりになっており、廊下から伸びた光の筋だけが頼りになる光源だった。後ろに続く男をまず部屋の中に入れてから、背を向けて、扉を閉じる。鍵をかける。そして壁際にある電気のスイッチに手を伸ばそうとした、その時だった。
「っ、いっ、あ」
伸ばした腕を取られて、背後の壁に背中をぶつけた。どすん、と大袈裟な音が鳴って、背骨に鈍い痛みが走る。強かにぶつけた場所はそれなりに痛く、衝撃で体が前に傾いた。何をするんだ、という文句も、あまりに突然のことで口から出ない。
「……」
「う、ん! ん!」
倒れかけた体を今度こそ壁に押さえつけられ、唇に熱い体温とぬめりを感じた。自分がいま何をされているか、理解する前に事が進んでゆく。脳の処理は男の行動の後追いに過ぎず、体はされるがままにその強行を許していた。
「んっ、う、ん……ん、っん」
「は……ん」
「うう、ん、んー! んっ!」
唇の隙間から、おそらく舌が、捩じ込まれている。漠然と事実を認識したきり、そこから頭には何も浮かばなかった。押し返せば良いのか唇を閉じれば良いのか、何が正解なのかまるで分からない。酸素は既に供給不足で、考え事もままならない。
「は、う、うう、ん」
ぴちゃ、と下品な音が耳に届いて、体が一気に熱くなった。体液を混ぜ合わせ、舌で口腔をまさぐられるたび、はしたない水音が鼓膜に響く。
「……ふ」
「んっ、ふ、ふぁ、う」
「……」
「あ、うぁ、う、んっう、う!」
声を上げて迫りくる肩を叩いたら漸く、体が僅かに離れた。伸びた唾液の糸に目もくれず、彼は首を傾けてじっと顔を覗いてくる。出した息が混ざり合って空気がやけに熱かった。頭に届く酸素はやはり薄いままで、思考が定まらない。
「……ひとつ聞くんだけどさ」
「……うん」
暗闇に落ちる声はやはり冷静で淡々とした調子だった。自分ばかりが呼吸を乱し、喘がされているのだ。それが何となく癪に障る。
「僕を部屋に呼んだのは、何かの意図があった? それとも単に、君の言うところの……独房暮らしの僕が可哀相だから?」
「ど、どういう意味」
「質問に質問で返さないで」
「……」
暴力みたいな口づけを強要したと思えば、正解が見えない質疑応答。表情の変化が乏しいその顔を見遣っても、やはり答えは出てこなかった。彼は伏せがちの瞳を僅かに持ち上げて、心なしか返答を強請っているように見えた。
「……二人の時間が、ゆっくり取れたらいいと思って」
電話越しではあったが以前、"答え合わせ"と称し、自分の思いの丈は伝えていた。しかしそれ以降、お互いに仕事や計画の準備で忙しくなって、時間は取れなくなっていた。クーデター事件後は尚更、顔を合わす機会こそあれどプライベートの時間など無に等しい。国の為世界の為、文字通りこの身を犠牲にして働いていた。公人としてどこに出ても恥ずかしくないように、自分を律し続けていた。
それはスザクも同じことで、上司部下の関係を頑なに守り抜いてきた。従者と主人は決して互いに対等で接してはならず、その立場は遵守されるべきなのだ。人目があろうとなかろうと、一歩外の世界に出ればたちまち二人は上下関係を巧みに演出し、その空気を周囲に気取らせない。
「誰でも部屋に入れたりしない?」
「するわけないだろ」
そう断言すると、顎をすくわれて唇に温もりが触れた。それは一瞬だけ当たって、すぐに離れてゆく。
「それは嫉妬か?」
「だって皆が知ってる君を今更知らされるのは、面白くないだろ。僕しか知らない君を集めたい」
「……恥ずかしい奴だな」
体の脇に腕が回され、そのまま正面から抱きつかれた。肩口に額を乗せてじゃれつくように身動ぐ男のつむじを、ぼんやり眺める。
日中に誰かが言ってた"天然たらし"という文句はあながち外れでもない。さらりと言葉にされた内容は脳内で反芻するたびじわじわと、体の熱を上げてゆく燃料になる。小さな火種は生ぬるい空気を含んで大きな炎に、そしてこの身を焦がす情熱へと姿を変えるのだ。
「これからもっと恥ずかしいことするよ」
「……」
「意味、どこまで分かってる?」
「何となく……」
抽象的なイメージを声にすると、スザクはそろそろと顔を上げた。真っ赤に腫れたみたいに紅潮する頬を隠す気もないのか、覚束ない視線と唇が惑うように動く。ゆらゆらと揺れる視線は酩酊を想起させた。
「本気で嫌だったらいいんだよ」
「お前は俺に何する気だ」
「……噛んだり、引っ掻いたり」
「それくらいなら多分、大丈夫だ」
自信なさそうに惑う視線を、顔の輪郭を包んで引き寄せる。熱い頬の体温が手のひらに伝わってびりびりと痺れた。暫く見つめ合うのも恥ずかしくなって、誤魔化すように唇を押し付けた。
「僕、死んじゃうかも」
「俺が良いって言うまでは駄目だ」
「うん……」
ぐずる子供みたいに擦り寄ってくる。頭を抱えて撫でてやると、ぐす、と鼻をすする音が聞こえて、思わず声を出して笑ってしまった。笑わないでよ、と拗ねた声に導かれて視線を向けると、今度はもう、笑えないくらい真剣な目をした男が立っていて、声が出なかった。
その服さあ、どうやって脱がせたらいい。
間延びした声が落ちてきて瞼を起こすと、情けない表情を浮かべるスザクが自分を見下ろしていた。
一人用のベッドに押し倒されて、シーツに背中を預けて、馬乗りにされて。自分は一体これからどうなってしまうんだ、と緊張のあまり何も考えられなくなった頭で、ひたすら思案を重ねていた。どう動けばいいのか、何を話せば、どこ見て、体勢はこれで合っているのか、懸念事項は数多く身の回りに転がっていた。
「どうって……」
「首のそれとか」
「スカーフのことか?」
首元に巻かれた薄い布に手を伸ばし、それを解いた。少し楽になった呼吸のお陰で、僅かに冷静さが取り戻された気がする。
「……」
依然としてスザクは無言で見下ろしてくる。顔の両横に置かれた手のひらはぴくりとも動かない。
何が分からないのだろうと疑問に思いながら、ベストを脱いでシャツのボタンをひとつずつ外した。前身頃がはだけて素肌が顕れると、彼は僅かに睫毛を震わせた。そして自分は漸くそこで、そいつの思惑に勘付いた。
「スザクも脱げ。なんで俺ばっかり」
「あは」
「誤魔化すな。もう……」
腕を伸ばして、目の前に垂れ下がったタイを引っ張った。その紐の結び目は存外緩く、軽く力を加えるだけでするりと解けてしまった。次いで、見えるシャツのボタンに指をかける。一番上の首元まで閉じたそれを外して、襟を開かせる。ぷち、ぷち、とひとつずつ開けると、内側に隠れていた肌色が目前に迫って、思わず唾を飲んだ。
彼は着痩せする性質なのか、存外その体はしっかりした筋肉に覆われていて、はっきりと作られた隆起とそこに落ちる影がいくつもの曲線美を描いていた。そっと触れると脈打つ感触が静かに伝わる。厚い胸板と薄っすら割れた腹筋、脇腹に臍の窪みと、手のひらを順番に動かしてゆく。
「満足いった?」
「お前は」
「え? 全然足りないよ」
何言ってるの、と呆けた顔を浮かべたスザクは、そっと顔を寄せてきた。襟のあたりを掴んでシャツを広げて、心臓がある位置に唇を落とす。
ちゅ、ちゅ、と丁寧な接吻を施していく様はまるでマーキングのようだ。薄ぼんやりとした理性は静かにそう告げて、目下で揺れる茶色の頭を見つめた。跳ねた毛先が皮膚を擽って、それがむず痒い。
「……あ」
「ちゃんと勃ってる」
右手はいつの間にか下半身に移動していて、下衣ごと揉み込むように股間をまさぐっていた。
そういうことをするんだろうと、頭では理解していた。しかし未だ輪郭を捉えきれない閨事の正体の断片を突きつけられて、追いつかない思考が僅かに、今になって危機感を募らせていた。
このまま身を任せていたら、自分はどうなるんだろう。何をするんだろう。彼に何をされるんだろう。
芽生え始めた恐怖心は直後、降り注ぐ刺激にすぐさま蹴散らされた。乱暴で粗雑で横柄な、性急過ぎる快楽であった。
「ちょっと早くない?」
「……う、あ」
寛げたスラックスの股へと素手が伸びて、薄い布に守られた性器を握られた。指で掴まれて、布越しに擦られる。上下に揺するだけの単調な刺激だったが、それでも、何も感じるなと言う方が酷なくらい、体はあからさまに感じ取っていた。指の動き、手の温度、布の内側の湿り気。
「んっ、あ、や、すざく……」
「何が嫌?」
「っお、俺ばっかり、さっきから、なんで……」
腕を伸ばして、肩に引っかかったままのシャツの裾を引っ張った。ちらりと視線をずらして下を向くと、布越しでも分かるくらい張り詰めた股ぐらがそこにあって、恥ずかしさで唇を噛んだ。
スザクが、興奮してる。自分を見て、触って、舐めて、興奮してる。
「怖くない?」
「……うん」
ぎらついた瞳に晒されて、目尻に涙が浮かんだ。喉元に据えられたナイフがきりきりと食い込もうとしている。そんな切迫した感覚に襲われて、言葉が出ない。
股間を寛げた男の、そこからまろび出た性器は、自分とは色も形も大きさも違っていた。そもそも、他人の勃起した性器なんて見たことがない。視界に入れるのも気まずくて、でも目を逸らすと、怖くないと答えたことが嘘になる。
「あ……」
「ん、じょうず。手貸して」
性器同士を擦り合わせて、それを握らされる。ぬるついた粘膜は充血しきってぱんぱんに膨らんでいた。彼も自分も同じように。
「きもちいね、ルルーシュ」
「んっ、うん、うん……」
「もっとさわって」
「あ、うう、ん……」
「ん……じょうずだよ……」
「ひっあ、ん、う」
手の指から溢れる体液は手首を伝って、シーツに落ちた。くちゅ、ぬちゅ、と粘着質な音を鳴らし泡立つそこは二人の両手に包まれて、じっくりと高められてゆく。
「はあ、すごい、ぬるぬる」
「あっう、ア、んう……」
「きもち、いね?」
「うん、うんっ、きもちっい、あ……!」
次第に育てられた性感と愛情は発露することを求めて、体中を駆け巡った。腰がシーツから浮いて背中は何度も跳ねる。抑えの効かない声と体が彼の目前に差し出される格好になった。
剥き出しの性欲を宛てがわれて、触れられて、見られて。興奮していたのは自分も同じだった。怖いとすら思えた彼の性欲も今は、性感を高める材料の一部だ。
「うう、あっ、あ! ん、う……」
「キス、したい。口あけて」
「は……ん、すざく」
名前を呼ぶと舌に噛みつかれて、歯がぶつかった。がち、と擦り合わせたあと舌が絡み付いて、それきり解けて抜けない。にちにちと隙間なく合わせられた唇の中で唾液が何度も混ざって、呼吸さえも共有して、粘膜を舐め合った。
「あ、やば、も」
「……う、ん」
額を合わせながらスザクが囁いた。もう、出ちゃうかも。二人きりの部屋で内緒話するみたいに、彼は恥ずかしそうに呟いた。
「ここをさ、擦って。ゆびで、そう」
「……ん、ん」
先端に這わせた人差し指をくりくりと動かし、粘液の溢れる口を押さえた。指先を僅かに食い込ませ、窪んだ穴に押し込む。
眉間に皺を寄せ、奥歯を噛み締める男の顔が目前にあった。スザクは何かを堪えるような表情をしていた。何か声をかけたほうが良いのだろうか。
そんな考えがふと浮かんだ瞬間、彼は肩のあたりに倒れ込んで、額を乗せてきた。ふうふうと荒い息が耳朶にかかって擽ったい。それと同時に手の甲へ生温かい液体がかかって、精のにおいが鼻をついた。
「さ、先にいっちゃった、うわ、恥ずかし……」
「へ……?」
「次はルルーシュの、番」
くちゃ、と音が鳴って、熱くなった陰茎を握り込まれた。精液に塗れた手のひらで思いきり扱かれた。加減のない力は痛いくらい気持ちよくて、為す術もなく身を捩った。でも大事な部分を握られている以上、そんな抵抗は時間稼ぎにすらならない。
「うあ、ん、や……」
「や、じゃないだろ。君も早く、出しちゃえよ」
鈴口に食い込んだ親指が弱い部分を抉って、爪で弾くように引っ掻いたのだ。その瞬間視界が白んで、全身に甘い痺れが走る。
「っあ、あ! あ、んん!」
「……かわいいね」
腹の上に温い液体がぴゅる、と掛かる。数度に分けて放たれたそれは体の上で飛沫を散らし、湿ったシーツを汚した。
ティッシュで体の表面と手のひらを拭われながら、今しがた身に起きた出来事をゆっくり振り返る。スザクは恭しく手のひらを取って、指の間や爪の先に纏わりついた粘液を拭き取ってくれていた。その目つきはどこか真剣そのもので、腹の上を滑る手指の感触に先程までの厭らしさは感じられなかった。
やけに冴え渡った頭の中は直面した現実を受け入れ難いことだと主張して止まない。例えば今、全力でスザクの世話になっている事でさえ信じたくないのだ。
なんて事を、自分はスザクと。
一旦冷静になると、もう耐え難かった。じわじわと込み上がってくる羞恥と罪悪感に苛まれる。未だ露出させたままの下半身はすっかり熱を失って力なく垂れていた。体がひどく怠く重い。部屋に漂う汗と精のにおいが後ろめたさを加速させる。
「今日はもう寝ようか」
「……ん」
「ほらパンツ穿いて」
ベッドの端に捨て置かれていた布を拾われ、力なくそれを受け取った。スザクはいつの間にか身支度を整えた状態で、甲斐甲斐しく世話をしてくれていたのだ。
さすが軍人、体力の底はそうそう尽きないのだろう。優しく微笑みを浮かべて見下されると、その余裕の差などを嫌というほど実感させられる。
ベッドに寝そべったまま腰を上げて、ひとまず下着だけを身に着けた。いつまでも局部を露出させるのははしたないからだ。だが、それ以上の行動はする気が起きなかった。
それから何となく意識が浮上したのは、何時間が経過してからだろう。
視界を巡らせるとスザクの姿が傍になく、しかし部屋の遠い場所から物音が聞こえた。ような気がした。デジタル時計を見遣ると午前三時何分と表示されており、暗闇に包まれた部屋はすっかり静寂に支配されている。しかしだからこそ、微かに聞こえる物音はいやに室内に響いていたのだ。
ゆったり体を動かし、四つん這いの体勢になったのち、ベッドから起き上がろうと試みた。掛け布団から這い出て覚束ない足元に力を込めた。寝ぼけ眼を擦って、音源へ向かってそっと歩み寄る。
寝室と隣接する書斎にスザクの姿はあった。小さな豆電球のような明かりだけをつけて、本に囲まれながら、彼は背を丸めていた。膝に乗る本の背表紙は随分と分厚く、手元に積み上げられていた書物も似たような大きさと太さをしていた。
「……こんな夜中に、何やってるんだ。お前は」
「ごめん、起こしちゃった?」
あまり物音を立てないようにしてたんだけど。開いていた本を慌てて閉じながら、彼は言い訳するように言葉を紡ぐ。右手に握られたペンは床に置かれ、両の目はこちらの動向を注意深く見つめていた。
「勉強熱心なのも良いけど、寝たほうがいい。程々にしておかないと、いつか体を壊すぞ」
「それは、そうだね」
「お前は特に、体が資本なんだから」
「うん」
「だから寝よう」
「うん」
スザクは分かりのいい相槌を打ちながらも、本の山から立ち上がろうとしない。口元に浮かべた微笑みはひどく軽薄で、冷たくて、寂しくなる。暗に自分は彼に突き放されているんだと、嫌でも分かってしまう。
「……一緒に寝たい。ベッドがシングルサイズなのが気に入らないか?」
「違う。違うけど……」
「添い寝してほしい」
「……」
明かりに照らされた頬はほんのり朱に染まって、首が小さく上下に振られた。
気の利いた、うまい誘い文句は思いつかなかった。慣れないことをするものじゃない。でも効き目は少なからずあったらしい。梃子でも動かなさそうな男をその場から立ち上がらせてやれた。
暗闇を這うように二人で歩いて、狭い寝台に向かい合わせで横になった。伸ばされた逞しい腕に首を置いて、暫く見つめ合う。暗がりの中でもきらきらと煌めく翡翠が眩しくて、心臓は高鳴ったまま落ち着かなかった。とても眠れる気はしないが、彼が朝まで傍に居てくれるなら些細な代償だ。
そうして迎えた翌朝、七時。
昨夜まで残っていた人影も熱源も瞼を起こせばそこになく、乱れたシーツと残り香だけが、彼に繋がる数少ない存在証明の手掛かりであった。
それは恐らく悪癖と称しても過言ではないだろう。
どれだけ過酷な任務に身を投じようと、目の回るスケジュールに振り回されようと、上官から厳しい叱責を飛ばされた日であろうと、スザクは毎夜、その疲弊しきった体に鞭打って勉学に励んでいた。その内容はよくよく見ると、どうやら多岐に渡るようだ。歴史から軍事、政治に司法、地理、時事……。あらゆる分野の知識を取り入れようと無我夢中で机に齧り付き、本の虫と化していた。
何をそんなに焦る必要がある。全知全能の神でも目指す気か。上昇志向は結構なことだが、お前の場合は真面目が行き過ぎだ。
そうした言葉をかけたのはもう何度目だろうか。目の下に表れた薄い隈が日ごと濃くなってゆくのを見るたび、自分の言葉は彼にどうして届かないのだろうと思い悩まされる。夜明け前の部屋の奥で仄かに灯された照明の影を認めると、彼を寝かさねばと思う前に、またか、と落胆することのほうが多くなっていた。
たとえば、月がやけに大きく見えたとある夜のことだ。
きりきり舞いの公務を済ませた一日の終わりは決まって必ず、二人きりの時間を設けるようにしていた。しかしそれは、事前に話し合って取り交わした約束事でも何でもなかった。
恋人どうしが毎晩のように同じ屋根の下、同じ布団で眠るとして、自然と"そういう雰囲気"になるのは最早避けられない生理現象だろう。どれだけ疲労困憊していようと、浅ましい肉体はたちまち熱が籠もり始めるのだ。そして同じく疲れ切った手指で、それを解してゆく。性欲処理と呼ぶにはどこか冷た過ぎるし、相瀬と呼ぶには甘さが少し足りない。二人してどこか性急で忙しなさを誤魔化せないのはたぶん、まだ付き合って日が浅く、余裕がないせいだ。
やがて性器を擦り合わせるだけでは物足りなさを覚えたのか、スザクは体のあちこちに好奇心じみた目を向けるようになっていた。首や鎖骨から、胸元と脇腹、臍、そして局部のあれそれ。なし崩しで始まる行為は毎回、いつの間にか身包みを剥がされ、自分ばかりが肌を晒す羽目になっていた。
「柔らかくなってきたね、ここ」
にちにちと音を立てながら指を動かす男は、他人事のような台詞を吐きながら醜態を晒す自分を見下ろしてくる。腕に引っかかったままのシャツは背中の下敷きになって皺が寄るし、足首のあたりで留まった下着は気にも留められない。
夜の匂いと微かな汗のにおいが混じって、胸がぐずぐずに濡れてゆく。熱くて恥ずかしくてみっともなくて、どうにかなりそうだった。
「指、三本入った」
「……あ、う」
「痛くない?」
「た、ぶん……」
一体どんな思いで自分が脚を開き、尻の穴を弄らせているのか、彼は知りもしない。知る術もない。知らなくていい。こんな気持ち、知られて堪るか。
「回してみるね」
「イっ、ひ、あゃ、あ」
真横に並んで突き刺された三本の指がぐり、ぐり、と中で埋まりながらゆっくり掻き回る。ぴったり閉じられた肉のあわいを無理やり抉じ開けながら押し進められる暴力的な行為に、それでも体は痛いくらい興奮していた。
体を割り開かれるたび、自分も知らなかった自分の一面が現れる。"そいつ"はスザクの目を喜ばせ、あるいは性欲を煽り立て、卑しく媚びるのを止めはしない。とんだ恥晒しだ。屈辱の極みである。最早この人格を同じ自分だとは認めたくない。
「やらしいルルーシュ。かわいいね」
軽口を叩きながら頭を撫でられると、馬鹿になった体は悦びを感じるらしい。後ろの窄まりがきゅう、と縮こまって、彼の指を締め付けた。粘膜越しにそのかたちを覚えて、また体の奥が震える。
「ん、ふぁ、あ……?」
「今度はもっと動かしてみようか」
「アっ、や、やだ、あ!」
「うん」
「やだっ、やぁ、や」
「痛くない。怖くない。じっとして」
「ひっう、うう、っん、あ! ア、あー、やっ、あ!」
「脚は開いたまま、お尻はこっち」
「う、うう、んー、あ!」
「良い子だから、怖がらないで」
「ちが、やっア、んっ、ッひ!」
腹の内側をごしごし擦られて、声を上げながら身を捩った。体内で暴れる指が容赦なく性感帯を圧迫し、反射的に仰け反る腰を押さえつけられ、逃げ場がなかった。無遠慮に注がれる強烈な快楽を往なす方法など思いつきもしない。許容を超えた刺激に四肢はのたうち、声が枯れた。
スザクは夜が訪れるたび、この体にとある起爆装置を仕掛けては、それが炸裂する為の準備を丹念に行っていた。その絡繰りの下準備は至って単純明快で、肛門の内側にある前立腺とやらの部位を内臓の内側から指圧する、というものだった。そこで快楽を得られると男同士の性行為はスムーズに、とくに女役の負担は大幅に軽減されるのだという。
最初はスザクが一体何の話をしているのか、さっぱり見当もつかなかった。なぜ尻で快感を覚えねばならない。指で刺激するとはどういう了見だ。医療行為でもなかなか聞いたことがない。排泄器官に触れるとは、この男は正気か。
不信感と猜疑心に苛まれつつ、自分はされるがままに体を明け渡した。しかしそれは、取り返しがつかない誤った判断だったのだ。
日を追うごとに増やされる指の本数や、出入りを繰り返すピストンの動きで漸く、この行為の果てにあるスザクの本懐に思い至ったのだ。自分は何と愚かで純木だったのだろう。呆れるくらい無知だった。なんと世間知らずで警戒心の足りない、おめでたい人間か。
しかし作り変えられた体はいつしかスザクの手中に収まり、彼の好みに仕上げられていた。白痴みたいに声を上げて泣きじゃくるこの自分を、体を、満足気に俯瞰していたのである。
体液を搾り取られ、情熱的な愛撫と責苦に喘がされ、くたくたになった体を寝具に預けたのは深夜零時を過ぎた頃だろうか。疲労感に苛まれ、眠気がひたひたと足音を立てながら忍び寄ってくる。頭の中は空っぽで、何をする気も起きなかった。
本能に任せて意識が遠退くのを感じながら、瞼を下ろそうとした、その時だった。
部屋の遠くで大きな物音が鳴って、微かな呻き声が続いて耳に届く。けたたましい衝撃音に思わず、反射的に体が飛び起きた。
縺れる足を引き摺りながら部屋を移動すると、そこには、本棚の壁に手を付きながら項垂れる男が突っ立っていた。足元には数冊の書物が落ちており、彼は空いたほうの片手で額を押さえている。
「スザク」
「ああ、ごめん。驚かせてしまって」
「何があった?」
「いや、何でも」
「何でもなくないだろ」
周囲を見回して、彼に詰め寄った。あまり良くない血色と下がった眉、力のない腕と、散乱した床。この状況を見てどうして何も無い、なんて嘘が吐けるのだろう。
「……ちょっとした立ち眩みだよ。頭をぶつけちゃって」
手が充てがわれていた額はやや赤みを帯び、その跡は痛々しい。無理やり作られた微笑みは歪んでいるし、とても平気とは思えなかった。
「もう寝ろ」
「……」
「この分からず屋」
「……だって、僕は」
「言い訳はさせない。今日は寝るんだ」
「ルルーシュ」
書斎の電気を消し、床に落ちた書物を足先で蹴散らしながら、スザクの腕を引いた。彼は俄に抵抗の意思を見せたが、もう構ってられない。
彼を押し倒すような形で二人してベッドに雪崩込み、足を縺れさせながら体を横にした。足元で絡まっていた掛布団を引き寄せて肩まで被せ、もちろん彼の体もすっぽり覆うようにしてやった。しかし一人用の布の面積では男二人を包むには無理があるらしい。少しでも隙間を埋めるべくぴったりと四肢を寄り添わせる。寒くないか、とそれとなく尋ねたら、彼は静かに首を横に振っていた。
スザクはほんの少し顔を赤くしながら、自分のされるがままだった。
自分たちはもっと恥ずかしいことをして、されているのに。今更添い寝のひとつやふたつで何を恥じればいいのだろう。
皮膚にこびり付いた残滓を丁寧に拭われ、下の世話を焼かれることにも、もう心が麻痺してしまったのか、今はさした羞恥も覚えなくなっていた。だからか、自分は些か大胆になっているのかもしれない。目の前に見える胸板に頬を擦り寄せると、彼の動揺が伝わってくる。とくとくと響いてくる心臓の音はやけにうるさかった。
最初からそうやって大人しくしていればいい。物分かりが良い振りをして、ついでに眠ってくれさえすれば。
そんな日が一週間ほど続いたのち、スザクの部屋は施工が完了し、とうとう寝泊まりが出来るようになった。寝室とリビング、事務机、そして本人の希望で小さな書斎スペースも設けた。いつ死んでも良いように物をあまり持たないと言っていたが、大きなクローゼットや収納棚をわざとたくさん置いてやった。欲しい物を聞いても無い、としか言い張らない男に対するちょっとした仕返しだ。これからの生活で欲しい物、大切な物を増やしていってほしかった。
だがひとつ、彼の私室を用意したうえで懸念事項があった。誰かの監視の目がない限り、奴は夜通し起き続けて勉強に明け暮れるに違いないだろう、というはっきりした予感である。
自分には学がないから、と自信なさげに言う。確かにスザクは小学校卒業後以降、今までずっと軍隊の一兵士として過ごしてきた。武器の扱いや動作、作戦の組み立て、実戦経験を通した知識に関しては成熟しているだろうが、学校で教わる国語や数学についてはからっきしのはずだ。
しかし、だからといって、学校で教わる教科書の内容が頭に入ってないから幻滅するわけでもないし、周囲からの評価に著しく影響を及ぼすわけでもない。知らないことや分からないことがあればその都度吸収していけばいいし、この世の全てを知る奴なんか居ない。そもそも彼の本分は騎士として主人を守ることにある。周囲に追いつこうと上昇志向を持ってくれるのは構わないが、それで体を壊されでもしたら堪ったもんじゃない。
ブリタニア宮廷には選りすぐりの逸材が多く出入りし、経歴も血統も完璧なエリートばかりだ。その背景には純血思想の影響もあるが、やはり実力主義を前面に出した思想がそうした土壌を形成したのだろう。だがシャルル皇帝よりも前から引き継がれてきた血統遵守の思想を前にすれば、その論調も一貫性がなくなる。転じて言えば、どれだけ武勇に富んだ兵士であろうと、ブリタニア人でなければ劣る、という風潮があるのだ。
スザクはたぶん、いや大いに、焦っているに違いないのだ。名誉軍人として長年従軍しているうちに根付いた劣等と自己嫌悪、自尊心の低さが彼をたらしめているうちは、解決しない問題であろうことも明らかだった。
強烈な自己否定が毎晩スザクを机に向かわせるのだとしたら、そんなことはないのだと、今のお前が良いんだと何度でも伝えてやりたい。しかし自分の声がどこまで彼の心に響くかは見当もつかず、そのことが少し、寂しいと思えた。