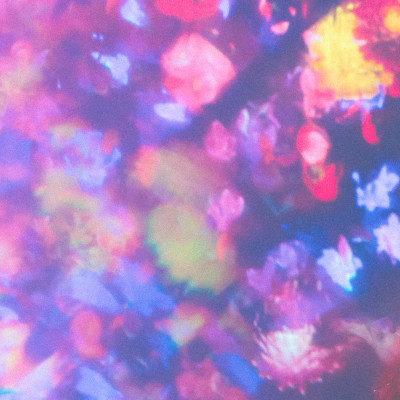
これをよすがとする 十一話
夜の澄んだ雰囲気は好きだ。音も匂いも色もない空気を肺に取り込んで、息を吐く。意識の外にあった時計の針が刻む音がふと耳に入って、頭を上げた。時刻は夜中の三時をまもなく迎えようとしていたらしい。顔の真横に置いた小型の照明の出力をもう一段階上げて手元を照らす。優しい光の色に網膜がひりついて、やけに眩しかった。
気にしないつもりだったのに、一度意識すると見て見ぬ振りもできなくなった。這い寄る睡魔と甘い睡眠欲が背後に纏わりついてきて、頭の中を埋め尽くそうとする。瞼が重い。せっかく明るくしたはずの光はもう視界の中で滲んで、手元の本に記された文字はうまく読めない。焦点が合わない。ゆらゆらと意識を弄ばれるように集中力が霧散してゆく。霞がった思考は正常に動かない。ふわ、と欠伸が漏れた。
でもまだ床に就く気はない。やらねばならない仕事がある。明日中に仕上げるもの、明後日中に提出するもの、来週の会議、スケジューリング、報告書。机の上には紙が散乱し、その真ん中に一台のノートパソコンを置いて、キャスター付きの棚の上には参考となる書物を積み重ねていた。まだまだやり残した作業は山積みで、とても安眠を貪れる状況じゃなかった。
ともすれば背後からずる、ずる、と何かを引き摺るような音が鳴った。その音源は不規則ながらも徐々に自分に近づいてくる。そうしてちょうどその音は、真後ろまでやってきたところでぴたりと止んだ。
「寝ぼけてる?」
椅子の背もたれにかけてあったブランケットを彼の肩にかけて、羽織らせてやった。涼しいこの部屋にそぐわない、やけに薄い布の寝間着が気になったからだ。彼は半分しか開かない目を擦りながら、ちらりとこちらの様子を窺っていた。自分の顔もそうだし、周りに散らばった仕事道具とその作業の痕跡。そしてその事務仕事が、まだ暫くは処理に時間を要するであろうこと。ひと目見れば分かるはずだ。
「……なんで、おきてる」
「なんでって」
見れば分かるだろうに、彼はどこか納得いかない態度を見せながらわざわざ尋ねてきた。仕事が少し残っているんだと素直に話すと、彼は眉間の皺を深くした。
「明日にしろ。何時だと思ってる」
「明朝は出張で、時間が取れないから」
「知ってる。俺の付き添いでな。不満か」
「そんなこと……」
ああ言えばこう言う。まるで彼とは話が噛み合わない。
そうやって男は横槍を入れ、作業を中断させ、気を散らそうと目論んでいるのだ。しかしその手には簡単に乗らない。そうこうしているうちに朝は近づいてくるのだから。
ブランケットの裾を握りながら尚も引き下がらない男を視界から外し、再び机に向き直った。書きかけの電子文書の続きを入力し、すでに出力してあった用紙にサインを残す。資料作成に必要なデータを探して、文献を元に文字を起こす。落ちかける瞼に力を込めて深呼吸を繰り返す。
「……」
机の脇に凭れ掛かり、腕を組みながら作業風景を見下ろしてくる。彼は口出しこそしなかったが、その目は体に穴が空きそうなほど強烈で力強かった。
キーボードの打鍵音と紙面をペン先が走る音、それから時計の針が刻む規則正しい音。気が遠くなるほど静かな部屋で、終わらない事務作業に相対し続けた。それでもまだ、進捗は乏しい。自分はよっぽど要領が悪いらしい。減らない書類はトレーに残り続け、机上が片付く気配はまるでない。
「……」
それまで長い一本の糸のように張り詰めていた気配がふと、僅かに揺れた気がした。久しぶりに変化する空気に目を動かす。
「ちょ、ちょっと」
立ちながら首をうつらうつらと揺らす男に思わず手を差し伸べ、肩を支えてやった。揺れる長い前髪が顔全体に影を落とし、その時どんな表情をしていたのかは見えない。でも彼は硬い声を喉から引き出して、平気だ、とだけ答えた。
「先に寝てて」
「嫌だ。お前が寝るまでここで見張る」
「困るよ……」
肩の羽織物を握りながら、男は意固地になっていた。彼をそうさせているのは何者でもなく自分に違いないのだろうが、梃子でも動かない様子を目の当たりにすると、言いたい言葉も出てこなかった。
前にも同じことがあったように思う。
もうすぐ、今から任務で出撃に行かねばならない。今回は長丁場になりそうだ。だから先に帰っててくれ。そう言ったのに、彼は話し合いの続きをしたいからと主張して憚らず、結局日付が過ぎる間際に帰還したら、待ちぼうけの彼に迎えられることになったのだ。
奴はちょっとばかり強引だ。自分が声にした内容は必ず実行するし、力技を使ってでも実現させてしまう。時には破壊も創造もやってのける。
そういう、荒っぽく頑固な一面に振り回されたこともあるが、しかし力強い手に引き上げられ、救われたのも事実だ。あの手があったから今自分はここに居られる。そのことを自覚しながらもやはり彼の行動に調子を狂わされると感じてしまうのは、自分が身勝手な人間だからなのか。
「……ルルーシュ」
再びうとうとと首を揺らし船を漕ぎ始めていた彼の名前を呼んだ。しかし呼びかけに反応しない。意識は半分眠ったまま戻ってこないのだろう。とはいえ立ったまま寝かせるわけにいかない。
「僕もう寝るよ、寝るから」
「ん……」
肩を揺すりながら話しかけると、ルルーシュはゆったりと視線を動かしながら頷いた。散らかったままの机は何も進展していないが、そのことは敢えて今は気に留めないようにした。
手を握りながら部屋の奥に進む。窓から見える景色はまだまだ夜明けからは程遠い暗黒色に染まっており、月も星も雲も見えやしなかった。
夜の冷たい空気を纏わせる寝室はベッドサイドの明かりにぼんやりと照らされ、とても静かで清潔だった。オレンジ色の優しい色が目に染みて、自然と口から欠伸が溢れる。
奥に備え付けられた寝台に二人で並んで腰掛けた。スリッパを脱いでベッドに上がって、布団を剥がしてシーツの間に体を滑り込ませる。二人分の体重を受けたスプリングは軋音を鳴らし、きしりと沈み込む。その感覚が心地よくて、今にも意識が遠退きそうだった。でも言わねばならないことがある。それはひとつじゃなく、たくさんある。
「別に付きっきりで起きてなくてもいいんだよ」
「お前が世話の焼ける奴だから……」
「逆だよ。そんな寒そうな格好でうろつかないで。風邪ひくよ」
「風邪なんかひかない」
機嫌の悪い声を作って、彼はそう呟く。毛布を肩まで被せて布団を重ねると冷たい素足が絡まった。こんなに体を冷やしたら体調に響くだろう、と口を開こうとしたが、暗闇で光る紫に射止められて、それは叶わなかった。
爛々と輝く薄紫は薄いまぶたの下でその存在を輝かしく、はっきりと主張していた。力強い瞳の光は彼の心根をまさに表していて、澄んだ虹彩と深い瞳孔のコントラストが美しい。吸い込まれそうで、夢中で追いかけたくなる。
「おやすみ、スザク」
「……うん。おやすみ」
差し伸べられた手を握って、握り返された。そのことにひどく安堵したような面持ちを浮かべた彼は、ゆっくりと瞼を下ろした。静かな寝息にじっと耳を澄ませる。規則正しく上下する肺の動きを、夜が明けるまで眺めていたい。
つかの間の幸せとささやかな温もりが、今の自分の拠り所だった。
ルルーシュの騎士として専任されてから、自分の生活環境は百八十度がらりと変わった。
衣服、機器、芸術、娯楽。あれが欲しいと言えば、給与の範囲なら給仕たちはなんでも用意する。これが似合いますよ、いま国民の間ではこれが人気のようで、どれがお好みですか、などと気立てよく接してくれるのだ。これまでの人生でかつてない経験だった。人に敬われたり、敬意を払われたり、そうした仕草とはまるで無縁の生涯だった。とても奇妙で不気味で違和を覚えた。
他に、食事の内容もまるで異なる。そもそも三食を毎日きちんと、しかも時間通りに口にできる生活をしてこなかったのだ。不定期で発令される出動要請に合わせた生活だったから食習慣は凄惨を極めていた。昼間は何にもありつけず、一日の終わりの直前にゼリーだけ胃に流して眠る日もあった。最低限の栄養さえ確保できれば良かったから、満腹感という感覚とはやはり無縁の暮らしであった。
そして一番の変化といえば、住処だ。これまでは特派の研究所を兼ねた移動式トレーラーの奥に借り暮らしをしていた。ワンルームの狭い室内に最低限の必需品だけを押し込んだような部屋は狭苦しく、ルルーシュ曰く独房らしい。が、自分は案外そこでの生活に順応していたようで、さして不便や苦痛は感じなかった。なんせ名誉軍人時代は集団生活が当たり前で、一人部屋すら持てなかったのだ。そこが劣悪な環境であろうと、自分だけの時間が持てるだけで他に何も要らないとすら思えた。
ブリタニア宮廷で住み込みで働くこととなり、自分専用の部屋が与えられると知った時は、何かの冗談か悪い夢だと思った。空いている物置きか格納庫の隅で十分だと主張したが、ルルーシュの手によって揉み消され。なら一番狭い部屋でいいから、と言ってみた。が、時既に遅かった。
一際広い空き部屋を工事して騎士侯の私室に改築している最中だと業者に告げられたときは、皇子に直談判した。自分は元々あまり物を持たないから広い部屋は必要ないし、こんな高待遇は身に余る。身分相応の暮らしをさせてくれ。そう伝えると彼は開口一番、お前は黙って今の待遇を有難く受け取っておけばいいんだ、と怒鳴られた。
その日は初めての大喧嘩に発展したが結局、騎士の意見は通らず、着々と出来上がる豪華な内装を遠巻きに眺めることしか出来なかったのである。
部屋の内装や家具の搬入が終わるまでの一週間は皇子の部屋に間借りしていたが、その後、(不本意ではあったが)充てがわれた私室に移動した。
内装はルルーシュが設計、デザインを一任したと聞いていたが成程、その室内はとても品が良く淑やかでひどく居心地良かった。ソファの手触り、絨毯の感触、テーブルの高さからソファの寝心地の良さ。何から何まで完璧な設計と計算によって形と色が組み合わされている。そこまでしてくれなくて良いのに、と何度も断ったが、厚意自体は素直に嬉しかった。
何より有り難かったのは、小さいながらも書斎スペースを設けてもらえたことだ。思えばブリタニア軍へ従軍してからというもの、勉学という分野に触れてさえおらず、そもそも同年代は学校に通っているという事実すら頭から抜けていた。いつ死ぬか分からない環境に身を置きながら文字の読み書きや四則計算、化学方程式を独学で学ぼうという気概は当然、微塵も起きなかった。
そもそも、そうしたことを学ばなくても生きていける環境だったからだ。名誉軍人として、あるいは特派のパイロットとして。明日を五体満足で迎えることすら不確定の日々で、今日という日を重ねていくだけで精一杯だった。紙とペンを握る余力があるなら鍛錬を行うほうがよっぽど有意義だった。致命傷ひとつ負えば死に直結する最前線において、学びは無用であり、当時の名誉人には物を知る権利さえなかった。
ブリタニア人は基本的に裕福で、生活水準が高く、一般人でも学習機会は広く用意されている。市民の大多数は大学部に進学するし、学習支援の場も多く設けられ、国が運営する学生支援のシステムや制度も存在する。この国の生涯学習度は世界と比べてもトップクラスであった。国民の多くが知識と教養に富み、一定基準の学殖を得ているのはある意味で当然なのだ。なんら不思議ではない。
宮廷に出入りする文官や軍人らも例に漏れず、学びの場を与えられていたのだろう。礼儀礼節を重んじ、課せられた任務を着実にこなし、帝国から高い評価を賜る彼らは皆一貫して優れた知見、あるいは深い造詣、教養を持つのだ。どうして彼らがそこまで学徳を兼ね備えているかは考えなくとも分かる。単に成熟した学習機会に恵まれ、教科書とノートとペンを与えてもらえたからだ。自分と彼らは根本的に環境が違う。比べるのも烏滸がましい。
生まれた環境を嘆くのは誰だって出来る。だから自分はせっかくの機会を活かし、今まで避けて通ることもできた勉学の道に、敢えて踏み込む決意をした。
日中は皇子殿下の専属騎士として、ほぼ付きっきりでルルーシュと行動を共にしている。打ち合わせや会議、外交と出張、いつ何時どこに居ようと、彼のいる場所が自分のあるべき場所であり帰る家だ。すべての行動の座標軸、帰結する点、一心同体。そんな言葉に置き換えても足りないくらい、皇子は自分にすべてを委ねてくれた。だから自分は皇子に出来る限り、いやそれ以上に、期待に応えたいと思った。
地獄の底に垂らされた蜘蛛の糸を必死で掴んでここまで来たのか。そんな揶揄の言葉は気にならない振りをして、着任以降は求められた結果を残すことだけに執心した。宮廷に出入りする軍部の高官たちは皆輝かしい功績を残し、ブリタニア国の繁栄と秩序と安寧の構築に貢献していた。彼らはどこに出しても恥ずかしくない精鋭ばかりだ。国家の誇りであり強さの証明であろう。まるで自分が場違いのように思えた。
それでもこの役職にしがみつく決意をしたのは、ルルーシュの手に手綱が握られ続ける限り、彼の傍に立つことを許されていたからだ。逆を言えば、ルルーシュを失望させたり期待に応えられなかったら、いつ見放されてもおかしくない、ということだ。
自分の代わりは居る。きっとルルーシュの周囲は元名誉人を騎士に据えることに反対しただろう。そうして、いつだって自分は逆境のど真ん中に立たされて、その性根と気概を試されている。もう何度目になるか分からない苦しい位置にいつまで立ち続けられるかは、自分でも分からなかった。
翌朝。首都ペンドラゴンを飛び立った浮遊艦体アヴァロンは約束の時刻通り、条約締結国の有する海上飛行場に降り立った。かの国が有する大型潜水艦は空母的な役割も果たしているようで、このアヴァロン以外にも多くの戦闘機やヘリが離発着をしていた。
艦体から降り立った皇子を出迎えたのは今回の条約締結にあたり尽力してくれた首脳陣であった。皇子は人好きのする笑みを浮かべながら彼らと握手を交わしていた。
「この度は遥々お越し頂き有難う御座います」
「こちらこそ。日程調整でたびたびご迷惑をおかけしまして、申し訳ありません……」
出迎えてくれた彼らに頭を下げる皇子に、一人の男が言葉を遮った。
「この情勢ですから、さぞお忙しいことでしょう。建国以来初の革命ともなれば寝る間もないのでは?」
「幸い、必要最低限の休眠は取れていますよ。日中は激務に違いありませんが」
皇子は苦々しい笑みを口元に浮かべながら、そんなことをぼやいていた。
帝政崩壊後、ブリタニア内部では帝政派と解放派の対立が激化していたが、玉座に着いたシュナイゼル主導による政治運営の元、帝政派の反対意見を押し切る形で帝国はすべての植民地私有権を失効した。支配下にあった各国は自治権を取り戻し独自政権を樹立させ、圧政に苦しみ喘いできた人民たちは喜びに湧いた。日本国を始めとした旧エリアは現在、帝国の援助を受けつつ国の運営や建て直しを図っている。
そうして先日、日本国で平和式典が行われた。未だ混乱渦巻く時勢の中で時期尚早との意見も見られたが、その時重要だったのは式典で述べられる演説でも平和宣言でもない。出席した国の代表者らにより賛成多数で可決され、調印が行われた和平条約の締結であった。
互いの所持する戦略兵器の内示や削減目標の開示、情報交換を目的とし、最終的には全武装の解除、およびサクラダイトの軍事転用禁止を最終目標として掲げてある。達成目標期間は三十年と設定され、国防問題とどう渡り合いながら達成へ近づけてゆくかが最大の課題であろう。
驚くことにこの条約の草案は帝国が明示したもので、発議のきっかけはシュナイゼルであった。膨れ上がりすぎた国防費や軍部の運用、兵士の管理や維持などに毎年多額の支出が計上されている。それよりも国民に対して少しでも還元出来れば、たとえば社会保障や福祉の充実に当てたほうが有用ではないか。和平条約は政治運営を有利に進めたい新皇帝の、そうした思惑も根底に存在した。
しかし国防問題は自国だけで解決できる事象でもなく、やはり各国との密な連携や信頼関係が必要だ。それらを築くためにもまずは形から、世界がブリタニアの動向に注目する今だからこそ行動を起こす必要性があるのだ。
海原に浮かぶ飛行場は海風が吹き荒び、皇子が身に纏う装束の裾を盛大にはためかせていた。体のラインに沿って揺れる布は彼の平坦でなだらかなシルエットを浮き上がらせ、無意識のうちに目を奪われる。細い柳腰に長い手足、小ぶりな臀部と薄い胸板。美しい曲線を描く背筋は、今は布に隠れてしまって見えない。
「……あ」
大きな風に煽られよろめく足元を視界に入れた瞬間、手を差し出そうとしたが、一歩遅かった。出迎えに訪れていた外交官の一人が皇子の肩を支える形でその細い体躯を背中から受け止め、彼はたたらを踏んだが転倒は免れた。
「大丈夫ですか、ルルーシュ様。お怪我は」
「え、ええ。申し訳ありません」
「海風はお身体にも障ります故……早速ですが格納庫へご案内致しましょう」
自然と交わされた会話と背中に触れられた男の手のひらを見つめていると、ひとつの感情が心の底に芽生えた。
気安く、ルルーシュに触らないでほしい。
「……殿下」
「ん?」
呼びかけながら、ルルーシュの傍に着く男をちらりと見遣る。そうすると視線がかち合い、男はそっと身を離した。
「いいえ何でも。海上は風が強いですからお気をつけ下さい」
「ああ、そうだな」
皇子は国の未来を背負う宝だ。国民の何万人の命をもってしても代えられない、尊い存在だ。それを理解しているから、かの外交官も物理的な距離を離したのだろう。牽制の意を込めた視線を投げかけてやれば誰も皇子には迂闊に触れないし近寄らない。ある意味で役得なのだ、専任騎士というのは。
「……人相が悪いぞ。寝不足のせいじゃないか?」
「ここは風が冷たいですから」
「ふん。お前は嘘を吐くとき、いつも目を逸らす」
「……」
「冗談だよ」
吹き荒ぶ風より冷たい声音で告げられた言葉は優しさの欠片も見当たらない。それが何だか突き放されたようにも思えて、ひどく悲しくやりきれなかった。
艦艇の内部に案内され、その奥に存在する格納庫を開示された。立ち並ぶナイトメアフレームは帝国が所持する量産型グラスゴークラスの機体だろうか。傍のコンテナにはミサイルやそれに相当する弾頭が数多く収納されてある。
「貴国のサクラダイト産出権は確か……」
「第四位です。年間数十トンですから、エナジーを大量消費する大型機は運用コストから鑑みて所持しておりません。ブリタニアではどのような運用を?」
「我々は現在産出権一位……実質的に言えば寡占状態ですから、大型機やフロートユニットの開発も行いました」
「やはり国防の要はナイトメアフレームですか」
「今日明日で解決できる問題ではありません。しかし我々はこの事実を深く受け止め、削減への取り組みを行っています」
嫌な話運びだ。ブリタニアに不利になるよう、あるいは答えにくい話へ持っていこうとしている。そしてルルーシュもそれを分かった上で、敢えて受け身になりながら会話を続けている。
「具体的にはどういったことを?」
「まずは各国との連携、不可侵条約を結び信頼関係を築くことです。そして旧植民地エリアには人道支援を行い続ける。ブリタニアが悪逆の象徴から平和の礎にならねばなりませんから」
「しかし国家とは別に、武勇軍やゲリラ、テロ組織も存在しているでしょう。そうした勢力とはどう戦う方針です?」
「和解の態度が見られなければ自衛権を発動させます。市民の生活が危険に侵されることは看過できませんから。サクラダイトを原動力にしたブレイズルミナスに取って代わる防護壁の開発、可動式堤防の建設などが挙げられます」
「あくまで反撃には出ず、守りに徹するというわけですか」
「基本的には」
「それで本当に国防問題が解決できるのか……」
「皇子は平和主義にやや傾倒しておられる」
「宰相閣下もあのご様子だ。前線を知らぬ若人に国防は務まらないだろう」
「枢木卿はいかがお考えかね」
一方的な論調の中、ふと話の矛先が自分に向けられた。視線が集まる。言いたいことと言っていいことを頭の中で選別しながら、ゆっくりと言葉を紡いだ。
「……私は同じ人間同士で信条の相違を理由に殺生を繰り返す戦争に反対です。とくにナイトメアフレームの破壊力は莫大なぶん、大量殺戮が可能ですから、本来、存在していい代物じゃないと」
「ですが貴方は軍人だ。それが本分なのでは」
「私は組織に与する人間ですから、それが意向とあれば従うまでです。一個人の意思は介入できません」
「貴殿はナイトメアフレームのエースパイロットと伺いましたが……その階位を得るまでに多くの人命を奪ってきたのでは?」
「国の命とあらば己を殺すまでです」
「はっはっは。本意ではないから自分は悪くないということか」
「……! そのようなことは」
反論しようと口を開きかけた時、肩を叩かれた。ルルーシュだ。ルルーシュの手がそっと肩に乗せられていた。続きの言葉はたちまち消えて、喉が支える。頭に上りかけた血がさっと冷えてゆく。
彼はこちらを見ず、苦笑を浮かべる首脳陣に向き直りながら愛想のいい表情を作ってみせた。
「他の場所もお見せ頂けませんか。兵士たちの訓練風景にも興味がありまして」
「承知しました。ではこちらへ、ご案内致します」
格納庫の奥に留まっていた一行は次の目的地を目指して移動を始めた。革靴が床のコンクリートを踏み締め、鳴り響く足音がやたらと耳障りに思えた。
「……よく我慢した」
「……」
前を歩く皇子が足音に紛れるように声を発した。それが一体何を指す言葉なのかは歴然であったが、敢えて返事はしなかった。
自分の未熟さや短絡さを暗に指摘されたようで、とても居た堪れない。もっと気の利いた言い方や方便、切り返しはあっただろう。彼ならうまいこと言い包めて話を受け流せたはずだ。でも自分はそれができない。建前と本音の使い分け、弁論術、口先の攻防は不慣れだった。足元を見られた質問内容は恐らく舐められているからだ。
男たちがわざと焚き付けるような、あるいは不利になるような会話に運ぶのは失言を誘発する為だろう。首脳会談での発言を槍玉に上げ、ここぞとばかりに新政権の批判を取り上げる。ブリタニアから世界的な実権を奪うには政権交代したばかりの今この瞬間が絶好のタイミングだ。彼らが狙うのはその点ばかりで、所詮は皇子の護衛でしかない自分の意見など鼻から聞く耳を持たない。
適当に右から左へ聞き流せば良いものを。そう頭で考えるのは簡単だが、実際に声にするのは難しい。
反撃には出ず、守りに徹する。その言葉を体現してみせたルルーシュは一方的な主張すべてに自身の意見を返していた。批判も偏見も文句にも、彼は眉一つ動かさず真摯に受け止める。健気で愚直で真面目な姿勢だ。皇子を揺さぶりたい男たちにとって、これ以上に退屈なことはないだろう。
だから自分はせめて、彼に降りかかる火の粉を払ってやるくらいのことはしたいのだ。あるいは、矢面に立たされる苦しみや葛藤を分かち合いたい。ルルーシュのことをよく知りもしない奴らに、悪く言われたくない。
まだ力不足な自分では盾にもならないだろうが。
そのことが歯痒くて悔しかった。どれだけ地位を築こうと周囲に認められようと、能力がなければガラクタに過ぎないのだと改めて痛感した。
午後の四時過ぎ。朱色に染め上げられた空が眩しく顔を覆いたくなる時分。粛々と行われた意見交換会は予定どおり終わった。
集った首脳陣はそれぞれの公用ジェット機やヘリに乗り込み、帰国の準備を滞り無く進めている。自分とルルーシュも同様に、海上飛行場に停泊させていたアヴァロンに足を向けた。
「動作チェック、オールクリアです。帰路の航巡をデータに反映させます」
「サーチライトオン、騒音軽減装置作動。タラップの格納を確認」
「上空の気流は安定しています。北北西の風、風速三メートル。気象状況も今晩から未明にかけて晴天とのことです」
艦艇に乗り込み、各員はまずサクラダイトの起動準備にとりかかる。動力源設備の光が明滅し、着陸安全装置が解除され、そうして巨大な機体は徐々に浮かび上がった。飛行艇は問題なく動作している。
「ルルーシュ様。機体が安定飛行水準に達しましたら自動操縦に切り替えます」
「ああ、分かった。エナジーフィラー残量はどのくらいだ?」
「今の巡航を維持し続けますと、およそ三十六時間は保つかと」
「なら充分だな」
ゆっくり移ろう外の景色をぼんやり眺めながら、管制室のやり取りを耳に入れた。
自分は最近知ったことだが、ルルーシュはサクラダイトを動力源とする戦略兵器の知識も兼ね備えているらしい。指揮官である彼はコーネリアのように自ら前線に出て戦うことはないにせよ、その扱いは心得ているらしく、ナイトメアフレーム適正もあるようだ。
政治的手腕に秀で、軍事では司令塔として見事な戦略性を披露し、兵器の扱いにも精通している。人並み以上の素養と知識を持ち得ているにも関わらず、さらにあらゆる分野や業界にも通暁しようとするその姿勢は素直に称賛に値するし、彼を同じ人として、上司としても尊敬できる。
人はいつだって無い物ねだりだ。隣の芝生は青く見えるし、屋根は赤い。
恐らくだが。ルルーシュの生まれ持った才覚と明晰な頭脳は、自分がどれだけ欲しても絶対に手に入らないだろう。努力だけでは埋められない差を人は才能と呼ぶらしいが、なら自分にはどれだけの才能とやらが秘められているのか。どこぞの誰かにこの階位を取って代わられないような強み。自分だけにしかない才能。長所。皇子は自分のどこを見出して、専任騎士の称号を与えたのだろう。
などと、そんな卑屈なことを考え出すと、抑えが効かなくなるのだ。散々自己否定を続ける自分さえ嫌になる。地位も名誉も富も環境も身に余るほど充実して、与えてもらってばかりだ。自分にはとても不釣り合いな待遇ばかりで、勿体無い。
だからそれに見合う人間になりたかった。誰よりも立派で強かでひときわ精彩を放つルルーシュの隣に立って、恥ずかしくない人間になりたかった。見劣りしないくらい、胸を張れる騎士侯になりたかった。
(こんなに悩むくらいなら名誉軍人時代のように、馬車馬のように扱き使われるほうが、よっぽど……)
――CAUTION,CAUTION……――
俯きかけた顔は、管制室に鳴り響いた警報音によって、進行方向に向き直った。
緊急事態を告げる警告音が機体内に鳴り響く。
「……空中衝突防止装置が作動しています」
前景に表示されるコックピットレーダーに映し出されたのは、復路となる飛行経路・高度上に正体不明の飛行物体を捉えたとの情報であった。対角線上に現れた機影は複数存在し、それは刻々とアヴァロンの飛行経路内に侵入しようとしていた。
「この近辺で戦闘機の模擬訓練が行われた情報はあるか」
「本日そのような報告は上がっておりません。民間機とは経路も高度も異なります」
穏やかな空気は一変し、室内に緊張感が走る。
通常運行で帰還する算段は立ち消えた。今は目前に迫る正体不明の機影の解析に、乗組員は一斉に当たった。
「機影の解析は勿論だが、他の経路も探せ」
「畏まりました」
ルルーシュは管制室の司令席に腰掛け、レーダーの集積情報を読み取りながら乗組員らに指示を飛ばした。
コックピットのディスプレイには回避指示の信号が点滅している。"monitor vertical speed"、つまり現行航路を逸脱しないよう速度と高度を維持せよ、ということだ。相手機の正体が分からない以上、手出しも解決策も立てられない。
「相手に敵意があるとしても、このアヴァロンの居場所と動きが割れなければ衝突回避は出来るかもしれない。今からステスル飛行での運行はできるか」
「……ステルスモードの場合、今からシステムの構築し直しとなれば……非常に申し上げにくいのですが、数十時間は要するかと……」
「そうか、分かった。緊急用の車両か小型機は内蔵あるか」
「協力を得られれば隣国のプライベート用空港に着陸後、車両を出すことは可能です。尚、警備を大勢要するのではっきりした所要時間は……」
「小型機はステルス未搭載のものしか積んでおりません。殿下を先に本国へお送りするなら車両の手配が堅実かと思われます」
「本国側ですぐに動ける軍はあるか?」
「ジェレミア卿の率いる部隊が残っています。しかし陸戦用の機体が大半で、航空戦となった場合やや打撃力に欠けるかと」「相手の素性が不明な限り、このアヴァロンを向かわせる方が確実ということか」
ルルーシュはそこまで言い終えると、ふうと息を吐いた。
「……分かった。少し考える。その間に機影の解析を急げ」
司令席に深く腰を下ろすルルーシュは、肘掛けを指で数度叩いた。
分からないことだらけの現状で、打てる手立ては限られている。彼は長い脚を数度組み替えながらレーダーを見据えた。
さて、どうしたものか。どの案も今ひとつ決定打に欠けている。未確定の不安要素を抱えている。
「……お前はどう思う、枢木卿」
ディスプレイから目を離さないまま、皇子は静かに問いかけてきた。
ルルーシュがどんな答えを欲して、期待しているかなんて分かりやしない。
自分は生憎、戦術兵器で戦線をかき乱すか陽動の囮になるくらいしか能がない。特派で課せられた任務はどれも命を捨てる覚悟がないと遂行できないような、無茶苦茶な内容ばかりだった。毎回負傷したし、機体の損傷も多かった。しかしどうにも悪運が強いらしい自分は、いずれの任務でも命からがら帰還を果たし、その成果をブリタニアに認められた。
恐らく最初から、自分には危うい道しか用意されていないのだ。逆境と批判、圧倒的不利な戦況。どれも身に沁みてるから慣れっこだ。慣れているんだと、自分に言い聞かせる。
「ランスロットにエナジーウィングを装備させ、飛行状態でわたくしと帰還すれば早いと思います。皇子にはコックピットに同乗して頂きます」
「相手に遭遇したらどうする」
「一掃して強行突破します」
呆れたように息を吐く男を他所に、足は既にランスロットを格納する倉庫へ向かっていた。他の乗組員たちはお互いに顔を見合わせ、驚きに言葉を失っている。しかし外野の意見に耳を貸してやれる時間はない。事は一刻を争う。肩に羽織った重たいローブを外し、管制室を後にする。
手にしていたのはランスロットの起動キーと、ルルーシュから受け取った騎士章だけだ。自分には初めからこれしかなかったのだ。知識教養もなければ、意見を論じることも、戦略性の高い作戦を立てることも。自分にはほとほと才がない。
厄介なことだ。火中の栗を拾う真似でもしないと、自分は真価を発揮できないらしい。
狭い操縦席に体を滑り込ませ、起動準備に入る。マスターキーを差し込みパスワードを入力すると電源が入り、サクラダイト動力の駆動音がマシンから響く。
「やっぱりお前で良かった」
「……殿下」
コックピットハッチを開きながら、頭上から声がかけられた。ルルーシュだ。彼は操縦席を見回しながら起動準備に入るモニタを見つめ、穏やかな口調で話し始めた。
「いつかの時みたいだな」
「そうですね」
「俺はどこに座ればいい」
「私の膝の上に、どうぞ」
「……やはりそうなるか」
力なく頷いた男は、狭い隙間を見繕いながら足を差し出す。面積の小さい床にそっと足を着けると、こちらの様子を伺いながら大人しく膝の間に腰を下ろしてくれた。体を捻りながら各種機器に決して触れないよう、細心の注意も払ってくれる。
ただでさえ余裕のない操縦席は本来一人乗りを想定しているから、二人も入ろうとすれば色々と無理が生じる。これ以上ない密着度であったが緊急事態だ。致し方ない。
コックピットハッチを閉じて、室内はランスロットの背面部分に自動で格納される。暗闇に包まれた箱の中は一瞬にして電子機器やランプ、液晶モニタが放つライトに照らされ明るくなった。
操縦桿を操作し機体の射出速度と角度を計算、調整する。調整とはいっても、自分はいつだって最高速度になるようそれを設定するわけだが。
「なあやっぱりこの体勢、どうにかならないか」
「腕は腰に回していいから」
「そういうことを言いたいわけじゃなく、」
「……喋ってると舌噛むよ」
ルルーシュの話を遮って、スイッチを押した。真横にある顔は一瞬呆けたが、直後、その瞳はめいっぱい見開かれる。
エンジンがフルスロットルで加速し、機体はアヴァロンの艦橋から射出された。はずみでルルーシュは頭を揺らしたが、空いた左手で包み込むように支えてやった。僅かな呻き声は布の中でくぐもってよく聞こえない。
「アンノウン反応のあった地点を迂回して本国の基地に戻ります! もしこちらの進行を阻害する機体が現れた場合は、」
「一掃して強行突破だろう?」
「当然」
「せいぜい安全運転で頼むよ」
「イエス、ユアハイネス」
機体の加速音が動力源を通じてコックピットにまで響く。安全運転とは言われたが、それは叶いそうにないと心の中で先に謝っておいた。
結果としてだが、敵機に遭遇することはなく。残してきたアヴァロンが襲撃に遭ったという情報も入ってこなかった。
ルルーシュは帰国後ブリタニア空軍を動員し、最優先でアンノウン機の捕獲を命じた。どこの所属で何の目的で経路に現れたのかを開示させ、理由によっては罰則を。もし要求に応じずこちらへ危害を加えるのであれば撃墜を。そして空路の安全が確保されてから、アヴァロンの回収に向かうよう指示を出した。
出動部隊の調査の結果、アンノウン機の正体はすぐに判明した。
「新政権反対派による過激運動、か」
内線で調査報告を受けたルルーシュは静かに言葉を溢すと、さして驚きもせず、報告の続きを促した。
報じられていた外交会談のニュースを耳にした活動家らは帰国途中のアヴァロン襲撃を目論んでいた。新政権発足直後の国防危機となれば人々の注目も浴び、市民には一定の不安が訪れるだろう。そうした浅はかな計略の元馬鹿正直に立ちはだかった彼らであったが、ステルス戦闘機でもない機体は当然レーダー上でアンノウンと検知されたわけだ。
が、そうした活動家集団の手元に戦闘機といった類の兵器が渡っていた現実は、重く受け止めねばならない。軍備取引の取締強化を促すも、国家非公認で重火器の横流しが広がる闇市場を撲滅しきれていない。政府認識の甘さがツケとなって今回の事態となったのだ。これだけは覆りようのない事実である。
調査報告や対策案構築の会議が続いたある日の深夜だった。朝から晩まで会議室にすし詰めにされ、それがもう三日目ときている。肉体的にもそうだが、精神は限界ぎりぎりだ。時刻は日付を超えてから三時間は経過しているだろう。
しかしどうにも、寝付ける気にはならなかった。明日に回せる仕事ばかりだったし、体は疲労困憊を極めている。瞼が重い。腕も足も気怠い。それでも何かやらねば、眠っている場合じゃない、と焦る心が訴える。
寝室の隣に備えられた狭い書斎スペースには、買い集めた書物がぎっしりと本棚に収まっている。この部屋を与えられたばかりの頃は空っぽだった収納はもう余力がなく、新たに棚を増築しないといけない頃合いだった。
カバーがかけられた本の背表紙からいくつか見繕い、机に並べて積んでいく。ページに貼られた付箋が本の隅からはみ出していて、それは無数に存在していた。もう何冊目になるか分からない大学ノートを事務机の引き出しから取って、隣に広げる。ペン立てに置かれた三色ボールペンと蛍光マーカー、定規、消しゴムを机の脇に並べて、ようやく机に向き直る。
日本国の地理は薄っすらと知識として頭に入ってある。なんせ長年住んでいた土地だ。誰かに教わった覚えはないが地名くらいはひととおり分かる。
問題はブリタニアの国土だ。今まで興味も関心もなければ直接的な関わりは一切なかった。覚える必要もなかったし、無くても暮らしていく分にはなんら支障はなかった。
でも今は事情が違う。たとえば今日のような有事の際、実地作戦が講じられるとして、戦術・戦略を練るにはまず地理の掌握が先決だ。山川の位置、市街地との距離、海抜の高さ。それらの知識がまず頭にないと話し合いにすら参加できないだろう。作戦要項を理解するのも困難だ。
自分は正規のブリタニア軍に属する軍人だ。騎士侯だ。なのに何も知りません、存じ上げません、ではいけない。皆が当然のようにこなすことを出来てから初めて、同じ土俵に上がれるのだ。今の自分は共に戦線に立つことさえ許されない。
そうして一時間ほどが経っただろうか。時計を見ることさえしていなかったから、体感時間だけが頼りだった。
部屋の反対側から物音が聞こえる。扉が開けられて、閉まる音。そしてスリッパで絨毯を撫でる足音。細やかな息遣い。
「こんな夜中に何をしている」
それはこちらの台詞だ。どうして君が、ルルーシュが僕の部屋に居る。
「言い訳は聞かない。早く寝ろ」
「……」
「熱心に何をしてるんだ?」
「……あ」
男は机に積まれていた書籍のひとつを手に取る。表紙をじっと眺める。ぱらぱらと中身のページを指で繰り、流し読みする。据わった目つきだった。
「ブリタニア国史」
「返してくれ」
「そっちの本は」
ノートの横に広げていた本をルルーシュは指さした。言われるまま本を持ち上げ、その表紙を掲げてみせる。
「王家の歴史と、こっちは国土分布か」
「……」
「勉強熱心だと、褒められるとでも思ったか」
手に取った本を棚に収めながら、ルルーシュは睨んだ。そうして積み上げられた書籍を一冊ずつ棚へ戻してゆく。
「ルルーシュ」
「……」
彼は始終無言だった。
しかしトン、と最後の一冊を本棚に収納し終えるや否や、唐突に話を切り出してくる。
「明日、スザクは休みだ。休みをやる」
「休みって、何?」
「ただしランスロットに触るな。勉強もするな。仕事をするな。何もするな。しなくていい」
「は?」
「いいか、この部屋で昼まで寝て、テレビでも見て、飯をだらだら食べておけ」
「どういう意味?」
「休養しろと言ってるんだ」
彼は威嚇するようにますます眼光を強めてくるが、そんなもので怯むほど自分は小心でない。その瞳と相対する形でこちらからも睨み返した。
「僕は毎日十分な睡眠と食事を取っていて」
「駄目だ」
食い下がる自分の声に、ルルーシュはさらに言葉を重ねて発言さえも遮ってみせる。
「ほらもう寝ろ。俺の命令が聞けないのか」
書斎の照明を消し、事務机からの離席を促してくる。腕を引かれて立ち上がると、そのまま連れて行かれたのは寝室だった。
「明日の君の警護は誰が」
「急遽になるが、ジェレミアに任せる」
「そんな……」
「いいから!」
抗議しようと声を上げたが案の定、それさえ許されないらしい。掴まれた腕に力が込められ、骨がきりきりと痛んだ。
足元の絨毯に落ちた二人分の暗い影は離れたままゆらゆらと揺れていて、暗がりの部屋でぼんやりと浮かんでいた。閉じられたカーテンやベッドメイクが施されたままの寝台は、昨日自分がここで睡眠を取らなかったことを暗に示している。皺ひとつないシーツや枕カバーは無言で佇むばかりで、それが実際に使われることは滅多に無かった。
折角大きめの、一人部屋には似つかわしいサイズのベッドを用意してもらったのに。そう頭のどこかでは思うが、思うだけだ。この部屋に越してからというもの、使用したことは片手で数える程度だった。自分は殆どこの寝室で眠らない。朝を迎えるのは大抵書斎に設けられた机の前で、ノートを頭の下敷きにして眠りこけていることが大半だ。
だから本当は、自分が何時に寝ているのかさえ把握していない。いつの間にか意識を失っていて、朝がやってくる。けたたましいアラーム音に覚醒すると同時に、自分の一日は始まるのだ。
ルルーシュには当然言ってないし、言わない。でも恐らくこの様子だと気づかれているだろう。どこか怒った表情を浮かべながら寝室を見渡して、そうして深い溜息を吐いていた。腕を掴む握力は未だ緩まない。そんなに力を込めなくとも、逃げる場所なんてありはしないのに。
「大きいベッドだから二人で眠るのも容易だな」
「……」
「スザク」
力づくで引かれるまま、寝台に腰を下ろした。きしりと音が響く。波打つシーツの上にルルーシュが先に寝そべり、お前もほら早く、と空いた場所を叩いて誘われた。
「俺の言いつけを守れよ?」
「……」
「返事は」
示された場所に体を寝かして、向かい合いながら言葉を交わした。視線が混ざり合って胸がちりちりと焼き焦げる。冷たい素足を絡ませて、手を握った。
「イエス、ユアハイネス」
「いい子だ。おやすみ」
「……おやすみ」
やがて間も置かず瞳を下ろすルルーシュに釣られて、自分も目を閉じる。とろとろと甘い睡魔に脳裏を侵され、意識が徐々に支配されてゆく。何も考えられない。
そういえばルルーシュとこうして密やかな会話をし、肌に触れたのは何日ぶりだろう。最後に彼に触れたのはいつだった?
共に眠るのはそれよりずっと前だ。破れかぶれの記憶の狭間で、自分はゆったりと意識を手放した。
翌朝目が覚めると、視界にまず入ったのは眩しい太陽光。そして、その光を受けた皺くちゃのシーツの海。中途半端に腕に引っかかった布団と毛布。それから朝の八時を示すアナログ時計。
(遅刻……!)
そう思ってベッドから起き上がりかけたが、部屋に漂う甘い香りに思考が停止した。匂いの元を辿ると、それの正体はリビングのテーブルに置かれた朝食のプレートであった。
紅茶とミルクと砂糖、そして蜂蜜がかかったトーストとサラダ。白い陶器に盛られた食材は湯気を立てながら、自分しか居ない部屋に置かれている。誰かが間違って運んだのかと思われたが、恐らくこれは正しく自分の分だ。
昨夜遅くにこの部屋へ訪れたルルーシュから、突然の休暇宣言を賜った。理由は分からない。聞いても教えちゃくれないし、いいから休めの一点張りだった。まるで話が通じない。強行が過ぎる。彼の悪いところだと思う。
自分が部屋の外へ出歩かなくて済むように、ルルーシュが配膳の指示をしたのだろう。立派なブレックファーストが私室に届けられたことはこれまで一度としてなかったし、まともに朝食を摂った記憶もない。これは妙な気遣いと親切心の具現だ。
ティーカップを持ち上げて中身を啜った。香りはするが味はよく分からない。ブリタニア人は紅茶を好んでよく口にするが、自分には合わない文化だ。
トーストにも手をつけようか迷ったが、結局触れることもしなかった。内線で呼びつけた給仕に配膳を片付けさせて、漸く心が落ち着いた気がする。時計を見ると時刻はまだ九時にもなっていない。途方もなく、気が遠くなる。時間の経過があまりに遅い。
ふと視界に入った液晶テレビが気になって、電源を入れた。テレビが置かれてあるのは知っていたが、使ったことはない。埃を被ったリモコンをティッシュで拭き取りながら、チャンネルや番組欄を操作してみる。
その電化製品は賑やかな音声を垂れ流し、あるいは面白おかしそうな映像を流し、人の興味や視線を引く。しかし今の自分にはどうにも肌に合わない。関心が持てる番組がない。つつが無く放映される内容は頭に入らなかった。時計を目にすると九時を少し過ぎたあたりだった。
いくつかのチャンネルを変えていると、少し趣の違う番組に巡り合った。それは国営テレビ局が放送するニュース番組だ。キャスターが報道の概要を読み上げ、映像が切り替わる。
「あ、ルルーシュだ」
それはつい十分程前に行われたらしい、国民向けの会見映像であった。多くのマスコミが会場に詰めかけ、その人物は無数のフラッシュライトに晒されている。会場中央の講壇に立ち、マイクに顔を近づけながら、事前に用意していたのであろう声明文を朗々と言葉にする。
――先日の騒動により国民の皆様を危険に晒したこと、ご不安にさせたことについて、心よりお詫び申し上げます。また現状で判明しました情報について、いくつか私の言葉でご説明をさせて頂きます。
カメラのシャッター音に被さるように、ルルーシュの声が響く。映像の下には番組が編集したのであろうテロップが流れている。
――正体不明の機体はブリタニア軍でかつて使用されていた戦闘機で、これらの乗組員はどの国家にも属さない義勇軍であることが分かりました。彼らは宰相閣下シュナイゼル皇帝により樹立したブリタニア新政権に対し、強い反対意見を訴えています。彼らの動機は新政権への抗議と、国防の混乱誘発の二点。我々は彼らをブリタニア国家の敵とみなし、近く軍事法廷で裁判を行う予定です。
淡々とした口調で事実が述べられる。現地に集った報道記者らは彼の言葉に、固唾を飲んで聞き入っていた。
――犯行グループに何故戦闘機が渡ったのか、その入手ルートは現在精査中です。本国軍部は適切な手順で機体を処分したと主張しており、その下請けや孫請けに不正がなかったかを取り調べています。ですが、闇ルートの存在を把握しておきながらこれを撲滅できなかったのは、我が国の行政と軍部の失態であり重大な過失で御座います。改めてこの場をお借りして陳謝致します。
フラッシュライトが一斉に炊かれ、ルルーシュはその真ん中で深々と頭を下げた。壇上の脇に立つ外交官や軍部の上層、そして彼の騎士を務めるジェレミアも同様に腰を折り曲げ、頭を下げる。
おおよそこれまでのブリタニアでは想像もつかない、異様な光景であった。かつてこの国においては、トップに立つ者の意見が絶対であり、少しでも異を唱えれば揉み消されるのが常だった。皇族は圧倒的優位な立場から人民の上に立ち、自らの正しさを主張する。そして軍人も平民も等しく皇帝への忠誠を誓い、これを遵守することを強要されていた。
だが今はどうだろう。彼らは自らの非を認め、これを謝罪しているのだ。目を疑う会見だ。
――わたくしからの説明は以上です。質疑応答があれば時間の許す限り行います。
ルルーシュは一歩も怯まず怖じけず、最後の時間まで講壇の前に立ち続けた。
番組内ではその会見についてキャスターやコメンテーターがいくつか意見を述べ、そして次のニュースに移った。
それ以降、どの番組にチャンネルを合わせても、ルルーシュの会見についてひっきりなしに報道がなされていた。
前代未聞の謝罪会見は人々の印象に強く残っただろう。一見すればブリタニア政府の失態でもあるが、その迅速な対応と真摯な説明会見はむしろ好印象すら与える。報道記者からの質問にも全て応じ、嫌な顔ひとつせず、答えにくい質問にも答えられる範囲で適切に言葉を選んでいた。守りに徹したようにも映るが、ある意味でこれは、別のアプローチからの攻勢だ。
不明機体の正体が新政府の敵、という事実も良い方向に作用したのだろう。国家国民全体の共通の敵だとして、一体感や連携が生まれやすい。犯行グループの処遇を明確にしたのも、恐らくそうした意識を根付かせる為の、ある種のパフォーマンスだ。
読み上げられた原稿や会見での振る舞いは、一体どこまでルルーシュの思惑によるものなのか。国民感情を煽る演出は見事としか言いようなく、政治家としての才覚も遺憾なく発揮されていた。
ルルーシュの傍に付き従うジェレミアも折り目正しい所作で、完璧に職務をこなしていた。いつ枢木スザクの代打を任されたのかは知る由もないが、それにしたって型に嵌まったかのように似合っていた。嫉妬してしまうくらいに。
よく眠れたせいで思考は冴え渡っている。自分をどこまでも卑下する悪い癖が、今日はとても捗るのだ。とてつもない自己嫌悪の波が押し寄せて息も苦しい。
未だ皺だらけのベッドに背中から横たわって、白い天井を見上げる。吊り下げられた照明は数多の硝子玉を抱えて、光を反射させていた。ちらちらと瞬くフィラメントは柔らかいオレンジ色を帯び、室内を照らしてくれている。
自分に出来ることって、何だろう。
もはや何度目になるか分からない。漠然とした問いが胸に芽生えて、微かな希死観念が喉元を過ぎる。それには見ないふりをするように、心に蓋をして、目を瞑った。
目元を手の甲で覆うと、微かに湿った感触を覚える。目尻を伝ってこめかみに消える細い雫が涙であることに、この時はまだ気がつかなかった。
重たい雲が幾層にも重なり、夕日の色はよく見えない。夜が近いと予感させる藍色が様々な濃淡で空を色付け、どこか気怠げで鬱蒼とした雰囲気を醸す。西の方角に目を凝らすと、地平線の近くで薄橙色に染まる雲が視界の端に入った。昼と夜の境を漂う雲はその時々の空の色を映すだけで、自分を持たない素直な子供のようだ。
ベッドの端に腰掛け、カーテンを手で避けて、窓の外をぼんやり見つめていた。今の時間は分からない。いつの間にか惰眠を貪り、意識を浮上させた時には夕暮れ色の空が目に映っていた。
背後から扉が開く音が聞こえる。
給仕がまた、食事を運びに来たのだろうか。そう思って、窓の向こうに目を遣ったまま声を発した。
「配膳は要りませんよ、勿体ないので下げてください」
「……馬鹿。俺だよ」
声のする方へ振り返ると、薄い笑みを浮かべる男が立っていた。
「仕事、もう終わったんだ」
「ああ」
重たいだけの装束を脱ぎ捨てた男は傍にあるソファに放り捨て、ゆったりと窓際に歩み寄ってくる。
「変わったことはなかったか」
「何も。退屈すぎて、どうにかなりそうだった」
「はは」
そして彼は何でもないように、自分の隣に腰掛けた。ベッドから僅かに沈んで、きしりと音が鳴る。
「食事は摂ったか」
「動かないからお腹が空かなくて」
「風呂は」
「今日はまだ……」
「あーもう。洗面台に入浴剤を置いてただろ」
「そういえば今日、鏡を見てない」
「……」
沈黙が落ちる。同時に痛いくらいの視線を感じる。首を傾げると、こちらを睨め付ける紫が爛々と光っていた。
「な、なに?」
「入るぞ、風呂」
えっ。何。なに。どうして?
しきりに質問を投げつけても、彼は見向きもしてくれない。
腕を力いっぱい引かれて、誘導されるままに立ち上がると、辿り着いたのは脱衣場だった。洗面台の脇には私物の歯ブラシや髭剃りに並んで、入浴剤のケースが置かれてある。
「わ、なに、ルルーシュ」
呆気に取られているうちに、今度は服を脱がしにかかろうとする。首元まで留まったボタンを丁寧に外され、寝間着のズボンを下ろされた。突然外気に触れさせられた肌は寒さで鳥肌が立つ。ちらりと目の前の表情を伺ったが、何故だかそれは真剣そのものだった。
「勘違いするな。自分で脱げ」
「えっ、あ、はい」
それだけ口にすると男はそっぽを向いて、浴室に足を踏み入れていた。浴槽に湯を貯めて、暖房のスイッチを入れる。バスタオルとシャンプー、ボディソープを棚から引っ張り出す。そうやって彼は何も言わず、ひととおりの入浴の準備を淡々と進めている。
「……」
自分はとうとう言葉を失くして、黙って脱衣する他なかった。脱いだ物を纏めて籠に入れると、彼もそれに倣って服を脱ぎ始めた。その動作に滞りも躊躇いもない。公衆浴場にでも訪れた心地だ。
ルルーシュは張られた湯船の中へ、色のついた丸い何かを入れた。
「バスボムだよ」
「……?」
それは湯の中で泡を立たせながら形を変える。そして透明な液体が色付いてゆく。まるで魔法でも見ているかのようだ。
そもそもだ。この浴室の湯船に、湯が満たされている光景は初めて見る。自分は徹底したシャワー派であり、湯船に浸かることはここ数年していないのだ。
そこそこ大きめに作られた真っ白の浴槽は、ここだけのオーダーメイドらしい。だから大の男が悠々と脚を伸ばしても余りあるくらい、広めに設計されている。
しかし当然ながら、設計段階では一人で使用することを前提にしている。成人男性と遜色ない体付きをした二人が同時に脚を伸ばすとなると、それはそれは、物理的に不都合が生じるだろう。火を見るより明らかだ。
「湯加減はどうだ」
「丁度良いよ」
手のひらで掬った湯は赤紫色に淡く濁り、微かに芳しい花の香りが鼻孔を擽る。彼いわく、血行促進と疲労緩和に効果があるという。バスボムが溶け切った湯船は鮮やかなラベンダー色に染まり、目にも優しい。
「蹴るな」
「蹴ってないって」
「今のは明らかにわざとだ」
「なわけないだろ」
浴槽の狭ささえ気にしなければ、入浴自体を満喫することは出来た。
ルルーシュと二人で向かい合って、伸ばしきれない脚を軽く折り畳み、そんな小競り合いを繰り返していた。なんせ脚を少し組み替えようとしただけで膝がぶつかり、相手の脛を蹴り上げてしまう始末なのだ。
「そもそもルルーシュが二人で入ろうって言い出すから」
「図体が無駄にでかいスザクが悪い」
「上背は君のほうが大きい」
「足のサイズはお前のほう、が……!?」
彼が口を開いた瞬間、水面を手のひらで掬って、そのまま顔面に向かってぶつけてやった。
暫く彼は呆けた顔をしていたが、徐々に何が起こったか理解したのだろう。唇を横に引き結んで、眉間に皺を寄せる。上目で見つめられたが、さして迫力はない。
「やっぱり鈍臭いなルルーシュ……っわ!」
目前に飛び込んできた水飛沫に、体の反応は追いつかなかった。盛大に頭から濡らされた。湯船に居るのにびしょ濡れだ。
ぽつぽつと前髪から滴る湯水を見て、彼は可笑しそうに笑っている。水面を弾いたらしい、右手が揺れていた。
「出たよ。負けず嫌いの悪い癖」
「お前が人のこと言えるか」
両目がじと、と睨みをきかせて、唇が尖る。その子供っぽい仕草が不釣り合いで、わざとらしくて、彼らしくない。
「はは、おかしなルルーシュ」
湯煙越しに見えた表情は年相応のあどけなさが残っていた。額に張り付く前髪から水滴が伝い落ちる。
「スザクの笑った顔、久しぶりに見た」
「……そう、かな」
「そうだよ」
どこか寂しそうな声音が浴室に響いて、でも返す言葉は見当たらなかった。
軽口を叩き合うのも、笑った顔や怒った顔を見るのも見せるのも、いつぶりなのだろう。
毎日のように行動を共にしていたのに、自分の記憶にあるルルーシュはどこか寂しく、悲しげで、迷子のようだった。
それもそのはずかもしれない。日中は激務に追われて、仕事が終われば禄に会話することもせず、自分は部屋に籠もってばかり居た。自分だけじゃなく、ルルーシュの気持ちも蔑ろにしていた。まともに休眠を取ろうとしない自分を心配してくれていたが、本当の彼は、自分とこうして時間を共有したかっただけなのかもしれない。
しかしルルーシュは一番大事にしたいこと、自分の欲求などは決して口にしようとしない。いつだって自身のことは二の次、三の次だ。心配している体を装って気にかけては、我儘を言わない。
ちらりと目が合う。交錯する視線に心臓が跳ねる。長い脚が揺れて水面に波紋が浮かぶ。彼は気まずそうに瞳を揺らしていた。
「気を遣わせてごめん。有難う」
「なんだ突然改まって」
きょとんとした表情を作るルルーシュに、自分の気持ちをおもむろに吐露した。
もう取り繕わず、素直に打ち明けよう。これまで抱いていた薄暗い、後ろめたい感情。情けない本性。脆く弱い覚悟。醜い人間性。堰を切ったように溢れ出るのは後悔の念ばかりだった。
「いいんだ、もう。僕のせいでルルーシュが気を揉む必要はない」
「……」
「テレビ、昼間観たよ。演説格好良かった」
ルルーシュの目を直視できなくて、俯いた。前髪から垂れる水滴がまるで涙のように流れて、顎の下へと伝い落ちる。
彼は何も言わない。どんな表情をしているのか、気になっても確認する勇気はない。
「ジェレミアさんも格好良かったなあ。……君の隣に立ってる姿、すっごく頼もしくてさ。それこそ僕なんか、よりも……」
「……」
「ルルーシュの隣にはずっと、僕が立っていたかった。でも僕より相応しい人はたくさん居てる。少なくとも僕じゃない誰かが、君の騎士に選ばれるべきだ」
「おい、何の話をしている?」
目の前の腕が揺れて差し伸ばされたが、やんわりと退けた。同情されるのは辛い。可哀想な奴だと思われるのは悔しい。たとえそれが事実だとしても、そういう目で見られることは耐え難い屈辱だった。だから顔を合わせる気概はなかった。
俯いた頬からぽつぽつと水滴が落ちて、湯船に波紋を生む。瞬きをすると溢れる涙が止め処なく落ちていって、どうしようもなかった。それを制御する術は持たない。
「言われなくても分かってるよ。ルルーシュの騎士に選ばれるべきは僕なんか、枢木スザクじゃないって」
「誰がいつ、そんなことを言った?」
「言われるというか、薄々、感じてたよ。……最近僕を見るルルーシュの目はちょっと怖くて」
「……」
言葉にするとそれが現実味を帯びて、胸が痛かった。
でも言わねばならない。いつまでもこうして、ルルーシュの脇に控えるお荷物になりたくない。迷惑をかけたくない。彼に相応しい人を押し退けてまで、隣に居たくない。
「なんであんな学も才もない、卑しい身分の男を騎士にしたんだって言われてるのも知ってるよ。僕のせいで君が悪く言われるのは嫌なんだ。だから……」
「……言いたいことはそれだけか?」
彼は声を低くして再度問うた。
「ルルーシュの、殿下の隣に立つ者として恥ずかしくないように、勉強も仕事も頑張った。……頑張ろうとしたけど、一朝一夕じゃどうにもならないんだ。僕にはなれない。それこそジェレミアさんみたいな、教養があって仕事もできる、そんな人のほうが相応しいって……」
剥き出しの気持ちだった。これ以上ない抜き身の本音は声が震えて、うまく届けられているか、自信がない。
それを良かれと思った彼に与えられた休暇は、自分の心を打ちのめす最後の追い打ちとなった。テレビ画面に映る皇子は立派に責務を果たし、評価も名声も得ようとしている。自分とは違う世界にいると思った。同じ世界に自分が足を踏み入れようなど、厚かましい考えだ。とんだ浅知恵だ。悪い心だ。
「じゃあなんでお前、いま、泣いてるんだ」
「……そ、れは」
自分の頬に手を当てると、いくつもの涙が皮膚を伝い流れていた。
「だ、だって、ルルーシュの隣に立つのは自分が……自分じゃないと嫌で、悔しいんだ。もう、自分が嫌になる……」
視界が濁って不透明になる。目の奥が熱い。嗚咽が止まらない。目から滴る水が収まらない。
「嫌だよルルーシュ……僕以外の人を、騎士にしないで」
「……誰もスザクに辞めろなんて言ってないよ」
その言葉に思わず顔を上げると、同時に体を引き寄せられた。ぬくい皮膚と平らな胸が、濡れて冷たくなった頬を暖める。湿った髪の毛を細い手指に掻き混ぜられる。その動作は頭を撫でるつもりだったんだと、そう気づいたのはすぐ後のことだった。
ラベンダー色の水面が跳ねて波がうねる。花の香りがふわりと舞って息を吸った。
「殴ってやるのは後だ」
「……」
「俺が半端な覚悟でお前を選ばない。誰にでも務まるわけないだろ。俺はそこまで自分を安売りしない」
「……」
「お前がいいんだよ、スザク」
輪郭を支えられ顔を上げると、真っ直ぐこちらを見据えるアメジストが優しく色づき、輝いているのがよく見えた。虹彩に映る自分の顔はどうしようもないくらい情けなくて。それに比べてルルーシュは、穏やかで美しい笑みを浮かべていた。
お前がいい。
その言葉は何よりも代え難く、今の自分が最も欲しかった音だ。
誰でもいいわけじゃない。頭がよく優秀な成績を残す兵士は掃いて捨てるほど居る。ジェレミアのような稀に見る忠義者も居る。
しかしそれらを差し置いてでも、自分がいい。ルルーシュはそう告白した。経歴や血統、成績、出自。どれも自慢できるものじゃないし、卑しい身分であることには違いない。しかし、そんなハンディキャップを差し引いても余り有るのだと、ルルーシュはしきりに言う。
人は彼を時代の寵児、あるいは王の器を宿す逸材、国の宝と持て囃す。そんな人間にお前しかいないのだと、お前がいいんだと熱烈に告げられて、嬉しくないはずがない。自分が信じる、最も尊敬する相手にそうまで言わせて、どうしようもなく幸せだった。この瞬間だけ、自分は世界一の果報者だった。
二人は逆上せそうになる体を一旦浴室の外へ移し、ひとまずゆっくり話し合うべきだという認識で合意した。
風呂から上がって身支度を整え、空きっ腹に物を詰め込み、そして気がつけば時刻は夜の九時を回っていた。そして明日の予定を一旦頭の中で整理したルルーシュは、今から話し合いするのは止めておくべきだと主張した。明日は早朝から軍事訓練の視察があり、海岸線にある空軍基地にまで出向かねばならないのだ。自分もルルーシュの意見を尊重し、時間の合うタイミングを見つけようということで話は纏まった。
ブリタニア大陸最東端の埋立地には、国内に複数ある空軍基地のうちのひとつが存在する。他の基地に比べ最も広い敷地面積を有し、戦闘機の発着は勿論、可翔式ナイトメアフレームの飛行テストが行われることもある。
そこは複数の司令塔が建てられ、それぞれに最新鋭のレーダーが備え付けられている。宇宙空間へ打ち上げられたブリタニア所有の人工衛星と合わせ、いつ如何なる時でも敵の襲来に対し捕捉できるよう、監視体制も万全だ。まさに大陸の最終防衛ラインとして、その機能を果たしている。
此度の視察の主目的は訓練現場の実情把握だが、それ以外にも皇子が直接出向かねばならない理由があった。
基地の内陸部に建てられた倉庫には食糧や武器の貯蔵がなされ、戦闘機の格納庫も隣接している。訓練用と実戦用で合わせると膨大な数の戦闘機を常に配置しており、ここが基地における戦局の要と言えるだろう。
その中のひとつに、最新鋭の無人戦闘機が配備されたという。先日の騒動直後というタイミングもあり、皇子は早速実物を見学しに来たのだ。
「ブリタニア国内で開発されました最新の無人機です。最大加速度の上昇、耐久力は勿論ですが、コンピュータに送られてくるGPS情報と実在地の誤差はほぼゼロ。遠隔による射撃でも高い有用性を誇るスペックへと進化致しました」
案内役の基地司令官が、その鉄の塊について流暢に説明をする。
現在の軍事産業において旬なトレンドといえば、無人兵器というキーワードだろう。人間と人間が戦地で衝突する戦はもはや前時代的で、現代は遠隔操作されたロボット兵器が相手の陣地をいかに焼き払い、多大な損害を与えられるかが鍵なのだ。 無人兵器の走り役であるドローンに爆弾を積むところから始まり、自動運転の戦車が開発され、最近では無人戦闘機の需要が高まっていると聞く。まさに今回の話は渡りに船であろう。
「ブリタニアはこれまで、そして今現在も、ナイトメアフレームの開発に注力しております。が、やはり次世代はこういった無人機が戦場の主力になっていくのだと、私は確信しています」
「理由を尋ねても?」
「最たるは軍全体の人員確保でしょう。兵士の育成には莫大な税金が投入されている。キャリアを積んだ優秀な兵士は技術もあり重宝しますが、前時代的戦法では貴重な兵力を使い捨てるばかりです」
「しかし兵器の無人化が進むと戦争が長引くことにならないか? 兵士不足という分かりやすい指標がきっかけで終結した例もあったが」
「だからこそ前線は高火力・高耐久の軍事兵器が必要となります。全面的な無人戦争はまだ先になるでしょうね。ブリタニアはとくに、ナイトメアフレームの依存度が高過ぎますゆえ」
「その依存度をどうコントロールし、抑えていくかが課題なんだが」
「とにかく実戦に投入していき、稼働率を落とすしかないんでしょう」
「……」
どこか納得いかない顔つきを浮かべるルルーシュはそうか、とだけ答え、全長数メートルにもなる戦闘機の外周をゆっくり歩いた。
戦争の無人化というのは現代以前より論じられてきた。集団よりも個を重視する社会理念が世界全体に築かれつつある中、この傾向は前述の理念に基づけば非常に合理的だ。
自軍の兵士が誰一人死なず勝てるなら、どこの将軍だってそうしたいに決まってる。兵士だって自分の命も大事にしたい。少ない労力、少ない犠牲で済むなら尚のことだ。
「枢木卿はいかがでしょう。ナイトメアフレームのエースパイロットとして、ブリタニア軍を率いる貴方の意見を伺いたい」
案内役の男は皇子の後ろを歩く自分に問うた。
「時代の流れがそうなのでしたら、ブリタニア軍も変わっていかないと、いけないんでしょう」
「ええ」
「しかし……」
案内役は眉を少し動かし、釈然といかない表情を浮かべる。しかし敢えて気には留めず、言葉を続ける。
「精神論を唱えるわけでありませんが……戦局を変えることができるのは、結局、その場に立つ人間だけだと思います。戦争に勝つのは決して数が多いほうとは限らないという理由が、そこにある」
「随分と曖昧で、抽象的なご意見だ」
嫌味っぽく所感を述べた男は自分を観察するようにじっと見つめてくる。そして彼は持論を展開した。
「ブリタニアはナイトメアフレームに頼る戦法で大成した。しかし人型ロボットではどうにもならない場面がこれから出てきてもおかしくない。対立国はナイトメアへの対策を確実に練っているのですよ!」
「サクラダイト貿易事業に関する世界条約が先日緩和されましたから、軍事バランスはさらに混迷を極めるでしょうね。それでも……」
鈍色に光る大きな体躯を見上げて、それからこう話した。
「私は最後の一人になるまでナイトメアフレームのパイロットとして戦場に立ちます。それが私に与えられた使命ですから」
その瞬間、場に沈黙が落ちた。案内役の彼は目を瞬かせ、皇子は俄に笑いを堪えるような、微妙な表情を浮かべている。
自分は自分にできることをするまでだ。それが求められている職務であり責任であり、ここに居てもいいという赦しだ。
皇子は暫く言葉を選ぶように唇を動かしていた。そして漸く、そこから言葉が紡がれる。それは自分の言いたかったことを的確に、要点を押さえた文脈だった。
「……戦局、場の流れを掌握するのはいつだって生身の人間であるんでしょう。気迫、プレッシャー、恐怖……。そうした障壁を超えた者は時として、我々統率側の予想を上回る働きを見せる。司令官もそうした経験に心当たりはないか?」
発言を受けた男は明るい表情を見せ、皇子と自分に向き直った。
「ああ成程……! 枢木卿のご主張がようやく腑に落ちました。機運を手にするのは心の宿らないロボットでなく、我々人間側であり……そうした者たちが自軍に勝利をもたらすと!」
理解を示した男は自分に非礼を詫びた。言葉足らずな自分にも非はあったはずなのに。気まずい心地で皇子の顔を盗み見ると、もっと自信を持てと言わんばかりに微笑まれたから、それ以上の言葉は持てなかった。
その日の夜。早速昨晩の仕切り直しと称して、ルルーシュを自室に招いた。
食事と風呂は先に済ませた。明日の仕事の準備も終えた。スケジュールは抜け目なく確認してある。
二人してリビングルームのソファに、隣合って座った。彼は風呂上がりのようで、仄かな石鹸とシャンプーの匂いを無防備に漂わせている。血色の良い頬が髪の毛の隙間からちらちらと見えて、やけに網膜に焼き付いた。
「まず前提として、俺はお前を辞めさせる気はない」
「ああ」
「そしてお前も、自ら望んで辞める気はない」
「そうだ」
ローテーブルに置かれたランタンの明かりだけが、この室内の唯一の光源だ。淡い光が頬の輪郭を包んで浮かび上がらせる。その色と形が、漠然とした不安が募る心を解いて溶かしていく。優しい色だった。紫の目に映り込むオレンジ色を追いかけたい。心の拠り所にしたい。
「どうして辞めたいと思ったんだ」
「そ、れは」
「……」
短い沈黙が続いた。膝の上で組んだ手が震える。
「……ゆっくりでいい。落ち着いて話してくれ」
言葉がかけられると同時に手が重なった。白くて柔らかくて温かい手。緊張が解れていく。
「有難う」
柔らかな声が重なって、空気に溶けた。
長年蓄積されて地層のように折り重なった、怨嗟と慟哭に塗れた生涯を、自分はルルーシュに語り聞かせた。
なぜ皇子はブリタニア貴族出身の軍人ではなく、ましてや名誉人を専任騎士に選ばれたんだ?
純血どころか元日本人の枢木卿はこの宮殿を出入りするに値しないだろう!
直接は言われはしないが、時折耳にする雑音。陰口。嫉妬。それらは全て日本出身という出自に起因するものであり、もはや自分の努力ではひっくり返らない問題だ。逆立ちしたってブリタニア人になれやしない。制度上ブリタニアに国籍を移したところで名誉人めが、と唾を吐かれる。言わずとも明らかなことだ。
それはまだいい。何故なら自分にしか向かわない悪感情だからだ。誰にも迷惑はかからないし、言わせておけばいい。
そういう奴らには、積んだ戦果を見せつけて黙らせておけばいい。自分はただ目の前のやることに集中するのみだ。武勲を打ち立て勝利を収め、戦場で指揮を執り、争いを諫める。ブリタニア本国軍部は徹底した実力主義の名の元に組織されているから、いずれは評価される時が来る。そう馬鹿正直に信じて、ここまでやってきた。けれど。
「国民の支持は得られても、宮廷内の……とくに俺の皇位継承権を僻む連中の顔色はますます悪くなった」
「ああ。僕をダシにして君をこき下ろそうとする」
ブリタニア帝政が崩壊し、植民地は解放されナンバーズという身分差別の概念は葬られた。新時代に向けて躍進する革命派を支持する声は大きいが、官僚や貴族からの目は冷たい。
シュナイゼルが率いるルルーシュ側が次に内政へ着手するとなれば、恐らく特権階級の廃止は確実であろうと言われている。勝者が敗者を虐げる世界ではなく皆が平等に暮らせる世界に。そういう謳い文句を掲げて奔走する彼らに、貴族階級の連中は警戒心を強めている。
事実、身分差別の是正はブリタニア国内の今後の課題として挙げられている。国家間での隔たりを無くし外交レベルで信頼関係を築くと同時に、国内で広がる貧富や身分格差の溝を埋めることも重要だ。
嫉妬と怨嗟が渦巻く貴族階級の間では専ら、皇子に対する悪評が付き纏った。とくに特権階級撤廃の働きかけは連中の神経を逆撫でするに十分だった。元名誉人の騎士という歪んだ存在は、彼らにとってちょうどよい批判材料だったのだ。
膝の上で組まれた指が忙しなく動く。落ち着きのない仕草は自分の今の心情をそのまま表しているようで。
「なんでここに居ることが許されてるのか、分からなくなった。情けなくて……」
「俺を守るためだろ」
「本質はそうだけど……」
どれだけ末席であろうとブリタニア家に生まれた子供は皆、幼い頃から帝王学は必ず学ばされる。ルルーシュもそうだったはずだ。それ以外にも英才教育とやらを叩き込まれ、どこに出しても恥ずかしくない皇族の資質を備えた人間に育てさせられる。
そして恐らく、貴族や上級軍人も似たような教育方針を施されるはずだ。誰しも学識を身に着けたうえで武を習得する。優れた体術センスは知能ある人間にしか宿らないという考え方が根底にあるのだろう。文武両道は会得して当然なのだ。
生き恥を晒すとはまさにこのことで。日々自分の能力の無さに、無教養さに、愚鈍さに、呆れて溜息を吐くのはこれが何度目か。
見劣りすると邪険にされ、自分だけが傷つくならまだ良いとしよう。でもそれを話をねたに、ルルーシュまで悪く言われるのは耐えられなかった。自分のせいで悪く言われる筋合いはないはずだが、事実彼は批判の的としてたびたび晒される。
「もう自分を貶すのは止めてくれ。どうしたら分かってくれる」
「ルルーシュ」
「俺にはもうお前しか居ないのに……」
手のひらを重ねられ、強く握られた。揺れる紫は俯いたままじっと足元を見つめている。
テレビの中に居た人物とは大違いだ。鋭い眼光と凛々しい柳眉が野次を封殺し、言葉を紡ぐ声は清澄としていて、でも伸びやかで力強い。伸びた背筋と確固たる足取り、ぴんと伸びた指先と。視線は少し動かすだけで緊張感が漂うし、ちょっとした仕草に人々の注目は集まる。男は大衆の興味関心を思うままに操っていた。
しかし今はどうだ。自分の気持ちが言葉に纏まらないのか、唇をしきりに震わせて、何かの機会を窺うように視線を彷徨わせている。自信なく頼りなさげに丸まった背中は痛いほど弱々しい。細く心許ない体の輪郭は今にも崩れそうだ。
「なあ、セックスしよう……」
「……えっ!?」
言葉の意味が一瞬分からず、大声で聞き返してしまった。真下に見える顔は僅かに紅潮している。触れていた手は仄かに温かい。
そんなことよりもだ。何の脈絡もない台詞に困惑させられた。頭の中は疑問符でいっぱいだ。
「声が大きい」
「いや、だって……」
ルルーシュはおもむろに手を解いて、着ていたシャツのボタンを上から順番に外していった。布の隙間から薄い胸板が見えて、シャツがはだける。淡い肌色が薄暗い室内で露わになり外気に晒される。
「触ってくれ」
「なんで」
「いいから」
「良くないよ」
部屋に置かれた大時計がごおん、ごおんと鈍い鐘の音を鳴らした。夜の九時を報せるその音に、ルルーシュは紛れるくらい小さな声で早く、と溢す。
「ここを、こうして」
「……わ」
右手を掬われ、平らな胸元に宛がわれる。皮膚の下では心臓の音が小さくとくとくと拍動しており、手のひら越しにその健気な鼓動が伝わる。物欲しげな瞳が揺れて、もっと、と強請るような声が漏れていた。
「んっ」
「胸、好き?」
「うん……」
薄茶色の粒を指先で抓ると、肩を揺らして目を蕩けさせていた。その顔をもっと見せてほしくて、長い襟足に隠れた後頭部に手を這わす。自然と上を向いた顔は熱に浮かされて、誘うような目つきでこちらを見ていた。
吸い寄せられるように口づけると、ルルーシュも応えてくれた。唇を食むと鼻から息を漏らして、擽ったそうに身悶える。同時に胸の突起を親指で押し潰すと、喉の奥からくぐもった声が聞こえた。
「っふ、うう、う」
「……ん」
「う、っン……」
シャツの隙間から指を差し入れ、滑らかな感触を堪能した。どこもかしこも綺麗で清潔で、なのに厭らしい。触れる場所すべてが性感帯になったみたいに、彼は何をされても大なり小なり反応を返してくれる。そのことがとてつもなく嬉しく、男冥利に尽きた。
ルルーシュは接吻の合間にもっと、もっと、と声を漏らす。何をされたくて、どうなりたくて、何が欲しいか。その言葉に教わるまま自分は彼の体に触れて、味わった。
「俺もスザクに、言わなきゃいけないことがあるんだ」
「狡いな……教えてよ」
耳元で囁くと、ルルーシュは腰を揺らして熱い息を漏らす。艶やかな吐息は湿った空気をさらに色濃くした。
「最近のスザクを見るたび、騎士に選んだのは間違いだったんじゃないかって、思うことがあった」
「……は」
蠢いていた指はぴたりと止まった。呼吸がひどくし辛い。心臓がばくばくと、嫌な音を立てて暴れ出す。
「……今ここにナイフがあったら、首を掻き切ってた」
「まだ死ぬなよ」
ルルーシュは自分の体にしどけなく凭れ掛かり、首に腕を回した。訝しく顰められた表情を見据えて、なおも彼は声を発する。
「ずっと考えていたんだ。お前をこの世界に引き込んで、縛り付けているのは俺だ」
「そんなこと、」
どうして君がそんなことを言うんだ。
そう言いかけた唇は音を出せず、彼の口の中で溶けた。唇をゆったりを離して、さらにルルーシュは話を続ける。
「スザクが得体の知れない悪意に晒されるたび、嫌なんだ。もっと俺がしっかりしなきゃいけないのに。全部跳ね除けれらるくらい、強い力が欲しい」
「ルルーシュが気に病むことなんて」
「誰かさんがさ。顔から笑顔がどんどん消えて、自分の心配もできないくらい頓着しなくなっていくんだ……。スザク、お前は気づいてたか?」
目を見合わせて尋ねられた。素直に首を横に振ると、彼は優しく微笑んでいた。
「俺はそれがすごく嫌で……本当は後悔してた。ごめん」
傍にあった腕が持ち上がって、シャツの襟を掴んだ。何もせずにその動向を視線で追っていると、細い指がボタンを外していく。小さく丸い爪がぷち、ぷち、と丁寧に衣服を乱してゆく。露わにされた肌はランタンの光に当てられ、ぼんやりと影を作っていた。
彼は目を伏せながら皮膚の上に唇を当て、舌で舐めた。唇をずらしながらちゅくちゅくと音を鳴らし、指先で乳首をなぞられる。どうということはないのに、拙い仕草はやけに煽情的だ。
ルルーシュからの奉仕は恐らく初めてだ。彼も勝手が分からないのか、たまに空いた片手が惑うように宙を彷徨う。ややあって太腿に置かれた手のひらは、衣服の上から熱を煽るように撫で上げる。たどたどしい舌の動きがもどかしく、どうかしてしまいそうになった。
「元を辿れば俺のせいだ。スザクに俺は枷をかけた。お前がそれを望もうと望むまいと、課せられた責任は死んでも付き纏う」
「つまりどっち? ルルーシュは僕に騎士を降りてほしいの?」
「断じて違う。俺はお前しか居ない」
「まあ僕もルルーシュ以外に仕えたくないな。ブリタニアに忠誠を誓ってるわけじゃないし」
「だろうな」
皮膚に息を吹きかけるように、ルルーシュは薄く笑った。
自分はそもそもブリタニアに忠誠を誓う敬虔で信心深い軍人ではない。ブリタニア軍に入隊した動機は、当時の自分に残された道がそれしかなかっただけだ。実父を殺め、帝国に日本人としての尊厳を踏みにじられ、古くから続く名家としての威厳も失墜した。あの家に自分が居られるはずもなく、とはいえただの子供だったから後ろ楯や拠り所はない。無条件で働けるのであれば、どんな劣悪な環境でも良かった。生かされているだけの肉の器に意思は存在しない。
ランスロットのパイロットに抜擢され、戦果を上げ、力を認められ。ブリタニアという国家の深部に自分が組み込まれてゆくたび、階位が上がるたび、制度の一部に取り込まれてゆくたび、妙な違和感を覚えるのだ。膝を付き頭を垂れるのは決してこの国の為じゃない。
ルルーシュに使役されたいと願う自分が居る。求められたいと思う。国に生かされていただけの、屍とさして変わらない、無意味な人生を送っていた自分に、彼は生きる理由と目的を与えてくれた。そのうち、自分の生きる理由そのものがルルーシュになっていた。
「こないだ休ませたのはスザクがもっと自分を省みてくれたらと……そういう時間が必要だと思ったからだ。でも逆効果だったらしいな」
「とうとうこの時が、ついに来たかってね。断頭台に上がるのを待つ気分だった」
色気もへったくれもない会話だ。雰囲気はどこか淀んでいて、それでもなおルルーシュは愛撫を施してくる。腹部を撫でられるとどうにも擽ったく、気恥ずかしさも相まって、思わず笑い声が漏れた。
ルルーシュの手が下腹部へ辿り着いて、股ぐらを触られた。
何となくそういうことをするんだと頭では分かっていたものの、体はまだ追いついていなかった。色事めいた気分に浸れる余裕もない。心情的にはまだ引っ掛かりやしこりが残っていて、消化不良気味だ。
騎士に選んだことを後悔していた。その言葉が胸に突き刺さって、何も手につかない。
「……勃ってないなんて、失礼な奴だ」
「こんな話をしながらどうしろって言うんだ」
まだ柔らかいままの性器を布の上からなぞられた。兆す気配はない。ルルーシュはとても不服そうだ。
だから今度は自分から腕を伸ばして、ルルーシュの体の線をなぞってみる。胸から腹にかけて形を覚えるみたいに何度も手を往復させ、下半身に触れる。股間を揉むと伝わる、布越しのその感触に思わずあれ? と声を出してしまった。
「……ルルーシュは勃ってたんだ」
「その言い方やめろ」
ちょっと拗ねたみたいにそっぽを向いて、顔を赤らめている。なんで自分だけ、と悪態をつきたい面持ちだ。
ルルーシュにも自分と同じ、必要最低限の性欲は備わっている。
頭では理解しつつも、そのあからさまな兆しを見せられるたび、心は歓喜するのだ。汚くて見苦しくて卑しいこの欲を彼も持て余している。それを実感するたび、薄暗い喜びと汚い好奇心に襲われる。
他所を向いた顔を前に向かせて、唇を吸った。同時に膨らみかけた股を撫でて、その形がはっきりするまで何度も手のひらで確かめた。下着の内側で大きくなって存在を主張する、ルルーシュの厭らしい部分。雄の象徴。気高く可憐な皇子は今や、自分の手の中ではしたない劣情を育てている。
「あっう、う」
手のひらを下着の内側に差し入れて、直接熱源を握った。湿った布の中はやけに狭くて暑苦しい。薄い下生えを撫でて擽ると、恥ずかしそうに身を捩らせた。
「やっあ、ん……」
「嫌なわけないだろう」
「だ、だって」
「うん?」
だからなんで俺ばっかり。
涙声で発せられた言葉に思わず首を傾げていると、ルルーシュはするりと体をずらして、そろそろと腕を伸ばしてくる。その腕は太腿のあたりを撫でて、やがて股ぐらに到達すると、おもむろに下衣を引っ張ってくるのだ。
「ルルーシュ?」
行動の意図が読めず困惑していると、ルルーシュは敢えて何も言わず体を屈ませ、顔をそこへ近づけてきた。前のめりに垂れた髪の毛を耳にかけながら、確実に着衣を乱してゆく。やがて寛げた下半身の、下着からまろび出た性器に触れられる。
そこまでされると否が応でもルルーシュのやろうとしていることが見えてきて、嗚呼どうして、と嘆きたくなった。君がそこまでする必要ないのに。躊躇いがちに開かれた小さな唇がゆっくりと先端に触れて、その感触と味を確かめようとする。
ふにふにと唇を押し当てられてから、やがて舌が伸ばされる。湿った粘膜が鈴口の窪みをなぞって、それからとうとう、彼の口内に招かれた。
「は、ちょっと、あ」
情けない声を出しながら、自分はその光景を眺めることしか出来なかった。ルルーシュの行動を制しようとした右手は宙を暫く彷徨ったあと、彼の後頭部を支えるだけに終始するのだ。
分かりやすく不慣れな奉仕の姿に、凪いでいた心がぐつぐつと煮えたぎってくる。じゅる、と唾液の啜る音に鼓膜が焼け切れた。温くて柔らかいものに包まれて、背筋が熱くなる。
「ルルーシュ、ん」
「……ふ」
耳にかけてあった黒の毛束がぱらぱらと落ちて、頬にかかる。それを指で掬ってかき上げると、涎を垂らしながら陰茎を舐めしゃぶる唇がよく見えた。ゆっくり頭が上下しながら彼の口内を行き来する様はたいそう目に毒で、悪い夢でもみている心地になる。
「も、もっと、咥えてみて」
「ん……」
馬鹿みたいに強請ると、ルルーシュは惑うように睫毛を揺らしながら、喉奥までそれを受け入れた。熱く絡み付いてくる感触が何とも言えず気持ちが良い。思わず目下の頭を撫でてやると、露出していた耳元がほんのり朱に染まった。
「はあ、すご……」
「う……」
粘っこい水音が鳴り始め、すっかりぱんぱんに膨らんだ性器を、彼は拙くも愛撫し続けた。飲み込めなかった体液などが口の端から漏れて、根本に添えられた手指を濡らしてゆく。ぐちゅ、と立てられた下品な音も彼には聞こえていないのか、構う様子もなく口淫は続けられる。
「もうじゅうぶん、すごく可愛かった、上手だよ、有難う」
「……」
唇から伸びた糸を指で断ち切って、濡れそぼった表面を拭ってやる。擽ったそうに目を細める仕草が愛らしい。
健気で純粋で可愛くて、だからルルーシュは奉仕という手を使って熱を高めてくれたのだろう。なんで自分ばっかり、という台詞は昂ぶった体のことを言っていたらしい。
「ベッド、行こっか」
「ん……」
それならもう大丈夫だ。彼に急かされるままに熱に浮かされたこの体は、本懐を成し得るだけのことしか考えられない。官能的な紫の眼差しは情欲を煽って止まないのである。
身に着けていたものをソファに置いて、テーブルの明かりを消して、開いていたカーテンを閉じた。二人の夜は密やかに、誰も知らないところで始まろうとしている。
もう余すことなく明け渡し、渡されたふたつの体は夜の帳が下りると同時に重なろうとしていた。
この手指に全てを委ねる覚悟をルルーシュはとっくに決めていたようで、徹頭徹尾穏やかに、緩やかに性感を拾い上げていた。抵抗の素振りなんてまるで見せない。それは自分が彼に心の奥深く、心臓の真ん中まで許されている何よりの証明だ。こんなにも分かりやすい愛情表現は他に知らない。
「もっと……」
「うん」
熱に浮かされ暗闇に溶ける声音は剥き出しの本音をそのまま映し出し、泣き過ぎて腫れぼったくなった眼尻はつるつると雫を溢した。
素直な言葉はそれだけで体を熱くし、血が燃え滾る。欲しがられれば思うままに与えて、欲しい分だけ彼の身体を貪った。
自分はそれを許されているから。愛されているから。ここに居ることも、身に余る地位や名誉、与えられた装飾品で身を包むこともきっと、彼に与えられた愛が形となって、自分を着飾らせるからだ。
だとすればそれは尊いことで、自分は無碍にできない。絶望感に似た諦念に身を焦がす自分を理解しようとしてくれた。
ルルーシュはこの世で自分を認めてくれる、愛してくれる唯一の人だ。
頬に触れる生ぬるい手の温度と泣き腫らした目。噛み跡が残る首筋と、か細い呼吸。全部自分のために用意された。差し出された。
だから自分はこれをよすがとすることにした。
ベッドから起き上がって、カーテンを開けた。眩い朝日が窓から溢れてシーツの海を優しく照らす。青い空が目に入って、呆けるようにその長閑な景色を眺めていた。
こうしてベッドで眠って朝日を浴びるという行為を、生まれて初めて経験した気がする。なんとも呑気で平凡で平和な一日の始まりだろう。妙に澄み渡った心はのんびりした感想を抱かせる。
昨日まで燻り続けていた苛立ちや不安がすっきりと無くなって、その代わりに面映ゆさや悦びが胸に満ちていた。健全な精神は健全な肉体に宿るという言葉の意味が今なら成程、よく分かる。睡眠の効果は絶大である。
「ま、ぶしい……」
「ああ、ごめん」
布団の山からくぐもった声が聞こえて、僅かにそれは身じろぐ。自分とは打って変わって、向こうは随分調子が悪そうだ。
後ろを振り返って布団を動かすと、その中からゆっくりと頭を持ち上げる人物の顔が見えた。長い前髪に埋もれた額を掻き分けて、うろうろと視線を彷徨わせている。
「おはよう。元気?」
「……あまり」
声が掠れていて、血色は悪い。ひとまず冷蔵庫から新品のペットボトルを渡してやったあと、ベッドの端に折り畳まれていた上着を細い肩にかけた。部屋は空調がきいているものの、寝起きで素肌を晒すのは体に良くない。下着だけでも身につけたらどうだと促してやった。
「カーテンを閉めてくれ、眩しい」
「相変わらず朝は弱いんだな」
「うるさい。一体誰のせいで、こんな……」
「誘ったのはそっちだろ」
寝癖がついたままの髪の毛を包むように頭を撫でてやると、そっぽを向いて唇を尖らせていた。夜の気配を滲ませる赤い目尻が前髪の隙間からちらりと覗いて、目に悪い。気を逸らすつもりで話題を変えた。
「なんで昨日は急に誘ったの? そんな雰囲気じゃなかったのに」
「……肌を合わせたほうがお互い素直に、気持ちが伝わるかと思って」
「へえ?」
「……変な顔するな」
肌を合わせたほうが、お互い素直に。
そんな言葉が彼の口から出るとは露にも思わず、つい口元が緩んでしまった。拙くてまどっころしい愛撫や舌技の諸々は、いつもよりちょっぴり素直になったルルーシュの本心の顕れだったらしい。そうとは知らず、ただ煽られるままに煽られて焚き付けられた己の短絡さには呆れてしまう。
でもルルーシュの言うとおり、自分の心にも少し、素直になれたかもしれない。差し出された愛を見過ごせるわけもなく、彼が良いというならそれに縋っていたいと思う。何かに凭れかかったり依存することを極度に恐れていたのはたぶん、不安定な生活基盤に長く身を置きすぎていたからだ。そして、許されない罪を背負い続けて、見えない敵意に怯えていたからだ。
それらの障壁をルルーシュは理解して、乗り越える為に手を握ってくれた。まだ具体的な解決には至っていないけれど、明日を迎える為に前を向く勇気をくれた。
「……伝わったよ十分。今回のことは、僕らの今後の課題だ」
「ああ」
ベッドに腰掛けたまま素足を揺らすルルーシュは、僅かに口元に笑みを浮かべていた。自然光の優しい明かりが彼の背中を照らして、柔らかい輪郭を際立たせる。波打つ白いシーツに映える華奢な四肢は少し恥ずかしそうに縮こまって、それから細い腕が伸びてきた。
「この先も俺の隣に立ってくれるか」
骨が浮き上がる薄い手の甲を拾って、指先を絡め取った。貝殻のような繊細な爪に肌を撫でられる。
向けられた手の甲を口元に寄せた。温かくてなめらかな肌を、かさついた唇でなぞる。
「イエス、ユアハイネス」
顔を上げた先にあった紫の双眸は細められ、どこか泣きそうに見えた。
その時の声と表情は、この先ずっと忘れたくないと思う。
完