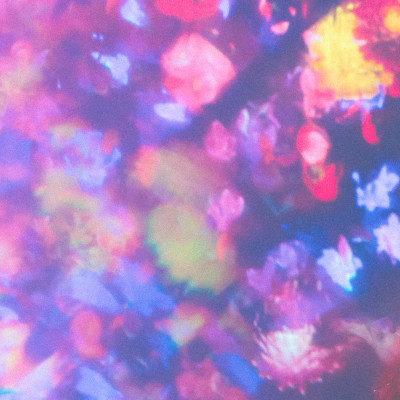
これをよすがとする 九話
内装の壁紙、床の絨毯、家具の採寸からカーテンの色まで、すべてオーダーメイドという拘りっぷりだった。一度凝り始めたら満足いくまで完璧に仕上げたくなるという、自分の悪い癖が如実に表れていた。
調度品の数々は自分の目で見て購入を決めた。寝台や棚といった実用品は"住人"の意見も取り入れつつ、やはり自分が主導で決定した。色も形も正直言って、自分の好みが全面に反映されている。
しかしそれは仕方ないことだった。なんせあの男と言えば、目利きは君のほうが優れているだろう? と肩を竦ませてばかりだったのだ。だからそんな彼の代わりに、内装フォームのレイアウトを考案した。してあげたのだ。
新築同然の部屋は来週から移り住むことが決定している人物の為に、わざわざ改築工事が施されたばかりだ。間仕切りの壁を抜いてワンルーム風に仕立て、ユニットバスの浴室はシャワーとトイレを別々に、いわゆるセパレート様式に変えた。
「殿下。こちらのクローゼットはどちらに」
「この事務机の横だ。ソファとテーブルはあちらに」
「畏まりました」
「テレビ台はどこに置きましょう」
「ソファで寛ぎながら観たいだろうから、あっちで」
配送業者に指示を出しながら、出来上がってゆく室内の景観をまじまじと眺めた。悪くない。むしろ完璧だ。映画の舞台セットよろしく、見事にそれらは調和していた。
我ながら中々、いや、手が付けられないほど浮かれているという自覚はあった。
次週からここに住む誰かの姿を想像するとしよう。この部屋に馴染む彼の様子を脳裏に描くたび、さすれば妥協は決して許されないと、何不自由なくここで暮らしてほしいと願ってしまう。あの狭苦しいワンルームと申し訳程度のユニットバスだけの空間が宿代わりだった男に、見返りをくれてやりたい。善意の押し付けと言われようが、ここにはお前の居場所がきちんと用意されているんだと分からせてやる為にも、これは必要なことだと思った。
「……あっ、副総……じゃなくて、殿下。こんなところに」
「スザク」
廊下の外を通りかかったらしい男が、まだ工事段階の室内を覗き込んでいた。そいつはまさに、次週からここが居住空間になる張本人だった。
が、その様態は見慣れた姿とは少し異なる。頭には包帯が巻かれ、顔や腕のあちこちに小さな絆創膏やガーゼが貼られている。服装は病人が身に着けるような白っぽい綿の布きれだ。見るからに危なっかしい。
「そんな格好で出歩いて大丈夫なのか?」
「はい。あくまで検査だけなので。それに今日の夕方にも退院予定です」
床に敷かれた半透明のビニールシートの上を歩きながら、彼ははっきりした口調でそう述べた。言われてみれば顔色もそう悪くなく、歩調も普段と変わらぬ様子である。
「ベッドで安静にしてても体が鈍りますし、仕事も早く覚えていきたいですから」
彼は未だ工事中の室内を見回しながら、そんな体のいい弁解を吐いていた。
激しい損傷を負ったランスロットで日本列島から本国へ帰還したのち、スザクはすぐさま近くの軍病院に担ぎ込まれて精密検査を受けた。というよりも、受けさせた。
本人は帰還最中の時間で回復したと言い張って憚らず、このくらいの怪我は自己治癒力でどうにかなる、の一点張りであった。しかし腕や脚と違って頭に異常があるとすれば、生命活動に支障をきたしかねない。今は良くても数日後に問題が発生するかもしれない。病も怪我も早期発見が肝要なのである。
そうしてスザクは数日の検査入院を余儀なくされ、この宮廷内の簡易病棟に移された。軍部の医療施設は先の戦いにより負傷者の治療で病床が足りず、感染症の恐れがない比較的軽症者は別の施設へ割り振られるという措置が講じられたのだ。
スザクの場合は以後宮廷での内勤が決定している為、ここの病棟に移動するのは初めから分かりきっていたことだが。
「ここ……ゲストルームではなく、本当に私が使って良い部屋なんですか?」
「ああ勿論」
「左様ですか……」
まるで他人事のように部屋中を見回して、感嘆したような声を漏らしていた。
本当に使って良いの、と彼がぼやくのは何もこれが初めてじゃない。施工前の段階から目を丸くして、こんな広い部屋は自分に勿体ない、と委縮しきっていた。とは言っても、いつまでもタコ部屋労働させるわけにもいくまい。
なんせ彼は騎士侯の勲位を賜る人物なのだから。
工事が終わった部屋へ順次家具が運ばれてきて、同時進行で電気の配線工事や電話の接続、水回りの施工が行われる。工期には当然間に合うだろうが、なんとも慌ただしい光景だ。最終的に家具家電が出揃い、掃除まで終えられるのは工期のぎりぎり直前になるであろう。
「ベッドはどのあたりに置く予定ですか?」
彼は周囲を見回しながら、なんの気無しに尋ねてくる。
自分はポケットに入れたタブレットを取り出し、レイアウト図面と購入予定のベッドの写真を画面に表示させてやった。窓際の真横に据える形で、オーソドックスなデザインのシングルベッドを置く。今はサイドテーブル用のランプの電気配線を設置中だから、まだベッドは置けていない。
「……シングルにされたんですか」
「うん? 一人用のベッドなんだから当然じゃないのか?」
「……ああ、その、ううん……」
ここはお前専用の部屋だぞ。そう付け加えると、彼は何かを思案しながらも言葉を紡いだ。
「実は私、寝相が少し、むしろかなり、悪いほうで」
「はは、そうか。事前に聞いておけば良かったな。今からサイズの変更を頼んでみるよ」
「……はい。有難う御座います」
液晶画面に触れて、購入予定のベッドのサイズの変更依頼を行った。その手元を覗き込む男は微笑みを浮かべながら感謝の言葉を述べていた。
ともすれば廊下の外から誰かがこちらへ駆け寄ってくる足音がする。一体なんだ騒がしいな、と部屋の扉を見遣れば、一人の兵士が既にそこに立っていた。
「お話し中のところ申し訳ありません殿下。シュナイゼル宰相から内線が入っております」
「分かった。執務室へ一旦戻る。……スザク、お前はここに残るか」
「私も同行して宜しいですか。殿下の執務室も実は拝見したことがなく」
ならついてくると良い。それだけ言うと彼は、黙って自分の三歩後ろを律儀に守って歩いていた。
部屋を移動する道中の廊下は大層騒がしく忙しなく落ち着きがなく、皆が皆東奔西走をしていた。携帯端末を肩に挟んで通話をしながら、立ち止まりもせず、メモとペンに両手を塞がれている人。両手に書類の荷物を抱えて走っていく人。大人数で連れ立ちながら早口で何かを捲し立てる人。おおよそ宮廷で働く人間たちは誰もが突如訪れた変化に対処しようと必死なのだ。無理もないだろう。
後ろをついて回る男は、右往左往する人々を興味深そうにしげしげと見つめていた。何がそんなに面白いんだ。そう尋ねると彼は、大勢のブリタニア人に紛れ込む自分が誰にも指さされないことが奇妙な感覚である、と呟いたのだ。
本気で奴がそう思っているなら、そんな常識は早めに捨てて切り替えたほうが良いだろう。なんせここはブリタニア帝国の中枢・首都ペンドラゴンの宮廷なのだ。ブリタニアの統治下にあったエリア11とは少し勝手が違う。
「……宰相閣下。ご用件とは如何ほどでしょう」
執務室に辿り着いてから、保留中にしていた内線に応答した。相手はブリタニア帝国宰相のシュナイゼルだ。用件の心当たりは山ほどある。なんせこの時期だ。
『急遽悪いんだけど、頼まれ事をしてほしい。日本国で明日平和式典が行われるようで、そこにルルーシュの出席依頼が届いた』
「明日? 急な話ですね。時間は何時頃」
『正午から始まるようだから、朝のうちに出発だろう。特別に使用許可を出すから、アヴァロンを使うといい。特派にも話は通してあるよ』
話を聞きながら、手近にある紙とペンで話の概要を走り書き残してゆく。脇に立つ男にそれとなく手元を見せつつ、電話の相手に予定の仔細を尋ねた。
『枢木卿の同行はどちらでも構わない。引継ぎだったりで忙しいだろうから、それは任せるよ』
「畏まりました」
一旦通話を切ってから、隣に立つ男にメモを見せる。乱雑な字で示されたそれに視線を巡らせる彼は、得心がいったように頷いていた。
「解放軍のメンバーとも顔を合わせる最後の機会だし、行ってもいいんじゃないか」
「ですが、自分は……」
「名誉人だから?」
男は控えめに頷いてから口を閉ざした。
「そんな制度はもう無くなったよ。お前は日本人だ」
「日本人でありながら、自分は、ブリタニア皇帝に膝をつく……」
「今更何を言う。お前は俺が拾ってきた逸材だ。それ以上文句を言うならランスロットの鍵を返してもらうぞ」
何か言いたげな表情をしきりに浮かべていたが、とうとう何も返してこなくなった。最初からそうやって物分かりの良い振りをしておけばいいのに。妙なところで繊細で低姿勢が過ぎる男には、このくらい強く言っておくくらいが丁度いいのだ。
エリア11を統括する軍部の崩壊、およびブリタニア総督府の解体、日本政府の統治権復権。軍部瓦解から誘発されるように、ルルーシュが目論んだこれら三つの目的は当初の計画どおり実現しつつあった。
エリア11に駐在していた帝国軍部は、一見寄せ集めに見えた人民解放軍の前になす術もなく総督府襲撃を許し、物資の喪失や人的被害を被った。圧倒的軍事力と人材、権力を握っていた独裁軍事政府は一夜にして無に帰したのである。軍部の横暴と圧力に耐えかねた市民の団結力、エリア11総督・副総督という双璧が解放軍陣営に寝返ったことによる大幅な戦費増強、軍部主導の脇が甘い杜撰な政治体制。これらすべての要因は腐敗しきった組織の崩落に繋がった。帝国により植民地化された土地で初めてクーデターが成功したと、世界から大々的に報道されたのは言うまでもない。
平和、自由、権利。耳馴染みの良い言葉の羅列は人々に無責任な希望や夢を抱かせる。人民は次なる一手を、明日への契機となる福音を心待ちにしていた。だから自分はこれに応えるべく、我武者羅に働くしかなかった。ブリタニアの宰相シュナイゼルと若き皇子ルルーシュが、今度はどんな手を使って停滞した世界情勢に風穴を開けてくれるのだろう。そうやって煽動された文句が独り歩きして、世界は二人の一挙一動に常に夢中になっていた。
執務室に居ると鳴り止まない電話に付きっきりになる。宰相からの内線はさすがに無視もできないが、それ以外の雑務が圧倒的に多い。なんせ現場は大混乱なのだ。新たな機構の構築、人事の決定。条約構文の草案作成に、メディア向けの演説。山のように押し寄せる仕事を担当部署に振り分け、必要に応じて現場に駆けつけ、会議に参加することもある。元副総督として、残された責務は最後まで全うせねばならないのだ。
何だって壊すのは簡単だ。前時代の概念、制度、思想、差別を法の名の下に裁き、濯ぎ流す。そのあと自分に待っている仕事は、灰燼と化した旧政府の上に新たな法治国家を樹立させることだ。つまり日本国家の復権と、もう二度とこうした悲劇が起きないよう、保障条約を定めて表明せねばならない。
日本国家の再建に伴い、各地に散らばっていた元政府官僚らが再度集まり、あるいは立候補者を募り、行政や司法の中枢を担うメンバーをいち早く選定するのだという。日本国民の有権者らが有志で選挙管理委員会を発足させ、来週にも全国一斉に信任選挙が行われる。国家として足並みが揃うまでの当面、解放派のシュナイゼルと自分を筆頭に組織された支援団体とともに、日本国の政治運営の一部を担うことになっている。当然、統治権の一切は日本国側にあるから、出来ることは些事であるが。
「枢木家の息子として政界入りするのも可能性としてはあったんじゃないか?」
「……御冗談を」
信念のない自分に日の丸を背負う資格なんてありませんから。悲しそうに笑う男の顔は諦念に満ちていた。名誉人を名乗り断罪され続けた過去は未だ、彼にとって大きな咎として残っているのだろう。一朝一夕で癒える傷ではないのは確かだ。だからこそ、それを分かっていて尚、自分の隣に居てほしいのはこの男だけだと確信した。
「なんだ、またプライベート通信……」
震える端末を手に取って着信に出た。液晶に表示された番号は見慣れぬ羅列であった。
同時に鳴り響いた外線電話は無視に限る。きりがない。
『久しいな、ルルーシュ』
「……その声は姉上ですね」
凛々しい声音に強い語調。暫く耳にしていなかった姉・コーネリアの声に思わず口元が緩む。お元気そうで何よりです、と自然に言葉が出た。
『今は本国に滞在か』
「ええ。総督府は大混乱ですから」
『随分と派手にやったそうじゃないか』
「姉上に比べれば、俺は穏健派ですよ」
冗談を交えてそう切り返すと、くすくすと可笑しそうな笑い声が聞こえた。
机に置かれてあった新聞紙を手繰り寄せ、その一面を広げた。屋根に大穴が空き、窓ガラスは割れ、ナイトメアフレームの残骸が建物の外に散らばり、外壁や道は崩壊しきっている。凄惨な様相を呈する総督府の現場写真がカラーで載せられ、大見出しを付けられた紙面は一目で有事であることが分かる。
ここまで酷い報道の切り取られ方は、個人的に思うところがある。ゲフィオンディスターバーで租界のサクラダイト機構を強制シャットダウンさせたのは、市民を中央府から遠ざける狙いもあった。その上で租界内の地層操作プログラムを改竄し中央を分断、物理的に市民生活とも遮断をさせた。幸いなことにその策が功を奏したのか、生活圏への被害報告は今の所一件も上がっていない。
「そちらの状況は如何でしょう。随分と後ろが騒がしいようですが」
別エリアの総督として赴任している彼女は、圧倒的戦力差と見事な戦略指揮で植民地を併合してみせた軍人勝りの皇女だ。自分とは意見が相容れないことを知りつつも、わざとらしく聞いてみたのはちょっとした出来心だった。
『エリア11が革命に成功した途端、世界中で同じような騒ぎが起こってるよ。私は一体"どちら"をブリタニアのご意向として捉えて行動すれば良いのか』
「どちら、ですか。貴女という人でも迷われることがあるんですね」
『国のトップがダブルスタンダードときたら組織はどう動けばいいか分からないだろう』
現時点で解放派の筆頭・宰相シュナイゼルと軍国主義を掲げる現皇帝シャルルの意見は真っ向から相反し、帝国内は両者の派閥による対立構造がより一層浮き彫りとなっていた。
国内外に波及する派閥構造は少なくとも数だけで見れば、シュナイゼル派が頭一つ抜きん出ている。帝国からの圧政に苦しむ諸外国が一斉に彼を支持し、それでなくとも革命に向けた足並みを揃えつつあったのだ。帝国の支配から逃れるエリアはこれからも現れるかもしれない。
一方でシャルルの意見に賛同するのは既得権益に群がる有力貴族や政府官僚、海外を見れば帝国の友好国とされる国家たちだ。シャルルは自身を支持する彼らに幅広い権限を持たせ、これをいつでも行使できる権利を与えている。純血派の多くも皇帝の富国強兵施策に賛同意見を示していた。
こうして見ると両者に総力的な優劣は存在しない。勝敗を決めるのは世界の意思だろう。
「……姉上」
その報せはあまりに唐突で、青天の霹靂であった。タブレットの液晶に灯ったランプと、そこに表示された文言に視線を落とす。
不意に目に入った文字の羅列を理解するのに一瞬、時間を要した。
『どうかしたか』
「世界の意思は我々を選んでくれたようです」
ブリタニア皇帝に対する不信任案の可決、および失脚決定のニュースは瞬時に海を超えて全世界に駆け巡った。
皇帝失脚の決定打となったのは、ある人体研究とそれに基づく論文データが露見したことだった。
解放軍の侵入を許した総督府の最奥に存在した部屋から見つかった一人の少女は人体実験の被検体であるとされ、研究の一部始終を知る関係者らの証言により実態は明らかになったのだ。古代文明と迷信、伝承の記録を元にして彼女に施された実験は現代医療や科学の域を超えた成果を残そうとしていた。怪我の再生、疾病や感染症の早期超回復、年月を経ても変わらぬ身体。いわゆる不老不死を実現させる為の、秘密裏にされてきた禁忌の数々であった。
それらの実験の全権限は皇帝シャルルが掌握し、研究員は目的を知りながらも皇帝の支配と圧力から逃れることはついぞ叶わなかった、と証言している。文官であるバトレーもこのうちの一人で、公務で総督府に出入りするたびに実験の一部を支援していたという。
シャルルが世界各地に領地を拡大したことは、単なる物資や戦力増強だけが目的ではなかった。各国に点在する遺跡や出土品、文化の記録なども同時に熱心に行っていたと言われ、それらが全て人体実験の材料、データ収集の為であったと報道されたのだ。大都市であろうと辺境の地であろうと、ブリタニアが進軍し土地を治めることに最後まで執着したことの理由として、納得はいかないが説明はつく。
富と権力と領土、名声、これら全てを思うままに手中へ収めた男が最後に欲したのは、科学領域からの超越、神域への第一歩であった。
しかし皇帝が持つ"全て"とは人間が作り上げた概念体系でしかなく、ブリタニア皇帝という肩書もまた、ある意味で人工物の域を出ない。人智の理、森羅万象までも掌握し制御しようなどという考えは驕り高ぶりに過ぎず、烏滸がましく意地汚い理念だ。
たとえばの話。いくら金持ちであろうと、貨幣制度という大前提が成立せねば紙幣など無価値だろう。人間の編み出した既成概念は人間の考えが及ぶ範囲でしか成立しない。だから皇帝の名を冠する者が人間界の頂点だとしても、自然界の掟を破ることは不可能なのだ。
その翌日、本国宮廷の屋上から飛行艇アヴァロンに乗り込み、特派の面々およびスザク、シュナイゼルらと数人の警備を連れて日本国へ向かった。
エリア11の総督府襲撃以降、改修と装甲開発が行われていたこの浮遊空母艦艇は元のスペックから大幅なアップデートが施された。艦体の下方にしか展開できなかったブレイズルミナスの範囲を大幅拡大、威力の出力数も上昇し、より堅牢な作りとなった。エネルギーの消費燃費も向上しており、長距離移動により対応できるようになった。ブリタニアと日本国の往復、つまりは太平洋の横断も容易とのことだ。
港近くの飛行場に降り立ったあと、用意されてあった公用車に乗り込み首都内に設けられた式典会場へ向かう。車は警備も含めて隊列を成し、上空にいくつも旋回するヘリが空からも警戒を強めていた。車内に流れるラジオはしきりに、日本国でこれから行われる平和式典の概要を伝え、これを持て囃している。
窓の外から見える景色は至って普通の、よくある高層ビル街だ。昼間の太陽の光を受けて反射する建物の側面が空模様を映し出し、流れる雲の動きを幻想的に捉える。道路の脇に均等に植えられた街路樹はコンクリートに覆われた街にささやかな彩りを与え、整合性の取れた景観を演出していた。
つまり首都の街中は騒動が起こる前と何一つ変わらない。ありふれた日常が流れたまま、今日この瞬間もつつがなく経済活動が営まれていたのだ。
「これが、君が守りたかったものかい」
「当たり前にあり過ぎて、失うことなど考えもしませんでした」
リムジンの後部座席でシュナイゼルと向かい合いながら、思うままに言葉を紡いだ。彼の騎士であるカノンはその隣に控え、表情を変えずに窓の外に視線を移していた。
「……スザクくんもそんなに緊張せず、今くらいはリラックスしておいたほうが良い」
「い、いえ、自分は」
隣に座る男は折り目正しく背筋を伸ばし、どこか挙動不審になりながら目線を彷徨わせている。着せられた服はこの日の為に誂えられた制服で、普段の特派の軍服とは様変わりした印象だ。しかし白の手袋に包まれた両手は膝の上で固く握られ、強張った肩とは車が揺れるたびにぶつかっていた。
「萎縮する必要ない。解放軍の奴らだって」
「ちっ違うんです。そうじゃなくて……嬉しいんです」
「……」
「殿下も落ち着いている振りをして、本当は同じなんでしょう。私の部屋のレイアウトにしたって、夜通し設計図を広げていたとジェレミア卿が」
「……枢木卿、もういい。お前は黙ってろ」
向かいに座る宰相と専任騎士からの生ぬるい視線や空気を瞬時に感じ取って、彼には悪いがそれ以上は黙らせた。そして堰を切った本人もそれを察したのか、それきり口を噤んでいた。
自分はスザクの指摘どおり、いつになく、ひどく浮かれていた。仕事があまりに忙し過ぎて、一日のうち公人として過ごす時間があまりに長過ぎて、それを実感する暇もなかった。
命を賭して皇子殿下を救出した勇敢さ、万全でないマシンにも拘らず複数機からの攻撃を躱す技術の卓抜。これらを評されたスザクは宰相直々に騎士侯の階級が与えられる。
名誉軍人出身の一兵士としては異例の出世だ。端的に言えば弱肉強食、良く言えば、成績さえ残せば相応の評価を下される超能力主義。その理念がスザクの栄転の大きな後押しにもなったのだろう。
エリア11の軍部が解体された今、名誉人制度自体は既に廃止され、彼らは等しく日本人を名乗ることを許され、日本人として扱われる。しかしスザクも内心思うことがあるのか、やはり元名誉人としての負い目や意識はまだまだ拭えないらしい。
長きに渡り差別の対象として手酷く扱われ続けた彼らは、時に不安に、時に帝国人に対する疑心暗鬼にも陥るだろう。制度としては無くなったものの、人々の意識の根底はそう易々と変えられない。見えざる差別はこの世界のどこかで横行もするだろう。
今度はそうした懸念と、自分は戦わねばならないのだ。
式典の会場は以前総督府の建物が存在していた敷地内で、付近にはまだ解体作業中の本部が防塵シートに覆われていた。まだまだ現地は完全整備とは程遠い有様で、悠長に式典など催している場合かと、苦情が届けられてもおかしくない。解体業者や工事車両が行き交い、片や解体が済んだ箇所は早速土砂やコンクリートでの埋め立て作業が同時進行で行われていた。
建物の解体が終わったあと、この土地は市民の娯楽施設を中心に様々な開発計画が持ち上がっているという。平和会館も設置されることが決定しているようで、日本国とブリタニアの国交記録を文章や写真を交えて、今日まで両国が辿った軌跡を解説するらしい。日本の被害者意識を刺激するのではなく、あくまで実際にそうした事実があった、ということを後世に残すことを目的にする。他にも両国出身の芸術家たちが残した作品を展示する美術館や博物館、図書館などの公共施設が案として浮上しているという。
ブリタニア側から開発事業に意見する権限はないが、資金援助や施工業者の斡旋、雇用の確保といった支援は可能だ。まだ発足したばかりがゆえに舵取りに戸惑う日本政府へ手を貸す形で、携わってゆくことになる。この国との関わりはこれからも暫く継続するであろう。
式典の参列者はかつてブリタニアの支配を受けていた反帝国派の国家の首脳や幹部らがこぞって揃っていた。封建支配の象徴であった施設の跡地で、新時代の到来を祝う。なんとも皮肉的で風刺的な儀式だ。
自分はこの式典に赴くにあたって、他所の国から罵詈雑言に晒されたり、傍迷惑なマスメディアに悪意を向けられたり、そうした嫌がらせを受ける覚悟をしていた。悪虐の限りを尽くしたブリタニア人が、よくものこのこと人前に出られたものだ。そんな憎悪の視線に貫かれ、毅然に振る舞う心積もりはしていた。
しかし現地に着くと予想に反して、彼らは友好的に、まるで旧知の友人の如く、親しく接してくれたのだ。むしろ感謝の言葉まで述べられる始末で、そんな彼らはみな口を揃えてこう言うのだ。――革命の旗印として前に立ってくれて有難う。と。
参列者の何人かと握手を交わし、挨拶や雑談、意見交換を交えていると、自分を呼ぶ声が聞こえた。しかもそれは今まで言葉を交わした参列者たちの中でも群を抜いて不躾で、厳かな場にそぐわない、賑やかな音だった。
「ルルーシュ様、お元気でいらっしゃいましたか!」
「お久しぶりですね、元副総督サマ」
「ちょっと二人共、失礼だって……」
人混みの中をかき分けるように現れた顔を見て、その賑やかさに得心がいった。いつかの日に枢木神社で落ち合った解放軍の三名だ。
「テレビ中継で観てましたが、一時はどうなることかと思いましたよ! 軍部の戦闘機が大群で、総督府の官邸へ突撃なんて!」
「神楽耶様、お声が大きいですよ」
「それを言うなら私も言いたいことが山程あるんですけど?」
解放軍の制服を身に纏ったカレンが突っ掛かってきた。周囲の警備はやや警戒の姿勢を見せたが、心配はないと視線を走らせると態勢は解かれた。
「あの後あたしは命からがら戦線を離脱したのよ? 輻射波動機構は量産が難しいから、機体を置いて脱出するのもままならなかったし!」
「そのわりにピンピンしてるな。丈夫そうでなにより」
「ムカつくわねその言い方! あんたが皇子じゃなかったら一番に殴らせてもらったのに!」
「カレン、皇子をあんた呼ばわりは良くないぞ」
「扇さんも文句があるなら今のうちよ?」
「扇は作戦の中盤で離脱してたじゃないか。レーダーから消失したからまさかとは思ったが」
痛いところを指摘された扇はばつが悪そうに俯いたあと、何かが吹っ切れたのか、カレンに加勢するように言い訳を投げつけてきた。
「そもそも俺たちは、あれだけの大軍が押し寄せるなんて聞いてなかったぞ。サクラダイトをシャットダウンさせてる間に軍部を壊滅に追い込むと、作戦では」
「実戦が想定通りにわけがないだろう。所詮は机上の空論に過ぎない」
「うわ、やな奴!」
カレンが大声で吠えた。周囲から好奇の目が集まっているが、当の彼らは頓着がない。
「そういう自分だって命からがら脱出してた癖に、ねえ。そこに立ってるのは例の騎士侯サマ?」
彼女が不躾に指をさした先には、無言を貫く男の顔があった。意図せずして場の注目を浴びた彼は一瞬驚く表情を見せたあと、一歩か二歩ほど前に出て口を開く。
「ええと……自分は枢木スザクといいます。貴女が紅蓮弐式のパイロットですか?」
「ええ、そうだけど?」
「そう……なんですね。少し驚きました」
「女が前線に出ることが?」
「いいえ、決してそうでは。あまりに普通の、可愛らしい女の子だったから、何だか……」
スザクの言葉はそこで不意に途切れた。次の瞬間、彼の口から漏れたのは苦しげな音で。
「ルルーシュ様? 何なのこの天然たらし!」
「い、痛い、痛いです、カレンさん」
どうやら彼女は容赦なくスザクの手の甲を抓り上げていたらしい。
「ルルーシュ様もこの男に絆されてんじゃないの!」
「そっそんなこと、自分は、ない……ですよね殿下?」
痛い痛い、と声を上げるスザクとおおむね照れ隠しであろうカレンのやり取りを視界の端にやりながら、低次元な言い合いが耳に入って思わず眉間を揉んだ。
「お二人共、各国首脳が来賓されている場でそのような振る舞いは恥ずかしいですよ!」
「神楽耶様」
「……神楽耶」
カレンが手を離したあと、スザクは鶴の声、もとい神楽耶のほうに向き直った。
「本意ではありませんでしたが、まさか志同じくして枢木家とキョウトが協力する日が来ようとは思いも寄りませんでした」
「……君が僕を枢木家の人間と認識してくれていたなんて、意外だな」
「貴方という人を差別しては、我が解放軍の結成理念に反しますから。あまり身勝手な振る舞いは謹んだほうが宜しくて、ですよ?」
神楽耶は和服の袖を揺らしながら腰に手を据えて、スザクにそう宣言した。彼は彼女の振る舞いに穏やかな笑みを浮かべて、約束するよ、とだけ呟いていた。
つつがなく終えた式典行事の後、どこか神聖で厳かな余韻を心に残しながら一行はアヴァロンに乗り込み、本国への帰還を目指した。
この行事の為に集まった帝国の代表ら、日本国政府の官僚、および各国首脳らは戦後処理や条約締結の為の準備が山積みであった。こうしている間にも自国では政権崩壊の混乱と祝賀ムードの渦が混じり合い、非常に不安定な情勢であることに変わり無かったのである。ほとぼりが冷めたら親睦会を兼ねた食事会を開催できたら、と話を交わし、式典後の壮行会は短時間でお開きの運びとなった。
艦艇の窓からは眩しい西日が差し込み、無機質な金属製の床を鮮やかな茜色に染め上げていた。雲の切れ間から見える太陽の光に背を向けるようにして移動する機体を、飛び立つ烏の群れが見送ってゆく。
操縦室から少し離れた場所にある控え室ではテレビが点けられており、垂れ流される映像はどれもこれも、今しがたの式典の様子を様々な角度から撮影した内容であった。朗々と平和宣言を語る帝国宰相・シュナイゼルの発言が文字に書き起こされ、テロップとして表記されていた。
――我が国は長きに渡る帝政制度に終止符を打ち、これまでの過ちに塗れた歴史に幕を下ろす。我が国の非人道的支配により苦しめられ続けた人民、兵士、国家に深くお詫びしたい。そして戦の前に命を散らした兵士や非戦闘員たちに哀悼の意を示すと共に、金輪際このような悲劇を起こさぬよう、我々は平和のための永久的な努力を惜しまない。それを今日、禍根を残すこの地で私は誓おう。私の発言はブリタニアの意志とみなし、国民にはこれを受け入れて頂くことを望む。
歓声と拍手が会場に巻き起こる。平和の象徴である白い鳩が、用意された籠から宣誓とともに一斉に解き放たれる。青い空に向かって高く高く飛び立ってゆく群れをカメラは追い続け、その後ろで鳴り止まない拍手が響いていた。
演出というのは人の心を動かす重要なファクターだ。音や映像の工夫次第で物事を意図的に好印象・悪印象に映すことができる。五感を刺激することは人心掌握の大前提である。テレビはそれを効果的に、しかも易々とやってのけることが可能な媒体だ。
「いわゆる刷り込み、プロパガンダと呼ばれる類と同じだな」
「でもそれはそうとして、ブリタニアが世界に向けて平和宣言を……一切の植民地を解放したのは事実じゃないか」
スザクはテレビ画面から視線を動かさないまま、そう呟いた。
「植民地を解放すれば争いは二度と生まれないとでも思ってるのか? 飢餓や貧困、難民問題や医療……争いの火種はそこかしこに孕んでいるのに」
「だからブリタニアは本国軍の解散をさせなかったんだろ。軍部がこれまで培った紛争地でのノウハウ、たとえば野営や野戦病院の設立、食糧備蓄の知識……これらが役立つ機会が必ず訪れる」
「……なんだ分かってるじゃないか。安心したよ」
「あっいま、僕を試したんだ?」
漸くテレビ画面から目を離したスザクは、少し怒ったような、あるいは拗ねたような表情を浮かべながらこちらを向いた。
「気づくのが遅い」
テーブルから水差しを持ち上げて、ガラスのコップに中身を注いだ。黄緑がかった液体は恐らく日本風の緑茶の類だろう。苦味のない口当たりと香ばしい匂いは、日本茶に馴染みがないブリタニア人でも飲みやすいよう改良が施されてある為だ。
視界の隅で、スザクは何やら本を読み始めた。
「なんだその本」
「ブリタニア国史だよ」
「へえ、これはまた勉強熱心な」
「君の隣に立つ人間として、恥ずかしくないようにね」
手持ちの荷物鞄から取り出されたのは手のひらに収まりそうな新書サイズの書籍であった。端がよれた紙のブックカバーと折り目のついた背表紙を見るに、何度もそれを読み込んでいるであろうと察せられる。
「どんなことが書かれてあるんだ」
「このページは未完に終わったフランス革命の説明」
「ふうん……」
彼の手元を覗き込んで、生返事を返した。
本の内容に純粋な興味があったのは本心だ。本意だ。でも、思ったより近くにあったスザクの顔のせいで言葉が出てこなくなったのは、不本意だった。
「どうしたの」
「……いや」
「お顔が赤いですよ、殿下?」
「お前な」
わざと茶化すように言葉遣いを改める彼に、それ以上の文句は浮かばなかった。ふわふわと浮足立つような感覚と、鳴り止まない鼓動が耳に届く。点けっぱなしのテレビの音声は聞こえなかったし、ひりつくような緑の視線に晒されて、喉はからからに乾いた。
「……」
ゆったり近づく頬に息が漏れる。伏せがちの瞳と瞼が揺れて、スローモーションのように見えた。柔らかい唇の感触は体がよく覚えている。心が歓喜と期待に震えて、喉が鳴った。
「ルルーシュ様、枢木卿。間もなく着陸とのことですので、管制室にお戻り頂けませんでしょうか」
「……分かった。すぐに向かう」
目前にあった緑の瞳と視線がかみ合う。反射的に伸ばしていた右手は彼の口元に宛てがわれていて、それはまるで接触を拒むような仕草だった。
「……ルルーシュ、これは酷くないか?」
「ご、ごめん。びっくりして、つい」
手のひらの中でもごもごと苦言を呈する男は忌々しげに扉へ視線を投げたあと、渋面を張り付けて睨みつけてきた。この手を外せと、言われなくともその台詞は伝わってくる。
しかしその我儘に屈したら、何か良くないことが起こる気がする。これは己の生存本能が告げる勘である。
「そうだ。お前、まだ部屋の工事が完成してなかっただろ。来週までは宿無しのはずだ」
「うん、まあそれは、そうだけど」
検査入院も終えた彼は寝に帰る場所がない。差し当たって一週間ほどは、仮設の私室が必要になる。
「特派のトレーラーに僕の部屋が」
「駄目だ。あんな独房みたいな空間に住まわせられるか」
「ど、独房……」
スザクはその言葉に眉を顰めて、じゃあどうすればいい、と問うてきた。
「……俺の部屋なら広いし、来てもらっても構わない」
「ルルーシュの?」
「そうだ」
「……いいの?」
「いいよ」
手のひらを外してやると、スザクはやけに落ち着き払った態度で立ち上がり、室内の出口の扉に手をかけた。凪いだ表情は皆がよく知る枢木スザクその人の顔をしていて、そのことに妙な安心感を覚えた。
扉の向こうから呼ぶ声がなければ、自分と彼はどうなっていただろう。頭の片隅で浮かぶ事象はただの妄想に過ぎなくて、そのどれもが艶事の可能性を孕む内容だったから、慌てて全ての想像を取り消した。脳裏に流れる映像はあやふやでぼやけていて、いかに自分がそうしたことに疎いのだと思い知らされる。漠然とした色っぽい何か、は常に靄がかっていて、明瞭になることはついぞなかった。
だから自分はこの時、知る由もななかったのだ。騎士然として腕を引く彼の手がやけに熱い理由も、ちりちりと焦げるような視線を感じる訳も、どこか釈然としない面持ちを浮かべる彼の心情も。
空を舞う巨体が下降する時の、微かな浮遊感と重力に顔を歪めた。隣に立つ男はどこ吹く風とでも言うように平然と、涼しい面持ちを浮かべている。
浮かべている、と思っていた。
ちらりと視界の端で盗み見ると、騎士はこちらをじっと、一点も逸らさず見つめていたのだ。喉元に冷たい刃物を這わされたような、嫌な感触が全身に迸る。その瞬間、彼は柔和な笑みを浮かべて、如何しましたか、と平坦な口調で声を発した。
「なんでもないよ」
「左様ですか」
短い会話であったが、漸くこの違和感の正体に気づいた。
スザクは自分にしか分からないくらい、小さな機微を見え隠れさせていた。じりじりと肌を焦がすような、じれったい熱の感触。かと思えば今度は、鋭く尖ったナイフみたいな冷たい温度。
その濁った瞳孔の裏にある獣じみた情欲は、自分にだけ向けられた一種の恋慕だった。