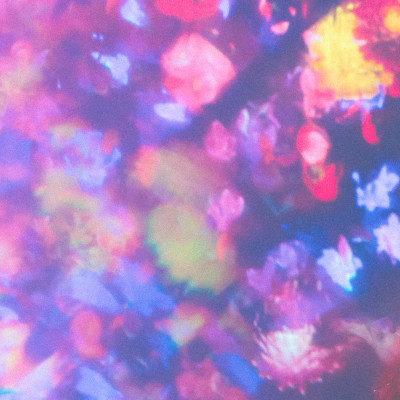
これをよすがとする 八話
「左翼の紅月部隊は総督府ごと取り囲むように前進。右翼の枢木准尉は建物背後からの奇襲を狙いつつ指示があるまで待機。フォーメーションアルファを展開しつつ攻撃の手を緩めるな」
『了解』
『了解』
膨大な数の敵影を捉えたモニタは、同時に味方機の動きをリアルタイムで映し出す。敵と味方、両機が接触した瞬間。消えたのは敵影で、自軍のマークはその場で表示され続けた。
「……よし」
思わず漏れた声は無意識のものだった。
カレンが乗る紅蓮弐式が対空ミサイルを放ち、総督府の正面に続く道を切り拓く。途端に集う敵機をひときわ目立つ紅蓮に引きつけ、その奥の援護部隊に混ざっていたジークフリードが群衆の合間を縫って飛び出す。既存のナイトメアフレームとは一線を画したフォルムは奇天烈な飛行物体とも形容できよう。試運転と調整が続けられた新型機が初めて公衆の面前に晒される瞬間だ。
攻撃の種類どころか動きすら予測しづらい機体に、軍部の展開する正面の陣形はたちまち崩壊を始めていた。どれだけトリッキーな戦術も対策を講じられれば無意味だが、使い所さえ誤らなければ絶大な効果を発揮する。切り札として、出すタイミングが肝心なのだ。
「ジェレミア、強気で行け。お前が進んだ道が後続部隊の足掛かりとなる」
『畏まりました』
短い返事のあと、ジークフリードは猛スピードで旋回と急上昇、急降下を繰り返した。彼が築いた道を縫うように、控えさせていた解放軍のナイトメアが一気に押し寄せる。既存の敵影はその流れを断ち切ろうと交戦、どちらも次々とロストマークを表示させた。恐らく内部に侵入できたのは控え軍の三分のニといったところか。予想では半分いけば上々と踏んでいた分、機運がこちらにあることを漸く感じれた。
日の落ちきったばかりの夜の始め。闇色の空に覆われた都会は遠雷のように鳴り響く轟音と、山火事のように明るい地平線を抱えていた。
租界の中央に据えられた省庁と軍部本基地、そして植民地の内政を司る総督府はバリケードで封鎖され、一般人は当然ながら無武装の官庁職員や研究員も立ち入ることが禁じられていた。マスコミはこぞってバリケードの前に張り込み、あるいは上空には報道ヘリを飛ばし、その内情を世界に向けてリアルタイムで発信しようと試みる。
しかしその同時刻、租界の上空は帝国の領空ではなくなっていた。人民解放軍を名乗る組織が帝国に代わって、これの占有権を主張していたのだ。帝国お抱えのマスコミは領空侵犯を恐れ、下手に空撮に踏み切れない。バリケードの内側で何が起こっているのか、知れる者はごく一部であった。
「兄上。空軍は差し押さえたようですね」
『ああ。本国から海を渡って援軍がやってきては厄怪だろう。これは短期決戦だ。その為の時間稼ぎなら何だってしてみせるさ』
「有難う御座います。援軍確保でき次第、包囲網に加勢して下さい」
『了解』
プライベート通信で聞こえる兄の冷静な声に、優勢ゆえに油断しかけていた心が瞬時に落ち着きを取り戻した。これはまだ前哨戦だ。そう言い聞かせて、依然優勢とも窺えるモニタを見つめた。
ことの発端は今から遡ること数時間前。
総督府にある一通の電報が届いた瞬間から全てが始まった。
――イレヴンたちが徒党を組んで総督府に強襲を仕掛けようとしている。これは近々起こるかもしれない。
差出人も情報筋も、裏も根拠も不明であった。
一見すると悪戯か愉快犯のように思える。しかしそれは平時であればの話だ。近頃のエリア11の治安はゲットーを中心に悪化しており、エリアの中央当局も手を出しづらい状況であった。イレヴンの支持を獲得し市民権を得ていた解放軍はその快進撃を世界に轟かせ、ブリタニアの敵対国だけでなく支配下に置かれていた国々からも多くの注目を集めていたのだ。
軍部は人事を一新させ、改革を試みた。なんせ租界に住まう本国からの植入者たちからの信頼は失墜し、彼らの不満や不安は日に日に増していたのだ。しかし依然として改善は見込まれず、テロという無差別的な暴力行為を抑え込むことが出来ずにいた。
帝国からの独立、支配からの脱却。いまの国際情勢の水面下で最も声高に叫ばれているスローガンである。しかしこれまでそれを成し得た国は存在せず、もしも達成できたとなれば前例のない奇跡だ。
しかし、とうとう彼ら解放軍は前例なき奇跡を打ち立てようとしている。彼らなら本当にやりかねない。夢にまで見たその光景を、明日への希望を見せてくれるに違いない。
軍部に届けられた信憑性のないメッセージはしかし、どこから漏れたのか世界的なニュース番組に取り上げられ、またたく間に各国へ延焼した。エリア11が日本国の国旗を再び翻すのだと喧伝され、反帝国主義のプロパガンダのごとく扱いを受けた。
ここまでの騒ぎになると、さすがの軍部も看過できなくなる。そうした計画が根も葉もない出鱈目だとしても、感化され暴徒と化したイレヴンが何を始めるか分からない。本気で計画を企てる輩が出てもおかしくない。有事に備えることが軍部の務めだ。治安維持とイレヴンの統率を大義名分に掲げた彼らは早速対策本部を立ち上げ、様々な施策を打ち出した。
この騒ぎを誰よりも早く聞きつけ、真っ先に対抗へ乗り出したのは総督と副総督を務めるエリア11の双璧だ。
『兄上。この騒ぎは』
『全く持って寝耳に水だ。どこからか情報が漏れたんだろう』
『だとしたら……』
『やることはひとつ。計画の大幅な前倒しだ。今から総督府ごと奇襲を仕掛ける』
突き刺さるような冷たい声音に背筋が震えた。一切の感情を取り払った、冴え渡る声とその思惑。焦りは感じ取れなかった。初めからそのつもりだったかのように、落ち着き払った抑揚のない口ぶりだった。
『……本意ではありませんが、致し方ないでしょう。分かりました。至急解放軍を招集にかけ、出撃させます』
『私は本国からの援軍対策に航路と空路を遮断してみるよ』
『……出来るんですか、そんなことが』
『少々力づくにはなってしまうがね』
どこか余裕すら感じられる言葉尻に、思わず笑みが溢れた。
本作戦の全指揮権は自分ひとりに委ねられている。つまりは最高司令官を任されたというわけだ。進撃も撤退も最終的には己の意志一つで決まる。やり直しは利かない。予想とはかけ離れた開戦の狼煙であったが、どんな状況においても軍隊を勝利へ導くのが指揮官の職務だ。
おおよそ一年近く前から練られた作戦は様々な事態を想定し綿密に作られてある。幾通りもある陣形のパターンから行動指針、機体からの脱出時の想定経路まで、すべて想定の範囲内で用意してみた。詰将棋的な戦法がどこまで通用するかは実際に始まらないと分からない。一抹の不安が全く無いと言えば嘘になる。
『……副総督』
『分かっております、総督』
手の震えはただの武者震いだ。喉がやたらと乾くのも空気が乾燥しているせいで、やけに落ち着かない心臓の音は恐らく気の所為で。
その言葉を一旦最後に通信は途切れた。
書類が散らばる事務机を傍目に、自分は執務室を飛び出し、各部隊への要請を急いだ。
移動式司令塔――飛行艇アヴァロンは総督府と相対する形で建物の正面を陣取り、一定の距離を置いて巡回し続けていた。
「エリア11政府軍部およびこれを擁する総督府に告ぐ。神聖ブリタニア帝国が第11皇子、我が名はルルーシュ・ヴィ・ブリタニア。これより総督府へ対し宣戦布告を申し入れると共に、降伏条件を宣言する」
エマージェンシーを告げる赤いランプが建物全体に灯り、非常事態であることを視覚的に伝える。周囲には厳戒態勢を既に取り始めた軍部のヘリの姿が見え始め、この空挺をどう撃ち落とさんとするか、解析をしているようだった。
「私の要求は三つだ。ひとつ、軍部の永久解体および既得権益の失効。ふたつ、帝国総督府のエリア11からの撤退。みっつ、日本国政府の復権と恒久的な平和を約束すること」
拡声装置によって呼びかけた声は総督府に届けられているはずだ。この文言を読み上げている間、中央政府周辺の地盤制御を作動させバリケードを張るとともに、租界を囲むようにゲフィオンディスターバーを起動、対策を講じていないサクラダイト機器やナイトメアフレームの一斉シャットダウンを試みる。すべてが予測通り噛み合えば租界の都市機能は麻痺し、漏れなく軍部の主力ナイトメアフレームは使い物にならなくなる。
「また、私の賛同者である帝国宰相シュナイゼル・エル・ブリタニアは日本国の復権をきっかけに、全世界に広がる帝国の占領地をすべて返還するご意向だ。この一揆が帝国史初の汚点になることを、私も宰相も願っている」
やがて租界の一斉停電が発生し、地盤装置が一気に稼働する。都市部と切り離され巨大な壁に取り囲まれた総督府は、もはや袋の鼠である。これは非常事態に備え、植民地の心臓でもある中央政府のみ隔離することを想定にして設計されたらしい。しかし今となってはそれが裏目に出た。租界の設計、インフラ、鉄道網、地下鉄、すべてを図面として頭に叩き込んである。副総督ともなればその程度の情報、事前に閲覧もできよう。
地形の条件を先に活用し、対策を講じていないサクラダイト装置を無効化させる。ゲフィオンディスターバーの絡繰を悟られる前にどこまで総督府の内部へ進撃できるかが本作戦の鍵だ。
そもそも、租界の外郭を囲むように設計された環状線路の高架線にゲフィオンディスターバーの装置を取り付け起動させてあるのだが、この一本線で結ばれた円形が重要なのだ。これがひとつでも欠け、円周を保てなくなったとき、装置の効力は失われる。眠りについた敵のナイトメアは一斉に覚醒し、たちまち包囲される解放軍は蜂の巣にされるだろう。そうなる前に何としてでも、王手に少しでも近づいておきたい。
『ルルーシュ様。こちら総督府の中庭へ突入致しました』
「よくやったジェレミア。ここから先、伏兵やトラップが仕掛けられている可能性が高い。必ず後方支援を連れて進軍すること」
『畏まりました』
「お前の突破力に期待している」
定期連絡の無線通信を切り、ふうと一息吐いた。
飛行艦艇アヴァロンの内部、一番高い位置にある司令席の座り心地はなかなかに悪くない。無線通信の電波や音声環境は良好だし、カメラから映される空撮映像は鮮明に撮られており、前方の巨大スクリーンに実況中継されている。
今回の作戦はまず、決定力は見劣りするものの機動性と速力に優れたジークフリードを基軸にし、単騎で正面突破を目論む。後続には機動性の劣る量産型ナイトメアを配備し、援護と数の確保を目的に力押しでやり過ごす。その脇には突破力に優れた紅蓮を囮として配置させ、後続援護をさらに支援、及び複数の敵機を引きつけ各個撃破させる。
軍部からは数はそれほど多くないものの、ゲフィオンディスターバーの効果を受けない――サクラダイトを動力源としない旧型ナイトメアフレーム・ガニメデを筆頭に、通常の石油燃料を用いる小型戦闘機、陸用戦車が迎撃と総督府正面玄関の死守に乗り出た。
しかし限られた軍備の中では勝負の明暗は歴然だ。ひとりひとりの兵士の質や士気、ポテンシャルは本国軍の圧倒的優位であるが、装備に差がある分それを戦術で埋めるのは至難の業であろう。むしろゲフィオンディスターバーが解除されてからが解放軍の正念場だ。今はまだ前哨戦の最中である。
建物内での戦闘は混戦・乱戦の様を呈しているように見受けられた。ジークフリードが孤立しないよう後援を送り込み、なるべく建物の最深部まで食い込めるよう善戦してもらう他ない。自軍の実力を正しく見極め作戦を立てるのが指揮官の役割であるが、兵士らの力を信じたくなるのもまた、この立場だからだ。
戦線がやや拮抗状態に陥る中、突如艦艇内に警告音が響いた。映像が切り替わるモニタを見遣ると、未確認飛行物体――アンノウン表記された機影が映し出されていた。その飛行物が一直線に向かう方向のちょうど真正面に紅蓮が構える形となっており、このまますれば数秒後二機は接触と相成る。
「カレン! 右側後方より飛行物体接近中だ! 恐らく目標は紅蓮であると予測される!」
『私も捉えています、目視で』
「何が見える?」
『エアキャヴァルリーを搭載した……戦闘機……いやナイトメアフレーム……』
「ランスロットではなく?」
『白と青と赤の装甲……』
「……何?」
通信はそこで途切れた。同時に猛烈な轟音が耳を劈き、爆風が粉塵と土煙を巻き上げて竜巻が起こる。アヴァロンに備え付けられたカメラを通して地上の様子を見た。
総督府内部の中庭にふたつのナイトメアフレームが折り重なるようにして倒れていた。地面に仰向けで押さえ付けられているのは紅蓮で、その上に伸し掛かるのは見慣れぬカラーリングの機体だ。
ひとつの嫌な予感が脳裏を過る。
すると次には、件のアンノウン機体からオープンチャンネルでの通信要請が入った。
「……所属は一体どこだ」
『酷いじゃないですか、殿下』
「その声……」
同時に映像が受信され、モニター全面に映し出される。その顔立ちはよく見覚えのある人物だった。
『ナイトオブラウンズが一人、ジノ・ヴァインベルグと申します。……殿下、何故帝国への反逆など企てるのですか』
「……皇帝からの出動要請か?」
『私の質問に答えて下さい』
ジノが操るナイトメアフレーム・トリスタンは戦闘機から人型へ形態を変容させた。その鮮やかな形態変化は思わず魅入ってしまうほどであったが、次の瞬間、トリスタンは内蔵機銃を取り出し、紅蓮のコックピットハッチ部分に銃口が突きつけたのだ。分かりやすい脅しだ。
「答えてどうなる?」
『真意を問うためです。同胞の、ましてや一度は忠誠を誓った相手を敵に回すなど、私にとってはとても心苦しいことだ』
「ふ、下らない。既得権益に群がる皇帝の犬よ」
『……何?』
「お前も所詮、我が身大事ということだ。そんな稚拙な押し問答で俺を出し抜けると思うな」
男の険しい顔つきが映し出される。彼は何も言わない。
「その様子じゃゲフィオンディスターバーはまだ攻略できていないようだな。第一駆動系のみの動きしか取れていない」
司令席の肘置きに両肘をつき、大袈裟な仕草で脚を組んだ。あくまで場の主導権は、優位にあるのはこちら側だということを知らしめなばならない。ここで弱気を見せるわけにはいかない。たとえそれが虚栄であろうともだ。
『貴方は本気で討つのですね、ブリタニアを』
「勿論だとも」
画面の端に映された地上の映像ではやや動きが見られた。トリスタンの下敷きになっていた紅蓮が、今この瞬間、本人の背後でその巨腕を振り被ろうと、右手を広げていた。
『……っと。油断も隙もないな』
間一髪、軽やかな身のこなしで紅蓮から退いたトリスタンは一旦距離を取り、庭園の端へ移動した。
「カレン。輻射波動でトリスタンを仕留めろ」
『了解』
右手の中央部が渦のような光を発し、周囲の空気を激しく揺さぶった。その装備が発動した右手では猛烈な高圧電磁が衝撃波と熱を生み出し、それを直接相手に浴びせるという容赦も手加減もない力技だ。輻射波動を食らったが最後、コックピット内部の人間は生きて帰れないだろう。
赤く明滅する手のひらがトリスタンのコックピットを捉え、それを掴み掛かる。周辺の空気を揺るがす波動はモニタ越しにも伝わる程、強烈な物だ。紅蓮の右手には閃光が迸り、ジノが搭乗しているであろう箱を外側からじわじわと蝕んでゆく。
その刹那だ。
司令塔であるアヴァロンが激しく揺れ、強烈な衝撃エネルギーを受けたというメッセージ音が艦艇内に轟く。
ノイズ混じりのモニターに映されたのは、新たなナイトメアフレームの姿であった。
「その赤紫の機体、さてはモルドレッドだな……!」
「……殿下! 租界包囲網の連絡部隊より通信です!」
「今度は何だ!」
「たった今、帝国軍によりゲフィオンディスターバーが突破されたとのこと! 租界内のサクラダイト機構は順次復旧しつつあるようです!」
セシルが悲痛な面持ちでそう叫ぶ。
「アヴァロンは至急、上空方向へ距離を取りつつブレイズルミナスを展開し、モルドレッドの強襲に備えろ! 奴のハドロン砲をまともに食らうと墜落は免れない!」
司令塔の陥落はつまり敗北を意味する。そうなる前に何としてでも、総督府を墜とさねばなるまい。
こちら側に残された手札は残り少ない。手詰まりになる前に行動を起こさねば戦況は変わらない。
元より兵士の数も武器やマシンのスペックだって、帝国軍に比べれば遥かに劣る。解放軍も粒揃いの精鋭かと言われるとそうとは言い難い。帝国への怒りだけを旗印に集った混成軍だ。あまつさえ指揮官の席に就く自分はブリタニア人ときて、自由な思想信条だけを手がかりに結束している。強固な弱肉強食の精神で長年に渡り鍛え上げられてきた帝国兵士とは、層の厚さも母数も比べるまでもないのだ。
ここまでよく善戦できたものだ。彼らをそう褒めてやりたい。一見不利に見える戦いを互角かそれ以上まで押し進め、時間を稼いでくれた。
司令席から立ち上がり、背後でアヴァロンのシステム管理を統括していたロイドに声をかけた。
「例のおもちゃは出せるか」
「……まだ調整段階、ですけど……?」
渋面を浮かべる男はそれが嫌であると、表情だけで分かりやすく伝えていた。しかしここまで来ればそうとも言ってられない。手段を選べるほどの余裕は、我々解放軍に最初からないのだ。
「なんだっていい。間もなく帝国軍のナイトメアフレームがアヴァロンに強襲を仕掛けるだろう。それを凌げれば良い」
「……殿下がそこまで言うなら、まあ……」
ロイドは渋々といった調子でポケットに手を差し伸ばし、一つの鍵を取り出した。それを受け取り、急いでナイトメアフレームの格納庫へ走った。
このアヴァロンは複数のナイトメアフレーム同時格納が可能で、艦首に備え付けられたランチャーから機体の射出を行える。つまりナイトメアの空母的な役割も果たしているのだ。
格納されていた予備機のうち、漆黒に身を包む新型機のハッチを解除した。正式なパイロットがまだ決まっていないこの機体は、ナイトメアフレーム第八世代に相当する。最新鋭にあたる次世代機ではこれまでのシリーズになかった新操縦システムが採用されており、従来の強大な突破力だけでない新たな性質を持つ。運用方法の幅は未知数と言えよう。
操縦席の形は新システム登用の為、見た目は大きく異なる。スラストレバーやスロットル、操縦桿といった物理機材は姿を消し、代わりに手元には大きなディスプレイモニターが配備されている。
この機体から新たに搭載されたドルイドシステムは攻撃や防御の演算をハイスピードで処理、展開する装置だ。ランスロットに搭載された情報収集装置ファクトスフィアを上回るスペックを持ち、より正確な予測攻撃、無駄のない防御を行うことが可能になる。
しかしこのシステムは運用方法は少々、いやかなり難ありだ。それらの演算および機体への入出力は操縦主の半手動となり、戦況を読み、戦線でうまく立ち回りつつそれを行わねばならない、という扱いづらさがあった。非常に長けた情報収集能力を持ちつつ、それをどう扱うかは、ひいてはマシンの能力をどこまで引き出せるかはパイロットのドルイド適性に依存する。
操縦席に体を滑らせ、起動キーを差し込んだ。タッチパネルに明かりが灯り、パスコードと生体認証が承認されるとすぐさま機体は起動する。
コックピットの脇にある無線機のスイッチを押し、外部接続用の周波数を決定する。そしてマイクを起動し、通信相手の機体番号を入力し、無線要請を送信する。声なき声はすぐさま届いたようで、通信はすぐさま接続された。
「スザク。そちらの状況は」
『上空からモルドレッドがハドロン砲を使って、アヴァロン相手に消耗戦を仕掛けてる。ゲフィオンディスターバーが破られた以上、これ以上の時間稼ぎは難しいだろう。是非、出撃許可を』
「お前は総督府の建物の背後を陣取る形で上昇しろ。地下通路を使って一台の車が現れるはずだから、その中の要人を守りつつ総督府本部の司令室へ向かえ」
『で、でもこの戦況では』
「構うな」
短く告げたあと、機体をアヴァロンから射出させた。上空を滑空しながら見下ろした地上では未だ帝国軍と解放軍の小競り合いが続き、総督府の建物からは黒煙が立ち上っている。
本部の前に立ちはだかる様にして、フロートシステムによって機体を浮遊させつつ、目視で確認できるほど差し迫っていたナイトメアフレームの群衆を、射程圏内に捉えた。
速度と範囲と出力量をドルイドシステムに手動で入力し、それらを殲滅する為の攻撃を算出させる。それと同時にこちらへ向かってくるミサイルや銃撃を受け流す為の防御装置にもアクセスし、入力を行った。
全ての操作を最終決定するエンターキーを叩く。
次の瞬間、コックピット前面の視界部分が閃光に塗り潰された。
この機体、蜃気楼は上腕部に備えたふたつのハドロン砲装置に加え、絶対守護領域と呼ばれる防護バリアシステムを展開することが可能だ。まだ調整中ということもありその最大出力は未知数ではあるが、恐らく現存する兵装ではそう貫くことは困難であろう。
無数の攻撃が炸裂する中、それらをすべて演算装置により弾いてゆく。気が遠くなる作業だ。一瞬の予断も許されない。ひとつのミスで機体はおろか、背後にある総督府ごと爆散させられるに違いない。
アヴァロンへの攻撃を一旦止めたモルドレッドが蜃気楼に照準を合わせ、四連のシュタルクハドロンを向けてきた。直後一斉照射が行われ、ドルイドシステムは即座に攻撃を弾く為守護領域を展開した。
「……ジェレミア。今居る位置から三時の方向に急上昇させ、その先にある赤紫のナイトメアフレームにジークフリードごとぶつけろ。この戦線から弾き飛ばせ」
『御意』
返事の直後、モルドレッドは上空数千メートルまで猛スピードで叩き出された。モニタに映るふたつの機影はぴったり寄り添うように射出されたあと、二機は同時にロストマークに変わった。
モルドレッドの砲撃力と突破力は一番の厄介だった。それを真っ先に解決できたことは大きな成果だ。
次に厄介なのは、もう一機のラウンズだ。これ以上ラウンズ機が合流されるのも作戦に支障が出る。こちらも早急に排除し片付けたい問題である。
「……カレン。右に10センチずれろ」
『……は、はい』
その指示の直後、蜃気楼が弾いた弾丸の一つが、紅蓮弐式とトリスタンの双方に向かって弾き飛ばされた。流れ弾のごとく地面に着弾し火薬が炸裂し、紅蓮はそれを間一髪のところで躱した。あと左に10センチでもずれていれば、コックピットに弾丸が着弾していたに違いない。
トリスタンも間一髪で避けたものの、着弾後の爆破威力までは想定していなかったらしい。大きく粉塵を上げるそれに視界と足元を取られ、受け身に徹した為に次の行動が半歩遅れた。
紅蓮は輻射波動を起動し、右腕を既に構えていた。開かれた鉤爪の手のひらはコックピットを掴むことはなかったものの、衝撃波をまともに食らったトリスタンは使い物にならない。コックピットはその場で緊急避難の為に射出され、ラウンズは続けて舞台から退場することとなった。
「よくやった、カレン」
『……』
あちらから声は聞こえない。むしろ、よくも出し抜いてくれたな、という怒りに似た雰囲気が伝わってくる。しかし今は機嫌を宥めてやれる余裕はない。
帝国軍が率いる大勢のナイトメアフレームの大群は第一波をなんとか往なし、続いて第二波がこちらに近づこうとしていた。だが彼らをここで相手していても埒が明かない。本作戦の目的は蜃気楼の動作テストでも帝国軍との手合わせでもない。
各個撃破はここまでにしておいて、ひとまず総督府の内部へ先に着いているであろうスザクともう一人を追うほうが適切だ。
「俺たちも追うぞ」
『何を?』
「今頃帝国宰相が相対してるだろうさ、皇帝の本当の目的に」
蜃気楼を建物の裏手に着け、コックピットから降りた。紅蓮はぎりぎり許容範囲内であるが、蜃気楼だと全高が建物内部の高さを超える為、搭乗したままでは立ち入れないのだ。そこで一旦機体を捨て置いて、紅蓮の肩に乗せてもらいながら内部へ進む、という急場しのぎの作戦を立てた。
裏庭も廊下も階段の踊り場も、目に映るすべての景色が見る影もなく荒れていた。戦いの痕跡が生々しく残るそこは、いまだ電源の入ったままのナイトメアフレームが横たわり、射出できずに留まったコックピットも散見される。帝国軍も開放軍も、この屋内での乱闘はほぼ互角だったと言えよう。
紅蓮の機体がキャッチする情報によると周辺に生体反応や稼働しているナイトメアフレームは一機も見当たらず、これらは全てロストしているか、パイロットがコックピットで絶命しているかのいずれかだ。
弔おうという気概はまだない。なぜなら戦いはまだこの先にも残っているからだ。
道すがら、紅蓮の通信ケーブルを用いてアヴァロンとの交信を試みた。司令官が不在となった後も、あの浮遊艦艇は今後の作戦で必要不可欠となる。
「セシル。ブレイズルミナスを発動させながら総督府施設付近まで下降してくれ」
『畏まりましたが……。帝国からの第二軍が戦線を保ったまま総攻撃をしかける可能性が』
「織り込み済みだ。アヴァロンを建物の三階、北西側に着けてくれないか」
『え、ええ』
「救助用ハッチを開放し、いつでも人が乗り込めるようにしておいてくれ」
『殿下がお乗りになられるのでしょうか』
「いいや、恐らく乗ることになるのは宰相だ」
『シュナイゼル様が……?』
何故ここでその名前が出るのだと驚く彼女の声を他所に、紅蓮は廊下の突き当り奥の扉の前で立ち止まった。
「では通信を切る。……無事を祈っている」
廊下からは部屋の物音が聞こえない。一体何が起こっているのか、ここからでは想像もつかなかった。
「カレン、開けてくれ」
紅蓮に乗りこむ彼女に指示を下すと、彼女は乱暴に木製扉を破壊してみせた。鉤爪の右手が振るわれると、呆気なくその入口は開かれる。
それは開けてみるまでは何が起きるか分からない、パンドラの箱でもあった。
「……こ、これは一体……何故副総督まで、ここに……」
毛足の短い絨毯が敷かれた室内は少々埃っぽい、しかし広々とした広間であった。北向きに面する窓際には執務机と応接用のソファやテーブルが備えられ、至ってなんの変哲もない作りに見えた。
扉とは対角線上に存在する、地続きの部屋を除いては。
「やあルルーシュ。首尾よくここまでたどり着けたようだね」
「兄上。ご無事で何よりです」
「枢木准尉の護衛のおかげさ」
「道中に敵兵でも潜伏していましたか」
そう尋ねると、シュナイゼルはゆったりと頷いた。
解放軍と帝国軍は相打ちとなり双方共倒れで決着が着いていたと思っていたが、結果は予想と反していたらしい。
ナイトメアフレームは使い物にならず、コックピットから抜け出した帝国軍の生存者らは、この建物内の各所に歩兵として潜伏。騒ぎが沈静化したあとに訪れるであろう解放軍の人間を捕捉し、皇帝に差し出そうという魂胆であった。
しかし実際に道中へ姿を見けたのはスザクが操るランスロットと、その装甲に生身で腰掛けるシュナイゼルであった。歩兵たちはこれでは戦いにならないと一目散に逃走を図ったが、ランスロットはシュナイゼルの命によりこれをすべて阻止し殲滅した。
「……そんなことよりも、だ」
シュナイゼルは冷たい笑みを貼り付けながら、広間の奥で立ち竦む一人の男を見据えた。
「バトレー将軍。このような騒ぎの最中、一体何用でこの空き部屋に?」
「シュナイゼル宰相……」
「正直に話してくれたら処分を見逃してやったっていい」
「兄上」
思わず声を出して彼の発言を遮った。
恐らく此度の黒幕、あるいは主要人物だ。最重要参考人である。捕縛し銃を突きつけ、知っていることをすべて吐かせたっていいくらいだ。背後に控えたままのランスロットは沈黙を保ったまま、事態を静観している。
「焦らなくとも大丈夫さ。このあとすぐに帝国からナイトメアフレームの大挙が押し寄せる予定だ。どのみち決着は見えている。……だからバトレー」
シュナイゼルは穏やかな口調で、いつになく落ち着きを払っていた。両手を背中で組みながらゆったりとした歩調で一歩ずつ、前へ進む。
「その奥に隠しているカプセルと、中で眠っている女性は何者だい?」
部屋の暗がりにあるらしいそれは、今の自分の位置からは見えない。なおも歩みを止めないシュナイゼルは、怖気づくように後退するバトレーを徐々に追い込んでゆく。
「皇帝の趣味かな」
「……け、研究を……」
「研究?」
宰相は語気を強め、言葉の先を求めた。
「皇帝は不老不死を夢見ておられるようで……その女が必要なのだと……研究を進めて解明しろと……」
バトレーは何かに怯えるように頭を抱え、膝を床に着けて震えていた。
研究というのは、たとえばどういう類のものだろうか。その女が生きているのか死んでいるのかも釈然としない。人体実験などとくれば人道的な問題も生じる。第一、不老不死の研究なんぞ現代の倫理観から大きく道を外しているし、科学的にも立証は不可能だ。いくら人類が夢見ようと、そこへ辿り着くことは出来やしないのだ。生きとし生けるものすべて、いつかは老いを経て死ぬ。不変的な自然界の条件は人間の力じゃ変えられない。
生の時間に限りがあるからこそ、今を生きる人間は与えられた時間をどう使おうか苦悩し、足掻き、意味や意義を見出すのだ。いつ死ぬか分からないから、今この瞬間に命を懸けて明日という人生の時間を欲する。限られた時間をどう生きるかを一生かけて探すことが、人生の意味そのものなのだ。
無限の生は想像するだけで恐ろしく無為で、無意味だ。抑揚も感動も変化もない、一次元的な世界。限りがないから明日への希望も絶望もなく、閉塞的な感性は先細って死んでいくに違いない。肉体の生が続こうと精神が先に死にかねない。心の機微が生まれず人間らしさを失った人間を、果たして生きていると手放しで形容することが出来ようか。
「……とにかくこの事は本国に持ち帰り、発議してみよう。皇帝に対する不信任と後退を意見として纏めてね」
シュナイゼルが声を落とした瞬間だ。
部屋の大窓のガラスが不意に割れ、破片が飛び散った。
『宰相閣下! 今すぐアヴァロンへ飛び乗って下さい!』
窓の外では待機させていた飛行艇が宙に留まり、拡声装置でそう呼びかけていた。窓の横に据えられるようにして伸びたタラップが暴風で揺れている。シュナイゼルは振り落とされないよう手摺に捕まりながら、飛行艇の内部へ避難した。
「バトレー、早く!」
「は、はい……!」
呼びかけられたバトレーは件の女を担ぎながら、同じようにタラップをよじ登っていった。紅蓮は割れかけた窓を突き破り、外への脱出を力づくで行う。
風向きが怪しい。雲の流れる方向と、窓の外に吹く風の方向は真逆に見える。直後、拡声装置からの声が響いた。
『総督府正面、第二軍到着します! 残りニ十秒で戦闘部隊のミサイルが着弾……!』
「予定変更だ! 俺はランスロットとここから離脱する! アヴァロン操行の指揮権はシュナイゼル宰相に移管させてもらう!」
『ですが援護もなしに単騎突破は』
「つべこべ言わず戦線離脱しろ! これは命令だ!」
アヴァロンが方向を百八十度変更させ、総督府から全速で飛び立ってゆく。かの飛行艇が搭載するブレイズルミナスはハドロン砲の攻撃さえ弾く、従来用の強化版だ。通常の対地ミサイルや砲撃を食らったところで痛くも痒くもない。
「ルルーシュ、早く飛び乗れ!」
コックピットハッチを半分ほど開放し、操縦席から顔を表したスザクが手を差し出した。ちょうど膝を付き地面に屈んだ姿勢のランスロットを見遣り、出された手を迷わず握った。すると腕の力ひとつで一気に難なく引き上げられ、次の瞬間にはコックピット内に体を押し込められていた。
「おま……」
「頭と膝、ぶつけないように気をつけて。オーバーヘッドパネルにはライトスイッチと失速警報装置が並んでる」
「知ってる。そうじゃなくて」
「全速発進、敵機との戦闘をなるべく避けつつ、本国への帰還に努めます」
「ああそうだ。でもお前、これは」
「ランスロット、発進します!」
話がまるで噛み合わないまま、機体は窓枠を破る形で外へ飛び出した。コアとなるサクラダイトが機体の速力を押し上げ、時速数百キロという猛スピードで闇夜を切り裂いた。
途端に体へかかる重力と圧力に息が詰まり、耳鳴りが脳髄に響く。思わず目を閉じ、重さと浮遊感に耐えた。
「僕にしがみついてて」
歯を食いしばりながら瞼を起こすと、平素と変わらない顔色を浮かべた男の横顔が目前に見えた。彼の膝の上で横向きになった体を預け、言われるがままモビルスーツ越しの体に腕を回した。
不本意ではあるが緊急事態ゆえ仕方ないことだ。予測不能な事象は自分の意思で制御下に置くことは非常に困難であり、それがたとえ望まぬ状況だとしても、まずは受け入れる覚悟が必要なのだ。そこからどうやって現状を脱却するか。司令塔の頭脳を務めた自分ならそのことを一番よく分かっているはずだ。
いるはずなのだが。
「……その、この体勢は操縦に不都合が生じないか」
「背に腹は代えられないだろ。それに僕的には、このほうが俄然負けられない気になる」
「馬鹿言うな」
背後からは複数の戦闘機がランスロットを追尾し、幾つもの照準点が機体の背中を這っていた。その後ろに控える一機のナイトメアフレームが誘導爆弾を一斉放射し、雲をかき分けて猛スピードで差し迫ろうとする。
「旋回してこれを撒きます」
宣言と同時に、彼は細かな計器類を操作しセンターペデスタルのレバーを握り締めた。
「……ッ」
視界が360度回転したと思えば、今度は体を押し潰すような強烈な重力、浮遊感の応酬。
コックピットの計器の針は激しく揺れ、機体の異常な動きを警告する装置がけたたましく鳴り響く。彼はそれを手動で切り、再び操縦桿へ右手を置いた。
誘導爆弾の追跡を何とか躱したかと思った矢先、今度は目前の視界を映すモニタに黒い影が一瞬、視界を遮った。
それの正体が一体何なのかを把握するより前に、強烈な爆風に機体が大きく煽られた。視界が揺れ、制御が出来なくなる。
「……っ、ぐぁ!」
どすん、と鈍い音が耳の傍で鳴ったかと思うと、隣からは苦しげな呻き声が漏れる。スザクは眉間に皺を寄せながら、操縦桿に両手でしがみつく様にして、機体の立て直しを図った。同時に速力は最大出力値を叩き出し、計器類は悲鳴を上げる。
コックピット内にまで激しい振動は伝わった。それは恐らく、ナイトメアフレームが物理的に耐えうるぎりぎりの最大速度なのだろう。これ以上の加速を行うと音速の壁を遥かに超えた機体は、衝撃波が生み出すソニックブームにより空中分解を起こす。設計上、想定外の物理衝撃はどんな装甲をも容易く砕くのである。
「……は、……」
「……スザク?」
ふ、ふ、と明らかな呼吸の乱れを触れてあった手のひら越しに感じ取り、その苦しげな顔に問うた。じっとりと輪郭を伝う汗と白み始めた唇の色は明らかな体調の異常を知らしめている。
「……ほんの軽い、脳震盪だよ……」
「っ、おい!」
操縦桿を握る両手は小刻みに震え、機体はやや左右にぶれるように揺蕩いながら不安定な直進を続けていた。
「み、右方向からレーザー光線の照準点が見える! 左向きにやや旋回しつつ、緩やかな上昇ののち急降下だ!」
「……了解」
次の瞬間、彼は体の変調に抗いながら、言葉通り完璧な操縦で大空へ翻ってみせた。殆ど閉じられかけた瞳で計器とモニタを見つめ、これを操作する。
「自覚症状は」
「視野狭窄と頭痛、吐き気、判断力の、低下……」
「おい! 今度は真後ろからミサイルだ、機体を左右に振って上昇しろ!」
「……了解」
引き絞るような声音を発した男は、言われたとおり目一杯機体を操作し、自分の言葉を忠実になぞる動きを行った。向けられたミサイルは空中で爆発しながらも、その風圧でランスロットの左腕部を弾き飛ばした。コックピットモニタには機体の欠損を示すエラーが表示され、警報音が鳴る。
このままでは徐々に機体は失速し、海の藻屑となるか撃墜されて空中で爆散する他ないだろう。コックピットの機器についてひととおりの知識は心得ているが、操作するとなれば話は異なってくる。あまりの扱いづらさで軍部の荷物になりかけていた究極の戦術兵器だ。理屈でどうにかできる代物ではない。
日本列島を数千キロ離れた今も、なお軍部の追撃は止まない。ここまで執拗に追い詰めるということは、皇帝からはランスロットの撃墜命令が下っているに違いない。総督府に隠されていた実験体を見られたからには、生きて帰さない。そういう執念を感じる。
建物から離れる前から軍部の猛攻に遭った。ともすれば皇帝の本心は、研究の証拠が残る総督府とともに瓦礫の下へ自分もスザクも、ひいてはシュナイゼルまで、生き埋めにする覚悟だった可能性が高い。死人に口なしだ。協力者であったバトレーごと地に埋め、無かったことにするつもりだったのだ。
到底許されざる行為だ。このままあの男の思惑通り事を進めて溜まるかと、猛烈な憤りと恨み辛みが募る。しかし恨み言を数えるより先に、現状の問題を解決するほうが先だ。
コックピットの外からは轟音が鳴り響き、先程受けた損傷の激しさを物語っていた。この悪夢のような戦況をひっくり返す一手を、暫く考えあぐねた。
『……やあ、ルルーシュ。ここまでよく持ち堪えてくれた』
「兄上……?」
激しく揺れる計器の物音に混じって響いたのは、久方ぶりに聞く気がする兄の声だ。オープンチャットを通じて繋がれた通信のようで、受信周波数を適切な数値にチューニングする。ついでに、コックピット内を映すカメラのスイッチは敢えて消しておいた。
『たった今、本国議会でシャルル・ジ・ブリタニアの退任が賛成多数で決議された。君たちを追尾する軍隊は皇帝の命令権失効により即時解体・帰還が命じられる。……私の名前でね』
狭い操縦席に響く吉報に、張り詰めていた緊張の糸が一気にほつれて千切れた。瞬間、どっと全身に湧き出す汗や喉の乾き、激しい心臓の動悸に気が取られる。人の心配をする前に、もっと自身を省みるべきだった。どうやらこの体も限界が近かったらしい。
『そのまま本国への帰還は可能かい? ランスロットの損傷が激しいのであれば一旦海に不時着してから、こちらで潜水艦を迎えに出そう』
「いえ。エナジーフィラー残量はまだありますから、このまま安全運航で本国へ向かいます。念の為現場には医療スタッフを集めて頂けませんか」
『分かった。何かあったらまた連絡するよ。くれぐれも気をつけて』
「はい」
音声通信を切って、先程から容赦なく伸し掛かってくる体に目を向けた。ぐったりした様子であるが、さすがの体力と言えようか。彼はなんと驚くことに、既に自身の治癒力で体調を立て直し始めていたのだ。血色の戻り始めた頬はつう、と汗の粒が滴っていた。
「戻ったら診てもらえよ」
「うん、そうする……」
機体を自動操縦に切り替え、彼は漸く操縦桿から手を離した。恐らく汗で滲んでいるのであろう、手指を覆う白い手袋をおもむろに外して床に落としていた。操縦席のシートに背中をゆったり預けて、ぐったりした面持ちで目を伏せる。額に張り付いた前髪が不快そうで、指でそれを払ってやった。
「……僕たち、助かったんだ……?」
「そうらしいな……」
「本当に……?」
「……たぶん」
けたたましく鳴り響いていたエラー音や警報装置は一切鳴り止み、代わりに平常運航を示す緑色のランプが全ての計器とスイッチ、パネルに灯っていた。
嵐みたいな急展開が続いて、心と体はまだ現実についてこない。いつもより速い拍動はとくとくと心臓を叩いて、先刻の戦闘状態の余韻が体のそこかしこに残っていた。疲労と興奮と神経の昂り。喉のひりつきと血が上った頭、力が入ったまま抜けない四肢。
「ああ、今ものすごくキスしたい。君とキスしたいなあ。帰ったらしてもいい?」
「もう好きにしろ。どうにでもしてくれ。どうにでもなれ。俺は今、何も考えたくないんだ」
「僕も同意見だ。難しいことは喋りたくない」
「そうだな。喋るのも億劫だ……」
くったりと力が抜けた肢体を預け、預けられ。折り重なるようにコックピット内で脱力しきった自分と彼は、いつもよりずっと短絡的になった頭で取り留めもない会話をした。脊髄反射でキャッチボールする気のない言葉を交わす。
――自分はまだこの世界に生きている。生き永らえることを許されている。
たったそれだけのことが、ささやかな実感と感慨深さを芽生えさせ、ひどく幸せだったのだ。