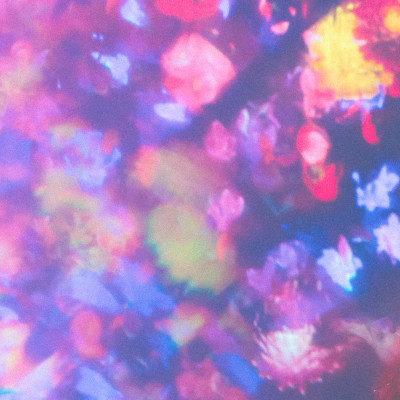
これをよすがとする 七話
世界中の報道関係、ニュース、新聞の一面を瞬く間に埋め尽くしたその人物の訃報は、今日日現在もあらゆる憶測や陰謀論、尾ひれのついた噂も含めて、多くの人々の記憶に深く刻まれている。
日本国首相・枢木ゲンブの急逝は当時の日本国全土を震撼させた。死因は自殺と発表された。しかし彼をよく知る政府関係者らはみな口を揃えて、”自殺の兆候は見られなかった”と供述している。
ゲンブは勤勉で生真面目で、自分にも他人にも厳しい人物だったという。どんな仕事に対しても真摯な姿勢で取り組み、国民に向けた演説や国会での答弁では豪胆無比を体現した昂然たる態度で意見を論述した。常に職務に誇りと自信を持ち、メディアに映るのはいつだって超然とした面持ちばかりだった。それは男の人となりを如実に表したものだった。
彼は帝国からの圧力に屈せんと、最後まで抗い続けた人物であった。世論の多くは帝国との戦争を支持しなかったが、この男だけは開戦も止む無しと捉えていたのだ。それを国会で発議したところ反対意見が噴出し、国民からも多くの反発を受けた。
しかし、かといって、ではこのまま日本を帝国に売り、植民地に成り下がるつもりか。抵抗の意思を示さねばそれは帝国の思う壺だ。戦わずして負けるなど国辱であろう。ならばやれるだけのことをやって、徹底抗戦をしたほうがベターだ。勝つことは絶望的かもしれない。だが、みすみす侵略を受けるより、何か一縷でも未来が変わる可能性があるなら、それに賭けたほうが建設的だ。
ゲンブは帝国への徹底抗戦を唱え続け、賛否両論を巻き起こし、政権の支持率は大幅に低下した。野党から不信任案が提出される事態に発展したが、これを棄却させ、その任期を全うすべく、暗雲が立ち込める未来の先を見据えていた。
彼の死はその矢先の出来事であった。前日まで国会で答弁を行い、会議に出席し、官僚幹部と意見交換を兼ねた食事会に参加していた。その翌朝一番のニュースで、首相の訃報が速報で流れたのだ。誰もが予想だにしなかった。
当初は誤報か人間違いだろうという意見が多く見られ、その速報を信用しなかった。速報テロップを流した放送局には苦情の問い合わせが寄せられ、事実確認の為、一時は速報が撤回されたほどである。
だがその後すぐ警視庁および国営放送局、そして政府からの公式会見が開かれ、ゲンブの死はまごうことなき真実であると証明されたのである。
いっそ事故死だと言ってくれたほうが、まだ信用できた。交通事故に巻き込まれたと言われたら、それは運命論じみた確率の話になるから、よっぽど運が悪かったのだろう、と納得できる。しかし自殺という表記は、誰もが理解すらできなかった。
自殺はさすがに有り得ない。嘘を吐くにしても、もっと上手くやれただろう。
テレビでは連日そうした声が聞こえ、それ以外の一般市民もそう思っていた。枢木ゲンブは何者かによって消されたのだと、口にせずともみな同じ意見を持っていた。
徹底抗戦を唱え続けた首相は多くの敵を作っていた。紛糾する国会は毎度怒号が飛び交っては収集がつかなくなるし、戦争に反対する国民の声も日ごとに大きくなっていた。首相は自分の意見を有利な状態で決議まで持ち込もうと、国会で意見論述する官僚や専門家たちを同じ思想の人種で構成させた。さすれば当然、首相一派と反対グループで完全に真っ二つの対立構造が生まれた。開戦するか、しないか。毎日のように討論はいつまでも平行線を辿り、論戦の収束は気配すら感じられなかった。
――ゲンブさえ政界から退場してくれれば、日本は帝国との戦争を回避できるのではないか。そんな愚かな妄想に耽る大馬鹿者が一人居たって、何らおかしくなかったかもしれない。国全体は毎日緊張状態に陥っていた。国民は恐る恐る日常生活を営むし、テレビは暗いニュースばかりだ。何か新しいことを始めようったって、でもいつ戦争が始まるか分からないし、と思うと気が滅入る。終末論じみた思想がまことしやかに巷で蔓延しだすと、いよいよもって市民の鬱憤や憂慮は集団ヒステリックへと加速していった。
ゲンブの訃報はある意味で、人によっては吉報だったかもしれない。開戦派の筆頭であり音頭を取っていたのはゲンブだった。彼が居なくなれば日本は戦争を始めない、という推論もある意味では正しかっただろう。
事実、日本は帝国との開戦を回避した。だから戦わずして負けることを認め、受け入れたのだ。ゲンブが最も恐れ、国辱だと謗った現実が、日本国に襲い掛かった。
既に過ぎた結果を見てどうこう言っても仕方ない。仕方ないのだが、あの当時の日本国は一進一退の猶予もなく、完全に手詰まりだった。逃げても攻めても訪れる結果は同じだとすれば、人死にを生まない今の現実がまだマシ、と言えるのだろうか。何を持ってマシだとか悪いとか、そうした判断に至るかは人それぞれの尺度によるだろう。(前述は命あっての物種、と考えた場合の話である。)
枢木ゲンブの死により開戦の道は閉ざされ、帝国の支配を甘んじて受け入れることに帰結した。傍から見れば首相の死が全てのトリガーのように思えるが、果たしてそうとも言い切れるだろうか。実際問題、日本は与えられた二枚のカードのどちらを切ろうと、同じ未来しか描けなかったはずだ。
なら、現状を回避するにはどうすれば良かったか。これも結末を知った今だから推察できることだが、最初に結ばれた日本と帝国の友好条約から、ひずみは生じていたのだろう。あの条約締結を契機として帝国は日本への圧力を加えてゆき、既得権益を貰い受けるまでになった。あの時点でもっと別の形の、たとえば多国家間による組織的な条約にするとか、やりようを変えれば未来の分岐はあったかもしれない。国家間の不均等な上下関係を是正するだけでも効果はあっただろう。日本は帝国相手に一対一で交渉を持ちかけたが、時期尚早だったのだ。
時計の時針は夜更けの時刻を指し、もう一時間もすれば日付を超えようかという頃合いだ。扉の向こうから音は聞こえない。
スザクが作戦から戻るまで、朝が来ようと待つつもりだった。待ち続ければいつかは帰ってくると分かっていたから、いつまでも待ってやろうと思えた。彼が戻るまで与えられた時間は自省と感情の整理と結論を出すために使うのだと、そう決めていた。だから待つことは苦でも退屈でもなかった。
時刻がちょうど日付を超えようとした時だった。
扉がノック音もなく唐突に開かれて。現れたのはここ数時間、帰りを待ち続けていたその人だ。ずっと見たかった顔が漸くこちらを向いて、少し驚いたように目を瞠っていた。
「スザク。おかえり」
「……あれ。ああ、そうか。ほんとに君、今までずっと、待ってて」
少し混乱した様子の彼は頭を抱えながら、何かを思い出そうと首を捻っていた。あー、とかうー、とか意味のない音が唇から漏れる。
「そうか。あれからずっと……」
「うん」
「そっか……」
数時間前までとは打って変わって、今度は随分と元気がなく委縮した様子だ。自信なさそうに宙を彷徨う視線はなかなか合わない。彼は覚束ない足取りで前に進んで、机の横に歩み寄った。
何も置かれてない机上の隅に、ぽつんと置き去りになっていたのは騎士章だ。物言わぬ証は人工的な照明に照らされ、誰かの手に収まることを待ちぼうけている。
「ごめん、ちょっと疲れてるから先、シャワー浴びてきて良い?」
「あ、ああ、うん。何なら明日にでも出直して……」
「いや待ってて。こんな時間まで待たせて帰すなんて悪いから」
「……」
「ね」
数時間前までとはやはり、別の人みたいだ。というより、自分がよく知るのは今のスザクで、取り繕ったような引き攣る笑みと下がった眉は、それだけ彼が体裁を保とうとしている証左だ。今は疲労感でそれもままならなくなっているようだ。
なら、この部屋を出て行く前の男は、スザクのどの部分が現れていたのだろう。
薄い壁を隔てた向こうから水の滴る音が断続的に響いていた。浴槽の床を叩く水の粒と、シャワーヘッドが壁にぶつかる音。ざあざあと鳴り続く雨飛沫は耳の遠くで木霊して、なかなか離れない。
奇妙な感触だ。彼の私生活に一歩踏み入って、知らない部分に触れていく喜びと、それを許される擽ったさ。上司と部下、上に立つ者と従う者、支配者と被支配者、明確な線引きがこれまでは二人の間に横たわっていた。でも今はその境界線がぼやけて曖昧になっているような気がした。飛び越えるというより、二人でその見えない線を消してゆくような感覚である。
踏み込むことを許す者、許される者。理解されたい人、したい人。自分たちもそうなれたら、理由がなくても親しい距離で居られるのだろうか。
スザクが戻ってきた時、対話を拒絶をされていたわけではないのだと気付いて、心底安堵した。でないと自分は、彼の口からその過去を語らせたことを一生悔いることになる。言いたくないことを言わせてしまったと、心の弱い部分へ無遠慮に踏み込んでしまったと、自責の念に駆られるだろう。そうなるともう、自分は彼に合わせる顔がない。
「……おまたせ」
「ん? は?」
ユニットバスの扉から顔を出した男の姿を見て、思わず険しい声が漏れた。
水気を含んだ髪の毛、何も身に着けてない上半身と、肩にかけられた湿ったタオル。本人の表情は至って平常どおりだ。むしろ湯を浴びて少々すっきりした面持ちですらある。
「風邪ひくだろ、服くらい着ろ。髪も乾かせろ」
「ルルーシュは僕のお母さんなわけ?」
「馬鹿言ってないでドライヤーを貸せ」
「自分でやる、やります、あんまり大きい声出さないでってば」
可笑しそうにけらけらと笑う男は再び扉の向こうに消えて、暫くしないうちにドライヤーの稼働音が聞こえてくる。モーターが鳴らす機械音は数分もしないうちに途切れて、それから、布の擦れる音が続く。
身支度を終えたらしい男が今度こそ浴室から抜け出て、狭い机の端に体重を預けるようにして、腰を据えた。
「これでいい?」
「及第点」
襟首の伸びたスエット生地の上着と、素足に室内用スリッパというだらしなさが視界の隅に映って、どうにも気になる。
手厳しいなあ、とのんびりした調子の声が落ちてきて、とくに相槌も打たず放っておいたら、会話はそこで終わった。しん、と静まった室内はどこか気の抜けた雰囲気が僅かに揺れ動く。じっとりと重々しい空気の温度は、数時間前に嫌というほど吸った匂いと似た何かだ。
「……僕らなんの話してたっけ」
「騎士になってくれと頼んだが、お前に振られた」
「振ら……」
「違うか」
引き攣る表情を張り付けたスザクの、ぱさついた前髪に触れた。ドライヤーの熱に当てられて乾燥してしまってるのだろう、毛先は傷んで跳ねている。ちゃんと手入れをしないからこうなるのだ。光に透かすと、色の抜けた枝毛が金糸のようにちらちらと煌めく。
「……言っただろう、僕は」
「親を殺した」
「……」
「でも誰も、僕を責めなかった。それをいけないことだと分かってるのに、叱られることもなく、守られてばかりだった」
「それを誰かに口外したことは」
「……君が初めてだ」
「どうして俺に教えたんだ」
「そうでもしないと、諦めてくれないと、思って」
跳ねた毛に隠れた瞳がちらりと顔色を窺ってくる。滲んだ緑がしきりに、不安そうに揺れていた。
「些事だ。それに、自分の過去を交渉の道具に使うな」
「な……」
「俺に七年越しの罪を与えられると、少しでも期待したか」
「……してない」
瞳を不意に逸らされた。否定した言葉を否定するかのような仕草だった。否定の否定は肯定だ。
前髪に触れていた右手を掬われて、机の上でゆったり握られた。気安く触らないで、と言われた気分になる。
控えめに竦められた肩と後ろめたそうに伏せられる瞳は何かに怯懦しているかのようだ。彼の心に巣食い続ける原罪は彼自身を雁字搦めにして、意思決定や行動指針にさえ影響を及ぼしている。むしろ彼は望んで罪の意識にすべてを委ねており、時にそれは命を投げ出すことにも繋がっている。
乱暴な言い方をすればある種の逃げ、思考の放棄だ。自死で許されるものかと、都合よく死ねたら満足するのはお前だけだと、そう言ってやりたい。
許されたいと願いながら自分を罰し続ける矛盾は、やがて彼自身の人格の一部分として確立された。それは恐らく、一生かけても残り続ける呪いだ。かさぶたを何度も剥がしては血を滲ませて、やっと塞がった傷口には一生消えない跡が残った。そんな消せない傷痕と、彼は一生寄り添うように暮らしてゆかねばならない。
「俺に一つ、考えがある」
触れられた手を握って、指を交わらせた。節くれ立った太い関節がきりきりと擦れて痛い。
「お前も知ってのとおり、俺は解放軍の指揮官だ。命令ひとつで兵士の生き死にが決まる。つまり俺の言葉は呪いみたいなもんなんだ。俺は罪のない兵士たちに呪いをかけてる」
「ま、待って」
焦ったようにスザクが声を上げた。
「そんなの物は言いようだ。君の命令で救われた場面も多くあるだろう。事実、解放軍は軍部を出し抜いて……」
「物は言いようだと? なら、お前は日本国の開戦を阻止した英雄じゃないか」
「は……」
表情がわかり易く強張った。開かれた目は怒りにも似た感情を孕んでいる。それでも構わずに言葉を続けた。
「首相が日本のトップに居続ける限り、帝国との戦争はいずれ不可避だった。あの男は策士だ。ある意味で優秀な政治家だった」
「知ったふうなことを……」
「分かるよ。俺の父親……ブリタニア皇帝は領地の拡大と争いにしか目がない。子供を競わせ、優秀な遺伝子を選定する。負ければ虐げに遭って……」
「……恨んでた?」
「ああとても。殺してやりたいくらい」
男は声を落としてそう、とだけ呟いた。
「スザクの過去を知って、俺は確信したよ。自分が納得する方法で得た結果を信じようとな。教えてくれて有難う」
「感謝されるとは、思わなかったな」
「なら礼のついでに受け取ってくれないか」
これを。
そう言いながら左手で差し出したのは騎士章だ。しかし尚もスザクは首を横にゆるく振る。ごめんね、それだけは受け取れない。優しく諭すように振りかぶられる頭のつむじを見つめた。丸まった毛先がふわふわと揺れるさまが、気が抜けるほど呑気だ。
「それに、俺ならお前の欲しいものをくれてやる」
「欲しいもの」
「罰が欲しいんだろう。いくらでもやるさ」
「……」
彼は唇を引き結んで、じいと見つめてきた。
「さっき言ったとおり、俺の言葉は呪いなんだ。誰も俺に逆らえない」
「……」
「スザクには生き汚くなってもらおう。そうだな、その命は罪滅ぼしではなく俺の為に使えば良い。俺を守る為に」
「……本気で言ってる?」
「お前にとって都合の良い罰ならそれは褒美だろ。甘えるな」
「だから生きろと」
「勿論」
"呪い"なんて所詮は体のいい口実だ。名目はなんだっていい。願い、祈り、望み、憧れ、夢。耳障りのいい言葉ならいくらだって、誰だって思いつく。でも月並みな標語じゃ心は揺さぶれない。今の彼にとって魅力的で、かつ興味が出るような、旗幟鮮明さ。
スザクもそれを理解しているだろう。こんなもの、要はただの言葉遊びだ。思いつきの出任せである。逆にそれしか、彼を説得させる方法が浮かばなかった。手も足も尽きて、最後に残った術だ。そして自分はこの言葉にしか縋れるものがない。
「受け取ってくれないか」
死にたがりの罪人に安楽死は許さない。それをするなら惨めたらしく長生きして、自分をここまで生き永らえさせた環境と人々に感謝してもらわねば困るのだ。
自尊心が低い奴、肯定感が弱い奴は総じて、自身の身の回りがどれだけの助け合いと個々人の努力で成り立っているかを知らない。自分だけが世界から弾き出されたような顔をしているがその実、地に足が着いている時点でその歯車の恩恵を受けているに違いないのだ。それを誰かに用意された運命だと悲観している。
スザクは感謝の言葉を口にすれど、その目に自分の姿が映ったことは一度としてない。虚空を映す無気力な瞳に生気はない。
感謝されたいわけじゃない。彼には今一度、どれだけ大勢の人に期待され、心配もされ、愛されているかを自覚してもらわねばならない。
「……受け取るよ、その呪い」
騎士章を置いた手のひらに、甲が重なる。
「過去の堕罪に上書きしたか?」
「うん、した。上書きした。上書きできたよ」
握られた手に痛いほどの力が籠められる。皮膚を抓り上げられるようなひりつきに、でもそのことは一切顔に出さないよう努めた。
「もう僕にはこれしかないんだ。……だから教えてほしい」
色の抜けた顔がゆっくり持ち上がる。目線を合わすように背中を屈めた男は感情の読めない声色でおそるおそる、それを尋ねてきた。
「どうして僕にそこまで拘る?」
「前にも言っただろ」
「友達だからって、本当にそれだけ? 友達なら君は、誰にでも騎士章を託す?」
「そ、そんなこと聞いて、どうする……」
「誤魔化さないで」
逸らそうとした視線を再び捉えようと、頬の輪郭のあたりに手が伸びた。顔ごと支えられるともう動かせない。気まずくて噤もうとした唇もあっさり見破られた。ルルーシュ、と強い口調で名前を呼ばれ詰問しようとする。
「誤魔化してなんか」
「してる。人には喋らせるくせにルルーシュはだんまり?」
「……」
そんなつもりはない。ないのだが、この状況では何を言おうと逆効果だ。場のイニシアチブは完全にこの男に委ねられていた。
鋭い眼光と据わった目つきは、一切の誤魔化しや御託を許さないのだろう。まるで身ぐるみを剥がされているような心地だ。深層心理を暴かんとする鮮やかな新緑が、その奥にある本能を引きずり出そうと躍起になっているのだ。
なんと言おう。どう表現すれば納得を得られるのだろう。端的でわかり易く、かつ相手の心に響く、印象的な表現。比喩。形容。描写。叙述。
「わ、わかった……」
「何が?」
「好きなんだと思う……俺は、スザクが」
「好き……」
「うん。だから、お前じゃないと駄目なんだ、俺は」
理由はもっと、人の感情の根源的な、シンプルで唯一無二の、他に言い換えの利かない、一元的な概念だった。
「あ、あは、ははは……そう、そっか、そうだったんだ……」
「なんでお前が赤くなる」
「答え合わせしなきゃ駄目?」
答え合わせ? どういう意味だ? そう首を傾げると、おもむろに顔が近づいてきた。なんで、と声を発しかけた瞬間、僅かに開かれた唇のあわいにそれがぴったりと折り重なるように触れる。
でこぼこを埋め合わせるみたいに、隙間なく、空気がそこで縮こまる。呼吸の流れが断ち切られ、時間の経過がやけに遅くなる。
「……あ」
「なんで……」
「口への接吻は、万国共通の意味、じゃなかった?」
「俺はそういうつもりじゃ、」
「じゃあもっかい試そうか。ルルーシュが自覚するまで何回でも、答え合わせしよう」
言葉の先をわざと遮って、スザクがよく分からない提案を持ち出してくる。先程まで消沈していたくせに、やけに血色の良いかんばせが恥ずかしいくらいの好意を伝えてくるから、断るに断れない。嫌な気はしなかった。
何度も口づけを施され、まるで浅瀬で泳ぐ魚の気分だ。水面から空を仰ぐように顔を上向きにさせられ、たまに与えられる息継ぎの瞬間に、緑色に透き通る眼と目が合う。水で湿った目尻がきらきらと光って、濡れた睫毛が揺らめく仕草を、ぼんやりと追っていた。
足りない酸素を補う為に口を開けば、その隙間を埋めるように唇が深く交わって、相手の呼気が口腔に満ちる。ふうふうと肩で息を繰り返しながら、差し伸べられた腕や肩にしがみつくので精一杯だった。深いことは何も考えられなかった。どうして、という主語のない疑問が脳裏を埋め尽くして、それを声にしようものなら、呼吸ごと奪われる。苦しい。でもそれだけじゃない。
「……嫌だった?」
耳の裏のあたりに指を差し入れて、スザクはことさら丁寧に問うた。
「……ううん」
「どんな感じ」
「ふわふわするような……」
「……ふわふわ?」
スザクは笑いを堪えるような素振りをしながら、言葉の続きを催促してきた。
どんな感じ、と言われても表現が難しい。熱いような熱くないような、溶けそうで溶けない、気が遠くなるようで現実に戻される。揺り籠で意識が揺すられるような感覚だ。酩酊ではなく心地よさが勝るくらいの、緩やかなリズムで揺さぶられる。
「もっとしてみようか」
「もっと……」
うん。二人で同時に頷いて、どちらからともなく顔を寄せ合った。
柔らかい唇は重なるたびに形が変わっていくし、熱い息が鼻の下に当たると動悸を覚えた。自然とそれを求めていたらしい自分は彼の体を無意識のうちに引き寄せていた。さらに強い力が籠もる彼の手は顎を掴んで離さない。
「う……」
「……」
「んう……ふ、う」
唇同士の交合に夢中になっていた。ばくばくと鳴り響く心臓が煩くて、それ以外は自分と彼の息の音しか聞こえなかった。
「ん……?」
だから気づくのが遅れた。腕のあたりに当たる何か、その存在を漸く悟ったのは身じろいだ瞬間のことだった。
「その、だから」
「……」
「出撃のあとはいつも、こうなんだ。神経が昂ぶってて……君を待たせたくなかったのも、それが理由で」
「は?」
「だって格好悪いじゃないか。それにルルーシュだって、嫌だろ」
後ろめたそうに目を背けた男は、密着させていた体をそっと離した。
僅かに兆していたらしい股間は曰く元からだったようで、言い訳じみたことを述べながら男は後頭部を掻いていた。一見だらしなく思える布の余ったスウェットは、身体の状態を隠すためのカモフラージュだったわけだ。
不思議と不快感や嫌悪感はなかった。同性のそうした仕草や欲の顕れなど、毛程も興味がないどころか不愉快でしかないのが常だったが。猥談や下世話な話題があまり得意ではないぶん、ましてや同性の肉欲の顕現を前にここまで冷静で居られるのは自分でも意外だ。
「嫌とかそんなの、なんでお前が決めつけるんだ」
「やってみないと分からないってこと?」
「やるって、何を」
スザクは一瞬、開きかけていた口を閉じた。
「……あー、うん、うん……何でもない……」
「スザク?」
「いや、ほんとに、違うから。うん、ルルーシュはすごく純朴で綺麗なんだって、よく分かった……」
「それは俺を馬鹿にしてるのか?」
「してない。自分の愚かさを思い知らされたんだ」
釈然としない供述だったが、これ以上何を言わせてもこれといった手がかりは掴めなかった。スザクが言わんとすることが結局分からないまま、時計の針はさらに進んでゆく。気がつけば間もなく深夜の二時を指そうとしていた。
「……そろそろ総督府に戻るよ」
「うん、そのほうがいい」
肩へ伸びかけていた手が引っ込んで、代わりに堅苦しい微笑みが返される。一体何のつもりだと睨むと、それより帰る手段は、と話題を変えられた。
「深夜勤務の当直警備に車を出してもらうさ」
「人使いが荒いって言われたことない?」
「身に覚えがないな」
「あはは、悪い顔してる」
端末を手に取りながら嘯くと、彼は可笑しそうに歯を見せて笑った。
「これ、貰っとくね」
「返されても受け取らない」
「うん。いいよ」
空いた右手にいつの間にか握られた騎士章は、満足そうに収まっている。艶々と輝く青の十字架と双翼の羽はどこか誇らしげにも見えた。彼と自分の、唯一無二の契約の証は優しく煌めいていた。
じゃあね、ルルーシュ。
部屋を出る直前、落とされた唇は小さなリップ音を鳴らしてすぐに離れていった。唇の表面を撫でるような軽い接触が交わされた。まばたきの次の瞬間には、微笑みを浮かべる男の顔が目の前にあった。
たったそれだけだ。さっきまではもっと、不純なことをしていたように思う。なのに、それだけなのに、心臓が馬鹿みたいに激しい鼓動を立てて、体中にせわしなく血潮が巡っていた。熱い。熱くて仕方ない。
いまだ夢見心地な脳内はその行為をはっきりと認識しようとしない。頭と体が切り離されたみたいに、地に足が着かない感覚が続いていた。
凛とした双眸は悔しいくらい涼しげだった。平素と何ら変わらないその眼差しに射抜かれると、自分が悪いことをした気になってしまう。小さな罪の意識と恥じらいが勝ってしまって、ついぞ何も言えないまま、スザクに背を向けてしまった。
ふらふらと覚束ない足元と茹だつ程の顔の熱をどうにかしたくて、そこからはどうやって自室に戻ったのか、記憶は曖昧だった。
気がついたら布団の上に、着の身着のままで突っ伏していた。眠っていたのか起きていたのか、気を失っていたのか。虚ろな意識は眠気という抗いきれないベールを纏っていて、思考は散らかり放題だ。
今の状態といえば、掛け布団の上から横たわり、枕だけは頭の下の定位置に収まっている。しかも部屋の電気はすべて点けっぱなしである。人のことを言えないくらいのだらしなさだ。
携帯端末の画面を覗くと深夜の三時を過ぎていた。時間の経過から察するに、少し眠っていたのかもしれない。
ひとまず起き上がって、着替えだけでも済まそうと思った。体に纏わりつく上等な布がやけに落ち着かなく、暑苦しいのだ。やけに暑い。暑すぎる。寝ぼけて暖房でも入れたのかと確認したが、空調は稼働していない。
ひとまず、身に着けている布をひととおり床に落とした。
じっとり汗が滲む肌と熱い呼気に俄な違和感を覚える。体がやけに怠く、重い。腕を動かすのも億劫だ。たちまち何もする気が起きなくなって、部屋の電気を消したあと、掛け布団を剥がしたベッドに再びうつ伏せで寝転んだ。ひんやりしたシーツが皮膚の温度を奪って心地良い。
「……」
暫くそうして目を瞑っていたが、どうにもやはり、落ち着かない。落ち着かない、という感覚を知覚した瞬間、その違和感は明確な輪郭を生み、その事実を"生理現象"として体に訴えかけてくるのだ。
「……あ」
緩く膨らんだ股間が寝台に擦れて、その瞬間、体がわざとみたいに震えた。
(……なんで)
そこへ視線を下ろすとやはり紛れもなく、兆した熱源が頭を擡げていた。どうして。そんな疑問が真っ先に頭に浮かんだあと、次に想ったのは彼の表情だ。
出撃後は興奮状態が冷めず、いわば生理現象としてこうなってしまうんだと弁明していた時の、スザクの居心地悪そうな表情。目を閉じると蘇るのは唇に受けた柔らかい感触のことばかりで、背筋の奥がじわりと濡れる。指先で自分の口に触れるとそこはもう乾いていて、ひどく名残惜しかった。
「……」
脚を動かすと下着の中でそれが擦れて、じんわりと熱が広がった。頭の奥がそのことでいっぱいになる。熱くてふわふわする。たぶんそれは気持ちが良い、ということだ。
無意識のうちに動いた右手が、下着の上からそれを撫でる。ふう、と熱い息が漏れた。それは甘くて心地よくて、癖になりそうだった。
その刹那である。
ピロン、ピロン、と無機質なメロディーが部屋いっぱいに響いたのだ。思考の靄が僅かに晴れてゆく。面倒だとは思いつつ、誰からの着信なのかだけでも確認せねばならない。おもむろに音源の端末を手に取った。
「……」
液晶に示された人物は今しがた、脳裏に描いていたその人であった。
「……もしもし」
『ああ、ごめん。もしかして起こしちゃった?』
潜められた声音に、どきりと心臓が跳ねた。吐息混じりの声が耳のそばで鮮明に聞こえる。
「いや……起きてた」
『そう。良かった。帰り際、ルルーシュの様子がなんか、変だったから』
「心配、されてたか」
『ちょっとだけ。今は部屋?』
「ん……うん……そうだな、部屋に居る」
『眠い?』
こちらの様子を気にかける声に悟られぬよう、息を細く吐いた。優しい声音に当てられて、体内で燻る熱が俄に焚き付けられそうになっていた。身じろぐだけでか細い声が漏れそうだ。だから細心の注意を払って、話しやすい体勢になるよう寝返りを打つ。
「ん、うん、少し……」
『はは。なら、もう切ろうか』
「いや……このままで、いい。話したい」
『そ、そっか』
「うん……」
上擦った相槌を聞きながら、胸がぎゅうと引き絞られる切なさを覚えた。
時折覗かせる硬い表情や余所余所しい態度、かと思えば甘い顔つきに熱っぽい瞳。くるくると変わる彼の雰囲気の正体と、噛み合わない会話の意味が、やっと解った気がする。
「答え合わせできたよ、スザク」
『答え合わせ?』
「ほら、さっき言ってたじゃないか……」
要領を得ない男に、懇切丁寧に説明を施してやった。今しがた胸に芽生えたばかりの小さな感情と欲のすべてを、なるべくわかり易く。彼は始終分かったのか分かっていないのか、あーとかうーとか、意味のない声を発していた。理解しているのかと今一度問うと、嫌というほど理解できた、とくぐもった音が返ってくる。だから今度会ったときは、再度確かめねばならない。
夜明けが差し迫る真夜中の他愛ないやりとりは、東の空が白み始めるまで続けられた。