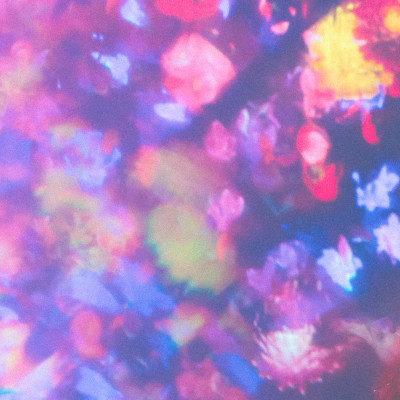
これをよすがとする 六話
家族と一口で言えど、その在り方は環境によって多種多様だし、時代によって定義も異なる。あるいは人によってもその捉え方は様々だろう。現代で言うところの家族といえば、共同生活を営む血縁者あるいは配偶者同士、と表現できるだろうか。
しかしブリタニア帝国の皇室における家族の捉え方は一般のそれらとは少々、趣が異なる。
血筋を絶やすことなく、かつ優秀な遺伝子を一人でも多く残すため、とにかく産めよ増やせよの一辺倒だった。自分が生まれるより少し前の年代の皇帝といえば、代わる代わる娶った后たちと生殖し、子を産ませたのだ。
実母のマリアンヌから生まれたのは自分と妹のナナリーだけだったが、いわゆる異母兄弟と呼ばれる血縁者が何人も居た。シュナイゼルやコーネリア、クロヴィスらはみな母親の違う兄弟だ。共通項といえば父親が同じであることと、同じ屋根の下で育てられたこと、そして生まれたときから皇位継承を巡って争わされたことだろう。
皇位継承争い。要は出世を賭けた椅子取りゲームだ。優秀な遺伝子を持つ子供らを争わせることにより兄弟たちは切磋琢磨し、より優れた人材に成長する。争いから弾かれた者、戦いから逃げた者には敗者の烙印が押され、一生肩身の狭い思いをして隠居するか外交取引で利用されるか、二つに一つだ。これは生存権を賭けた戦争なのである。
ブリタニアの歴史を振り返れば、いつだって戦争ばかりだ。争い合うことで強者はさらなる高みへ目指すことができる。競い合わされるのは皇族だけでなく民衆も同じだ。そうして勝ち上がってきた者達で国家を運営し、比類ない軍事力は脈々と受け継がれてきたのである。それがブリタニア帝国という世界最大規模を誇る国家の強さの正体だ。
幼い頃から競わされ、闘争心を植え付けられてきた。それは自分だけでなく皇室生まれの子供全員に例外なく言える。よって、皇室の子供らは同腹の兄弟であろうと基本的に、仲は良好ではない。彼らは最高権力者の玉座を我が物にすべく、その為に必要な教育を施されてきた。坊主憎けりゃ何とやらと言わんばかりに、敵対と闘争を煽られ続けてきたのだ。それが皇室のあるべき姿だと吹聴されて。
しかし子供の成長とは大人の思惑や予想をひと回り、ふた回りも飛び越えるものだ。子供たちは幸いにも自由な主義思想に触れることや、平等な学習機会を与えられていた。そのことが結果的に彼らの意思決定に幅を与えた契機となり、幾通りの選択肢が委ねられた。
要するに、皇室の中には例外的に、良好な関係を築く兄弟もいくつか存在したのである。教育係を任されていた大人たちはそれを看過できぬ事象と捉えたこともあったが、今となっては笑い話だ。帝国宰相を務めるシュナイゼルを筆頭に、女帝コーネリアもそうした例外のひとりだ。帝国内外で権力を誇示する彼らに今更苦言を呈せる者は居ない。
ブレックファーストの為にに出されたプレートにはライ麦パンと牛挽肉のオムレツ、シーザーサラダが一緒くたに乗せられ、脇の小鉢にはフルーツヨーグルトが入っていた。白いティーカップには朝の為のブレンドティーが芳しい香りを引き立てながら、柔らかい湯気を上らせている。朝日の自然光をめいっぱい浴びるダイニングテーブルは二人分の食事が乗せられ、清潔な陶磁器の皿や銀食器は眩い光沢を見せた。
白いテーブルクロスに置かれたフォークを手に取り、千切られたレタスとホウレン草をドレッシングに絡めた。向かいに座る男の顔をちらりと見たが、目は合わない。彼はナイフでバターを掬って、パンにそれを塗っていた。
柔らかい匂いを漂わす紅茶で口内を潤し、箸休めと言わんばかりにフォークを皿の端に置いた。会話はこれといってとくになかった。
ふと顔を上げると、今度こそ目が合った。しかも先に視線を寄越していたのは彼の方だった。柔和な眼差しがそれとなく揺れて、ゆっくり瞬きを繰り返していた。
「朝食を共にするとは、一体何年ぶりのことだろうね」
「兄上は出世が早かったから、俺が十歳になる頃にはもう宮廷で顔を合わすことも減っていましたよ」
「そうだったかい。それは寂しい思いを、可愛い弟にさせていたわけだ」
「ふ。子供相手のチェス遊びで、一度も手を抜いてすら下さらなかった貴方が」
「ルルーシュは本当に強かったからね。やっぱり敗北というのは悔しいだろう? いついかなる時でもさ」
プレートの食材を胃に収めていきながら、当たり障りない会話に興じた。そしてこの男も同じく世間話に徹しようとしていた。ティーカップの持ち手を掴んで中身を啜る。パンを千切ってバターを塗る。ヨーグルトをスプーンで掬う。同時に進められる話題は行き当たりばったりの、中身のない内容だ。
何てことない仕草や一挙一動の際に、ほんの僅かに感じる視線の動き。指先の揺れ。息遣いとリズム、表情の機微。
これは和やかな朝の風景に見せかけてるだけで、その実、腹の探り合いと心理戦が水面下で行われている。洞察力に優れた兄の能力は自分をも凌駕し、時に圧倒されては辛酸を舐める羽目になるのだ。昔から自分はこの人だけには、どうにも敵わない。だからせめて敵ではなく味方であってほしいと、そんな気弱な本音さえ心に浮かばれる。
「兄上でも敗北に悔悟の念を持つのですね」
「ああ、勿論。私を信じてくれた人に申し訳が立たないだろう」
「そういうことでしたか」
「ふふ。君はいつだって勝ちに拘るね。しかも戦術的な勝利や辛勝ではなく、圧倒的な快勝に」
異母兄にあたるシュナイゼルがエリア11の総督として赴任してきた三日目の朝。せっかく同じ場所で、ビジネスパートナーとして共に職務に当たるのだから、ゆっくり話でもしませんか。そう誘ったのは自分からである。兄はふたつ返事でその頼みを快諾した。つい先日行われた宴会での、ちょっとした会話でのやり取りの中で行われた。
兄が突然エリア11に赴任した理由を、副総督の身分である自分はまだ直接聞かされていない。なんなら事前に相談のひとつくらいあって然るべきであろうが、はたまた説明するまでもないと思われているのか。それらの意向も含めて、自分は彼にその真意を問い質したかった。
事前に話し合いを進めていたコーネリアにも伺ってみたが、尤もらしい情報は掴めなかった。――兄弟たちはみな、皇帝が広げ過ぎた領土の統治に奔走していて、自分だけが楽な仕事を選ぶのは気が引けるから。――今まで経験のない仕事に携わることで自己成長も促せると思ったから。角の立たない無難な理由の列挙は耳障りこそ良いものの、だからこそ疑心が生じた。
なぜわざわざこのタイミングで、無理やりコーネリアを別エリアの担当に変えさせる必要があったのか。
しかもシュナイゼルは、自分が彼女に託していたマイクロチップの存在に感づいていたという。ともすれば彼は、この無謀で破天荒とも思える計画を知った上で、何かしらの働きかけを、直接行いに来たのではないか。そこまでの推察を、昨日の宴会で顔を合わせた瞬間まで浮かべていた。
問題はシュナイゼルがこの計画においての味方か敵か、そのどちらかを明らかにせねばならなかった。ただ傍観者に徹するのであれば今まで通り内政にだけ腰を据えていればいいし、わざわざ行動を起こすということは、それなりの意図があってこそだ。
「それはそうでしょう。どうせ勝つなら完璧な勝ちでないと勿体ないし、なんなら意味がない」
「何故意味がないと言える?」
「それこそ兄上の言う”信じてくれた人に申し訳が立たない”からですよ。自軍に損害を被る、あるいは不利な条件を飲まねばならなくなる」
「不利な条件……たとえばこの、エリア11のように?」
「……」
シュナイゼルは絶対的、圧倒的な勝利という形に拘らない。負けさえしなければ良い、というスタンスで外交を取り持ったり軍事の指揮を執る。その成果を収めるにまず大前提として必要なのは敵となる相手を最大限警戒し、こちらの思惑を悟られないようにすることだ。いついかなるゲームでも盤上の流れをいち早く読み取り先手を打ったほうが有利となる。
だから彼は鋭い洞察と看破力で相手の本質を見抜こうとするし、専任騎士のカノンを連れて歩く。
昨晩シュナイゼルが会場に現れる直前までは、敵か味方か、釈然としなかった。しかし声を掛けられ、顔を見た瞬間、自分には彼がどちら側の人間なのかが手に取るように分かってしまったのだ。賢い兄は弟にわざと悟らせるため、そういう振る舞いをした。
そして今だってそうだ。ぴりぴりと張り付くような視線も饒舌な文句を垂れる弁舌も、すっかり鳴りを潜めている。
「兄上。俺は完璧な勝利にしか興味ありません。そしてそれをこの日本国に齎すことができると……いや、してみせます」
「私は何も、言ってないはずなんだけど……」
「嫌でも分かりますよ。貴方が俺の作戦に助太刀する為、わざわざ総督の肩書きを自ら名乗ろうとしてくださった」
持ち上げたティーカップの中身を空にしてソーサーに置いた。その動きに釣られるように、兄もティーカップの縁に唇をつけた。
「さすがは我が弟……と言いたいところだが、君と私は少々目的に対する意識に差があるらしい」
「と、言うと」
「私が君と同じく、日本国の政権返還を望むのはあくまで日本国の為ではなくブリタニアの為だ」
「……」
「帝国は広げ過ぎた領地の整備と人民の統治に、正直言って既に手一杯なんだ。これ以上植民地を増やすと今度は本国の内政が疎かになりかねない」
帝国は日本国を併合するより以前から世界の大陸三分の一を占める領土を持つ。たった一国でそれだけの土地、資源、人口を抱える国家は他に例がなく、言わずもがな世界最大規模だ。他の国が束になって襲い掛かろうと、潤沢な軍設備と資源は既に確保されているし、同盟国も世界に点在する。世界の軍事バランスが今のまま保たれるのであれば、帝国首都ペンドラゴンが陥落する可能性は確実にないと言える。
それゆえにシュナイゼルは、新たな戦争の火種を生むくらいであれば全ての植民地の返還、ゆくゆくは帝政の解体をも望むのだという。今の帝政のシステムを維持し続けるのは将来的に難しくなり、国力の摩耗に繋がる。植民地から噴出する抗議の声や、もはや日常茶飯事となったテロ、クーデターが散見される現状がすべての証左だ。力だけで彼らを抑え込むことは既に限界を迎えており、いつ被差別人種らが束になって帝国に襲い掛かるか分からない。
そうしたリスクを抱え続けるくらいならいっそ全てを手放し、今一度国の運営を根本から見直すべきだ。シュナイゼルはどこか強い口調で持論を展開してみせた。
「しかしこれは結果的に日本国の恒久的な平和にも繋がる。私とルルーシュの目的は同じと言えよう」
「成程。しかし少し、意外でした」
「意外?」
兄は薄く笑みを浮かべながら尋ねた。予想とは異なる反応に純粋な興味があるのだろう。
「国家の中枢に位置する貴方は安定と不変に重きを置いているように見えていたので、そういった展望を持っていたとは知らず……」
「言ったろう、私たちが負けることは許されないんだ。それに王から動かないと民はついてこない。私たちを信用してくれる国民たちが。青臭いと笑うかい?」
「いいえそのようなこと。思えば貴方はいつも契機を窺うに長けた人で、大胆さは折り紙つきでしたね」
いつも負かされていたチェスのゲームを思い出す。兄はこちらの手や思考を読み、揺さぶり、観察する。むず痒くじれったい時間はいつだって自分が先に痺れを切らすのだが、彼の本当の打ち筋はいつもその後に発揮される。容赦ない戦法に完封負けしたことも数多で、”完璧な勝利に拘らない”とはどの口が言えたことか、とすら思う。
柔らかい生地の背凭れに体重を預け、肘掛に腕を置く。食後の胃に負担をかけぬよう、ふうと息を吐いて窓の外を見た。今日は見事な快晴だ。雲も少ない。澄んだ景色は遠くまでよく見渡せる。
ともすれば、シュナイゼルはふと思い出したように口を開いた。
「これから本格的に活動を始めるとすると、ルルーシュ。君も騎士を選んでおいたほうがいいかもしれない。何事も備えておいて損はないだろう」
「騎士……」
皇族は副総督以上の階級に着くと同時に、専任騎士を任命できる権利が付与される。専任騎士は一般市民だろうと見境なく選べるわけでなく、ブリタニアの帝国軍に属している騎士侯階級以上の人間が対象だ。
自分は副総督の立場にある為、とうにその権利を得ている。しかしそれを行使しなかったのは、ちょっとした思惑を抱えているからだ。
「ジェレミア卿はどうだい。私の騎士であるカノンは彼から仕事を教わっているようでね。とても頼りになる人だと言っていたよ」
「左様ですか。本人にも伝えておきます」
「なんだ。他に候補が決まっているのかい」
「……その」
ジェレミア卿はヴィ家が本国在籍時から仕えてくれていた騎士侯だ。厚い忠義忠誠を誓い、とくに故マリアンヌ妃に対する想いは人一倍であった。彼女の実子である自分やナナリーに対してもそれは同様で、兄妹はマリアンヌが残した宝だと言って憚らない。
彼ならきっと、己が騎士になれと命じれば恭しく頭を垂れ、その任を快く、なんならそれが本望だと言わんばかりに引き受けてくれるだろう。ヴィ家への忠義者である彼を悪く言う者は宮廷内に居ないし、仕事態度も性格も真面目で実直な男だ。嘘はつかないし約束も破らない。これ以上ないほどの適任であろう。
それを重々承知した上で、しかし自分は背中を預ける相手にジェレミアを選ばなかった。
「……すまない、意地悪な聞き方をしたね。彼だろう。特派に配属されたばかりの、ほら、名誉上がりの」
「何故そう思われます?」
「小耳に挟んだんだ。副総督のお墨付きだって、ロイドから」
「……は、あの男」
「何も隠すことないだろう。実際、適性検査も実戦成績も優秀じゃないか。元々ナイトメアフレーム操縦の素養があるんだろうね。よく見つけてこられたと思うよ」
「……」
「ランスロットを乗りこなせるパイロットはとうとう現れないかと思ったけれど。優れたマシンのスペックを、彼なら引き出してくれるんじゃないかな」
何とも形容しがたいむず痒さを感じる。他人から、ましてや身内から彼の印象を聞かされることになろうとは。駄目出しのひとつでもあれば良かったかもしれない。聞くに耐えないほどの賛辞に、何故かこちらが恥ずかしくなるのだ。
「……でも彼、枢木スザクはまだ一等兵だ。騎士侯でないと選任は認められないはずだよ」
「奴は僅かな期間で多大な戦績を上げ、ゲットーの治安維持に大きく貢献しています。あくまで前例がないだけで、名誉人に騎士侯階級が賜られないという条文はなかったはず」
「物は言いようだね」
「軍部へのクーデターが成功すれば枢木一等兵の昇進は間違いないでしょう。最終決定権を握る帝国宰相は貴方だ」
「ははは、これは困った」
嘘つけ、と言いたくなるほど楽しそうな声色と表情だった。まるで台詞と噛み合わない。暗に、お前の好きにしなさい、と言われているような心地になった。
シュナイゼル新総督が着任してから、おおよそひと月が経った頃だろうか。エリア11では総督の交代に際してもゲットー内で混乱や抗議が起きることはなく、それ以前と変わらない混沌とした情勢がなおも続いていた。日本解放軍の活動に触発された模倣犯、一派が乱立し、ブリタニア人に対する迷惑行為や犯罪、テロや抗議声明の宣言といった抵抗は変わらず継続している。その度に、エリア内に散在する駐屯地からは名誉軍人が鎮圧部隊として出動し、軍部はそれをいわば口減らしとして利用していた。治安維持という大義名分の元、名もない若き兵士たちは命を散らしてゆくのだ。
しかし、それが強く問題視されたのは数週間も前までのことだ。ここ最近、記憶に新しい出来事の中ではむしろ、戦場では解放軍側が圧倒的優位に立ち回ることが増えたらしい。
当初解放軍が所持していたというナイトメアフレームは数機のみで、そのどれもが火力不足のプロトタイプばかりであった。帝国に占領されるより以前に日本政府が所持していた機体のうち、解放軍が政府関係者から秘密裏に横流しを受けた物の残存機である。
当時日本政府の持っていた兵器の類は須らく帝国が差し押さえ処分したとされているが、それはあくまで公式記録上の話だけであって実情は異なる。その一方、解体させられた旧財閥家門のキョウトが主導で手引きを行ったと噂されているが、真相は未だ闇に包まれている。
帝国軍の圧力により解放軍の軍備や組織人口は縮小の一途を辿り、一時は壊滅寸前とまで言われていた。解放軍に資金援助しているのはキョウトの連中だとまことしやかに囁かれることもあるが、数々の特権を封殺された家門たちの体力は現状を鑑みるにジリ貧だろう。他国とのパイプがあるような素振りもなく、解放軍は八方塞がりの岐路に立たされていた。
はずだったのだ。
近頃また勢いを増してきた彼らの動きは実に不可解であった。エリア11に拠点を構える軍部はこれについての精査を最重要課題として取り上げ、資金や兵器の調達ルートを血眼になって探っている。
プロトタイプのお下がりしか持たなかった彼らは、今や帝国でも採用されている最新鋭の量産型世代を多数所持し、それに伴って必要となるサクラダイトや装備品、パーツ類も数々入手していると見られる。一体なぜ、どこで、誰が、どうやって。挙げられるだけの可能性を虱潰しに調査したが、目ぼしい収穫は得られなかった。
解放軍の謎の快進撃により、ゲットーに住まうイレヴンたちは彼らの活躍に一縷の可能性を見出していた。前途ある若者は解放軍への入団を希望し、生活に余力のある者は個人的に出資したりと、多くのイレヴンは解放軍の活動に協力的だ。当然当局はこの動きを取り締まろうと躍起になるが、まるで事前に軍部の動きを察知していたかのように、解放軍のナイトメアフレームがこれを一網打尽にしようとする。
変容したのは武器の数だけでない。無秩序なゲリラ的戦法から、緻密な計算と作戦による洗練された戦略にシフトされたのだ。解放軍はひとつの組織として完璧に統率を取り、また実戦においても鮮やかな戦術によって軍部の部隊を翻弄し、出し抜いてみせる。そうして軍部はなす術もなく戦線を撤退、離脱する他ないのだ。
組織力は指揮官の質によって雲泥の差が生じる。愚鈍な指揮官に率いられた組織は最早烏合の衆と呼べるし、有能な指揮の元に在れば国の軍隊をも凌駕する。つまり今の解放軍には優秀で頭の切れる統率者を有しているということだ。
今や軍部と解放軍の形勢は逆転しかけていた。
その要因は解放軍の自助努力でなく、外部からの膨大な資金援助による賜物であるのは明白だ。しかし軍部は依然として、裏で糸を引く影の正体を掴めずに居た。
租界内に停泊している特派ヘッドトレーラーに赴くのは、今月だけで何度目になるだろうか。
そこは特派の研究チームがランスロットの開発から機体の整備に至るまで全てを行う為の、唯一無二の仕事場だ。トレーラーと呼べるだけあって当然陸路移動も可能だ。軍部から出動要請があればどこへでも駆けつけることができる。ランスロットの格納庫としての役割も果たしており、戦闘データの収集やメンテナンスも一括して行える。非常に合理性の高い作りだ。
ひとつ欠点を挙げるとすれば、トレーラーはランスロットの研究専門所と化しており、副資材や武器の研究開発は行えない。そもそも特派は軍部からの決められた予算ほぼ全額をランスロットの開発に注ぎ込んでおり(だからこその高火力とスペックを持ち合わせているが)、その極端な活動が軍部にとっては気に障るのだろう。
通常の市街地作戦やテロの鎮圧に対して、特派に出動要請は滅多に寄越されない。軍部としてもプライドがあるのだろう。変人博士のおもちゃに名誉人パイロットが乗り、それで戦果を横取りされたら面目が潰れる。とは言え、シュナイゼルという後ろ楯がある以上蔑ろにも出来ない。
だから主にランスロットの出番があるときは単騎での戦線攪乱、先陣切っての陽動、囮、単独作戦などだ。要は味方から露骨な冷遇を受けているわけである。
名誉人でありながらナイトメアフレームへの搭乗を黙認されているスザクは軍部の中でもとりわけ異端だ。軍部はこれを目の上のたんこぶ扱いして排除したがっているが、上昇志向が高いらしい彼は回ってくる数少ない任務を完璧に、あるいは求められた以上の働きを見せ、戦果を残していた。そういうこともあって、軍部は一概にランスロットを開発停止に追い込むわけにもいかず、その扱いに手をこまねいている状態だ。
トレーラー内部の研究室に足を踏み入れると、見慣れた面々がいつもと変わらぬ調子で仕事に当たっていた。一見して場当たり的にも見える光景だったが、彼らは出動要請が来ないと本領発揮に至れない。今日のこの様子を見る限り、ここ数日暇を持て余していたんだろうな、という想像が容易につく。
「スザクくんなら休憩室に居ると思いますよ」
「ああ、有難う」
モニタから顔を上げたセシルが何も言わずとも答えてくれた。副総督という特権を行使しているのもあるが、今更誰も彼も、自分がここへ来ることになんの違和も覚えなくなっていた。
「スザク、居るか」
「はい」
短い返事のあと自動扉が開かれる。狭い部屋の中で分厚いテキスト片手に書き物に耽っていたらしい男が、顔を上げてこちらを見た。
「今日は何の勉強だ?」
「近々ランスロットに新しい武装が増えるらしいから、マニュアルを予習してて」
「へえ」
とくに断りもなくずけずけと部屋に踏み入り、その手元を上から覗き込んだ。彼のペン先には丸い影が落ちる。
わずかな期間でずいぶんと自分も彼も、気を許す関係になったと思う。これだけ距離を詰めても彼は何も言わないし、自分も平然とそうした態度を取る。二人にとってこれは当たり前でよくある日常的場面の一部だ。世間一般で言うところの”友達”という仲の距離感を忠実に真似するかのように。
勉強熱心な奴だと思う。実際に機械に触れながら覚えることも出来るだろうに、生真面目な彼は予習と予行に余念がない。真剣な眼差しを見せる横顔を眺めると、そうやって茶化す気も失せてしまった。
先日から受け取っている活動報告に記された懸念材料が、頭の片隅でずっと引っ掛かり続けていた。
ある種の自殺願望かそれに近い思念を抱いている人間のような振る舞いを、どうして戦場で行うのか。お前は死にたいのか。危ないから止めとけ。そう軽口を叩くように言えたらどれだけ良かっただろう。いざこうして顔を合わすと、そんなふうには微塵も見えないから、余計に混乱した。殉職を本望にしているようには、どうにも思えないのだ。
あるいは、思いたくない。何かの悪い夢か、行き過ぎた妄想だということにしたい。丸い緑の瞳が緩んで目尻が下がる。眉が下がって、そんなに見つめてどうしたの、とはにかんだ口元が白い歯を覗かせる。自分に向けられる優しさの片鱗に触れるたび、どうにも問い質す勇気が削がれた。
「エアキャヴァルリーにブレイズルミナス……まだデビュー戦からそんなに経ってないのに、もうグレードアップか」
「交戦はあまりしないけど、それ以外のところで要請が度々あってさ」
「たとえば?」
「違法薬物の密輸現場に強行したり、来賓の警備とか、パトロールや救護も……」
「警察や消防の仕事じゃないのか」
「行政機関は今どこも手一杯なんだってさ」
「ああ、それでか」
ナイトメアフレームの喪失など、多額の損害費用を計上する軍部に予算が嵩む一方で、行政機関は人件費を削減する方向に移行している。警察や消防といった市民の生活に直結する業種はとくに人手不足が危ぶまれ、体制の維持に影響が出かねないという。エリア11という占有地の運営に少しずつ綻びが出ている証拠だ。
「それで、君の用件は何だったの?」
「ああ、そうそう」
話に気を取られていた。言われて漸く思い出し、一旦スザクの元から離れる。
「このパソコンを借りてもいいか」
「どうぞ」
テーブルの端に置かれたノートパソコンの画面を開き、電源を入れた。ついでに懐から取り出したメモリーカードを機械の脇にあるポートに挿入し、データの読み取りを試みる。有線のマウスケーブルを接続させて読み取り用フォルダを開いた。
「これは?」
いつの間にか真横に居たスザクは小型のパソコンモニタを覗き込んでいた。不思議そうに目を瞬かせる横顔は何も知らない子供のようだ。
「純日本製の新型ナイトメアフレームだ」
「……これが?」
「そうとも」
解放軍の活動に支援声明をくれたインド軍区出身の技術者が設計に携わり、解放軍という旗印の元に集結した技師らが作り上げた現代の最高傑作だ。唯一の第七世代と呼ばれるランスロットと比肩するポテンシャルを持ち、多数のギミックが内蔵されている。
「”紅蓮弐式”だ」
「紅蓮……」
液晶に映る真っ赤な躯体は、既存のナイトメアフレームと明らかに一線を画す。独特の造形をした装甲に、右腕部から伸びた巨大な武装と、鍵爪のような右手。異様な出で立ちのそれは一体どんな戦いぶりを見せるのか、想像もつかない。
「解放軍にひとり、腕利きのパイロットが居るようでな。そいつに鍵を託そうと思ってる」
「ふうん」
「この右腕は輻射波動機構という武装が搭載されているんだ。電磁波を高出力で放つことによる熱放射で敵機を破壊……文章だけじゃ理解し難いな。お前はどう思う?」
「……」
返事が返されないことに疑問を持ち、視線を画面から逸らした。首を傾けた先にスザクの横顔と、そこに浮かぶ不服そうな面持ちが見える。唇を少し尖らせて、むくれっ面を浮かべていた。
「なんだ」
「別に?」
「……ランスロットも十分すごいだろう」
「出番取られちゃうかも」
「何拗ねてるんだ、お前」
「拗ねてなんかないよ」
明らかに臍を曲げてるだろ、と言いたかったがそれ以上の言及は止めておいた。言い出すときりがないし、彼はますます機嫌を悪くする。
聞かない振りをして、画面を切り替えた。ドキュメントファイルを開いて閲覧モードで表示する。
「最近のレポートだ。先日の作戦も軍部にはかなり効いたようで、本国から人員を急遽増やすことになったらしい」
「結果的に兵力増強されたってことじゃない?」
「肝心のナイトメアフレームがまだ準備できてない。愚かな指揮官の元では優秀な兵士も雑魚に成り下がるんだよ」
「解放軍の指揮官は君なのか」
「当然」
画面をスクロールしながらスザクの問いに頷いた。
ともすれば、マウスを握る手に彼の手が重なる。急にどうした、と言えば、今の画像もっかい見せて、と早口で言われた。
「勝手に動かすな、こら」
「もっと上にスクロールして」
手を無理やり動かされ、画面が切り替わる。
次の瞬間映されたのは一枚の画像写真だ。解放軍の格納庫に収められたナイトメアフレームが立ち並ぶ、壮観な光景である。
「これも全部、君が?」
「中華連邦がくれたおもちゃを改造した。ブリタニアが敵を作ってくれたおかげだ。どの国も交渉すれば譲ってくれる」
「うわ、ひどい言い草」
「事実を言ったまでだ」
悪びれずそう答えてやると、スザクは可笑しそうに笑っていた。握られていた手が離れていく。
「ルルーシュのそういうとこ、嫌いじゃないよ」
「それはどうも」
続いて聞こえてくる笑い声に思わず息を吐いた。
資料になるファイルや画像はまだまだあるが、これ以上見せてもあまり意味はなさそうだ。確かにこれらの手配や根回し、作戦の立案は全て自分のものだが、気にしてほしいのはそこじゃない。戦場の前線に立つ人間の目から見て、提案や助言があればと思ったのだが。
図らずもその瞬間、静かだった部屋に無機質な電子音が響く。上着のポケットが俄かに震えて、ランプが点滅を繰り返していた。端末を手に取ると、その液晶には電話の受話を求めるメッセージが表示されていた。
ちらりとスザクの顔を窺うと、彼は人好きのする顔をして頷いてくれた。出ていいよ、と唇が動く。
「……もしもし、俺だ」
携帯の着信は解放軍の一員からのものだった。
「ああ扇か。明日の件か?」
解放軍の実質リーダーを務める男は律儀で真面目な奴だ。定期的な諸連絡も怠らないし、変わったことがあればすぐ伝えてくれる。
テロリスト、という文字と音の響きからして、粗野で人の話を聞かない人種の寄せ集めなのだろう、という先入的な意識は正直言って、あった。暴力に物を言わせて主義主張を通そうとする短絡的な奴らに果たして軍隊行動を言って聞かせることができるのか、やってみるまでは分からなかった。
しかし彼らは存外、忠実に首尾よく指示行動をこなしてくれる、聞き分けの良い兵士であった。
「待ち合わせは……ああ、うん。場所は知ってる」
ひとりひとりは我が強く意見はいつだってばらばらだ。衝突することも多いようで、そのたびに収集がつかなくなるらしい。それでも、そんな集まりがひとつの組織として行動できるのはひとえに、このリーダーの存在が大きい。
メンバーは全員、扇を慕い尊敬し、みな彼の言うことを律儀に守る。号令をかければすぐさま全員集合するし、武器を取れと言えば銃火器を手に敵へ立ち向かう。死ねと言えば死ぬことだって厭わないだろう。彼らにはそんな気迫と命知らずさを感じるのだ。
「時間はそちらに任せる」
扇を含め、解放軍とは直接面と向かって接触を図ったことはまだなかった。音声あるいはビデオ通話による通信だけがすべての連絡手段だった。戦線への指揮も通話のみのオペレーションだ。なんせ直接会うにはリスクが伴うし、両陣営ともに仲間意識が根付いてないと難しい。密告者を出すわけにはいかない。
「分かった。切るぞ」
短い相槌と共に音声は途切れ、画面には数分にも満たない通話時間が記録として表示されてある。端末を閉じて振り返ると、不思議そうにこちらを見つめるスザクと目が合った。
「明日、初めて顔を合わせることになるんだ」
「いよいよって感じだね」
「むしろ……ここからやっとスタートラインだ」
その返事を聞いて、彼は少し意外そうな表情を浮かべていた。
自分たちが引き起こそうとしているのは一過性の混乱や災害ではない。軍事政権と揶揄される軍部の横暴、越権行為を阻止し、これらを瓦解へと導く。そして日本国へ自治権を返還する。エリア11の動きに波及され、世界各地で民衆の運動が活発化すれば、帝国の今の地位や帝政維持もいよいよ危ぶまれるだろう。
エリア11はドミノ倒しの最初の一手だ。ここで不発に終われば帝国軍の介入がさらに激しく、警備もより強化されるだろう。二度目の機会は訪れない。
今は、軍部が解放軍に力負けしているという現状をなるべく印象強く、世界中に広める必要がある。どんな力にも数と戦略さえ揃えれば勝てるのだと意識付ければ、希望は伝播してゆくのだ。
あとは帝国の出方次第、といったところだろうか。世界有数の兵力を抱えているのは事実として存在し、サクラダイトの占有率も世界一だ。真っ向から挑もうものなら戦線は三日も保たない。だから外堀から埋めていき、政権の崩壊を促す。
「……あともうひとつ、お前に伝えることがある」
「うん?」
「手を出してくれ」
言われるがままおずおずと差し伸ばされた手のひらに、ある物を乗せた。彼は暫く黙り込んで手のひらの上を見つめていたが、徐々に開かれる瞳孔は恐らく、合点がいったということだろう。それでも続く沈黙に先に耐えかねたのは自分だった。
「騎士章だよ」
「……それは知ってる、けど」
「作戦がうまく進んで、この国がまた日の丸を掲げられるようになったら、スザクの功績を讃えて昇進もやむ無しだと。帝国宰相の言質は取ってある」
「ま、待ってくれ」
「出世したくないのか」
「そうじゃなくて」
惑う瞳が手のひらと自分を交互に見つめては、唇を戦慄かせていた。
「つまりどういうこと」
「お前を俺の騎士に任命したい」
瞬きすら忘れたのか、スザクは一瞬固まった。耳に入った言葉の理解に時間がかかっているようで、反応はいやに薄い。
「なんで……」
「今更理由が要るのか?」
「だって、僕以外にも……」
開いたままの手に手を重ねて、指を折り、それを握らせた。
「自分以外に適任が居るとか、思ってても言うなよ。聞きたくない」
「う……」
それきりスザクは口籠ったまま、何も言わなかった。というより、何も訴えても聞き入れられないと判断したのだろう。この手の相手には真面目に説得するより諦めさせるほうが早いのだ。
「一週間後くらいにまた来る。それまで、それは持っとけ。失くさないように、枕の下にでも入れて寝ろ」
「失くしたらどうなる?」
「責任を取ってもらう」
「ああ、冗談みたいに打つ手が無いな……」
途方に暮れたように呟かれる言葉は敢えて無視した。食い下がらない様子には見ぬ振りだ。
スザクは結局最後まで、それを引き受けるとも断るとも明言しなかった。始終曖昧に笑って、本心を話そうとしない。
話したくないなら話さなくてもいい。無理に吐かせようとは思わない。けれど、目に分かるように隠し事をされるのは自然と距離を置かれたような気がして、少し傷つく。また次会うときはもっと話す時間が必要だ、ということだけは確かだった。
数か月前に見た景色は、記憶とは寸分変わらぬ色をしていた。砂埃が舞う石階段、手入れのされていない雑木林の森、人の気配が薄い郊外の外れ。関東北部地方の山麓は人の記憶から忘れ去られたかのように、今日も前回と変わらず人影ひとつも認められなかった。
解放軍のリーダー役である扇から指定された待ち合わせ場所は枢木神社であった。一度訪れたことのあるこの土地に何か因縁めいたものを感じながら、目の前に聳える数百段の階段に意を決して足を置いた。
ここら一帯の土地といえば、キョウト一派にかつては数えられた枢木家の所有物であり、軍部も下手に手を出せない"曰くつき"だという。財閥は解体され、それとは無関係に財産や既得権益も差し押さえられ、枢木という氏に今や権威はない。それでもなおこの土地が不可侵であることに、意味があるとしたらそれは何なのか。
人の記憶からとうに忘れ去られたのか。噂でしかないキョウトとやらの暗躍が実存しているのか。この国に深く根ざす問題は、知らないだけでもまだまだ多くあるらしい。
階段を上りきって、まず入り口となる鳥居が目に入った。時刻は正午。太陽は高い位置で光り、これでもかと日光が地面に注ぐ。どっと押し寄せる疲労感に足をひきずりながら、玉砂利が敷かれた参道をゆっくり進んだ。
日陰になっている拝殿の軒下のあたりに三人、見知らぬ顔ぶれがあった。開けた視界の先では人影がすぐに見つかる。向こうもこちらの存在に気づいたようで、三人ともに目が合った。
「初めまして。副総督……で宜しかったですか」
「ああ、お前がリーダーの扇要か。初めまして」
「こ、この度はご足労頂き誠に……」
「ちょっと扇さん、しっかりしてよ」
緊張した面持ちの男に対し、脇に控える女が小声でそう諭した。
「彼女は?」
「私は紅月カレンです。初めまして」
「紅月……紅蓮弐式のパイロットとは貴方のことか」
「そ、そうだ。うちで一番の腕利きだ」
「ああよく知ってる。旧型グラスゴーで軍部相手に市街地戦をやってのけてくれた。そうか、まさか学生だったとは」
学生服に身を包む彼女は赤い髪を揺らしながら光栄です、と短く返事した。隣に立つ扇も心無しか誇らしげな表情を浮かべている。
しかし身に着けていた制服をよく見ると、あることに気づいた。
「その制服、租界内のブリタニア人学校だろう? 通っているのか?」
「カレン……紅月隊員はブリタニア人とのハーフで、ブリタニア姓で学校に通ってるんだ。日本人の血も半分入ってることは隠してな」
「なるほど。そうしてカモフラージュしてるんだな。どおりで顔立ちの雰囲気が違うわけだ」
木を隠すなら森とも言えようか。テロリストはその身元や普段の活動拠点を、当局の監視から逃れつつ暮らしている。彼らは漏れなく全員指名手配犯だ。素性が知られるわけにいかないのが常だが、敢えて懐に潜り込む大胆さは畏れ入る。
「それにしても、副総督様とあろう御人が本当に一人で来ると思わなかったわ。今日まで頑なに会おうとしなかったし、扇さんが来なかったら私も来てなかった」
「カレン」
「だってそうでしょう? 罠の可能性だって」
「……それはない」
疑り深い彼女の話を敢えて遮る形で、その主張に反論した。
「この期に及んでお前達テロリストを告発してどうする。全ての指揮権は俺が握ってるんだ、共倒れになるだけだろう」
「それはそうかもだけど……」
「時間がかかったのはメンバーからの信頼を得る為だ。密告者を出すわけにもいかないし……」
「ルルーシュ様、私ともお話してくださいませ!」
「……はっ?」
突然背中のあたりにどすん、と何かがぶつかる衝撃を受けて体が前のめりによろめいた。右足が一歩前に出て、たたらを踏む。視界がぶれて、二人とも驚くような、困惑するような表情を浮かべていた。
転倒だけはなんとか免れた。地面は固い玉砂利で埋め尽くされている。転んだら出血だけで済まないかもしれない。
「……おい、一体」
「私のこと、もうお忘れですかルルーシュ様?」
腰のあたりにしがみついてくる子供はそう言って、こちらを見上げていた。
黒く長い髪は切り揃えられ、緑の大きな瞳が潤む。白い肌と赤い唇。裾の長い桃色の和装姿。
「お前……あの時の……?」
こてん、と首を傾かせる子供は、柔和な笑みを浮かべたまま依然として見つめてくる。
「神楽耶様、あんまり副総督を困らせないで……」
「困らせてなんかいません! 私達はいま、感動の再会を果たしたんですよ、ねっ」
「……扇、この子供は一体誰だ? 解放軍のメンバーか?」
全身に急激な違和と薄気味悪さが迸る。手のひらはじっとりと嫌な汗が滲み、喉はやけにひりついた。
「わたくし、皇神楽耶と申します! 以前お会いした際は名乗ってませんもんね、ごめんなさい。お気軽に神楽耶とお呼びくださいませ!」
「二人はお知り合い?」
「いや、そういうんじゃない」
カレンの訝しげな目線を受けて即答した。
この子供と自分は初対面だ。少なくとも自分の中では。そのはずだった。
「以前この枢木神社にお越しになっていらしたでしょう?」
「……ああ、そうだな」
「なんだやっぱり二人は知り合いだったの」
「外野は黙っててくれ」
横槍を入れてきたカレンにそう釘を刺すと、彼女はあからさまに渋面を作った。しかし今、他の人間に構ってやれる余裕はない。
確かに自分は以前、この神社に一度だけ訪れたことがある。このエリアの副総督を担当するにあたって、どうしても消息の手掛かりを掴みたい人物が居た。枢木スザクだ。彼についての情報が少しでも欲しくて、藁にも縋る思いでこの神社に足を踏み入れたのだ。理由は名前が共通するから、という単純なことだ。
植民地としてこの国が併合され、日本という名前を喪って以来、その足取りがまったく掴めなくなっていた。彼の実父であり日本の首相であった枢木ゲンブは志半ばにも関わらず自殺を遂げ、以来この国は帝国に蹂躪される運命を辿る。ゆえに枢木家は歴史の闇に消え、ある種のタブー視をされていたのだ。どれだけ文献を漁っても一家についての情報は手に入らなかった。少なくともブリタニア本国に居た頃は占領エリアの歴史書や文献など入手さえ困難であった。
寂れた神社に佇む少女は昔からこの近くに住んでいたと、しかし枢木家が一家離散となった後はどうなったのか、その顛末はよく知らないと、そう宣っていた。
「スメラギ……その姓はキョウトの者だろう」
「あら。やはりよくご存知なんですね!」
「……茶化すのも大概にしろ」
「そんな怖い顔、しないでください。私について特別にお教えするとですね、実は皇家の長女でして、キョウトの当主も務めております」
ますます訳が分からない。この口ぶりからしてこの子供は神社で出会った時点で、自分の正体を知っていたということだ。副総督と分かっていたはずなのに、子供は悪びれもせず、エリア11に隠された権威構造を包み隠さず喋った。恐らくは何かしらの思惑を抱いて。キョウトの真実と枢木家の顛末を撒き餌にでもするように。
「扇! なんでこの女をここへ連れてきた!」
「か、神楽耶様は……キョウトは前々から解放軍に活動資金の援助をしてくれてたんだ。副総督が声をかけてくれるよりも前から……キョウトの後ろ楯がなかったら解放軍はとっくに存続できてなかった」
「キョウトは反帝国勢力のパトロンとして暗躍してた……そういうことか?」
「左様ですとも」
神楽耶は口元に薄い笑みを作り、扇と目を合わせていた。
齢十四、五くらいだろうか。幼さが残る顔立ちをした少女がまさか、この国の暗部を知るどころかその中核を担っていたとは、露にも思わない。お転婆でお気楽を体現する振る舞いからも、その気配は一切感じられない。俄に信じ難いことだ。純粋な気味の悪さと不信感が胸の内にじわりと広がる。
「それで扇。彼女に作戦の内容は伝えたのか?」
「あっ、ああ。キョウト六家の中でも当主の神楽耶様にだけ、だけど……」
「ルルーシュ様は何をそこまで恐れるんです?」
あっけらんとした声音が鼓膜に響いて、思わず苛立ちが募る。
生活の一切が帝国の監視下に置かれたこのエリアにおいて、裏社会だの金の横流しだの、そう容易にできるはずが無い。なにかトリックがあるにせよ、総督府の目を掻い潜ってのうのうと暮らしていけるほど、この国の生活は楽でないはずだ。
何も知らないわけがない。馬鹿な振りをしているだけなのだ、この子供は。
「キョウトは六家の一角である枢木家を除籍したと言っていたな。跡取り息子である枢木スザクが帝国軍に入隊したから。彼は日本人であることを捨て、帝国に身売りした……」
「ええそうですね」
「ならなぜ、この作戦に同意した?」
「なぜって? そんなの……」
彼女は至極不思議そうに上目遣いで見つめてきたあと、気まずそうに言葉を漏らした。
「反勢力はジリ貧でしたもの! でも今更諦めることもできないでしょう? 日本政府の復権のためならわたくし、何でもする所存ですから」
「……」
「枢木家が関わるくらい、痛くも痒くもありませんわ。それに我が解放軍は追い風。お釣りが来るくらいです!」
そう言って啖呵を切る少女に、もう何を言う気も起きなかった。溜息をつきながら、分かったよ、と力なく答えるだけで精一杯だ。
「これから末永く、どうぞ宜しくお願い致しますねルルーシュ様! お慕いしておりますから!」
その笑顔の裏にどんな策謀が隠れているのかと必要以上に勘繰ったせいで余計に体力を消耗させられた。どこまでが彼女の意図するところなのか知りようがないが、もしかすると、この女は出たとこ勝負で何の思惑も持ち合わせちゃいないのかもしれない。
「しかしキョウトが関わってくるとなると厄介だ。あくまで資金援助という形だけにしておいて、作戦決行までは接触を控えよう」
「えーっ! 酷いですわルルーシュ様! せっかくこうして再会できたのに、また会えなくなるなんて!」
頭の中でキョウト六家を加えた組織図を描く最中、耳を劈く少女の甲高い声にまたもや気を揉まされる。どうして神楽耶はこうまで自分に付き纏うのか。
「ひとまず今日はこれでお開きにしよう。カレンは紅蓮の操縦に慣れておいてくれ」
「分かったわ」
「ルルーシュ様、私にも出来る事があれば何でも仰ってくださいませ」
「あ、ああ……」
神楽耶の扱い方だけは心得ることが叶わなかったが、この日はそのままお開きとなった。階段を降りてから各々が散り散りに解散し、自分は租界内に滞在しているであろう特派の本拠地にその足で向かった。
一週間後に、と昨日伝えた手前だ。駄目元で話せる時間はあるかとスザクに通信で尋ねたところ、夜から出動予定が入っている為それまでであれば何とか、とのことだった。正午を迎えた神社から租界に戻ってから、既に数時間は経過している。傾き始めた太陽が橙色の光を帯び始め、空の色は少しずつ夕暮れに向かって移ろいでいた。
鉄は熱いうちに打て、ではないが、こうした情報は早めに伝えておきたい。スザク本人もどこまで知り得ているか想像の余地を出ないし、何か思うことがあるかもしれない。
思えばスザクからキョウトについて、知っている話を聞いたことはなかった。まさか知らないとは言わないだろうが、彼は小学校を卒業するくらいの年で家元を離れている。事情が事情なだけに、キョウトの情報が彼の耳に入るとは思えないのだ。当主の態度からして、もはや絶縁状態と思っていいだろう。
特派の移動トレーラーの奥に設けられたスザク用の個室に入ると、昨日と同じく、彼は部屋の備え付け机に向かって何やら書き物をしていた。周囲には紙束の資料が数枚散らばっている。何かの報告書か日報の類だろうか。
パイロットである彼の為に設けられた一室は、いわゆるビジネスホテルのような手狭さと作りになっている。扉を開けてすぐ横の壁際ににスリッパやハンガーラックを収納する小型のロッカーがあって、その真向かいはトイレとシャワースペースが一緒くたにされた個室がある。いわゆるユニットバスと呼ばれる構造だ。そして少し進むと机と椅子が一組ずつ。残りのスペースにはシングルベッドが置かれ、サイドテーブルは小さな照明と目覚まし用のアラーム時計が設置されてある。
住むのに必要最低限の要素がひととおり揃ったその部屋を、いまのスザクはおもな住処にしている。名誉軍人として地方の駐屯地に配属されていた際は寮に住み込み、集団生活をしていたという。いくら狭くても一人部屋に勝る快適さはないと言う彼は、今のこの部屋を気に入っているらしい。
昨日と様子が違う箇所があるとするなら、その格好だろうか。今晩からの出動に備えて既に準備は済ませてあるらしく、パイロット専用のバイタルスーツに身を包んでいた。
「すまないな、忙しい時に」
「時間はまだ一時間くらいあるから平気。それより、急な話って何?」
椅子に座ったまま一旦手を止めて、スザクはこちらを見遣った。どこか不安げに揺れる瞳に、無表情の自分の顔が映り込む。
「確認なんだが。スザク、皇神楽耶という人物に心当たりはあるか?」
「神楽耶? ああ知ってるとも。僕の従兄妹だよ」
「まさか。親戚なのか、皇家と」
「僕もあまり詳しくはないけど、遠戚だったかな。どうしてルルーシュが神楽耶のことを?」
なんてこと無いようにそこまで答えるスザクに、自分は意を決して口を開いた。
「解放軍に皇家が……いや、キョウトの連中が絡んでいたんだ。俺がこの作戦に着手する前から、彼らは反帝国勢力の一大組織としてエリア11で暗躍してたと。奴らは解放軍のパトロンだったらしい」
「……今日会った解放軍の人の中に、神楽耶が居たの?」
「ああ。組織のリーダーと紅蓮のパイロット候補、それから皇の女の三人だ」
「……」
スザクはたちまち表情を曇らせ視線を落とした。何かを言い淀んでいるのか、沈黙を続けている。
「何か思い当たる心配事か?」
「……ううん。僕はもうキョウトの人たちと疎遠だし、無関係と思ってていい」
「そうか」
彼は自身の立ち位置と財閥家門らの関係性を俯瞰的に捉えていたようで、冷静にそう口にした。そのことはもういいんだ、と付け加えて、本人はさして気にもしてない様子だ。親戚や出自に関して、スザクの中では未練や後悔はとっくに過去に置いてきたのだろう。
「それより、その。神楽耶は僕のこと、何か言ってた?」
「ん? いや……まあ、軍隊に入ったことを良く思ってない、ふうなことはぼやいてたけど」
「そうか」
短い相槌のあと、それきりスザクは黙ってしまった。俯いた顔は表情が読めないし、脚の間で組まれた両手は何が落ち着かないのか、しきりに指を交わしていた。
沈黙が続いて、壁掛け時計の秒針が会話を急かすように音を刻んだ。
彼は心配事を抱えているふうだが、自分にはそれが見当もつかない。本人が自ら口を開いてくれるのを辛抱強く待つ他ないだろう。
すると唐突に、けたたましいコール音が部屋に響いたのだ。思わず肩が跳ねたが、対してスザクは驚くでもなく慌てる様子もない。机の端に寄せられていた端末を手に取り、おもむろに通話をし始めた。
「はい枢木です。はい……はい、分かりました」
その間僅か数秒だ。さっさと通話を終えてしまった彼は、右手に持つ携帯とともに机に広げられていた紙やノートを一纏めにして、鞄の中へ乱雑に放った。紙が折れ曲がるような音も聞こえたが、本人は頓着する素振りもない。
「ごめん。このあとすぐ出動しなきゃいけなくなった」
「何かあったのか」
「租界近くで暴動だって。市街地だから急がないと」
「……」
淡々と身の回りを片づけたあと、スザクは机の一番上の引き出しから何かを取り出した。
昨日渡した騎士章だ。
「ごめん。返すよこれ」
借り物のペンを渡すみたいに、軽い口調でそう言われた。躊躇いが一切ない、あまりに自然な動作だった。差し出された右手には昨日渡したそれが綺麗に収まっていた。
既に自分の中で、突き返される覚悟も予想も出来ていた。ああやはりそうなるのか、という落胆と妙な納得感が胸に込み上げる。
「どうして?」
「僕はルルーシュの隣に立てないよ。君の足を引っ張ると思う」
「それは俺が決めることだ」
「話が通じないな。もう諦めてくれないか」
「それは悪かったな。お前こそなんでそこまでして、自分を卑下するんだ?」
「……」
七年ぶりに再会した時から頭の片隅に横たわっていた違和感が、ついに口から飛び出した。
別に聞く気はなかった。しかし七年前の彼といえば、もっと自尊心が強く、意見も真っ直ぐ言う奴だったように思う。成長の過程で性質の矯正や変容はあるだろうが、こうも正反対に振る舞われると純粋な疑問が生まれる。彼の身に何かあったのではないかと勘繰ってしまう。生まれつきの性格を覆すような、たとえば大きな事件だったり、トラウマに見舞われたとか。
スザクは続きの言葉をどう言おうか迷っていた。再び会話に少しの間が生まれた。右手に握ったままの騎士章を緑の目が静かに見据えていた。
「僕の父親、自殺しただろ」
「ああ、知ってる」
「あれさ、自殺じゃないよ。殺したんだ」
「……は」
「僕が殺したんだ」
感情のない平坦な声音だった。無機質な表情は心を映さないし、瞳はひどく濁った色をしていた。
スザクは開いたままの引き出しを閉じて、右手に握ったままの騎士章を机の上に置いた。差し出してもなかなか受け取らないから痺れを切らしたのだろう。それから、はあ、とわざとらしい溜息を溢してみせた。
「もう今日は夜遅くなると思うから、総督府に戻ったほうがいいよ」
「……待つよ」
「え?」
「お前が戻るまで居る」
「……困るから、そういうの」
そう呟いて立ち上がった男は、自分の横を通り過ぎて部屋の扉へ向かった。白のスーツに身を包んだその背中を見遣る。ぴんと伸びた背筋と大きな歩幅、力強い足取りがスザクの人となりを表しているようだった。
彼は馬鹿がつくほど素直で真面目だ。それでいて不器用である。奴が罪の意識に囚われ続けていることなんて、今なら手に取るように分かる。ともすればそれは、この期に及ぶまでその片鱗を一切見せなかった、痛ましいほどの努力が影にあったわけだ。
喉がつっかえて言葉が上手く出せなかった。なんと返すのが最適解なのか、あるいはこの世にそんな言葉が存在するのか。想像もつかない。
「帰る気ないの」
「俺は待つ」
「ああそう。もう好きにしてくれ」
背中を向けたままそれだけ言い残していた。
スザクは一瞥もくれることなく、部屋から出て行ってしまったのだ。
これではとても話し合いどころじゃない。一人きりになった部屋に残る空気までもが最悪に重苦しかった。
時刻はまだ夕方の六時を少し過ぎたくらいで、いつ戻るとは言及していなかった。遅くなるとは言っていたが、日付が超えるまでに戻れば早い方だろうか。
スザクは怒ってるとも悲しんでるとも、呆れてるともつかない態度で、始終突き放そうとしていた。目も合わせてくれなかった。険しく固い声と冷たく澄んだ瞳は、まるで別人のように見えた。
「……」
空いた椅子に腰掛けて、低い天井を仰ぎ見る。大きな溜息が口から勝手に出た。秒針の音が頭の片隅にまでこびりついて鬱陶しい。何か気を紛らわすものはないのかと周囲を見回すが、テレビも雑誌もこの部屋には見当たらなかった。
そうだ。スザクの部屋は著しく物が少ないのだ。先程見えた机の引き出しの中は空だったし、足元には小さな手提げ鞄だけしか置かれていない。娯楽に代わるものは勿論、おおよそ生活に必要になりそうな物まで不揃いなのだ。
一体彼はこの部屋で普段、どう過ごしているのだろう。
生活感がまるで感じられない室内を見渡して、ひとつの可能性に行き着くのは時間の問題だった。
スザクはいつ死ぬか分からない環境に長く身を置いてきた。そのせいで物を多く持たないことが習慣となり、彼のなかでそれが当たり前になっていたのだ。遺品整理を誰かにさせることを想定して、常に生活を送っている。それは現代の人間らしい生活とはかけ離れた、もはやただの生命維持活動だ。
ベッドの脇にあるごみ箱をちらりと覗くと、ゼリー飲料だとかカロリーバーだとか、いわゆる栄養補給だけに重きを置いた食糧品の紙くずなどが見えた。おおよそ想像していた食生活よりずっと、何倍も酷い内容だと推測できた。これ以外に、たとえば現場での配給や差し入れの食事を口にすることはあるのだろうか。そうであってくれと、願うしかない。
机に置かれた騎士章に視線を落とした。
一度はスザクの手の中に握られたそれは、あえなく突き返されてしまった。抑揚のない冷え切った声音を思い返そうとするだけで、喉の奥にどんよりと重く冷たい何かが溜まっていくような、嫌な心地になる。純粋に、ただただ悲しかった。
七年ぶりの邂逅と意思の疎通に喜んだのは自分だけじゃない。彼もきっと、これを喜ばしいことだと思ってくれたはずだ。そう信じたいのに、そうとも言い切れない今の状況が苦しい。
少し浮かれていたかもしれない。友達という関係の心地よさに甘えた節もあった。彼も自分と同じ気持ちだと勘違いして、空回って、結局自分は何も知らなかったのだ。スザクがこの七年間をどう生きて、どんな気持ちで軍門に下ったのか。
彼がどんな思いで過ごしてきたかなんて聞かずとも、その波乱に満ちた経歴を知れば薄々想像はつく。だから具体的に知らなくても、その想像だけの空虚なピースを組み合わせて、彼に寄り添ったつもりでいた。
さぞ辛かっただろう。苦しかっただろう。恐ろしかっただろう。痛かっただろう。
でもそれは単なる自己満足だ。他人の苦しみの最大値を頭で勝手に決め付けて、知った気になっていた。
今は知りたいと思う。スザクのことをもっと知って、孤独と罪悪に触れたい。恐らく胸の内にある、本人も気付いていないであろう薄っすらした希死観念、根底に聳える自罰的な思考、愛情の飢餓、放逸的な生き方。今のスザクを繋ぎ止めるのは自責の念と、それからあとは何だろう。吹けば飛ぶような今の在り方を否定せず、満たしてやるにはどうすれば良いのだろう。
監獄にも似た狭いワンルームで、自分はスザクの帰りを待ち続けた。なんの保障も担保もないくせに、必ず彼は戻ってくると信じていた。