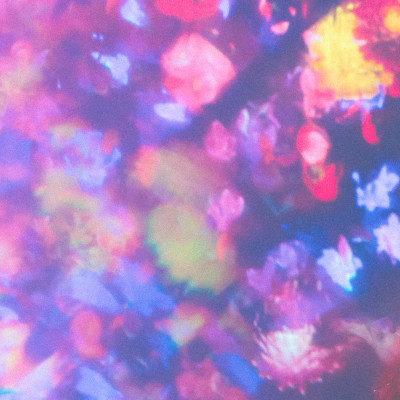
これをよすがとする 五話
吹き抜けの講堂は朝日を浴びて瑞々しい空気を孕んでいる。アーチ状の屋根がガラス張りになっており、天気の良い日は天井から自然光が差し込むのだ。朝の弱々しい太陽の光はとくに静かで厳かで、神聖な雰囲気すら室内に醸し出す。壁に嵌め込まれた大窓にはカーテンが掛けられ、隙間から漏れる光が床にちらちらと影を作っていた。
真っ白のテーブルクロス、汚れのない陶器に、艶々の銀食器、足元に敷かれた赤絨毯。縦に長い卓上へ置かれたプリザードフラワーは色とりどりの花弁を広げている。まだ食材も人も集まっちゃいないが、目を瞑るだけで賑やかな光景が眼裏に描かれる。
今日の夜はエリア11の総督であるコーネリアの武勲を称え、これを祝うという名目の、軍部主催の宴会が開かれるという話だ。なんでも数日前に中東地方の敵対勢力に対し、彼女が率いる軍が勝利を収め、帝国の新たな植民地・エリア18として併合を成し遂げたのである。彼女の成し得た偉業は列挙すればきりがないが、その中でも特に敵地平定はいっとう目覚ましい活躍であった。
敵対国からはブリタニアの魔女と渾名され恐れられる彼女であるが、味方となればこれ以上に心強いことはない。彼女に仕える騎士や親衛隊も忠義に厚く、上司部下ともに慕い・慕われる関係であるという。
ゆえに今晩は、そんな彼女を労うための会なのだ。これを称えると同時に、軍部全体の士気向上も図りたいのだろう。なんせエリア11は名誉人制度の制定に伴い内外でも意見対立の溝が深まり、治安は悪化の一途を辿っているのだ。総督コーネリアが一貫して純血派を主張している今はそちらが優勢ではあるが、名誉軍人を抱えるエリア11の駐屯地は混迷している状況だ。今一度意見交換を行い、名誉軍人の正しい運用方法を見出さねばならないタイミングなのだろう。
講堂の扉から一番遠い上座から見て、同じ卓の、反対側の席。その端から二番目の椅子を引いて腰掛けると、室内全体の様子がよく見渡せる。テーブルの食器類を揺らさぬよう椅子に座ると、あの日の夜のことがまざまざと鮮明に、今なお思い出せた。
七年前、日本国から渡ってきた首相らとの会食も、この講堂と同じ作りの部屋で行われた。一番奥の席には日本国の代表者がおり、その隣に齢十歳の嫡男が座していた。彼の隣には日本国を率いる大臣や官僚が順番に席に着き、帝国の官僚らと向かい合って食事を摂っていた。
自分の居た席からはその様子がよく見えた。首相の息子とやらは始終むくれ面を隠そうともせず、出されたコース料理に殆ど口をつけないのだ。なんて横柄で我儘な子供なのだろうと思った。それを注意しない周囲の大人たちにも疑問を抱いた。子供のことなんか視界にすら入らないような周囲の振る舞いに、ある種の恐怖心と嫌悪感を俄に感じた。
あの子供はたぶん、誰かに構ってほしかったのかもしれない。七年経った今だから言えることだ。少年は確かに、横柄で我儘な子供だった。けれど人並みの好奇心や興味、親切心を持って自分に接してくれたし、心を開いてくれた。心を打ち明けられる人が訪れてくれることを願って、粗野な振る舞いを繰り返していたとしたら、なんと不器用でいじらしい感情表現なのだろう。鬱屈した少年期を過ごした彼の心を想像すると切なくもなるし、やはり無理にでも引き留めておけばと後悔の念が募る。
講堂の前方にあるグランドピアノは物言わず鎮座しており、カーテンの隙間から差す細長い日光に足元を照らされていた。真紅の薄布がかけられており、黒光りする巨体には目隠しが施されている。照明すら点いていない室内は全体的に薄暗く物々しい空気が漂うが、それが逆に神々しさを醸すのだ。
日光に照らされた空気はそこだけ埃や塵が舞っているのがよく見える。肉眼では到底見えない物が可視化されるのはとても不思議な感覚だ。
実際に目で捉えられるものなんてごく一部でしかない。目で見えるもの全てが世界の本質だと考えるのは傲慢で視野が狭窄しきっている証左だ。そう思わずにはいられない。
「……ああこんなところに居たのか、副総督」
「コーネリア総督」
声のする方へ視線を動かすと、そこには見知った顔――家族でありビジネスパートナーでもあるコーネリアが立っていた。
「なんだ、楽しみで待ちきれなくなったか」
「ふ。まあ、そんなところでしょうか」
彼女はヒールの甲高い足音を立てながら近寄り、卓の向かい側の空席に腰を下ろした。
「して、総督。私にご用件でしょうか」
「先日依頼されたデータの収集が完了したから、それを渡そうと思ってな」
「さすが、仕事がお早い」
「この私を小間使いするなど貴様くらいだろうな」
「滅相もありませんよ。軍部とのパイプが強い総督にしか頼めないことですから」
彼女はワインレッドに染まる唇を緩ませ、嘲るように笑った。同時にテーブルクロスに囲われたテーブルの下から手を伸ばされる。自然な動きでそれを掴むと、手のひらに何かを押し付けられ、そのまま受け取った。
「なら副総督にとって、奴ならもっと心強いだろうな」
「……奴とは」
伸ばした腕を引っ込めて、彼女は椅子の肘掛けで頬杖をついた。
「副総督には先に話しておこう。これはまだオフレコだが、私は先日平定したエリア18の総督に任命される予定だ」
「それは兼任という意味ですか」
「いいや、ここエリア11は別の者が選任されるようだ」
「コーネリア総督のご判断でしょうか」
「奴を推薦したのは私だが、本人がそれを引き受けるとは思いも寄らなかった」
こちらの反応を愉しむかのように唇を歪ませる。鋭い視線は何かを企むように細められていた。あくまで公私混同を嫌う彼女が、今だけは弟をからかう姉の顔つきをしている。
「つまり、どういうことです?」
「シュナイゼルだよ。奴がエリア11の新たな総督になる」
「兄上……宰相がですか? 本国の内政にしか関与しないのでは」
「私もそう思っていたがな。特派の動きに感化されたのか、あの重い腰を上げるそうだ」
これまでブリタニア本国の内部で政治に携わってきたシュナイゼルは、卓越した外交術や広い見識、先見性のある政治的手腕により安定性のある国政を築いてきた宰相でもある。彼の支持率は国内でも高く、次期皇帝に最も相応しい器だとして喧伝されているほどだ。
彼の精彩はこれまで国内政治でしか発揮されておらず、併合地へ関心が向けられたことはない。軍事には疎いという噂も一時あったが、ユーロピア圏で起こった紛争では彼が指揮権を握った。その際は快勝を収め、帝国の名を轟かせるにまで至った。
「軍事に消極的な方だと思っていましたが、エリアの治安安定化のために何か働きかけを……」
「案外、副総督と考えは似ているのかもしれない」
「私と?」
「戦わずして、あるいは争い事を最小限に抑えたうえで勝利を齎す。宰相のやり方は私と真逆だから最初は手探りになるだろうけど……副総督なら上手く舵取りできるだろう」
「……この件に関して、宰相にお話をされたのですか」
先ほどテーブルの下で受け渡されたそれを懐から取り出し、手のひらに収めて見せた。その様子を見たコーネリアは静かに首を横に振った。
「いいや。本人は何か感づいているかもしれないが」
「そうですか」
「相談してみるといい。可愛い弟からの頼みなら、奴だって嫌な顔はしないだろうさ」
「総督」
「冗談だ」
ふ、と一瞬だけ笑みを溢すが、それも束の間だ。瞬きの次にはいつもの厳しい表情に戻っていた。
「……それともうひとつ。個人的に気掛かりなことがあったから、念の為お前にも伝えておこう」
「気掛かり、ですか」
雰囲気を一変させ、彼女はより一層声量を落とし言葉を紡いだ。
「此処、総督府の最奥、北側に面する部屋に気を付けろ」
「気を付けろとは」
「本国の文官が何度か立ち入っているらしい。私は直接見たことはないが、以前ユフィが言っていたんだ」
青紫の瞳がぎらりと光り、警戒心を掻き立てる。
「彼らは怪しげな文書を腕に抱えて、一目散にその部屋へ消えていくんだと。緑色の髪をした女の写真が写った、謎の資料だそうだ」
「緑の、髪……?」
「心当たりがないならいいんだ。変なことを言ってすまなかったな」
鋭い眼光を放つ瞳はすぐさま元の色に戻り、釣り上がる眦は垂れ下がった。瞬時に表情や身に纏う空気を一変させるその仕草は有能な指揮官だからこそ備わった世渡りの為の術なのだろう。呆気に取られている間に話は済んでしまったようで、コーネリアは涼しい面持ちで端末の時計を見遣った。
やがて彼女は緩慢な仕草で立ち上がり、肩から羽織っていた外套の裾を靡かせた。
「私は基地に戻り終日機体のメンテナンスに立ち会う。副総督のご予定は」
「総督から頂いたデータの精査に取り掛かります。午後は、特派からの活動報告を受け取る予定です」
「そうか。分かった。また今晩、楽しみにしているよ」
「ええ。こちらこそ」
去りゆく堂々とした背中を視界の端に収めたのち、再び一人きりになった講堂を見渡した。静かに響くのは自分の呼吸音と椅子を引く摩擦音くらいで、あとは何も聞こえない。ここがあと半日も経てば人で溢れ返り、賑やかな声と匂いとピアノの音色に包まれるのだろう。俄に信じ難いが、会期は刻々と近づいている。
恐らく溜まりに溜まっているであろう事務机の書類の山をふと思い出し、ようやく椅子から立ち上がった。そういえば朝食すらまだ摂っていないことも同時に思い出し、講堂から足早に立ち去った。
枢木名誉一等兵が特派に転属されてから、すでにひと月と少しが経っていた。本人とは直接的なやり取りや接触は一切なかったが、定期的に送られてくる活動報告は彼の名で記されたものであった。そしてそれが、彼の生存を知ることができる唯一の媒体だった。
元々軍部と密接な関係である総督にもそれは送られていたが、特派に人材を斡旋した自分も、彼ら組織の関係者としていちおうは見做されているのだろうか。一組織を動かせるほどの権限は副総督の立場上持ち合わせていないが、その捉え方は様々だろう。
軍部における特派の特殊な立ち位置も作用していたのかもしれない。組織の代表であるロイド伯爵公はシュナイゼルと旧知の仲であり、シュナイゼルはロイドの研究開発事業を全面的に支援していた。ゆえに軍部内でもその活動内容や予算繰りにかなりのお目溢しを貰っているようだ。帝国宰相公認という肩書は伊達じゃない。組織の奔放ぶりに灸を据えたい高官も居るようだが、実際にそのようなことがあったという報告は上がっていない。
名誉軍人を最新鋭ナイトメアフレームのパイロットに任命するという前代未聞の事態に、軍部も今回ばかりはさすがに黙っては居られなかったらしい。直談判とまではいかないが、軍部の議会では苦言を呈する場面が相次いだようだ。しかし特派のバックボーンが名誉人パイロットを黙認したことで、それらの意見も同時に黙殺されたのだという。
エリア11はこれまで純血派を主張するコーネリアが総督として指揮を執り、同じ主義主張の軍人らが幅を利かせていた。しかし一風変わって、そうした争いや主張を好まないシュナイゼルがエリアの代表となると軍部の組織図も一変するかもしれないのだ。軍の存在意義にも関わるかもしれない。
これを好機として利用できるかどうかは自分次第だ。まずはそれまでに味方を作って、組織でうまく立ち回れるよう準備を進めておく必要がある。
受け取った特派からの報告書に目を通しながら、具現化してゆく己の計画の構想に黙々と耽っていた。
だだっ広い室内に並べられた卓上には、今朝にはなかった食事や大皿、食器、酒のボトルが無数に置かれており、まさに宴の様相を呈していた。吹き抜けの天井にまで木霊する話し声とピアノの音色は空気の中で互いに混ぜ合わさり、有象無象の雑音となって耳に届く。それを快か不快かと問われれば人によりけりだろうが、こうして身分や立場を違える仲間が一同に会する機会はそうそうなく、珍しい光景だと思う。
室内の中央にあるテーブルの一番奥、その中でも短辺の中央に座席を指定されていた彼女は当然、この宴会の主役だ。入れ替わり立ち替わり多くの人が彼女の元に訪れ、挨拶を交わしてゆく。グラスに注がれては口内に消えるシャンパンは、ボトルが何本あっても足りないほどのペースで消費されていた。これは夜通し続きそうだと、誰の目から見てもその賑やかぶりはあきらかだ。
主賓のコーネリアから向かって右側に自分は座っていた。会が始まって一時間ほどが経とうとする頃、何故だが自分の向かい側の席、つまり彼女から見て左手はいつまで経っても空席のままだった。
「姉上。こちらの席は一体、どなたが」
周囲を見回すと彼女の騎士や親衛隊、ユーフェミアやナナリーの姿もある。親しい面子は思いつく限り、ひととおり揃っている。
「……ああ。噂をすればほら、来たじゃないか」
コーネリアは淡く色づく飲料をグラスで燻らせながら、おもむろに顔を上げた。その視線はちょうど、自分の背後にあった。
「やあ、コーネリア。ルルーシュも」
顔を上げると久方ぶりに見る兄の、元気そうな姿があった。
「遅れてすまないね。手続きに時間がかかってしまって」
「手続き?」
「聞いていなかったかな。私がエリア11の総督になるという話」
「姉上から伺ってはいましたが……まさか」
シュナイゼルは可笑しそうに目を細めると、手袋に包まれた白い人差し指を口元に当てた。
「ちょうど人も揃っているしね。立派な壇上も用意されているし、あとで使わせてもらうよ」
「まさか姉上、このことをご存知で教えて下さらなかったのですか?」
同じく可笑しそうに笑いを堪える彼女に訴えると、悪びれもせずこう宣うのだ。
「お前は賢いからとっくに勘繰っていると思ってたよ」
「まさか。兄上が今夜、総督に即位されるとは思いも寄りません」
「ならルルーシュはまだ半人前だ」
くつくつと笑う兄と姉の顔を睨みながら、冷めかけていたスープにスプーンを浸した。
まったく大胆不敵な皇族(かぞく)たちだ。なんの緊張感もなく目の前の席に着いた兄に対し、口に出せない思いの丈を視線だけでぶつけてみる。
総督が代わるというだけでも一大事なのに、今夜からというのはあまりに唐突過ぎる。副総督である自分も数時間前の今朝に聞かされたばかりで、急な事態をまだ飲み込んでいる最中だというのに。明日は昨日今日の延長線だと信じて疑わない思いが、来る変革を受け入れ難いと訴えているのだ。
「コーネリアはいつもアルコールが入ると話が長くなるからね。手短に頼むよ」
「そ、そのようなことは」
「時間オーバーしたらギルフォード卿に頼んで舞台袖に運んでもらおうか」
「ユフィの前でそのような醜態は断じて晒しませんから」
「はは、言ったね。登壇の時間が楽しみだ」
「……」
気の抜けた家族の会話に肩の力が一気に抜けた。スープと入れ替えに、目前に置かれたマリネサラダの盛り付けになんの感想も抱かずフォークを手に取った。バルサミコの酸味とピスタチオの香りが合わさって口の中に広がる。脇に置かれた温かいパンを掴み、皿に残ったソースにつけて食べた。
「なんだいルルーシュ、機嫌が悪そうだな」
「いいえ、俺のことは良いのでどうぞご歓談を」
「まあまあそう気を荒立てずに。私がこの場に居るということは、彼らもこの会場のどこかに居るはずだよ」
「彼ら?」
魚料理のメインディッシュが運ばれ、白身魚にかけられたホワイトソースの香りが鼻孔を擽る。付け合せの温野菜が料理に彩りを添えており、白い陶器によく映えていた。
「例の報告書、君も受けているだろう。書かれてなかったかい」
「……いえ、そうした記述は」
「そうかい。私が来たときは入口近くの席で見かけたけどなあ」
ちらりと背中側、入り口となる扉の方向に首を動かした。人混みに紛れているせいか、兄の言う者達の姿はよく見えない。
「そのうち各々で席移動が始まるだろう。それまでじっとしておけ、ルルーシュ」
「コーネリアは特派に反対だったっけ。気を悪くしたかな」
声を尖らせる彼女に、すかさず兄は話を振った。
「……いえ。主義の異なる兄上のやり方も私は反対しません。しかし少々、綺麗事が……理想が過ぎるかと。争いなくして平和が訪れた時代は人類史上ありませんから」
「そうだね。でも私たちはその理想を現実にするためにこの職務に就いている。少なくとも私はそういう理念の元に働いてるよ。それが市民が求める宰相のあるべき姿だと思っているから」
「兄上」
「すまない、出過ぎたことを言ったね」
彼は最後にそれだけ言うとおもむろに席を立ち、壇上を見遣った。マイクや音響のセッティングが整ったらしく、上手側の舞台袖から数人の係員が顔を覗かせて合図を送っていた。
「さあコーネリア。この場に居る全員が君の登壇を待ってる。存分に話を聞かせてやっておいで」
コーネリアの手を取り、壇上までの階段をシュナイゼルがエスコートしてみせた。この場ではあくまで彼女が主役なのだ。長いスカートの裾を持ち上げながら、彼女は足音を消して静かに階段を上がった。
シュナイゼルの姿を目に留めた各所では、どよめきすら巻き起こる。しかしその様子に喝を入れるのは勿論彼女の役目だ。マイクを通して轟く勇ましい声に、賑やかな会場は一転して水を打つ静けさに包まれた。この場に集まった全員が彼女の主義に賛同していると言っても過言ではないのだ。誰もが自分の席に戻り、壇上に上がる彼女の一挙一動を固唾を飲んで見守る。
「愛する我が兵士たちよ」
マイクを通して響く声は一転して優しい音に変わった。どこか切なげな、慈しむような表情が浮かばれる。
「此度はこのような素晴らしい宴を催してくれて有難う。こうして人に感謝することは久方ぶりだ。常日頃戦に奔走する私が言えたことではないかもしれないが……」
コーネリアは一旦そこで言葉を区切り、言い惑うように唇を動かす。しかし表情には決意の思いが満ちていた。
「ここまで着いてきてくれた兵士たち皆に感謝する。皆の活躍がなければ、私は今ここに立てていないからだ。とくに我が騎士ギルフォードと、親衛隊たちよ。此度の武勲もまた、私だけの物でなく私達で得た勝利なのだ。それを重々理解し、肝に銘じてほしい」
名指しされた彼らは彼女の言葉を受け敬礼してみせた。一糸乱れぬ統率の取れた親衛隊は彼女が鍛え上げた軍隊だ。それが誇りだというように、彼らは表情を引き締めている。
「そして私からはもうひとつ。突然の発表となるが、あまり騒がず静粛に聞いてほしい」
静まり返る会場にはマイク越しの声音だけが響く。彼女は面々を見渡し、言葉の続きを紡ぐ。
「現在此処エリア11の総督を務めるコーネリア・リ・ブリタニアだが、任期を本日までとする。明日以降、私の後代として総督を務めるのは本国宰相シュナイゼル・エル・ブリタニアとなる。私は先日併合した中東地区のエリア18新総督として、明日から任に着かせてもらう」
コーネリアの前置きもあったが、やはりどよめきが巻き起こる。それも致し方ないだろう。自分と席の近いコーネリアの親衛隊たちは動揺した様子もないから、恐らくは彼女の口から事前に周知されていたのだ。ユーフェミアやナナリーの反応も冷静だった。この卓で試されていたのはどうやら自分だけだったらしい。
会場のざわめきを物ともせず、コーネリアはマイクをシュナイゼルへ手渡した。
「……まずは急な告知と決定になって申し訳ない。明日から此処エリア11の新総督となるシュナイゼル・エル・ブリタニアだ。神聖ブリタニア帝国宰相として任を全うしつつ、此方の軍事や内政に関わっていく所存だ。副総督のルルーシュともこれまで以上に連携を取りながら、より健全な統治を進めていきたい」
壇上の男がこちらをちらりと見遣る。投げかけられた視線に瞬きだけで返すと、彼は言葉を続けた。
「私は抜本的な意識改革を、エリア11の軍部に呼びかけるつもりだ。これは前々から既に本国で決定されていたことだから、私にもそれなりの準備はある。世界各国の研究機関や民間企業に兵器の開発をしてもらっていて、それらの最初の実戦突入をエリア11で行えるよう、まずは計画を立てていきたい」
シュナイゼルが兵器開発に多額の投資を行っていたことは、特派への支援姿勢から鑑みるにさして驚くことではない。それより重要なのはその後の発言だ。最初の実戦投入。そのための計画。むき出しの思惑は寝耳に水である。
「私は計画実現の為ならどんな手段も講じるつもりだ。勿論平和的な方法で。しかしそれらの意に沿わない者や思想を排除することも、私は厭わないつもりだ」
彼はそこまで言い切ると、いつの間にか静寂が訪れていた会場と集った面々を再び見渡す。
「時代に求められる素質は柔軟な発想力と機動性、そして傾聴の姿勢だ。これなくして市民が理想とする国家は築けない。ここに居る全員に、与えられている職務とそれが与えられた理由について、今一度向き合ってほしいと思っている。そして是非、理想を叶える為にも、協力を願いたい。私からは以上だ」
そこまで言い切ると、彼は傍にあった演台にマイクを置いて頭を下げた。静まる室内に途端、鳴り響いたのは小さな拍手の音だった。遠い場所から聞こえた音は一人分だろうか。
それに重ねるように自分も手を叩いた。衝撃的な内容だが、だからこそ人の記憶に残る立派な演説だ。素直に敬服の念を込めた。
すると波及するように、周囲からも音が響き、それは会場全体を包む大きな波となって合わさった。漸く顔を上げた男と再び目が合う。してやってくれたな、という目で見つめると、彼は柔らかく微笑みを返した。このアウェーの雰囲気の中でも堂々たる態度だ。並大抵の心臓の持ち主ではない。
鳴り止まない拍手に包まれる中、おもむろにマイクを再度手にしたのはコーネリアだった。彼女はシュナイゼルより一歩前に出て口を開く。
「私と宰相閣下は異なる主義主張を持つ。ゆえにやり方は違うものになるだろうし、兵士らは戸惑うこともあるだろう。しかし宰相閣下は争うこと以外で開かれる平和の道を明示して下さった。私はこれを信じる。だから私にこれを誓った宰相閣下を、皆は信じてほしい」
それはエリア11の軍部、ひいては本国に蔓延る純血主義との決別をも示唆する言葉だった。なおも彼女はこう続ける。
「しかし勘違いするな。私は元来、ひとつの思想が他者を傷付ける為の道具として利用されることに反対している。具体的な明言は此処では避けるが、こと軍部においては、その配慮が著しく欠けている。私は、それは是正されるべき傾向と捉えているし、宰相閣下とも意見は合致した。私が成し得なかった軍部の変革と新しい在り方の提示を、宰相閣下に委ねたいと思っている」
兄と姉は顔を見合わせたあと互いの手を取り握手を交わした。友好とはかくあるべきである、という好例のような光景だった。
二人が降壇すると、会場は止まっていた時間が動き出したかのように、飛び交う話し声と音楽、革靴の足音に包まれた。
とはいえそれは別の卓の話であって、渦中の二人が集うこのテーブルには多くの人が詰めかけては矢継ぎ早に質問を投げかけていた。
「明日また会見と演説を行うつもりだから、そこで質問に答えるよ。今日は一足先に場を借りて、話をしたかっただけなんだ。驚かせてすまないね」
「まあそう慌てるな。私が死ぬわけじゃあるまいし、お前たちが食いっぱぐれる心配もない。帝国に忠誠を誓うお前たちは誰が指揮官だろうがとっくに立派な戦士じゃないか」
その若さで一国を束ねる男と武勇を恣にする女、ブリタニア帝国皇室が代表する二大頭はそう笑いながら詰め寄る者達を往なしていた。
「兄上。先程の登壇の際、いの一番に拍手を寄越してきたのはやはり」
「ああロイドだろう。彼は良くも悪くも空気を読まないから」
「相変わらず変人に好かれるんですね」
「コーネリアは変人ではないだろう」
「またおかしなことをおっしゃる」
照れ隠しにワイングラスを傾ける姉に、兄は微笑みを溢す。
シュナイゼルはその言葉と同時にふと周囲を見回して、今度はこちらに視線を寄越してきた。
「ルルーシュ。もう自由な席移動が始まって、宴は中盤に差し掛かってる。行くなら今が丁度いい」
「……兄上。自分は何も、言ってませんが」
「何。さっきからちらちらと入口の方を見ていたじゃないか。そんなに気になるなら早く顔を出してきなさい。私はこのとおり、下手に動けないからね」
「……」
すっかりお見通しだったらしい。彼の観察眼を前にすれば、どんな演技もポーカーフェイスも素人の付け焼き刃に成り下がる。
軍部の高官や関係者に囲われるシュナイゼルは静かに笑いながら、離席を促してくれた。ここは兄の言葉に甘える他ない。
自分は意を決して、空のグラスを片手に漸く席を立った。
特派をこの会に招いたのは紛れもなくシュナイゼルであろう。軍部から腫れ物じみた扱いを受ける枢木スザクを要する組織が末席であれ席が用意されている事自体、何者かが仕組んでいない限り実現不可能だ。シュナイゼルが出席すると知った時点で、そのことにいち早く察するべきだった。
入口近くの卓を見渡すと他とは違う色味の軍服に身を包む女性と、珍しくスーツ姿の男がすぐ目に入った。しかし件の青年の顔は見当たらないのだ。
「スザクくんなら宰相の演説のあと、すぐ席を立ってしまって。まだ戻ってないんです」
「道に迷っちゃったんじゃないかなあ」
「まさか。案内状に建物内の地図が同封されていましたし……」
「でもさあ、ほら。彼の分の案内状、テーブルに置きっぱなしだしねえ」
「まあ、本当だわ」
二人の軽快なやり取りを見て、思わず溜息を吐いた。
いつぞやの、もっと言えば七年前の再演かのようなシチュエーションだ。右手に持ったままの空グラスは彼の席に一旦置いて、再び周囲を見渡した。
「どこかで挨拶回りをしているとか、知り合いに会ってるとか……」
「スザクくんのグラスはここに置きっぱなしだし、戻ってはないと思いますよ?」
頬杖をつくロイドがそう話す。
「私が探して呼び戻してきます」
「いえ。総督府の敷地は私が一番詳しいですから、見てきますよ。女性にご足労頂くのも悪いですし」
立ち上がろうとしたセシルを制止させ、入口の扉に視線を遣った。
「申し訳ないです」
「お気になさらず」
二人に笑いかけながら、自分は卓から立ち去った。
総督府の敷地内は、赴任した当日から道順も部屋の位置も全て頭に入っていた。なんせ生まれてから十七年間、ずっと暮らしていたブリタニア本国の宮廷、および離宮の構造と、総督府と呼ばれる建物の構造は瓜二つだったのだ。そもそもの敷地面積が異なるゆえに完全なコピーとまでは呼べないが、間取りや尺度、役割ごとの部屋の位置まで一致している。敷地の裏側に面する庭はアリエスの離宮で見られた庭園と全く同じ風景が広がっている始末だ。
現総督コーネリアの前任であるクロヴィスが立案、設計したこの建物は本国宮廷の摸倣品であった。彼は宮廷の建築をいたく気に入っており、ブリタニアの建築技術や美術を海外に広める名目で設計を指示したという。この建物は彼の愛国心を象徴しているのだ。
先程の講堂もまた、宮廷内に実存する大広間を模して設計されている。照明の位置からガラス天井の構造、壁や柱に設置されたフレスコ壁画や彫刻に至るまで完全再現という熱の入りようである。多額の予算を費やして建てられた建物は一種の権力誇示という見方もできるが、大半の識者はこれを無駄遣いとして糾弾し、前任の彼は敢え無くその任を解かれる羽目となったが。
部屋を出て廊下を暫く道なりに歩く。やたらと静かな道は周囲の一切の物音を拾わず、ただ自分の足音を響かせるだけだ。
突き当りに差し掛かって角を曲がると、その先の遠くに影があった。壁に嵌め込まれた大窓に面して立ち竦む人影は、歩み寄るほどにその人物の正体に確信が持てた。どこか憂いを帯びた横顔は照明のせいで、そう見えるだけだろうか。天井に吊るされたシャンデリアは硝子細工の中で光を乱反射させ、廊下を眩く照らしている。窓の外は暗転し、星も見えなかった。
「迷子か?」
「……」
声をかける前からこちらの存在に気づいていたくせに。
彼が顔をこちらへ向けたのはそれがきっかけだった。ゆったりした動作で体ごと動かした男は何も言わず、視線をくれるだけだ。
「それともまた、戻りたくない、か?」
「……探させてしまいましたか」
「案内状がテーブルに置き去りになっていた」
「申し訳ありません」
小さな封筒を手渡せば彼はそれを大人しく受け取る。が、それを右手に持った瞬間、訝しげな顔つきを浮かべた。
「これは一体……」
「表には出すなよ。話があるんだ」
封筒の中でかさかさと音を立てる物の正体ははマイクロチップだ。要はデジタル記録媒体である。小指の爪ほどしかない大きさのそれは丁重に扱わねばすぐに紛失してしまう。
「話、とは」
「こちらに入れ。何、人払いがなくとも立ち聞かれる心配はない」
一番傍にあったとある部屋のドアノブを握り、おもむろにその一室へ招いて見せた。明かりのない室内は暗闇に包まれており、少し肌寒い。
廊下の外、ドアの目の前で棒立ちになる男に声をかけた。早く入れ。何をしてる、と。
「ここは何の部屋ですか」
「俺の私室だ」
「……副総督」
彼は顔を強張らせて半歩後退った。しかしそれを許すほどこちらも脇は甘くない。
壁際に触れていた腕を咄嗟に掴み取り、揺れる緑を見つめた。
「あの時と同じだ。懐かしいだろう?」
「招いて頂いた講堂も、この廊下も、ひどく見覚えがあります。吐き気がするほどに」
「だろうな。この建物は本国の宮廷とそっくりそのまま、模して建てられたんだ」
「悪趣味な……この招待状も副総督の差し金で?」
「いや、俺の意思は一切関与していない。兄上が勝手にやったことだよ」
その返答が予想と反していたから気に食わなかったのか。彼は眉間の皺を深くし、感情のない瞳を向けた。
「私がここで叫びでもすればすぐ誰かが駆けつけるでしょう」
「やれるものならやってみろ」
掴んでいた腕にほんの一瞬だけ、力を込めることを止めた。
その瞬間だ。たたらを踏み瞠目する男の様を、この両目が捉えた。
下肢のバランスが僅かに崩れたところを狙い、再度腕を掴んで手前に引き込む。瞬時に扉を閉める。ガチャリ、とロックがかかる金属音が頭の片隅に響いて、それから目前にあるのは怒りでも悲しみでもない、どこか軽蔑するような表情を浮かべるスザクの姿だった。
七年前の仕返しである。
人は予想だにしない衝撃が加わると一瞬だけ、判断も思考も反射神経も失われる空白の時間が生じる。それを教えてくれたのは紛れもなくこの男であった。
広々とした私室はさながら高級ホテルのスイートルー厶を想起させる。入ってすぐのエントランスを抜けると間仕切りのないリビングが見え、その奥に続くこじんまりしたゲストルームには二対のソファとスツール、そしてローテーブルが置かれている。壁と扉を隔てた向こうには寝室や浴室、小さなキッチンスペースといったプライベートゾーンも設置されてある。決して狭くない自分専用の空間は一人で使うには少々、いやかなり持て余す。
身内以外、滅多に人を通さないゲストルームのソファにスザクを座らせ、その向かいの椅子に自分も腰掛けた。彼は先程まで見せていた抵抗の意思を完全に失ったようで、背筋を伸ばしたまま黙っていた。視線はガラス張りのテーブルに注がれており、こちらとは目が合わない。合わす気がない、とも言える。
茶でも飲むかと尋ねたが、いいえ、と短い返事を返されて終わった。真一文字に固く結ばれた唇はそれ以降音を発さなかった。
我慢比べ、揺さぶり、機微の観察。すべて自分の得意分野だ。
ゆえに、彼の口を開かせるのは容易なことだった。
「お前に頼みたい任務がある。これはスザク、お前にしか頼めないことだ」
テーブルの端に追いやられていた封筒を手に取り、中からマイクロチップを取り出した。ガラスのテーブルに音を立てながら落ちたそれを、男は視線だけで追う。
「作戦要綱を先に言おうか。目的はエリア11を統括し、駐在を続ける軍部の解体だ」
「……」
男の眉根が動く。その変化を視界の端に捉えながら、ゆっくり言葉を紡いだ。
「方法として、ざっくり言うと……イレヴンが結成した"日本解放軍"と俺が手を組み、軍部の転覆を引き起こす」
「……」
「そのチップは日本解放軍のメンバー情報と本拠地が記録されてある。既に彼らのグループリーダーと連絡は取れているし、先日からのクーデターの幾つかは俺が裏を取って先導した」
「……は」
「解放軍が俺の話を信用してくれているかどうか、確認する意味もあった。結果は成功だ。軍部には僅かであるがナイトメアフレーム数機を失う損害を与えた」
彼は依然黙ったままだが、震える唇は何かを言いたげだ。
「最終目標は租界内の軍部本基地の包囲だ。勿論人殺しはさせないし、元よりするつもりもない」
「……」
「この作戦を成功させるにおいて、最も必要なことはふたつだ。こちら側、つまり総督府内に俺の味方をつけること。もうひとつは突破力」
「……」
「味方はすでに居る。前総督のコーネリアと彼女の親衛隊たち、そしてロイドとセシル……」
「……ま、待ってください」
「話は最後まで聞け。ブリタニア家に仕えるジェレミア卿と、そしてもうひとり。これは直接確認できていないが恐らく帝国宰相……シュナイゼルもこちら側に着いていると俺は確信している」
「……は。随分な自信家でいらっしゃる……」
「シュナイゼルは俺の作戦を察知してエリア11の総督に名乗りを上げたと想像している。作戦に協力していたコーネリアとシュナイゼルは幾度か本国で接触をしていたからな」
「……」
スザクは聞き飽きたと言わんばかりに天井を仰ぎ、かぶりを振った。どこか否定的な態度はそのままに、懐疑的な口調と目つきがこちらを窺う。
「ロイドさんとセシルさんが副総督の話に乗ったと……そして宰相まで……」
「スザクには俺たち解放軍側の突破力……つまり攻撃の軸になってほしいんだ。軍部は決して一枚岩の組織ではないし優秀な指揮官やパイロットが数多在席する。母数の数も桁違いだ。多勢に無勢、正面からぶつかればこちらに勝機はない」
「……そこまで分かっていて、どうしてそんな博打を打つ必要がおありなんでしょう」
「特派から送られてくる報告書を見た。そこで、俺はお前の優秀な戦績と機体適応力に賭けたいと思った」
「私が名誉人だからではなく?」
スザクは低い声でそう尋ねてきた。
疑り深い人間の警戒心を解くに一番最適なのは、嘘を吐かず真摯に向き合うことだ。だからたとえそれが憚られることでも、適当な嘘を吐くくらいなら、包み隠さず話したほうがよっぽどマシなのだ。
「……ああ。それもある。解放軍は全員日本人で構成されているから、お前のような存在は大きな旗印となり得る」
「人を駒扱いですか?」
「違う」
「……本気で人に物を頼むなら、それなりの誠意を見せるのは如何です?」
「たとえば」
彼は目も合わせず、冗談めかしてこう宣った。
「ああそうだな、日本式の土下座なんてどうでしょう」
「分かった」
椅子から立ち上がり、その場で床に両膝をつけた。地べたに座り込むような姿勢のまま膝の前に両手を置き、頭を下ろす。額は床に置いた手の甲に乗せるよう、背中を曲げて――
「やめてください」
頭上から落ちた声に首を持ち上げると、焦った面持ちの男から腕を差し伸べられていた。
いつの間にかソファから席を立っていた彼は、自分に寄り添うように、片膝をついて体を屈めている。伸ばされた手に痛いくらい肩を掴まれ、床から引き起こさんと揺り動かされていた。
「冗談じゃない」
「俺は本気だ」
「そんな貴方は見たくない」
「なら、どうすればいい」
「……」
上半身を起こして、漸く目が合った。間近に見える翡翠の双眸はやはり戸惑うように揺れ続けている。
暫く無言が続いたが、言葉を待った。少々意地の悪いことをしてしまったから、彼にそれを言い渋らせてしまった。
「何故、私に拘るんですか。他にも優秀な兵士は山程……」
「お前を信用したいからだ」
「だから、それは何故だと聞いているんです」
「……」
「……」
鋭い眼光が顔中だけでなく全身を射抜く。悪い思惑を腹の中に隠しているんだろう、という疑いの眼差しだ。
長い沈黙はスザクに余計、疑念を抱かせることになる。包み隠さず胸の内を打ち明けねば、彼と自分の間に聳える溝は一向に埋まらない。
「……友達に、なってくれただろう」
「……え?」
「だから……」
徐々に俯きがちになる目線や顔に集まる熱は隠しようがない。剥き出しの本心とそれを見せることの意味を、彼はどこまで理解してくれるだろう。これは最早祈りに近い。
「ブリタニア人を心底嫌うお前が、俺を特別だと言ってくれた。なのに俺は……その信用を裏切るようなことをしてしまったと……」
「……」
「日本を元通りにして、スザクに返したいんだ」
「……」
「……なあ、何か言うことはないのか」
俯く顔の向きはそのままで、恥も外聞もなく、思わず返事を乞うてしまった。
なんせ隣の男からは一声も言葉が発せられないのだ。自分ばかり本音を言わされるのは、何とも癪である。
「……ふ」
「……」
「……は、はは」
「何、笑ってる」
顔を上げて隣を向くと、今度は彼が顔を伏せていた。肩が震えている。
「いや、だってそんな、君が」
「……なんだ」
小刻みに揺れる肩は、笑いを堪えているからだ。口元を手で抑えるのは吹き出すのを我慢するからだ。赤くなった頬や緩んだ目元も明るい声音も、きっとそのせいである。
「七年前のことをずっと、今も根に持ってたなんて、ああ、可笑しい」
「そんな言い方するなよ」
「とんでもない執念だ……はは。七年越しに不敬罪でしょっ引かれるんだと、ずっと思ってた」
そんな訳があるかと言いかけたが、安堵に満ちた表情を見て、それが彼の本心の全てであったと確信した。よほど自分には信用がないらしい。
「君はいつも強引過ぎるんだ。再会した時だって急に乗り込んできてさ。僕にも心の準備をさせてほしいよ」
「……それは」
「心当たりが無いとは言わせないから」
随分な回り道も己の言動が原因とくれば、言い返す言葉は見当たらない。釘を刺すような彼の発言に押し黙ると、また可笑しそうな笑い声を聞かせてくれた。
「ああそれで、本題は何だっけ」
「王政復古の大号令、もとい、日本政権復古の為の作戦参加を要請しに来た」
スザクは口元に弧を描きながら見つめてくる。無言で視線を返してやるとそれだけで彼は満足そうに微笑んで、唇を開いた。
「イエス、ユアハイネス」
恭しく跪いた彼の所作はどこで覚えたのか完璧なもので、見惚れるほど美しかった。
しかしその本心だけは口に出せなかった。首肯するだけに留まったのは何よりも気恥ずかしさの所為であり、湧き上がる名前のない感情に気づかぬ振りをするので精一杯だった。
気だるい体に重い瞼、遠くなる視界に虚ろな意識。これはいけないと頭を振って、一旦キーボードから手を離した。
眠気覚ましのブラックコーヒーを啜りながら、霞み始めた視界を元に戻そうと目頭を揉んだ。数度瞬きすると成程、原因が眼球の乾燥だとはっきり分かった。潤いの戻った網膜越しにパソコンの画面を覗くと、二重にぶれて見えていた文字が今やくっきりと鮮明に書かれてある。数字の1と7、6と8を見間違えそうになっていたが、今はそれらの区別がはっきりとつく。固まりきった背筋を伸ばし、ふうと息を吐いて、暫く離れていた右手を再びマウスに置いた。
麗らかな午後の昼下り、とくに予定のない日はこうして事務作業に明け暮れるのが常だ。とはいえ、メールボックスの未開封受信数は表示できる数字の限界値を超えかけており、サイン待ちの調書や提出書類はトレーに山積みになっている。どれだけ暇な時間が出来ようと到底捌ける量じゃない。
ついつい優先順位を後ろに回して溜め込んでしまいがちな事務処理は、爆発寸前まで置き去りにしてしまいがちだ。それらはさながら時限爆弾である。
そして途方も無い手つかずの作業残数に、つい気が逸れてしまう。さきほど体に流し込んだばかりのコーヒーを再び口に入れて、今度こそ意識の散漫を防がねばならない。
「ルルーシュ。今、少しいいかな」
「……はい、どうぞ」
今度は一体なんなんだ。
一向に進まないメールの返信画面から視線をずらして執務室の扉を見つめる。姿を現したのはコーネリアであった。
「この時間帯は眠気で作業効率が落ちるだろう。今は無理して進めても、あまり意味がないよ」
事務机の散乱ぷりを見かねた彼女は、苦笑いを浮かべながらそんな助言をくれた。
頭では分かっているのだが、こうでもしないと一生かかっても終わる気がしないのだ。そんな本音は喉元に仕舞い込んで、それもそうですねと愛想笑いを浮かべた。
「それで姉上。ご用件とは」
「兄上へ仕事の引き継ぎをしている最中、届け物が見つかったから渡しておこうと思ってな」
「……ああ」
机の端に置かれたのは特派からの活動報告書だ。とくに目立った活躍をしたり戦果を残した時はよく報告が上がってくる。
「お前が見立てた名誉人、上々の成績を残しているようだ」
「……」
「初陣は周囲のエンジニアや研究者らが度肝を抜かれたらしい。なんせエンジンはフルスロットルで全開、スラッシュハーケンを手足のように操って狭い市街地を物ともせず移動と……」
「……」
「卓越した機体操作で戦闘を繰り広げるも、路肩に避難していたイレヴンの救助に当たった……とのことだ」
「はい?」
思わずパソコン画面から顔を上げると、どこか険しい顔つきを浮かべたコーネリアが報告書の紙面を見つめていた。
戦闘中に人助けなど聞いたことがない。
確かに、非戦闘員の市民への被害を必要最小限に収める努力はされるべきだ。広範囲への影響が懸念される化学兵器の使用、被害が甚大となる核爆弾の投入といった必要以上の破壊活動は禁止されている。無武装の市民に対する暴行および殺害も法に抵触する。
しかし敵を前にして人助け、つまりは気を逸らして背を向けるような行為はご法度だ。悠長なことをしてる奴から死んでいく。彼はたまたま今回、運が良かっただけだ。
「ランスロットの機体スペックを最大値まで引き出す活躍は文句なしに褒められるべきだが……ルルーシュ。お前はどう思う?」
「戦闘データについて詳しくお見せ頂けませんか」
「ああ。ここの項目からだ」
差し出された紙面にはびっしりとバイタルデータが記載され、マシンとの相性や身体負荷、稼働率といった、あらゆる要素が数値化されてある。
適正は申し分なしだ。身体への影響も無問題で、心拍数や血液酸素量といった呼吸器系の動きも正常値の範囲内で推移している。つまりは過度な興奮、視野狭窄、焦りや緊張がないという裏付けだ。
「……だからこそ、気になりますね。向こう見ずな行動が散見される」
初陣なら目を瞑れることでも、二度、三度となれば捉え方も変わってくる。
なるべく短時間で、かつ完璧な、求められる以上の戦績を残すことにどこか固執しているようにも見える。あるいは命知らずの馬鹿なのか。何を生き急いでいるのか。
「ロイド伯爵がデータ収集の為、そうした働きを要求している、という可能性は?」
「どうだろうな。ランスロットの射出速度はマッハこそ超えなかったが、それに近い速度が出ているらしい」
「音速……あまりに危険ではありませんか」
「ああ。いくら機体の中に居るとはいえ衝撃波を全て往なせるとは考えにくいし、さすがにあの男でも人体への影響が出るほどのオペレーションはしないだろうよ」
装甲もどこまでの衝撃を想定しているのか。通常の旅客機などは音速の壁を超えると激しい振動により空中分解を起こすとされている。衝撃波、いわゆるソニックブームは素人が想像するよりずっと恐ろしい現象だ。
「これからも経過を観察していくとともに、特派の管理責任者にはこの件に関して厳重に注意するよう、申し出しておきます」
「ああ頼んだよ」
彼女は険しい顔つきをいくらか緩めて、そう答えた。
これでは死にたがりの無鉄砲が過ぎる。そう判断されてもおかしくないであろうことに、スザク本人は自覚しているのか。果敢に敵に挑む姿勢と、恐れ知らずで無責任な行動を履き違えているのか。
戦場においてリスク管理もできない兵士は能力が低いと見られるし、戦うことが趣味ならそこらへんで喧嘩でもすればいい。軍隊は数の確保、戦線の維持が最重要だ。向こう見ずの軽はずみな行動が戦線の崩壊を招くことを、彼が理解できていないはずはない。死亡率の高い最前線で幾度の死線を掻い潜ってきた兵士だ。組織に組する以上、最適解の働き方は心得ているだろう。
だからどうして、スザクがそこまで自らを危険な状況に置きたがるのか、まるでさっぱり想像つかなかった。何か意図してそのように振る舞うのだとすれば? 死に最も近い場所に身を投げ出す理由なんて考えたくもない。
希死念慮に苛まれた兵士を戦場に送り込むなど、本来あってはならないはずなのだ。