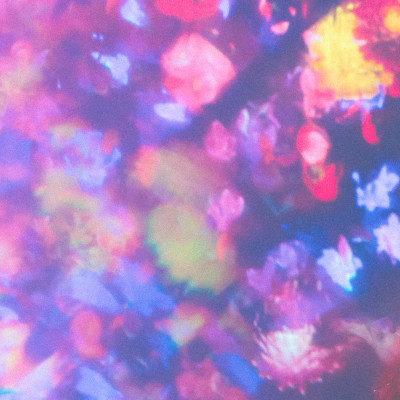
これをよすがとする 四話
名誉ブリタニア人制度を利用した帝国軍への入隊者は総じて手酷い扱いを受ける、という話は軍内に限らず有名だ。致死率はどの部隊よりも抜きん出ているが、理由としては、名誉軍人が一切の銃火器装備を認められていないことと、ろくな訓練もなく戦場に立たされることの二点が挙げられる。ようは最初から使い潰しとして用意される人員であり、これまでどの作戦においても名誉軍人による活躍は見られていない。
徹底した人種差別政策によって生まれた歪みのような彼らの存在を、本国軍も日本人も良く思っていない。帝国に魂を売り渡した売国奴として常に後ろ指をさされ続ける彼らが声を上げる機会はなく、常に差別と抑圧の嵐に晒されている。
戦場において銃火器の携帯が認められない名誉軍人は刃物と通信機を身に着けて、ろくな防護服も支給されず、陽動であったり囮作戦であったり、逃亡した犯人グループを捜索する仕事などが回される。反帝国主義を掲げるイレヴンのグループが起こす暴動の鎮圧に当たることも当然ある。彼らは与えられた指示通り任務に当たる他ない。それがたとえ、同じ日本人を相手に戦えと言われたとしてもだ。
名誉軍人の五年生存率は二割から三割程度と言われている。たいていの兵士は右も左も分からない新米時代に命を落とす。そうでなくとも危険な現場の最前線に繰り出されることが多いので、致死率は非常に高い。
兵士としてのキャリアや経験、戦績を積むことは困難だ。そのため名誉軍人の殆どは一等兵階級で構成されている。そもそもイレヴンである時点で出世の道は閉ざされたも同然であるのだ。
ここまでの強烈な人種差別の原因の根底に、純血主義という帝国主導の考え方が存在する。強い肉体や精神はブリタニア人の血に宿る為、混血人や外国人は劣っているという排他的思想である。帝国の内部では一般人にもこの考え方がポピュラーなものとして広く受け入れられており、軍事関係ではとくにその傾向が顕著だ。戦線に立つ者たちは名誉人という"ならず者"にきつく当たる。
その現状を、現場責任者や軍部の上官たちは見て見ぬ振りどころか推奨している始末なのだ。国を売りプライドを捨てた、どっちかずの人でなし。名誉軍人の存在は日本国にとって国恥であると帝国人は吹聴し、彼らから正しい判断や思考、抗おうとする意思を根こそぎ奪ってゆく。いわば洗脳だ。戦意喪失を促し、思考することを止め肉の器だけになった若き兵士たちを、軍部は片道切符で送り出す。
まずは腐敗しきったエリア11の軍部の在り方を変えねば、日本国に未来はない。しかし議会での発言力や票数、物理的な数の多さで言えば純血派が圧倒的に幅を利かせているせいで、現状まともな議論は成り立たない。彼らに楯突けば自分の立場も危ういだろう。
腹違いの姉・コーネリアは根っからの武人であり、数々の戦地で上げ続けた輝かしい戦績を評価され、今の地位を築いた。本人の卓越したナイトメアフレームの操縦技術も去ることながら、武官として戦線の指揮にも当たる。戦況を瞬時に読み、相手の心理や作戦の隙きを突く。そうしたやり方で帝国軍に数多くの勝利をもたらし、コーネリアはブリタニアの魔女とも綽名されているのだ。
そして彼女もまた純血派の思想を持つ。名誉人を兵士として投入することに制度発足時から否定的であった彼女は、その根底に"どっちかずの人種に高い志は宿らない"とした考えを持っていた。そもそも”帝国軍”とはブリタニアという国家と皇帝に忠誠を誓い、命を賭けてでも戦うことを大義名分に掲げている組織だ。その日暮らしのために国を捨てるような奴に兵士が務まるはずがないと、そんな恨み言が彼女の口癖でもあった。
それは同時に、名誉人制度そのものへの懐疑を意味していた。
エリア11では度重なる暴動に対し、毎回鎮圧部隊が出動する事態が恒常化しており、そのたびに発生する損害や費用なども積もり積もれば莫大だ。少しでも損失を抑えたい軍上層部や本国の内政側の立場からすれば、名誉軍人の登用は経費節約という意味で理にかなっている。
しかしコーネリアは、そうした目先の損得勘定には真っ向から否定的だ。強い意志と国への忠節を誓えぬ者にブリタニア軍人を名乗る資格はないとする強気な姿勢を固持し、軍上層部とはその点において対立関係にある。そして自分も、名誉人の登用については長らく否定的な考えを持っていたから、そこだけは同意見だった。
七年前に出会った少年が今、占領された生まれ故郷で、名誉軍人として従軍している。
思いがけない事実を突き付けられ、自分はすっかり消沈していた。せめてひっそりとどこかの片田舎で暮らしていてくれたら良いものを。そんな淡い期待や祈りは尽く消え去った。
しかし姉からの連絡いわく、彼はいまだ一等兵としてブリタニア軍に在籍しているという。また、枢木神社で出会った少女の話では小学校卒業後、少年は行方をくらましたとされている。となると、彼は五年もの間、あの曰く付きの軍隊で働いているということだ。限りなく低いとされる五年生存率を乗り越え、あの男は今もなお死線に立ち続けている。その事実と途方も無い年数に胸が抉られるような心地になった。
時刻はちょうど昼休みが終わった頃。執務室のデスクでパソコンの画面を見つめながら、脇に立ててある卓上カレンダーを視界に入れた。予定の文字でほとんど余白を埋め尽くされた紙面を遠い目で眺めて、思案に耽る。
会いに行こうと思えば容易に行ける距離だ。ゲットー付近の駐屯地となれば、車を飛ばせば数十分もあれば辿り着く。しかし、自分はまだ行動に移せていなかった。
どんな顔をして、今更何を話せばいいのか。久しぶり、元気にしていたか。……なんて口が裂けても言えない。彼の苦難と苦労を思えば合わせる顔もなくて。
自分と彼とでは立場があまりに違う。恐らく、ろくに取り合えないだろう。名誉軍人の端くれの男と、副総督を務める皇族の自分。身分不相応として面会さえ謝絶されるかもしれない。それは彼の意思でなく軍部の意向として、だ。
だから彼と接触を図るとするなら、理由が必要なのだ。単なる視察ではなく大義名分が。
話のネタになれば何だっていい。取っ掛かりになる丁度いい話題があれば、あとは適当に丸め込ませれば何とでもなる。出任せのひとつやふたつ、喋ることは慣れたものだ。生まれたときから身を置かされた皇位継承権争いは伊達じゃない。
答えの出ない考え事に頭を捻らせていた時、ふとプライベート通信の着信通知が鳴り響いた。相手はユーフェミアからだ。
『もしもしルルーシュ? ちょっと話をしたいのだけど、会うことはできそうかしら?』
明朗快活な声音に肩の力が抜ける。しかし言わんとする内容は釈然としない。
「話ってなんだ、急に」
『ええっと、"新しい軍用機の開発を進めたいから、エリア11副総督の知見をお借りしたい"……とのことですって』
「誰からの相談だ?」
『特別派遣……嚮導技術部……?』
「ああ、特派か。確か兄上お抱えの研究団体」
『資料だけ渡されちゃったから、今から持って行くわね。執務室で良かった?』
「今から? ちょうど居るから構わないけど、ユフィはトウキョウ租界に滞在しているのか」
平時といえば本国の宮廷で暮らしている彼女が、珍しくエリア11に訪れているらしい。
『私は仕事でちょっと用があって。ついでにルルーシュに渡してきてほしいって言われちゃったの』
「ふうん。そんなに大事な物なら自分の足で来るか、データでくれたらいいのに」
『だってルルーシュ……姉さんから聞いたけど、軍部に目を付けられそうになってるんでしょう? 特派と軍部は反りが合わないって有名な話じゃない』
「気にし過ぎだよ。それに、ちょっと嫌われたからって辞任に追い込まれることもないだろう。俺はそこまでヤワじゃない」
受話器を耳にあてながら、呆れるように溜息を吐いた。
特派といえばブリタニア軍の内部に存在する、軍用武器の研究開発を専門にした機関である。軍事関連の事業に多額の予算を割り当てるなど投資に余念のない本国では、とくに第二皇子のシュナイゼルが組織のバックアップに大きく貢献している。
しかし研究機関の産物は未だ現場投入されていないようだから、その存在自体を邪険にしていたり、金の無駄だと切り捨てる見方をする者も少なくない。それは主に実力・成果主義の軍部で多く散見される。だがそれでも、シュナイゼルの保護下にあるという事実が強い盾となり、研究所の存続は未だ守られたままなのだ。
無から有を生み出す開発や技術の進歩というのは、どれだけ先鋭化されようと一朝一夕では実らないのが鉄則だ。盤石な理論に結果は伴わない。それを自分は重々承知しているし、だからこそ特派が進める開発とやらに、純粋な興味が湧いた。断る理由はなかった。
室内に漂う紅茶の香りは幾らか、さざめく精神を落ち着ける作用があるらしい。ここ数日、余裕がなかった自分を漸く俯瞰することが出来た。
執務室に訪れたユーフェミアをソファに座らせ、持参してきたという紙媒体の資料をテーブルに広げた。彼女はそれが何なのか、どういったことが記されているのかまでは理解していないらしい。きょとんとした顔のまま、白いティーカップを持ち上げて口元を綻ばせていた。
くるくると明るく映える表情の変化や、いやに物怖じのない言動や仕草を見ていると、立ち止まって悩み続けることが馬鹿馬鹿しく思えてくる。それは現状を蔑ろにして逃避するのではなく、早く前に進まねば、と心を焚き付けてくれるのだ。
「何か分かりそうなことはありました?」
「……特派はどうしてこれを俺に寄越したのか、話は聞いているか」
「ええと。確かその軍用機は扱いが難しいから、適合者が見つからないと言っていたかしら」
「じゃあ俺はその適合者を見繕えと?」
「姉さんやシュナイゼル兄様にも既に依頼はあったようなんだけど、未だ見つかってないようで。ほら、名誉人兵士さんたちがエリア11には多くいらっしゃるでしょう」
ティーカップにミルクを加えながら、ユーフェミアは明るく答えた。
「ユフィ。これはただの軍用機じゃない、次世代ナイトメアフレームの設計図と説明書だ」
「ナイトメアフレーム? それが?」
驚きを隠さないまま、彼女はテーブルに散らばる紙に視線を巡らせる。自分の手元にあった設計見本図を目前に差し出してやると、ああ、と声を上げた。
「こんな白い機体は見たことないわ。姉さんのナイトメアフレームとは全然違う」
「グロースターか。確かに見た目もだが、説明を読むと能力値……機体のポテンシャルが段違いだ」
「なら姉さんが乗れば、とっても強いんじゃ……」
「いや。戦闘能力が大幅に向上している代わりに、操縦の煩雑さや生体適性の基準はシビアに設定されてる。恐らく姉上もテストは行ったんだろうが、俺にこの資料が回されたということは」
「姉さんも乗りこなせなかった、ということ?」
「あくまで推測でしかないが」
巨額の投資と長い期間を要して生み出された巨躰は肝心の操縦者が不在のまま、狭い研究所で今日も据え置かれているらしい。このまま埃を被り続けるにはあまりに惜しい。が、乗りこなせる者が居ないとただのガラクタだ。
「しかしナイトメアフレームの搭乗が許されるのはブリタニア軍人の騎士侯だけだ。本来、名誉人に搭乗する資格は」
「試しに乗るだけでも駄目なの? あるいはお兄様から軍部へ掛け合ってもらって、特別に許可を……」
「そんなの前例がないし、そもそも名誉軍人の中に適任者が居るかどうかなんて、」
「分からないなら試すしかないじゃない! だってこんな凄いナイトメアフレーム、ずっと仕舞われたままじゃ勿体ないでしょう。前例がないなら作ればいいし、ねえ。検討の余地はあるんじゃない?」
「……」
政治や軍事に疎い彼女はそうまくし立てて止まない。簡単に話が進めばいいが、現実はかくも厳しく、甘くないのだ。
「特派はシュナイゼルお兄様の庇護があるし、軍部もそう強く出られないでしょう。やってみませんか?」
「……そこまで言うなら、やるだけやってみるか」
眉間に寄った皺を伸ばしながらそう呟くと、ユーフェミアは分かりやすく喜んでみせた。そうこなくっちゃ、と息巻く彼女は底抜けに明るく単純だ。見ているこちらが危ういと感じるほどに。
「それにしても。名誉軍人らに片っ端からテストさせるのは途方も無いな。最初になにか、分かりやすいボーダーラインを設けたほうがいい」
「たとえば?」
「運動能力や筆記試験、あるいは年齢だったり健康状態で絞り込んで……」
「従軍期間はどう? たとえば五年以上の期間とか」
「五年か……」
五年生存率の低さで有名な部隊だ。それだけの年月活動を続けているならそれは運の良さ以外に、本人の身体能力の高さも大きく関わってくるだろう。煩雑な操作や咄嗟の判断が要求されるパイロットに必要な資質を問うには、確かに手っ取り早い基準なのかもしれない。
「ならそれで話を通してみよう。駄目元だが」
「いいじゃない。採用されなくても、お兄様なら代わりになる案を検討してくれるかもしれないし」
「お前は楽観的というか、呆れるくらいのポジティブ気質だな」
「あら。ルルーシュだって大概、反骨精神旺盛なくせに」
「ユフィの強かさには及ばないよ」
苦笑いしながら素直に述べると、彼女は可笑しそうに笑っていた。
後日、ユーフェミアとともに本国へ渡り、内政を務めているシュナイゼルへ話を持ち掛けた。ユーフェミアはきっと大丈夫、と前向きな姿勢を崩さなかったが、自分は内心、この案は通るはずがないと高を括っていた。最新鋭のナイトメアフレームにテストとはいえ名誉人が触れるとなれば、軍部から反対意見が噴出するに違いないからだ。ただでさえ風当たりの強い名誉人らに果たしてそれが許可されるかどうかは、確率的に低いと思えた。
しかし自分のこうした予想はあっさりと覆された。シュナイゼルは神妙な面持ちでユーフェミアの話を聞き入れると、二つ返事で許諾したのだ。本当に良いのかと再三尋ねたが、あくまで戦闘データ収集用のデバイサーだから、と微笑まれた。ともすれば実戦登用は別なのかという話になるが、それについてははぐらかされてしまった。
本国での滞在も程々に、慌ただしくエリア11へ戻ると、今度は総督であるコーネリアに厳しい詰問を受けた。先にシュナイゼルには話を通してあるからと丸め込ませたが、その代わり今件に関しての現場判断はお前に一任すると言われた。それは許されたというより見放されたに近い。それも覚悟の上であったから、当然受け入れたが。
本国に所在していた特派の研究所兼移動式トレーラーがエリア11に到着し、いよいよデヴァイサーの選考が行われるその日。
まずは関東地区に存在する駐屯地から従軍期間の長い兵士を、租界近くのゲットーに招集した。そこで順次テストを行い、特派の責任者が適任を選ぶ。該当者がなければ別の地区から招集するまでである。
移動用の公用車から降り立つと、出迎えてくれたのは特派の研究員で責任者であるロイドと助手のセシルだ。顔を合わすのはこれが初めてで、軽い挨拶と握手を交わす。
「初めましてロイド伯爵。遠路はるばるご足労頂き有難う御座います。本日は宜しくお願いします」
「これは副総督。こちらこそどうぞ宜しくお願いします。……と言いたいところなんですが~」
「……」
「もう先にテストをやっちゃいまして、まあ、一人しか居ませんでしたから。それでもって、彼に決めまして」
「待ってくださいロイド先生! デヴァイサー決定の件は私も聞かされていないのですが」
「ああうん、今喋りながら決めたから」
「ちょ、ちょっと!」
ロイドの隣に立つセシルは慌てた様子で百面相を浮かべていた。無論、今到着したばかりの自分も聞かされていない。
「……セシルさん、ひとつお伺いして宜しいですか」
「は、はい」
決定権はあちらにある分、口出しをする気はない。しかし、どうしても確かめたいことがある。
呼び止められた彼女は背筋を伸ばしてこちらを見据えた。
「一人しか居なかったとは? 今回設けた招集基準は五年以上の従軍経験を要する者です。大半は任務で来られなかったのでしょうか」
「いえ。恐らく該当者が一人しか居なかったということかと……」
「そう、でしたか」
「そうそう。栄えある選ばれしデヴァイサー殿にランスロットのマスターキーを渡そうと思うんだけど、セシルくん。いま持ってるかな」
「はい、ありますよ。ロイドさんから是非、彼にお渡ししてあげてください」
「いいや、ここは駆け付けてくれた副総督に」
セシルはナイトメアフレームの起動に必要となる小さな鍵を手渡してくれた。
「彼を紹介して下さったのは副総督ですものね」
「新しいパーツ……じゃなくて、デヴァイサーはトレーラーの奥にある控室に居るはずだから」
あっちです、とロイドが指差す方向に視線を向ける。積み上がった精密機器やそれらに繋がるコードが無数に壁や床に伸び、奥を覗くと雑然とした景色はさらに混沌としていた。
「本人はこの決定を」
「まだ知りませんよ」
「そうですか」
手の中でマスターキーがかちゃり、と音を立てる。
動き出す運命の歯車の存在を予兆させるかのような物音は、やけに耳に残り続けていた。
移動式トレーラーの奥へ進むと、ロイドの言っていた控室らしき入口がやがて見える。扉の前に立っておもむろ声をかけると軽い返事が響いて、耳に届く。それは自動ドアになっており、天井付近に設置されたセンサーが生体を感知すれば開く仕組みだ。
あと一歩体を前に動かせば開くはずだった。でも鳴り止まない心臓の鼓動がやたらと忙しなく、握り締めた拳は嫌な汗で湿っていた。
「……あの」
一歩前に踏み出そうとした瞬間、同時に電動ドアが開かれた。中から現れたのは茶髪に緑の瞳を持つ、一人の青年であった。
「……も、申し訳ありませんルルーシュ副総督」
二人はほんの僅かな間、顔を見合わせた。それこそ瞬きと同じくらいの時間。驚きに見開かれた瞳孔には同じく、驚いた表情の自分が映っていた。
「初めてお目にかかります。枢木スザクと申します」
しかしそれもほんの一瞬の出来事だ。彼は反射的に床へと膝をつき跪いたかと思うと、皇族に対する口上を述べた。身に纏う軍服は名誉軍人のもので、一等兵だ。
「……副総督」
「……面を上げて、立て」
「はい」
彼は音も無く立ち上がる。どこか強張った表情は緊張のせいだろうか。とにかく、感情の読めない顔つきであった。
「ロイド伯爵から言付けと、預かり物がある。手を出せ」
「……」
眉を俄に動かしながら、彼は大人しく両の手のひらを差し向けた。命令に忠実で従順な、一介の兵士然とした態度だ。
「枢木一等兵」
「はい」
「……これを」
「……」
小さな鍵を手のひらに落としてやった。彼はまだその真意を解っていない。
「お前がデヴァイサーに選ばれた。これは第七世代ナイトメアフレーム……ランスロットのマスターキーだ」
「な……」
「くれぐれも紛失しないように。あと、決定権は俺でなくロイド伯爵に委ねられている。反論があるなら奴に言え」
「……」
手渡された鍵を、信じられないという面持ちで見つめている。開きかけた口から質問攻めに遭うのは予想がついたので先に釘を刺すと、彼は大人しく唇を引き結んだ。納得がいかないという心持ちは、声にせずとも表情だけで伝わるが。
「それと、もうひとつ」
「はい」
「ニ歩下がれ」
「……はい」
従順な兵士は指示通り、部屋の奥側へ下がってみせた。それがどういう意味だとか、意見する素振りは一切ない。
二人の間に空間が生まれた。ちょうど人ひとりが入れるくらいの、一メートル程度の距離だ。開かれたままの扉がちょうど境目になるように相対する。
彼は真意の分からない自分の命令に、戸惑いを見せていた。
「……初めましてだと? 白々しいな」
二歩進んで室内に足を踏み入れた瞬間、後ろ手で扉の開閉ボタンを押した。同時に扉は閉じられ、そこを背もたれにして立つと、もう彼はこの空間から逃げられない。
「やあ、久しいじゃないかスザク。まさか忘れたか?」
「……」
「ロイドに聴いた話だが、この部屋にカメラや盗聴の類は設置されてないよ」
「……」
「なんだ。それともブリタニア語が聞き取れないか」
「……いいえ。ひととおり習得しています」
「そうか」
彼は言葉選びにひどく迷いながら、声を発していた。流暢な発語は七年前当時の拙さから想像もできない。それだけ上達できるくらい、彼がこの世界に身を置いてきたということだ。褒めるべきであろうが、素直にそれを口にするのは憚られた。
「堅苦しい言葉遣いも不要だ」
「……それは、できません」
「何故?」
「私のような一介の兵士が、このような……お言葉ですが、副総督は何か勘違いされていらっしゃる」
下唇を噛む男は、苦しそうにそう主張した。
「立場も状況も、七年前とは異なります。たとえ副総督に許されようと、私は私を許せません。身分を弁えることは兵士の務めです」
「えらく詰まらないことに拘るんだな」
「私は軍規に従うまでです」
「自分の心を殺してでも遵守することか」
「それが命とあるなら」
その発言は国への忠義忠節というより、愚直で真面目一辺倒な内面が所以だろう。記憶にある彼といえばもっと突飛で落ち着きのない、気分屋な性格を模していたはずだ。
抑圧された環境の中で自分の身を守るのにそれが適していたのだろうか。彼の本性は定かでないが、かつての乱暴さ、活発さはとっくに消え失せていた。それを惜しいと思ったのは不覚であったし、とても言葉にはできない。
どこか鬱蒼とした瞳の色や生傷が散見される顔の皮膚は、紛れもなく敷かれた環境が彼を変えたせいなのだ。そして現状に至るまで、図らずしも加担しているのは自分である。
殴られても文句は言えないであろうこの瞬間でも、彼は背筋を伸ばして静かにこちらを見据えたままだった。言葉より先に手が出るあの時の少年とはまるで別人で、見る影もない。成熟した人としての成長を喜ぶべきなのに、どうにも素直にそうは思えなかった。
「……お前は次週以降、帝国軍部から特別派遣嚮導技術部への配属となる。恐らくロイドとセシルの二人が上司になるだろう。それまでに操縦の講習を受けておいたほうがいいかもしれない」
「承知しました。それと、副総督。先ほどのテストで大体の操作方法は覚えましたから、次回からは実戦への配備を願います」
「へえ」
淡々とそう述べる男は、なんてこと無いように言ってのけた。
「直属の上司はロイドになるから、奴に言えばいい。即戦力として扱ってくれるだろう」
「承知しました」
真っ直ぐに自分を射抜く目に感情はなかった。意思の介在はまるで感じられない。自身を"物"だとでも思い込んでいるのか。
だとしたらそれはとても、悲しいことだ。
ロイドに挨拶がしたいと彼が言うので、部屋の扉を開けてやった。これ以上の話し合いは意味がないと思えた。彼は意固地だ。精悍な横顔はこちらに一瞥もくれない。
ぴん、と伸びた背筋を遠目に見遣る。その後ろ姿は広く逞しかった。七年という年月を経た友人は見違えるように立派で、残酷なほど人間味のない男に成長していたのである。
前ページ / 次ページ
Photo by 0501 : Design by x103