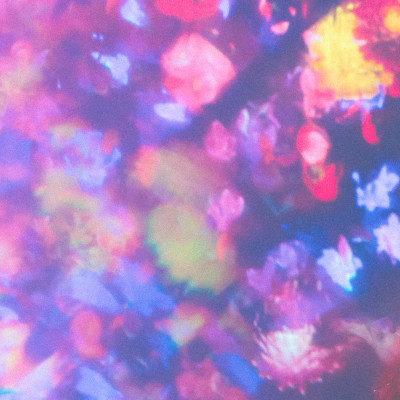
これをよすがとする 三話
初めて顔を合わせたのは十歳になるかならないかくらいの年の頃だった。
つい先日友好条約を結んだ国からの来賓として、交流会と称して招待された貴国の官僚や政治家の面々の中に"そいつ"は混じって出席していた。話によると何でも、そいつは貴国――日本国の現首相の息子にあたるようだ。つまり国の未来を担うことになる、かもしれない人物らしい。
それは条約締結後の食事会のことである。
親睦を深めるという名目で場は設けられた。ブリタニア本国の宮廷内にある大広間は来賓者たちを気持ち良く迎えるため、豪勢な料理と豪華絢爛な飾り付けでもって、遠路遥々やって来た彼らをもてなした。たとえば長テーブルの中央に置かれた一輪の生花ですら、この日のために生けられたものだ。それだけじゃない。食器の取皿だって宮廷の特注品だし、広間で音楽を奏でるブリタニア人の演奏家たちは世界で活躍する一流のプロばかりで。来賓者らの口に運ばれる料理はいわずもがな、である。
「……」
しかしそいつはテーブルに配膳された食事に興味を示すことも、目を瞠ることもせず、銀色の食器をぼんやりと見つめていたのである。
彼は婉曲に歪んだスプーンをおもむろに持ち上げる。かと思えば無表情のまま丸い部分を暫くぼうっと見つめて、冷えかけていたスープに食器を浸した。一口ぶんだけ掬って、口に運ぶ。再びスプーンを持ち上げたかと思えば、食器はテーブルに置かれる。それでおしまい。
周囲の大人たちはとっくにスープの皿を空にしていて、それどころかすでに次のコース料理が運ばれ始めていた。給仕たちは忙しなく働いていて、そのうちの一人がろくに口をつけられていないスープを見て少年に声をかけていた。
会場の声はがやがやと反響し合っていたし、自分は”そいつ”とは少し離れた席に居たから会話の内容は知らない。何も聞こえない。けれど唇の動きから察するに、もうお召し上がりになりませんか、とか、次のお料理を御用意して宜しいですか、とか、そういう質問だったのだろう。しかし”そいつ”は給仕に見向きもせず首を横に振るだけに留まっていた。
そいつの周囲に同年代の子供は座っていない。だから話し相手もろくに居ないだろう。さらに不幸なことに、周囲の大人たちですら幼い彼に話しかける素振りがなかった。
少年の真横、上座側に座る中年の男は”そいつ”と対照的に、はきはきとした物言いで饒舌にしゃべくりを披露していた。件の、貴国の首相なのだろう。その向かいに座るのはブリタニアの官僚らだ。彼らは首相の話を神妙な面持ちで伺っている。
「……」
少し遅れて彼の前に運ばれたのは前菜だ。ブリタニア国産の野菜や生ハム、生魚と、オイルやビネガーを用いたカルパッチョサラダである。
彼は皿に一番近い位置にあるフォークを手に取ったあと、暫くサラダを見つめていた。葉物が苦手なのか、あるいは彼の国で生野菜を食す文化は根付いていないのか。そんなことを一瞬考えたがその思惑はすぐに外れた。そいつの隣の男は躊躇いなくサラダを食べていたのだ。
皿に盛られた葉や調味料を見つめること数分。ようやくそいつは右手を動かし、一切れの葉を口に入れた。……かと思えば、すぐにフォークをテーブルに置いてしまう。小さなグラスに入った水を飲んでから、彼の行動はそこで終了した。
次に出てきたのは魚料理である。オマール海老をボイルして特製の調味料で味付けされたそれは、前菜や副菜よりも大味で子供でも食べやすい。食事会でよく口にするこの料理は自分もとくに気に入っていた。
殆ど手がつけられなかったカルパッチョはあっさりと下げられてしまう。その代わりに、茹でられたエビが盛られた深皿がそいつの前に置かれる。
「……」
しかし少年は今回も、目の前に何を置かれようが動じなかった。ほのかに鼻をくすぐる魚介風味のスープの匂いも出汁の染みたエビの身にも、一切合切興味を示さないのだ。
少し大きめのフォークをようやく握ったかと思えば、やはり皿をじっと見つめたまま手を止めていた。そして僅かに動いたフォークの先がエビの身を突いて、矛先に刺さる。口に入った身はなんと一欠片だけだった。やがて、握られていたフォークはさっさとテーブルの隅に置かれた。
少年は俯いた姿勢はそのままに、おもむろに立ち上がって席から外れた。周囲の大人たちは気にするどころか目もくれない。自分にしか見えない幽霊かと思うほど、誰も彼もその存在の有無を気にしていなかった。談笑の声はうまく耳に入らなかった。ぽっかりと生まれた空席には冷めた料理だけが手付かずのまま置き去りにされていた。
「……お兄様?」
「ああ、いや」
真横からの唐突な声に肩が揺れた。顔を元の位置に戻すと、訝しげな表情が視界いっぱいに広がっていた。
「どうかされましたか。あまり食欲が優れませんか」
好物であるはずの料理になかなか手がつけられていない。食べるのが早い人は既に次の料理が用意され始めていた。自分の手元と隣の彼女の皿を見比べてもそれは一目瞭然だった。
「……そうかもしれない。少し席を外すよ」
「誰かお呼びしましょうか。お薬の御用意も」
「いいや大丈夫。でも、戻るのは遅くなるかもしれない」
「分かりました。シュナイゼル兄様には私からお伝えしておきますね」
アッシュブラウンの髪の毛が不安げに揺れている。薄紫色の瞳にごめんよと目配せして、ゆっくり卓から抜け出した。
賑やかな広間に背中を向けて、室内からそっと脱出しようと思った。重たい扉もゆっくり動かせば音はしない。蝶番が軋まないよう注意を払い、小さい子供がすり抜けられる分だけ開けて、静かな廊下に躍り出た。
足音さえも吸収する重厚な絨毯はどこまでも続く。ただでさえ広い道幅だから左右を十二分に見渡した。するとそこまで遠くない目先の場所に、見慣れぬ人影があった。小さな背中。茶色の癖毛頭。小奇麗な礼服を身に纏う子供。先程の少年に違いないだろう。
「なあ、そこの……」
小走りで歩み寄って、声をかけながらその肩に触れた。
使い慣れない彼の母国語、日本国の発音は果たして合っているだろうか。伝わるだろうか。自信は今ひとつだ。それと、肝心のそいつの名前は出てこなかったから、なんと呼べばいいかは分からなかった。
「どこかに用か?」
「……」
さして驚くふうでもなく、少年はゆっくり振り向いたあと黙ってこちらを見上げていた。意思や感情のない静かな瞳が僅かに揺れていた。大きな瞼が数度瞬く。
「お手洗いなら反対側、だけど」
「……いや、別に」
「あまり彷徨くと迷うよ。ここは広いから」
「……」
用を足しに離席したわけでないらしい。言葉は何とか伝わっている。口数は異様に少ないが、顔色が悪いようにも見えない。
ならどうしたんだろう。料理を前にしていたときからそいつは様子がおかしい。
「ていうか、誰?」
「え?」
「お前誰?」
少年はあからさまに目を逸らし、低い声を使ってそんな暴言を吐いてきた。
初対面相手に、子供だからって。お前呼ばわりはふつうないだろう。肩に触れていた手指に力がかかりそうになったが、必死に堪えた。
「……僕はルルーシュだ。ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア。写真撮影のときに僕の兄から挨拶させてもらった……」
「覚えてないし」
「……覚えてもらわなくていいけど、とにかく、用がないなら戻ったほうが」
「なんで?」
「なんで、って」
この建物は矢鱈と広い。子供の足ではさして遠くに行けずとも、道に迷うのは容易だ。手洗い以外で不用意に出歩かないほうが良い。でないと後々、大の大人たちに居場所を探させる羽目になるのだから。
「長時間居なくなったら、みんな、心配するよ」
「しない」
「するよ」
「……さっきから何なんだよ」
「え?」
「何なんだって、言ったんだ」
大きな目が釣り上がって、こちらを睨みつける。ついでに肩に乗ったままの手も払い除けられて、ぱしんと乾いた音が鳴った。ひりつく手の甲を思わず押さえると、そいつはますます不機嫌な表情を顕わにする。剥き出しの敵意が全身に突き刺さった。
「ブリタニア人なんかと、なんで仲良くしなきゃいけないんだ」
「……」
「どうせお前も内心、馬鹿にしてるんだろ。日本人のこと」
「そんな」
「言いたいことがあるなら言ってみろよ!」
急に胸倉を掴まれて顔が近づいた。間近に見えた緑の両目は静かな怒りに満ち、憎々しい表情でこちらを見据えていた。
自分は、自分たちの人種は、心底、少年に嫌われていたらしい。
「こんなに弱っちいくせに」
襟首を締め上げるようにして固く握られた指に、きりきりと力が込もる。首が締まって、息がしづらい。苦しい。皮膚に食い込む布地が痛い。寄せられた眉間の皺が深く、濃くなる。
「なんも言えないのかよ。つまんない奴」
襟から手が離れた。一瞬だけ呼吸が楽になる。
しかし安堵も束の間、今度は左肩に衝撃を受けた。突然のことで体は受け身を取る間もなく、背中から床に落ちた。背骨に激痛が伴い、肘が擦り剥く。痛みに顔と声が歪む。
「……ぐっ!」
目を開けると体の脇で拳を握り締めた少年が、こちらを忌々しげに見下していた。自分は為す術もなく見事に転ばされたのである。逆光が差す彼の顔は陰鬱な印象を受けた。
肘を使って起き上がろうとすると体の節々が痛かった。頭をぶつけなくて良かったと心底思う。これがただのコンクリート製の床だったらもっと惨事になっていた。
「あ、危ないだろ!」
「お前の国だって同じだ。弱い者いじめするくせに」
「僕のことを弱いって言う君だって、それを言うなら……やってることは同じじゃないか……」
体を動かそうとするたび、腕の下あたりにぴりりと痛みが走る。嫌な予感がして薄手の長袖を捲ると、外気に触れた皮膚は擦り剥けて血が滲んでいた。その血は服にも付着し、赤い斑点を残している。
無言を貫く少年をちらりと盗み見る。するとどうだろう。そいつは無様にも、俄に瞳を揺らして突っ立っていたのだ。彼の視線は血が浮かんだこの腕に向かっている。
「……怪我、したのか」
「見たら分かるだろ。だったら何だよ、一体……」
「……見せてみろ」
少年は眉を寄せながらこちらへ歩み寄り、立膝の姿勢になるようにしゃがみ込んだ。そうしてぷつぷつと血の浮かぶ腕を取り、怪我の部分をじっと見つめる。
傷の場所を引っ掻かれるか、指で抉られるか、腕をもがれるか。今度は一体何をされるのかと本当は内心、戦々恐々だった。しかし意外なことに、そいつは静かな顔つきで患部を見下ろすだけだった。だけだと思われたのだが。
「……ひっ!」
「動くな」
「く、喰われる……!」
あろうことか、そいつは傷ついた腕を持ち上げて裂傷部分を口に運んだのだ。
噛み千切られる。そう直感し、声を荒げて暴れそうになった。
「喰わない」
「い、っいた……」
「……」
「……っう」
唇が僅かに動いて、皮膚を滑る。そして直後に走る鋭い痛み。傷が滲みるような感触。恐らく傷口を吸われている。
少年はそこから唇を離し、床に唾を吐いた。無作法も甚だしい行為だが、すっかり気が動転しているせいでかける言葉も見当たらない。
「あとでちゃんと消毒、してもらったほうがいい」
「あ……」
彼はズボンのポケットから取り出したハンカチを長方形に折り畳んで、腕に巻いてみせた。塗した唾液は消毒液代わりのつもりらしい。
「血がついちゃうからいいよ」
「じゃあそれ、やるから」
白のハンカチで結び目を作ってから、彼は言った。
「……怪我、させるつもりはなかったんだ。だから、ごめん」
「……」
「まだ、痛むか」
「ううん……」
屈んだ彼はこちらの顔色を窺うように首を僅かに傾けた。その年相応な仕草を見て途端に、体の力が抜けてしまった。
自分は咄嗟に嘘を吐いた。強かに地面へ打ち付けた背中や臀部は鈍痛が抜けないし、腕の傷口も滲みるような痛みが続いている。
それでも、やけにしおらしい様子の少年にこれ以上の抗議をする気が失せてしまったのだ。怒ったり悲しんだりする気は既にさらさらない。溜飲が下がったとも言う。
「本当に悪いと思うなら、食事に戻ろうよ」
「……それは嫌だ」
「なんで?」
「……」
少年は目を伏せて無言を貫いた。膝の上で握られた拳は開いたり閉じたりを繰り返していて、彼が何かを言い淀んでいることは明白だ。でも言葉にしてくれない。打ち明ける相手が自分じゃ力不足らしい。
「なあ」
「うん?」
「ここって何があるんだ」
「何って……」
彼はおもむろに立ち上がって周囲を見回した。
寸分の狂いなく張り巡らされたペールカラーの壁紙と、赤みがかった毛足の短い絨毯が地続きに広がっている。それだけだ。窓の外は暗くなっていて、庭に続く扉もとっくに施錠されている。
「ここは遊ばせてもらえないのか」
「遊ぶ?」
「外に出て虫を採ったり、川で魚を捕まえたり、山の中を探検したり」
「しないよ、そんなの」
「ふうん」
立ち上がって、少年は窓越しに外を見た。ガラスには心底退屈そうな顔が映り込んでいて、恐らくは外に出たいんだろう。そんな心情が十分伝わる。
「キゾクってふだん、何するんだ?」
「僕は勉強したり、習い事をしたり……」
「ふーん。つまんなそー」
「ナナ……妹とピアノを弾いたり、楽しいよ」
「ぴあの?」
「ああ。もしかして知らない?」
「いや、知ってる。けど、本物は見たことない……」
窓ガラスに背中を預けた彼は一瞬だけこちらを盗み見る。その目つきからは何となく、子供っぽい好奇心がちらちらと見え隠れしていた。唇を少し尖らせながら足のつま先で床の柄をなぞっている。
「気になる?」
「……別に」
「嘘だね」
ふふん、と鼻を鳴らしながら立ち上がった。少年はこちらをじっと見つめてくる。
「グランドピアノって知ってる? 両腕を広げてもぜーんぜん足りないくらい、おっきい鍵盤があってさ。押すとすっごく大きい音が鳴るんだよ」
「へー……」
「左側は低くて怖い音が鳴るんだけど、右側は高くて可愛い音になるんだ。見た目は黒くておっきくて、天板の中には弦とハンマーがいっぱい並んでる」
「ふうん」
「見たいと思わない?」
「……ちょっとだけ」
彼は気まずそうに視線を彷徨わせる。きっと素直になりきれなくて、照れてるだけだろう。
「実はあるんだ。僕の部屋に」
「部屋に?」
「ああ。ここの近くだよ」
「……」
分かりやすく目を輝かせ始める彼に思わず笑ってしまった。
まだ微かに痛む足を動かしながら歩くと、彼も従うようにして後ろをついて来た。その方向は元居た大広間の部屋とは真逆だった。
しかし致し方ないだろう。なんたってこの少年はどうしてもあの場に戻りたくない、と言い張るのだ。それに彼はもしかすると根っからの悪者ではないかもしれない。それを確かめる必要もある。そうやって、食事会に戻らない理由と言い訳を頭の中でいくつも並べ立てた。
背後から聞こえる宮廷音楽と談話の声を頭の片隅に追いやりながら、二人は足音を潜めて廊下の先へ歩を進めていった。ほんの少しの罪悪感より、圧倒的な好奇心と興味のほうが子供にとっての原動力なのだ。
ぽろぽろと響く音色は自らの意思を持って切なくも明るくも変化する。音の粒は色や形を変えて相手の耳に、心に届けられる。だからどんなふうに弾きたいか、伝えたいかを常に念頭に置いて演奏すれば、奏者の想いは聞き手の心にきちんと伝わる。
ピアノの稽古をつけてくれる先生の言葉を脳内で反芻しながら、弾き慣れた曲を演奏した。
彼がそれを見たいと言ったから。興味があると目を輝かせたから。見せてやってもいいと自分が言うと、彼が黙ってついて来たから。
なのに、奴ときたらどうだ。つい先程までは興味津々に手元を覗き込んで音楽に耳を傾けていたはずが、とっくに傾聴には飽きたらしい。今は磨き上げられた真っ黒の側面に体を寄せて、持ち上げた屋根の中身に好奇心の矛先が向けられているのだ。
鍵盤を押すと同時にハンマーが跳ね上がり、その振動が弦に伝わって音と成る。その一連の規則的な動きに、彼はすっかり目を奪われているようだ。
原理を説明するのは簡単である。しかしそれが実際に目の前で成り立っているのを見るとちょっとした感動すら覚える。一見単純で単調に思える動作がここまでの大きな響きを生むのだ。そのことを、こいつも感じ取っているのだろうか。
暫く練習がてら弾き続けていると、ある時、後頭部に何か尖った物がぶつかる感触がした。地味な痛みを伴うそれを看過できるはずもなく、思わず手を止めて振り向いてしまった。
「あはは、やっとこっち向いた」
「なんだよさっきから……」
ぶつかった箇所を手で擦りながら周囲を見渡すと、床に落っこちていたある物に気づく。ピアノの椅子から下りて拾い上げたが、それの正体がさっぱり分からなかった。
「何、これ」
「知らないのか?」
「うん。知らない」
紙を折って作られた三角形の、何か。両手で持ちながらそれをじい、と見つめる。そんな自分を、彼は可笑しそうに見つめてくる。
「紙飛行機だ」
「紙ヒコーキ?」
「ペーパーエアプレーン!」
彼はそう得意げに話す。ブリタニア語を真似た発音はとても拙かった。
そしてそれだけ言うと次は、テーブルに置かれてあるいくつかの長方形の紙を折ったり曲げたり畳んだりし始めた。テーブの上で紙を何度か回転させ、ひっくり返し、折り曲げて。少しの間、遠目でその工程を見つめていた。
「できた。見てろよ、ルルーシュ」
「……え、あっ」
ファーストネームを不意に呼ばれたせいで、一瞬だけ反応が遅れた。
彼は靴を脱いだ足でテーブルに上り、手にしていた”紙飛行機”とやらを空中に放ってしまったのだ。それは部屋の中を気儘に滑空し、旋回しながら、ゆっくり地面に降りる。するりと足元に落ちてきた紙飛行機を拾い上げると、隣からはどうだ見たかと、大きな声が響いた。
「貴族は折り紙を知らないんだな」
「折り……?」
「折り紙。虫も花も作れるんだ」
いそいそとテーブルから下りたそいつは、そこらにある紙を拾い上げて再び折り目をつけ始めた。ついつい自分も興味に惹かれてその手元を覗こうと近寄ってみる。
が、そこでとある事実に気づいた。妙に光沢のある艶やかなその紙面にはひどく見覚えがあるのだ。
「その紙は折っちゃ駄目だ!」
「なんで?」
「ナナリーの、ピアノの発表会のチラシなんだ」
「ふーん。せっかく鶴にしてやろうと思ったのに」
「ツル? ツルなら白い紙のほうが良いんじゃないか」
「白はつまんないだろ。黒か赤が一番かっこいい」
折り畳まれたチラシの皺を伸ばしながら、彼の言い分を頭の片隅で唱えた。
黒い紙。赤い紙。工作の宿題で使ったものがまだ残っていただろうか。引き出しから鋏や糊、定規などの文房具類を引っ張り出し、棚の奥で下敷きになっていた画用紙をいくつか取り出した。その中には使いかけの色画用紙が幾つも入ってあって、黒色の紙は残っていたが生憎、赤色はなかった。しかしどうせ鶴を作るなら白色がいいと思って、自分は真っ白の画用紙を取り出した。
「これを正方形に切ってさ」
「うん」
「こっちはルルーシュのぶん」
「あ、有難う」
鋏で正方形に切り出した用紙の白いほうを手渡してくれた。少年は俺のを見て真似をして、と言いながらさっそく真っ黒の紙を折り始めていた。
しかしそれよりもひとつ、自分には気になることがあった。
覚えてない、と吐き捨てたその口でファーストネームを呼んでくれたこともそうだが、だからこそ知っておかねばならないことがある。
「……なあ」
「うん」
「名前、聞きそびれてた。なんて呼べばいい?」
「マイ、ネーム、イズ……」
「ははは、下手くそ。日本語で良いよ」
「枢木スザクだ。スザクでいい。あと下手くそって言うな!」
片言な外国語に思わず吹き出してしまう。それでも彼はさして動じず、むしろ釣られるようにして一緒に笑っていた。
「ルルーシュは日本語上手いよな。勉強したのか?」
「ああ、そうだよ」
「なんでわざわざ日本語を?」
「周りに話せる人が少なかったから。欧州や中華連邦の言語とはまるきり文法が違うし、難しいけど、勉強してみると面白いよ」
「へえ……」
彼は少し意外そうな目で見つめてきた。しきりに瞬いて揺れる睫毛が疑問を呈する。そんな素直すぎる様子に笑みが溢れた。
「スザクは勉強してないのか?」
「俺は別に、将来も日本で過ごすし」
「でも今はブリタニアに来てるじゃないか」
「これは父さんの仕事でついて来さされたんだ。本当は来たくなかったのに」
「どうして? 外で遊べないから?」
「それもそう、だけど……」
何となしに問うと声のトーンが少し落ちた。顔は向いてくれない。代わりにテーブルの上で折り畳まれた途中の紙に緑の視線が注がれている。
「俺は嫌いなんだ。父さんの仕事も、周りの大人も、ブリタニアも……」
「……」
平たく短い爪が紙の角をしきりに引っ掻き、居心地悪そうな足元がそわそわと動いた。
「なんでって聞いたら、怒る?」
「……ルルーシュは怒らないのか」
「どういう意味だ?」
「だって俺はブリタニア人が嫌いなのに」
「それは理由にもよるけど。……というか僕もブリタニア人だけど、それは良いの?」
「うん。ルルーシュはブリタニア人だけど、たぶん良い奴だから」
「あはは。そっか。それなら僕も怒らないよ」
「そうなんだな」
素っ気ない返事のあと彼の手の中で数度折り返された紙は、羽を広げた鶴の形に様変わりしていた。会話の内容に集中していたせいで、自分の手元の紙片は未だ四角く畳まれたままである。
「なんでスザクはそこまで、ブリタニアのことを嫌うんだ?」
「それは……」
小さな唇が惑うように震えた。誰にも言わないよ、約束するから。そう小声で付け足すと漸く彼は決心がついたのか、ゆっくりした口調で幼い心情を吐露してくれた。
ブリタニアは古くから敷いてきた富国強兵と徹底した身分制度によって今の国力を得てきた。現代においては領土だけで世界地図の三分の一を占めるほどにまで成長を遂げたのである。ひとえにそれは時流を読んだ政治的采配や、敵国の内乱などの外的要因もあろうが、何よりもまず言えることはその長い歴史で一貫された政治的・軍事的方針が功を奏したからだ。
そして未だにその精神は根強く残り、現皇帝のシャルルは領土拡大に向けた舵取りを行っている。とくに好戦的な現皇帝は世界各地へ帝国軍を送り込み、植民地の獲得に躍起になっている。そうなると言わずもがな、軍事関係への設備・人的投資は膨大だ。しかしその分メリットも多いようで、とくべつ軍部の権力は国内でも絶大的である。
そんな中で今の軍部が最も欲しているのは地下資源のサクラダイトと呼ばれる動力源だ。産業革命の火種となった石炭に代わり、近代に突入した折に燃料資源は石油へと刷新された。しかしこと現代においては、前述した天然資源が新エネルギーとして注目されているのだ。
軍事産業の最先端で活躍する人型可変兵器・ナイトメアフレームを動かす為に使用されるこの物質は、今の軍事産業を語る上で欠かせない要素だ。サクラダイトがなければナイトメアフレームは動かせない。もはや現代の戦争を征するに必要不可欠なのは核弾頭でも無人ステルス戦闘機でもない。サクラダイトの占有量が国家軍事力のバロメーターそのものと称しても過言ではないのだ。
サクラダイトの採掘場所というのはそもそも地球上の各地に散見されるが、極東の島国である日本国に埋蔵量が集中している、という説が有力視されている。当然ながら世界各国はこぞって日本と和平条約や地下資源の共有を認めた条文の締結、宣言書を発行するなどの行動に移った。言ってしまえば日本のご機嫌を取りつつ甘い蜜を啜ろう、お裾分けを貰おう、という魂胆だ。
しかし帝国はその流れを断ち切るように、大胆な行動に出た。
「……先日の、ブリタニアの宣戦布告か」
「そうだ。帝国は元々ナイトメアフレームを多く持っていたし、兵力は世界でもトップクラスに強くて、相手が日本じゃ言わずもがな……」
日本は元々サクラダイトの産出量が各国に比べて多かったが、実際の自国調達量や軍事転用に関しては厳しい規制がかけられていた。というのも毎年サクラダイトに関する世界条約の会談が行われる際、そこでの発言力はブリタニア帝国が最も強い。日本国が抜きん出た軍設備を持つことに関して、兎にも角にも帝国は強い警戒心を持っていたのだ。そこで帝国は世界各国を味方につけ票集めをすることにより、正攻法の妨害策に打って出た。そして日本が軍事力を台頭させぬよう根回しをし、これを阻んだのだ。
「日本の開戦論者に対して多くの人は絶望的敗北を喫すると言っていた。だから和平の道を、話し合いによる平和的解決を模索したんだ。結果的に帝国は宣戦布告を撤回した」
「それは国民にとって、良いことじゃないか」
「俺もそう思ってた。でもこの友好条約は、帝国の一方的な優位立場を許すものだって……」
「……」
「俺の父さんは国民に向けて、戦争は行わないと誓った。でもそれと同じくらい、いや、もっと酷いかもしれない仕打ちを、近いうちに受けるんだ」
「どうしてそう言える? 条文にはそんなこと……」
「聞いたんだ、俺。帝国は、日本の無血開城に成功してしまったんだって。いずれは他所みたいに、植民地にされて、食い物にされる」
膝の上で作られた拳を思わず手に取っていた。血の気の引いた顔は青白く、不安げに顰められた眉は悲壮感すら漂う。
「憶測と推論ばかりじゃないか。何を怯えてるんだよ。そんな噂話、真に受ける必要ないさ」
「父さんも周りの大人も、ブリタニア人もみんな、嘘つきだ。こんな将来を平和と呼ぶならいっそ、戦争したほうが」
「スザク」
「……ごめん」
彼は唇を震わせて、再び俯いた。
この国のこと、世界のこと。今の自分にとって広くて大きくて、分からないことだらけだ。大人たちがあの会食でどんな話をしていたのか、聞き耳を立てても半分だって分からない。口先では平和、平和と声を揃える彼らが、腹の中ではどんな思いで高尚な演説を披露しているのか。毎年行われるサクラダイトの条約会議で、なぜどの国も"もう止めましょう"と言い出さないのか。
自分は、本当は分かっていたのかもしれない。莫大な資金をはたいて作られた兵器の威力が実は、日本国の領土を軽く吹き飛ばせるほどだったかもしれないこと。例えばサクラダイトのエネルギーを濃縮した爆発物、だとか。
そんな恐ろしい物を。みんなそれを知っていて、でも敢えて口にせず、その兵器を牽制として利用し帝国は優位に立ち回ろうとする。それは人道的、倫理的に間違っているだろう。恐怖によって民を治めるのは平和的な統治と言えない。
でも実際、現実的に俯瞰するとこの国は平和だ。他国からの攻撃を受けたところで水際で弾かれるし、ライフラインも食糧も安定して供給される。だがその安寧の足元には、例えば目の前の少年のような存在が居たかもしれない。知っていながら、それでも自分は知らぬ存ぜぬ振りをしていた。
だからといって今の日本が帝国の属国に、植民地化されるというのは話の飛躍が過ぎるだろう。敗戦したならまだしもだ。
日本の無血開城。そんな結末ともなれば世界中の世論が日本の味方をするだろうし、帝国への批判は想像し難いほどに強烈だ。いくら超大国として名を轟かせようと、世界から孤立すればこの国に生き残る術はない。横との繋がりを失った国家はゆっくりと崩壊する。
「……大丈夫だよ」
「ルルーシュ」
「そんな悲しいことにはならないさ。スザクのお父さんも仕事を頑張ってて、だから今回はうちに来てくれたんだろう。杞憂だよ」
「……」
「なあスザク、また来てくれないか。ブリタニア人はいけ好かなくても、僕のことはそう思わないんだろう」
「……うん」
「実は僕の妹や姉も、みんな優しくて良い人ばかりなんだ。紹介したい」
少年は重ねられた手に自らの手のひらを置いた。そして漸く俯いた顔を上げてくれた。見つめられた瞳の色に一瞬、どきりとする。
「分かった。ルルーシュの話を信じる」
「ああ」
解かれた手指はテーブルの上で鎮座する鶴に向かった。作りかけのまま置かれた白い紙は彼の手によって形を変え、やがて白い翼を羽ばたかせようとする一羽の鶴に様変わりした。白と黒で対になった折り鶴は向かい合って、テーブルの真ん中に据えられる。
「ルルーシュ。折り鶴って平和の象徴なんだって。知ってた?」
「ううん。初めて知った」
「今度来たときは妹……ナナリーにも教えてやるよ。ピアノも聞きに来るからさ」
折り目のついたチラシを手にしながら、彼は緩い笑みを浮かべていた。
時計を見ると食事会が終わる予定の間際になっていて、慌てて彼を連れて広間に戻った。まだ会は続いていたが、それぞれのテーブルには食後のコーヒーと思われる白いティーカップとソーサーが並べられていた。ともすれば間もなくお開きなのだろう。子供二人が抜け出していたことによる騒ぎのようなものも見受けられなかった。
彼は何事もなかったかのように自席へ戻っていった。別れる直前、一瞬だけ振り向いた少年は悪戯っぽい笑みを浮かべてありがとう、と唇を動かしていた。
「……ごめんナナリー、長い間席を外してしまって」
「お兄様。体調はもう悪くありませんか?」
「ああ、うん。大丈夫」
そういえばそんな口実で抜け出していたんだと、ふと思い出した。曖昧な笑みを見せながら妹の話に合わせる。
「兄上たちは心配してなかった?」
「はい、とくには」
「そうか。良かった」
「どこに行かれてたんですか? お部屋でお休みに?」
「友達が出来たから、ちょっと」
え、と目を瞬かせる彼女の口元に人差し指を当てた。
「あとで話すよ。ナナリーにも近いうち、紹介できるかもしれないから」
「それはとっても気になりますね」
二人で顔を見合わせ、声を潜めてくすくすと笑った。
遠い席の彼とも隣席だったら、この場でもっとたくさん話ができたかもしれない。そう思うと少し残念だが、そのぶんまた会える日が楽しみだった。
そうしてスザクらが帰国した直後、帝国と日本の情勢は急速に変化した。
帝国が地下資源採掘の権限を日本から一部譲り受けたことをきっかけに、帝国は日本の既得権益を徐々に我が物にしていったのだ。それは当初の友好条約になかったが、日を追うごとに権益収奪を認める条文が盛り込まれていった。
当然帝国は日本国、ひいては世界各国から批判の的となった。しかし帝国は世界各地に有する植民地に対し圧力をかけ、言論封鎖を行い、それ以外の弱小国家も含めて恐怖による支配で批判を”なかったこと”に仕立て上げたのだ。
今の帝国と戦争を起こして勝てる、あるいは引き分けに持ち越せる国家はないに等しかった。世界一のサクラダイト産出国として帝国にせしめられた以上、どの国もそう容易に手出しができない。今ここで日本を支援したところで勝算が持てる国家はそう存在しない。正義の為の戦争を起こせる体力などどこも持ち合わせていなかったし、帝国が秘密裏に開発していた核弾頭――通称フレイヤ爆弾開発成功の噂が現実味を帯びてきたと、軍需産業では話題になっている。
そうした要因を経て、友好条約締結のわずか一年後。
日本国は正式にブリタニア帝国の植民地として併合され、国名をエリア11に改めた。日本人らは帝国が掲げる植民地法に則り、被支配者として暮らすことを余儀なくされた。彼ら国民の基本的人権が尊重されることはなくなり、来日し移住してきたブリタニア人によって住処や財産、職を奪われていった。日本の政治機能は完全に失われ、スザクの父親は日本国最後の首相として歴史にその名を刻むこととなった。
帝国による徹底した人種差別、封建支配により、国内では通称解放軍と呼ばれる市民組織が徒党を組み、過激なテロ活動を引き起こす事例が相次いだ。日本人――今で言うところのイレヴン――は居住区域を限られるという措置に遭っていたが、その区域では治安が急激に悪化。ブリタニア人を狙った殺人事件も増加の一途を辿っていた。
圧政を敷いた当然の結果とも言えたが、帝国が打ち出したのは名誉ブリタニア人制度という新たな仕組みだ。イレヴンの中から希望者を募り、名誉ブリタニア人として国籍を変えれば一部の経済活動の制限が緩和される。いくつかの緩和策が盛り込まれたが、そのうちのひとつに帝国軍の兵士に所属する権利も含まれた。
言ってしまえば、イレヴンを兵力の頭数にしたいという魂胆が透けて見える愚策だ。つまりは自国民の兵士の数は守りつつ、同族同士で争わせるというのだ。この施策にもやはり非難が殺到したが、もはや帝国による治外法権となったエリア11では主義主張を持つことさえ許されなかった。すぐさま言論統制が行われ、公で意見する者は一人も居なくなった。
そしてその水面下では、職を失い明日の生活もままならないイレヴンたちがこぞって名誉人へと国籍を移し、帝国軍の兵士として身を置くことを希望した。決して安寧秩序が約束されるわけではないが、イレヴンであることに拘りを捨てれば現状よりマシな衣食住を確保できる。そうした貧困層の弱者らは名誉人を名乗ることを余儀なくされるのだ。
世界情勢は昔より今のほうがずっと、不安定で混沌を極めていた。連日報道される爆炎と灰色の景色はもう何度目になるか分からないほど目にしてきた。そのどれもが帝国軍の勝利だったり、植民地として統治されることを声高らかに宣言する。カメラに収まらないフレームの外側では一体どれだけの人が苦しみにあえぎ、慟哭に声を詰まらせているのか。
「……ルルーシュ様、ご準備は整いましたでしょうか」
「ああ」
扉のノックに対し短い返事を返すと、廊下に続く隔たりは開かれる。赤い敷布が張られた絨毯とペールトーンの壁紙は何年も経つのに色褪せず、物心ついたときの記憶と寸分変わらない光景だった。どこまでも続く長い廊下は気が遠くなるほど果てまで伸びている。
この広過ぎる宮廷の内部構造はすっかり頭に入ってある。幼いころはよく廊下の真ん中で迷っては、そこらを出入りする使いの者に道を尋ねていた。しかし十七年も我が家同然に使っていれば、その複雑な回路も手に取るように分かってくるのだ。
先を歩く兵士に続いてゆっくりと歩いた。窓を見ると呆れるくらいの快晴が広がっており、のんびり流れる白い雲は柔らかい日差しを隠したり覗かせたりしている。平和な景観だった。
「緊張はされていますか?」
「いいや、全く」
「左様ですか」
兵士が世間話を振ってくるので、適当に答えてやる。
「今のエリア11は帝国にとって政治的・軍事的に重要な拠点ですし、ある意味で因縁の国ですから。その若さで副総督に抜擢とは流石で御座います」
「……」
「皇帝陛下もきっと鼻が高いでしょうね」
「……」
それきり始終無言で、長い道を歩いた。
本当に長い道のりだった。七年間、それこそ血が滲む努力を続けた。知らないことも知りたいことも、知りたくないことも沢山あった。どれだけ力を手に入れようが、弱肉強食の世界で勝ち上がろうが、一番上の玉座に位置する男が居る限りどうにもならない現実が歯痒かった。
ここまで来るのに七年もかかってしまった。我武者羅に、周りも自分も顧みず突っ走ってきた。
しかしこの耐え難い七年は彼の境遇を思えば比較にも値しないのだ。比べるのも烏滸がましい。贅沢極まる衣食住と質の良い学習環境。どれもこれも身に余る恩恵だ。そしてこれらは決して自助努力による賜物ではないことも、肝に銘じ続けてきた。
十七歳を迎えたその日、自分は正式にエリア11の副総督に任命された。総督は皇位継承順位が己より上位にあたる姉のコーネリアだ。彼女の実妹であるユーフェミアが当初副総督に選ばれる予定であったが、それを遮って自ら希望した。
エリア11は帝国が有する植民地の中でも治安の悪化が激しく、割かれる軍事費や人員は膨大であった。歴代代表を務めた皇族らも手を焼くその土地の統治権を、有したいとする変わり者はブリタニア家の中ではそうそう現れなかった。
しかしこれは逆に言えば好機でもあった。自分の計画が予定通り進むための、最後のトリガーだった。
報道関係者がつめかけた会場は既に満員状態だ。これだけのカメラがあれば彼もどこかでこの様子を、中継を見てくれているかもしれない。そう思うと微塵もなかったはずの緊張感が俄に芽生え始める。
「……本日からこのエリア11の副総督として着任致します、ルルーシュ・ヴィ・ブリタニアと申します」
この国のどこかで健やかに、ささやかでも、幸せに暮らしていてほしい。この時の自分はそう願わずに居られなかった。