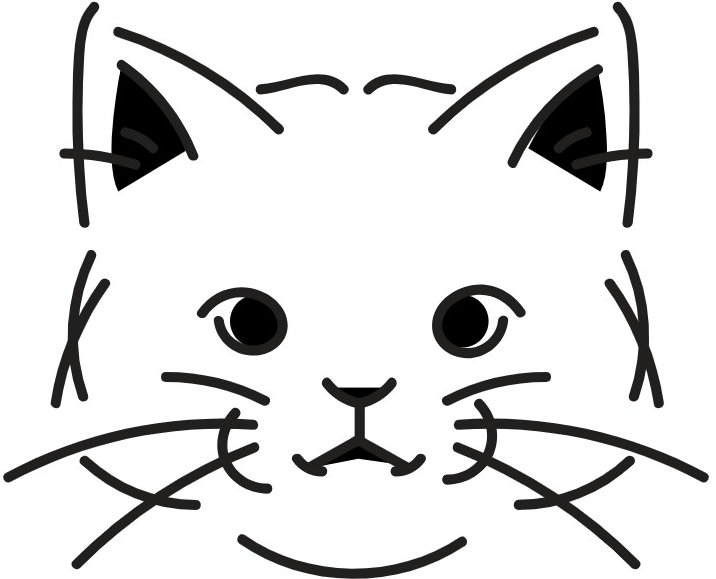
猫のいる暮らし 2
朝から宮中を騒がせた男は今、何をしているのかというと。執務室の椅子にちょこんと腰かけて、膝を抱え、じっと床の絨毯を見つめていた。
幾何学模様の絨毯には金糸が編み込まれている。これは中東オアシスの地域から輸入した職人の手工芸品で、皇帝陛下である紅玉が出張先で一目見て購入を決めた代物だという。最初は額縁に入れて壁掛けにしていたが、書類などの仕事道具が増えて収納場所が必要となり、泣く泣く壁掛けから床敷きに役割を変えられたのである。
が、そんな込み入った経緯を男は知る由もないだろう。
男の向かいの机には書類の束が置かれている。数刻前、彼はそこに少しだけ手をつけてはいたものの気が散ってしまったんだろう。今では退屈そうに体を縮こめている。
「おい黒猫。仕事をしないなら摘まみ出すぞ」
「つまんねえよ、こんな作業!」
黒猫は足元に転がしていた筆を蹴飛ばし、そう喚いた。
「ただの書き写しで何を言う。こんなもの猿でも出来るぞ」
「俺は猫だし」
「本気で追い出されたいか?」
筆には墨が残っていたので、白龍は慌てて拾い上げて文机に置き直した。もし絨毯に墨汁が付着してしまったらただじゃ済まない。これは買うて陛下のお気に入りの逸品である。
「黒猫さんを拾ってから、やけに部屋が賑やかになったわねぇ」
執務室の奥から聞こえた声音に、白龍は条件反射的に背筋を伸ばし、そして深々と頭を下げていた。
「も、申し訳御座いません陛下。公務の最中だというのに私語が多くなってしまい、」
「そうじゃなくってぇ。私は黒猫さんに興味があるのよぉ」
机から立ち上がった彼女はそう言うや否や、駆け足でこちらに歩み寄ってきた。
「ねぇ黒猫さん。貴方はどこからいらしたの?」
「覚えてねえ。知らない路地とか、店とか、空き地を転々としてて」
「じゃあ捨て猫ではなくて、最初から野良だったの?」
「さぁ……よく知らねぇけど、そういうことになるんじゃね」
「今までご飯はどうしてたのよぉ」
「知らねー人から貰ったり、店から盗んだりだな……てかさぁ」
言葉遣いが悪いことは今だけ目を瞑ろうか。彼には役職の概念など分かる筈もない。だが初対面の相手に対してその言葉遣いはあり得ないだろう。椅子に座る姿勢もだらしない。
対して彼女は彼の警戒心を少しでも解くためか、目線を合わせるようにして背を屈ませている。その気遣いは見ているだけで伝わってくる。だからこそ男の不遜な態度が頭にくるのだが。
「お前、すっげー化粧濃いな。ババァだからか?」
「な……な……」
「おい貴様、皇帝陛下になんと無礼なっ……!」
卒倒しそうになる陛下の肩を支えつつ、白龍は男の胸倉を掴んでいた。
今朝も感じたことだが、彼の体はやけに貧弱だ。少し腕で押すだけで体勢がよろけて、そのまま体がひっくり返るし、まともに受け身も取れない。
だからこの時も白龍が黒猫の胸倉を掴んだ瞬間。その体は大きくよろめき、椅子が転倒するけたたましい音が鳴り響いたのである。
「駄目よぉ白龍ちゃん。暴力に訴えるなんて」
「い、いや俺は、そこまでするつもりじゃ……」
野良猫はろくに飯にありつけていなかったと溢していた。飼い猫なら栄養のある餌を貰えるだろうが、外を彷徨う定住地のない彼ならそうもいかない。その日暮らしの飯にありつけたら御の字、といったところか。
「ってーな、離せよ」
「あ……」
黒猫は覚束ない様子でこちらの手を振り解いたあと、倒れてしまった椅子を元に戻した。ついでに乱れた衿を直し、こちらに向き直る。
「このつまんねー作業する以外で、ハクリュウと友達になる方法はない?」
「ない。あと、先ほどの無礼な発言を陛下に謝れ」
「えーっ。ホントのことを言っただけで……」
「いい加減にしろ!」
白龍は今度こそ胸倉を掴まないようにして、しかし凄んだ声で相手を怯ませた。
「お前の処遇は俺が決める。今すぐに出て行ってもらうことだって、俺は命じれる立場にある」
「そんなの友達じゃねーよ!」
黒猫は尚も自分の立場を理解していないようだ。だから語気を強めて、頭の悪い猫に説き伏せた。
「会ったばかりの奴と仲良くなるには段階を踏んで、好感度を上げるのが常套手段だ。いいか黒猫。今のお前は、俺から見ればただの邪魔者だ」
「じゃ、邪魔者……」
「少しでも俺に好かれたいなら、まずは陛下に謝罪しろ。それから任された仕事をしろ」
「……」
猫は後頭部を掻きながら、ほんの少しだけ背を丸めた。
「えと、さっきはスミマセンでした、ヘイカさん?」
「練紅玉陛下だ。名前くらい覚えろ」
「……ふふ。いいわよぉ白龍ちゃん。謝ってくれてありがとね、黒猫さん」
くすくすと可笑しそうに笑う紅玉の顔をまじまじと見つめた猫は、不思議そうな表情を浮かべていた。
「……怒ってねーの?」
「白龍ちゃんが私の代わりに怒ってくれたから平気よぉ。まあ、次に同じことを言ったらタダじゃ済まないけど」
「……」
「うふふ冗談よ。さぁ気持ちを切り替えて、公務に励むわよぉ」
明るい表情を作ってみせた彼女はそう声を張って、自身の机に戻っていった。
その後の黒猫の様子といえば。
一度厳しく叱りつけたのが功を奏したんだろう。依頼した書き写しの作業を集中して続けてくれた。猫背のまま片膝を抱えて座るような姿勢で、見てくれは大層悪かったが、それ以外は文句のつけようがない。私語を挟むことは一度もなく、手書きの文字は決して達筆とは言えないが丁寧で、本人の頑張りが透けて見える。
「なんだ、やれば出来るじゃないか」
「へ?」
「初めてなのによく頑張ったな」
「へ……」
白龍はやろうと思えば出来るのに努力しない奴、頑張らない奴にはとことん厳しく接する。が、やるべきことをきちんと遂行した者にはそれなりに褒めているつもりだった。皇帝陛下の職務を補佐する役職に就いてから、とくに意識するようになったことだ。それは肩書きを持たない部下や下働きの者に対しても平等に、褒められる部分は褒めるように心がけている。
「なんだ、その顔は」
机に散らばる紙はきっと墨を乾かす為なのだろう。絨毯は高価な物だと一度教えたら、彼は布を汚さぬよう仕事をするようになった。元から覚えが良いほうなのかもしれない。
白龍は何気なく猫に話しかけ、そしていつも部下にそうするのと同じように、猫の仕事ぶりを褒めてやった。たったそれだけだ。
だが猫の反応はというと。
「なっなんだよ急に!」
「何が?」
「さっきまであんだけ怒ってたくせに! 急にどうしちまったんだよ!」
顔を真っ赤にして吠えていた。
「お前が思ったより使える人間……いや猫だと気づいて、褒めてやったんだ」
「あ、あっそ!」
猫は顔を真っ赤にしたまま再び筆を握り直し、紙面に向かった。
しかし、その手元の動きは覚束ない。先ほどより文字が稚拙になっているし、筆圧の強弱も不安定だ。おまけに墨が服の裾に飛んで汚れてしまった。黒っぽい布地だから目立たないものの、彼からすれば借り物の衣服である。
「あ、あとで洗って返すから!」
「安物の服だ。別に気にしなくても」
「い、いい。ちゃんと洗う」
鍛錬の際に着ることもある。むしろ多少汚れても構わないつもりで貸してやったのだが、猫はどうしても譲れないようだ。
「だって寝床汚したら、お前血相変えてたし」
「布団は清潔にしておくものだ。それとこれとは話が」
違うから。
そう言いかけたところで、どこからか妙な音が鳴った。きゅう、と虫の鳴き声みたいな音だった。
「お、俺の腹から変な音が……」
「ああ、人間は腹が減ると音が鳴るんだ。仕方ない。昼餉にしよう」
「ひるげ……」
猫は口をきゅっと一文字に結び、喉を鳴らしていた。やはり食欲はきちんと備わっているらしい。ひるげ、の三文字で分かり易く目を輝かせたので、思わず笑ってしまいそうになった。
猫が相手なら牛乳や煮干しを与えていたところだが、人間なら訳が違う。本人の味の好みを調べる為にも、白龍はあらゆる味の料理――甘いものからしょっぱいもの、酸っぱいもの、薄いや濃いを取り揃え、黒猫の好き嫌いを判定しようと思った。
なんせ黒猫は人間の体を得て初めての食事である。何が口に合うか合わないか、どんな味がするのかも本人は想像がつかないだろう。野良猫時代にどんな餌を与えられていたかは知らないが、おおよそ人の口には入らないような物だと推察する。
だから白龍は得意の中華料理を中心に、普段作る料理より些か豪勢な昼食を振る舞ってみせた。
「これ、全部俺が食っていいのか?」
「よくよく考えてみればお前、今朝から何も食ってなかっただろ。腹が減ったと自覚してなかったか?」
厨房の隅に備え付けられた卓に黒猫を座らせて、料理の皿を並べてみた次第である。執務室の文机には到底収まりきらない品数だったので、わざわざ場所を借りたのだ。
「常に腹が減ってるから、あんま気にしたことなかったな」
「そうか。だからお前、そんなに痩せてるのか」
卓を挟んで黒猫の向かいに背もたれのない丸椅子を置き、そこへ腰かけた。向かい合った彼は目を瞬かせて、そうなのか? と不思議な面持ちをしてみせる。
「もっと食ったほうがいい。食事の仕方は分かるか?」
「見たことはあるけど……」
彼は銀色の匙を掴み、麻婆豆腐の表面を僅かに掬った。
「うっま! 何だよこれ!」
拳を握るようにして匙を掴み、白の丸皿ごと持ち上げて料理を頬張っている。見ていて気持ちがいいくらいの食べっぷりだ。
きっと箸の持ち方も知らないだろう。荒っぽい所作は少々目に余るが、それを教えるのは後回しだ。先に腹いっぱいまで飯を食わせないと、いずれ栄養不足で倒れてしまうかもしれない。
「慌てて食べると喉を詰まらせるぞ。しっかり噛んで食え」
「ん、おう」
頬を膨らませているが、麻婆豆腐はほぼ流し込んでいるようだ。そんなに急がなくたって料理はすぐに冷めやしない。
「香辛料を多めに使ったんだが、辛くはないか?」
「美味すぎてビビるぜ。ハクリュウも食えよ」
「いや、俺は味見したからいい」
注いできた茶を啜りながら答えると、黒猫は手を止めてこちらの顔を見つめた。
「味見? てことは、これハクリュウが作ったってこと?」
「まあ、そうだな」
黒猫はまんまるの目を大きく見開き、改めて卓上の品々に視線を配らせていた。色とりどりの食材が並び、豪勢な食事が振る舞われている。人間一日目の素人目から見ても、それが絶品であること、そして白龍の料理の腕前が一般人以上であることが察せられる。
「ハクリュウって凄いんだな。それとも人間ってみんなそうなのか?」
「誰しも得手不得手はある」
自分の得意分野がたまたま料理だっただけだ、ということを白龍は言いたかった。しかし黒猫は釈然としない面持ちで、ふうんと生返事だけを寄越した。
「なあ、この丸っこいやつは何?」
「それは餃子だ。タレをつけて食うんだ。ああ、匙じゃなくて箸を使え」
小皿にタレを移して手渡し、ついでに箸も握らせた。持ち方も教えてやる。
「突き刺すんじゃねーのか」
「違う違う。二本の箸で挟むんだ、こうやって」
「おお、上手いな」
さすがは人間初心者。目に入る情報全てが新鮮で仕方ないんだろう。箸の使い方を褒められるのは人生で初めてだった。
「箸は難しいな」
「まあ、毎日使ううちに覚えるだろう」
見よう見まねで餃子を掴み、口に入れた。通常の倍以上の時間はかかったが、彼はこれも美味い、と感想を漏らした。
「ニンニクやニラを使ってるんだが、これも平気か?」
「何が何の味か知らねーけど、皮の中身はうめぇよ」
尤もな感想が返ってきた。食材に関する知識もない相手に、込み入ったことを尋ねてしまった。
白龍は次に炒飯の皿を引き寄せて、これはどうだ、と勧めてみた。
炒飯にはふんだんに炒り卵を使用している。人間でも卵アレルギーがあったりするから、おそらく卵慣れしてないであろう黒猫の体に合うかどうかを試したかったのだ。
「うお、これもうめぇ!」
今度は匙で掬う食事だったので、彼は手早くそれを口にかきこんだ。大して咀嚼もせず喉に流し込もうとする悪癖があるので、ちゃんと噛めと口酸っぱく注意しておいた。
「体に異変はないか」
「うん? 俺はまだまだ食べれるぜ」
「そうか、ならいい」
的を射ない答えだったが本人は至って元気そうだ。
次は胡麻団子と杏仁豆腐、桃の切り身を引き寄せた。甘味は人によって苦手だったりする。それと果物も、中にはアレルギーであったり食わず嫌いが生じる可能性もある。
「うおっなんだこれ! 不思議な味がする!」
「それは甘味だ。甘いものは平気か?」
「おう! とくにこの、白くて丸っこいやつ、これが一番美味い」
彼は桃の切り身を箸で突き刺し、興奮した様子で唾を飛ばしていた。大層行儀が悪い。
「箸を使うな。これを使え」
「……木の棒?」
手渡した爪楊枝を顔に近づけて、尖った先端をじっと見つめている。なんだか危なっかしいので一旦彼の手から取り上げたのち、剥き身の白桃に突き刺しておいた。
「じゃあこれはどうだ」
次は生野菜だ。キャベツを千切りにしたもの、トマトを櫛切りにしたもの、きゅうりを乱切りにしたもの。それぞれを深皿に盛り付けて胡麻のドレッシングをかけた。
「うわっ、ナニコレ」
「野菜は苦手か」
「この緑は道に生えてる葉っぱか? 赤いのはまだイケるけど」
「雑草じゃない。キャベツという立派な野菜だ」
「俺、これ嫌い。ハクリュウにあげる」
ドレッシングのかかった部分を少しだけ口に入れたようだが、合わなかったらしい。まるで子供舌だ。味の濃いもの、甘いものは相当お気に召したようだが。
「なあ、桃ってやつもっと食いたい」
「今日の分は終わりだ。ほら、食べ終わったなら仕事に戻るぞ」
「えーっ今から!?」
ふわぁ、と大きな欠伸を漏らす男は動くことに難色を示していた。これだけ大量の炭水化物を一度に食えば、無理もないか。
しかし午睡を取れるほど時間はない。すぐ執務室に戻り、午後からの業務に戻らねばなるまい。その為にはまず、うとうとと寝落ちしかけている男を叩き起こし、動かさねばならないのだが。
「おい猫、ここで寝るな!」
「猫は飯食ったあとは寝るモンだぜ……」
「今は人間だろうが。その言い訳は通用しないぞ」
白龍はさっそく卓の皿を片づけて水洗いし、男を椅子から動かそうと躍起になった。頼むからここで寝るな、せめて寝室に行け、とも付け足した。
「寝室なら寝てもいいのか?」
「……飯を食わせ過ぎた俺も悪い」
腹いっぱいでもう動けない。こんなのは初めてだ。そう零す男の肩を揺すりながら、白龍は途方に暮れた。
今日だけは特別に午睡を許可することにした白龍は、寝ぼけまなこの男をどうにかして私室の長椅子まで案内してやった。寝具類は今朝しがた洗濯し、今も乾かしている最中なので、敢えて寝台は使わせなかった。
「うーん、腹いっぱい……」
「俺は仕事に戻る」
白龍が男を寝かせたあとそう告げた。しかし掴んでいた腕を離した途端、逆に握り返されてしまった。先ほどより幾分か力が籠っている。飯を食って体力が回復したせいだろうか。
「ハクリュウも一緒に昼寝しようぜ」
「俺はあいにくお前よりまともな人間だ。昼寝はしない」
「人間は昼寝しない動物なのか?」
「する奴もいるが、俺はしない」
「じゃあいいじゃん。ハクリュウも寝ようぜ」
ころりと寝返りを打った男は椅子の座面に隙間を作り、ここに寝転べよ、と指図してくる。
「俺はいい。一人で寝てろ」
「ケチ……」
掴まれていた力は、しかし貧弱だ。白龍はいとも簡単に黒猫の手を振り解いたあと、その場から立ち去ろうとした。
しかしその去り際である。一旦振り向いた白龍は、既に半分意識を飛ばしていた男に向かってとある忠告をした。
「今日は俺が戻るまでこの部屋で留守番してろよ。いいな」
「んー……」
返事なのか寝言なのか区別のつかない声を発した黒猫を後目に、白龍はようやくその場を後にした。
午後からは会議続きで、簡単な事務作業しか出来ない黒猫の出る幕はなかった。なんたって朝一番に行う筈の会議を寝坊ですっぽかしてしまい、それに加えて新たな議題――黒猫男の処遇についてどうするかという問題が発生してしまったからだ。
男の処遇については三者三様の意見が噴出した。身寄りもないようだから下働きとして雇えばいいという意見、宮中の関係者ではない以上追い出すしかないという意見、医学的に研究すべきだから解剖したらいいという意見。思惑は人それぞれだろうが、どの意見も理解は出来る。
本案件について取り纏めを行うのは白龍の役目だった。なんせ火種は白龍の部屋から発生した。もっと言えば事件の原因を呼び込んだのも白龍だった。悪い言い方をすれば、あの日の夜に黒猫を部屋に迎えなければこのような事態を招くことはなかったわけで。
すべての意見を総合した結果、白龍が導き出した答えはひとつだった。
「ということは暫くは殿下があの黒猫の面倒を見ると?」
「まあ、猫は俺に一番懐いてると見えるし……それに」
会議が終わったあと、白龍にいの一番に話しかけてきたのは夏黄文だった。彼は少し意外そうな面持ちでこう尋ねてきた。
「てっきり追い出すのかと思っておりました。今朝から息巻いておられましたし」
夏黄文も宮中から追い出すべきだと意見した者のひとりである。彼に食わす飯や着せる服だってタダじゃない。国民の血税から捻出されるのだ。宮殿は保育園でも、難民シェルターでもない。どうしても身寄りがなければ、そういう人を引き受けてくれる公的機関を斡旋してやれば済む話でもある。
「もしかしたら猫に戻る方法があるかもしれないと思ってな。奴は人間生活に向いてないと見た」
「ああ、成程。人間として生きるより猫として生きたほうが奴にとって幸せだろう、と」
「寝ている最中の夢で願ったら人間になったと聞く。なら同じように、再び猫に戻りたいと願ったら……」
あくまでこれは仮説だ。医学的根拠は一切ない。そもそも猫が人間に変身する、なんて眉唾話の原理さえ分からないのだが。
「あるいは、そういう魔法があるのやもしれませぬ」
「ああ。あいつの口からマギという言葉も出たしな。もしかすると本当に……」
憎たらしい、人を挑発するような笑みを浮かべる男が脳裏に蘇る。
彼がマギだという仮説は俄かに信じがたいが、でないと猫が人間に変身する現象に説明がつかない。(マギだから、という理由で片付く事象でもないだろうが。)
「一旦アラジン殿に相談してみては?」
「俺もそのつもりで今朝から連絡していたんだが、返事がなくてな」
遠隔で通信ができる電子機器の端末で何度も呼んでいるが、応答がない。仕事が忙しいんだろうか。
「それでは皇帝陛下の名で奴を呼んでみましょう。さすがに彼も無視できない筈」
「そ、そんな簡単に陛下の名をお借りしていいのか?」
黄夏文は皇帝陛下の側近だ。仕事の補佐だけでなくある程度の判断、権限、公務の代行を許されている身だが、その定義や線引きは曖昧だ。
「これは宮中だけの問題ではありませぬ。国防に拘わる一大事でありますよ」
「国防?」
「なんせ奴は身元不明の侵入者。どこの馬の骨とも知れぬ奴を国家の中枢に易々と招き入れてしまった。一国の恥であります。もし奴が他国の諜報員で、機密情報が漏れたり皇帝陛下の身に何かあれば」
「ま、まさか……」
黄夏文に捲し立てられた白龍は、そこまで言われてふと、とあることを思い出した。
「……そういやあいつを厨房に置き去りにしてしまった」
「その場に監視の者は」
「確か、誰も居なかった気がする……」
自身の失態を自覚した白龍は慌ててその場から駆け出していた。背後から己の名を呼ぶ声が聞こえたが、今は黒猫の居場所で頭がいっぱいだった。
自分が戻るまでは勝手に動くなと言いつけておいた。しかし当時の彼は半分眠っているような状態で、どこまで言うことを覚えているか分からない。それでなくても落ち着きがなく、従順とは正反対の反抗的な奴だった。少なくとも自分の言うことを素直に聞くようなタマじゃあない。
白龍は黄夏文が言う諜報員がどうとかという話を否定したいような心地で、厨房までの長い道のりを進んだ。
結論から言うと、黒猫は厨房から姿を消していた。
他の厨房当番の者に聞き込みを行うと、彼は平らげた皿を水場に運んで見よう見まねで自分で洗い、片付けたのち、どこかへ立ち去ったという。ただの厠だろうと周囲の者は思っていたが、それから暫く戻っていない。最後に姿を見たのは一刻ほど前だという証言も得た。
「最悪だ……」
この広い宮中で一人の人間、しかも行動パターンがさっぱり読めない相手を探すのは至難の業である。白龍は頭を抱えるしかなかった。
厠に行ってから迷子になっただけならまだいい。禁足地に侵入したり、機密情報を手にするようなことがあれば即お縄だ。それが故意であろうが何だろうが、罪であることに変わりはない。
いけないことだとは知りませんでした、が通用するなら警察は要らないのだ。知らないのであれば無知を自覚し覚えさせなければならない。もしそうなったら、きちんと猫の躾と監視を行わなかった白龍にも責任の一端はあると見做される。言い逃れはできまい。
厨房で彼の帰りを辛抱強く待つつもりだったが居ても立っても居られず、気がついたら廊下に出ていた。宛もなく周囲を歩き回っていると、曲がり角で誰かとぶつかりかけてしまった。
「白龍?」
「あ、姉上!」
彼女は両手に荷物を抱えて、どこか慌てた様子でこちらを見つめてきた。進行方向をあまり見ていなかったのは自分だけじゃなかったらしい。
「すみません、あまり前を見ておらず。姉上も如何なさいましたか。お忙しそうですが」
「あの人……黒猫の衣服と食事代を計算して予算に組み込めと陛下から言われてね。いますぐ修正しようと」
彼女の腕の中には書類や筆だけでなく算盤も混ざっていた。
「かたじけない。ご迷惑をおかけしてしまって」
「いえ、いいのよ。それよりあの人、落ち込んでたようだけど大丈夫?」
「落ち込む……?」
白瑛のその一言で、白龍は思わず彼女の肩を掴んでいた。
「どっどこかで見かけたのですか!?」
「え、ええ。ほら、白龍がさっき言っていた……」
白瑛は元来た道の向こう側を指さして、何かを思い出すような顔つきで答えた。
「黒猫を最初に発見したっていう中庭の傍よ。階段の近くで蹲って……って、白龍?」
白龍は白瑛の言葉を最後まで聞き終わるより先に走り出していた。彼女は驚いたような声を発したが、何かを察したらしい。転ばないように気をつけなさい、とだけ付け加えて、あっという間に小さくなる背中を見届けた。
そいつが居たのは白龍が最初に猫を見つけた場所とまったく同じだった。廊下から庭に降りる為に設置された三段ほどの小さな階段の影に、膝を抱えて蹲っていた。猫のときは階段の影に身を隠すことも出来ただろうが、図体の大きい人の姿だとそれも出来ない。
「あの時みたいに鳴いてくれたらすぐ見つけられたのに」
太陽の位置は気がついたら西に傾き始めており、美しい中庭は燃えるような赤に染まっている。どこからか香る金木犀の匂いで肺を満たしつつ、彼の背中に近づいた。
「……俺、ちゃんと留守番してたんだぜ?」
彼は抱えた膝に額を擦り付けて、弱々しい声で話をし始めた。白龍は彼と距離を少し空けて、階段の隅に腰掛けた。
夕日に当たってきらきらと光る池の水面を見つめた。その水面は天高く飛び立つ鴉の群れを映しており、西の空に向かって巣に帰る様子が切り取られていた。
「でもよお、この家ちょっと広すぎて……」
「道に迷った?」
「……」
白龍は肩の力を落とし、落胆と安堵が混ざった溜息を吐いた。
夏黄文は黒猫を全面的に疑っている。金品を盗みに来た不法侵入、あるいは国家機密を狙った諜報員。他の者たちもそうだ。出処が分からない、自分の出身や名前も言えないような奴の肩を持つ者はそう居ない。
白龍も彼をどこまで信用し、歩み寄り、力を貸せばいいか、正直計りかねている。懐いてくれていると実感はするが、それだけだ。まだ出会って一日の相手。これだけ面倒を見て、迷惑を被って、我慢しているだけでも褒められたいくらいには。
「今のお前は厄介者だよ」
「……」
「会議の話を外から盗み聞きしたのか?」
どうして彼がここまで気落ちしてるのか、理由は分からない。しかし可能性を上げるならひとつしかないだろう。
「別にわざとじゃねーんだ。道に迷って、誰かに聞こうとしたら、話し声が……」
「わざとじゃないのは分かった」
「ほ、ほんとだって!」
「ああ。俺は疑ってない」
彼は恐らく会議の途中までしか話を聞いていないのだろう。宮中に居る全員から邪魔者扱いされていると、思い込んでしまっている。
会議のさなかは彼を追い出したほうが良い、という意見が優勢だった。しかし取り纏めをするのは白龍の役目だった。最終的に白龍が出した答えは、大多数の意見とは異なる内容だった。
「これから俺は、お前を猫に戻す方法を探す。それまでは俺が責任を持ってお前の面倒を見ることにした」
「……えっ?」
「追い出されると思ったか」
顔を上げると彼とちょうど目が合った。驚きで見開かれる瞳はきらきらと輝いていて、まるで夕日に彩られる池の水面みたいだった。
「俺、人間のままでもいいよ」
「良くないだろ。どうやってこれから生きていくんだ。読み書きも出来ないのに」
「それは……」
白龍と友達になりたい、という一心で人間になることを望んだ。彼のささやかな望みは神様のいたずらか、いとも簡単に叶ってしまった。
念の為、今朝から部屋の隅々まで黒猫が居ないか探してはいた。あれは男の妄言で黒猫は部屋の何処かに居るのかもしれない、という可能性もある。しかしいくら捜索しても黒い小動物は見つからず、また宮中でも目撃情報は出てこなかった。
忽然と姿を消した黒猫と、人間に変身したという見知らぬ男の証言。不可思議な状況は奇妙なことに一致してしまった。だから現時点で男の証言を否定できる材料は存在せず、誰も彼もが狐に化かされた心地で彼の主張を信じる他なかった。
「俺を猫に戻すって、方法はあんのかよ」
「現時点では見つかってない。ただ……」
唇を尖らせる男は不満げに眉を顰めていた。
「そういう不思議な現象に詳しい奴なら居る」
「……詳しい奴?」
「そいつに聞けば何か分かるかもしれない」
赤々と輝く西の空に鴉の群れが連なって飛んでいる。横並びの彼らは大小様々で、おそらくは家族なんだろうと想像がついた。
「俺は今猫に戻っても野良に逆戻りだ。帰る場所も身寄りもない」
あの鴉たちとは正反対だな、と西の空を見上げながら呟いていた。紅蓮の瞳は夕日に照らされている。
「お前が猫に戻る保証ができたら、里親探しも同時に行おう。それで手を打ってみないか」
「そんな上手い話……」
「俺を誰だと思ってるんだ」
白龍はその場から立ち上がり、黒猫の丸い頭頂部を見下ろした。燃え上がる空を背負い、男に微笑みかける。
「俺は陛下の代理執政官を担っている。つまりこの国のナンバーツーだ」
「それってスゲーの?」
「勿論」
得心がいかないようで、彼は目を細めるばかりだ。
「里親が見つかるまでは俺がお前の世話係になってやろう」
「いいのか?」
「俺と友達になりたくて人間になったんだろ? なら責任の一端は俺にもある」
その責任を取る形で世話係に立候補した。ついでに里親探しも主導する。これで誰も文句はないだろう。いちおう、友達になるという願いも叶うかもしれない。
「てことは、俺たちは今から友達?」
「いいや、まだだ」
猫は立ち上がって白龍に握手を求めようとしたが、その手は宙ぶらりんのまま握り返されることはなかった。
「まずはやることが色々ある。部屋に戻ろう」
白龍が先に階段を上り、廊下に躍り出た。誰も居ない無人の回廊は静かにひっそりと、通行人を待つだけだ。そこへ白龍が先頭に立ち猫の顔を見た。
俺について来い、と視線だけで訴えると、どうやら通じたらしい。猫は大きく頷きながら前を行く男の背中について走った。その後ろ姿はまるで主人と飼い猫と瓜二つであった。