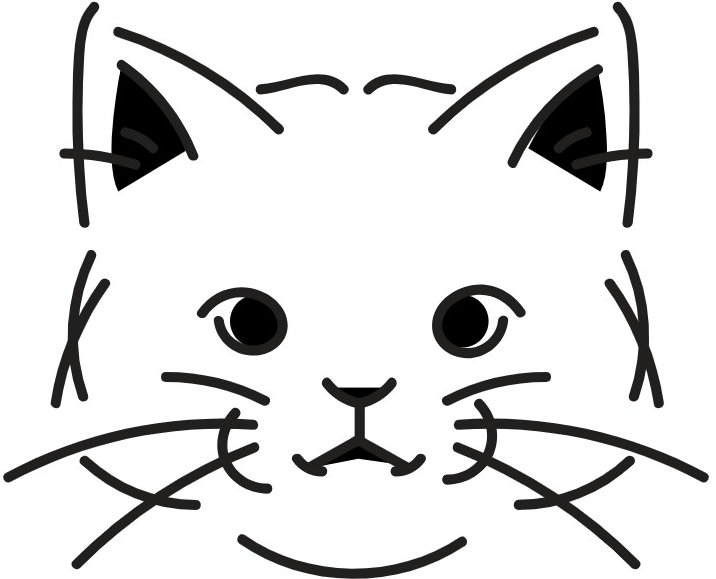
猫のいる暮らし 3
白龍は猫を私室に呼びつけた途端、あることを言い出した。
「お前、名前は?」
「ん?」
「だから、名前」
そう言いながら本棚のあるほうへ歩み寄り、一冊の書籍を手に取った。
「俺は飼われてなかったから名前なんかねーよ」
「そうか」
想定内の答えだった。彼は周囲にどんな呼ばれ方をされても、良いとも嫌とも言わなかった。つまり正解がない。名無しの権兵衛だ。ついでに言えば、彼が自身の名を名乗っている場面すら見たことがない。
「ならまずは名前を決めよう」
「えー」
「名前がないとどう呼べばいいか分からないだろう」
今は暫定的に黒猫、猫、野良と呼ばれている。が、固有名詞がないと後々不便になりそうだ。
「何でもいいな。名前なんか」
「名はその人の心と体を表すんだぞ。蔑ろに出来ない」
「へぇ……」
白龍がぱらぱらと頁を捲る本を、真似でもするみたいに猫も覗き込んだ。
「とはいえ猫の名づけなんて経験がない。何かアイデアがあればと思ったんだが」
「何の本?」
黒猫が尋ねると、白龍は書籍を持ち上げて表紙を見せた。そこにはアラビアンナイト、と表題が記されている。
「どういう本なんだ?」
「世界で最も有名な説話集だ。様々な国、境遇の人物が出てくる」
「へぇ」
聞いたはいいものの、猫は本自体にさして興味はなかったらしい。ただ、白龍が何をしているのか気になっただけだった。
「黒い毛に赤い瞳、太い眉……」
「何ブツブツ言ってんだ?」
「お前と容姿が似ている登場人物は居ないかと思って」
「そんな、絵本でもあるまいし」
「でも挿絵が入っている」
白龍は挿絵のある頁を中心に本を捲り始めた。男や女、若者や老人、赤子や死体など、様々な場面を切り取った絵が挿入されている。だがどの頁もぱっとしない。なんせ絵は白黒で、色がついていないからだ。
「容姿に関する記述はどこにもないな」
「じゃあどうすんだ?」
「うーん」
何か取っ掛かりになる要素はないものかと、白龍が再び初めから頁を捲り始めた、ちょうどその頃である。
白龍はあっと声を上げて、それからとある頁の挿絵を指さした。
「こいつの顔、お前に似てる」
「えー?」
白龍が指をさしたのは吊り上がった眉と瞳が特徴的な、痩せた男の顔だった。髪の毛はさして長くないが、毛先の一本一本まで丁寧に黒塗りにされている。
「こいつはジュダルという人物らしい」
「俺、こいつに似てんの?」
「なんだ、気に入らないか」
白龍は本を閉じて本棚に仕舞ったあと、傍にある長椅子に腰かけた。そして空いている場所を手のひらで叩き、お前もここに座れ、と視線で誘導した。
「お前は今日からジュダルだ。きちんと覚えておけ」
「変な名前」
「猫に人名をつけるほうが変だろう」
「俺は人間だっつーの!」
「でもいずれ猫に戻る」
それは確かにこの国の人らしい名前ではない。どちらかと言えば煌帝国から見てもっと西側にある砂漠地帯にありそうな名前だ。
だが違和感があるのは相手が人間だったら、という条件での話。これは猫につける名前の話だ。むしろ短くて呼びやすいほうが便利だろう。
「改めて宜しくな、ジュダル」
「ふん!」
彼はその名前を受け入れるのに難色を示していた。それから暫くジュダル、と呼びかけてみたが反応してもらえることはなかった。代わりに黒猫、と呼べば振り向いてくれる。人間扱いしてほしいと口にする傍ら、猫と呼ばれたらきちんと反応するのは一体どういう了見なのだろう。扱いが難しい男である。その気性はまるで猫そのものだと思った。
その後の夜。そのまま白龍の部屋で夕餉を取り、風呂に入りたがらない男に湯水を浴びせ、湯浴みの仕方を教えて、ようやく寝床に就こうとした。
寝台は一人用だ。二人でも寝そべることは出来るが、寝返りを打つとぶつかってしまう。第一、男同士で共寝なんて気色悪い。彼が人間でなく猫の姿であれば問題ないが、男同士で寝る趣味はない。それに無駄に大きい図体では隣に並ぶのも難しいと見た。しかも上背は白龍よりも僅かに勝っている始末だ。
「別にいいじゃん。一緒に寝ようぜ」
「断る。お前寝相悪そうだし、寝台は一日交代で使うことにしよう」
彼は白龍と一緒に寝たいとしつこくせがんだが、その要求はすべて断った。彼はまだ自分が人間だという自覚がないんだろうか。
「じゃあハクリュウはどこで寝んの?」
「ああ、そうだな……」
いずれは彼用にもう一台、寝台を用意したほうがいいかもしれない。いや、その頃になれば彼も人間の体の扱いに慣れて一人で生活出来るようになるだろうか。
今でこそ手取り足取り白龍が人間生活のイロハを教えてやってはいるが、子供じゃあるまいし、いつまでも世話を焼いてはいられない。白龍にも仕事と私生活のバランスやリズムがあって、今は仕方なく辛抱しているだけなのだ。この生活が一生続くとなったら、さすがの白龍も黒猫の世話係を辞退するつもりだ。
「今日は俺が長椅子を使うから、お前が寝台で寝たらいい」
「椅子って眠れんの?」
「人間初日で疲れただろう。お前に譲るよ」
掛け布団を捲って、ここで横になれと視線で示した。彼はいそいそと布団の間に体を滑りこませ、枕を後頭部に敷き、眠る体勢に入った。
「おやすみ、ジュダル」
「……あ、ハクリュウ」
掛けてやった布団から手を離そうとすると、今度は布団の下から黒猫の手が伸びてきた。何か気になることでも? と首を傾げると、彼は少し言いづらそうにしながら口を開いた。
「ハクリュウの名前はなんでハクリュウなんだ?」
不思議そうに瞬く赤の瞳は暗がりでも目映く光っていた。白龍は問われた意味について暫し逡巡したあと、正直に打ち明けた。
「父の名前が白徳だったから、俺の他に居る兄弟全員に『白』の一文字が入っている。あとの一文字は縁起のいい字をゲン担ぎで当て嵌めたんだろう。白雄、白蓮、白瑛などだな」
「ハクリュウのリュウは縁起がいいのか?」
「古くからこの国では伝説上の生き物として崇められている。昇り龍も縁起物として重宝されているな」
彼は白龍の着物の絵柄にちらりと視線を移した。
「だからハクリュウはハクリュウなのか」
「そんなに不思議なことか?」
彼はようやく腑に落ちた表情をして、こう答えた。
「人に特定の名前で呼ばれたことがなかったし、どうやって決めてるのか分からなくて」
「……」
「名前は心と体を表すのか……」
赤い瞳が柔らかく細められて、口角が緩く持ち上がる。
「お前にぴったりだ、白龍。良い名前を付けてもらったんだな」
「……有難う」
闇夜に溶けた彼の声音はどこまでも優しく、甘ったるかった。
白龍はその声が暫く頭から離れず、なかなか寝付けなかった。いつもなら仕事の疲れですぐに意識を手放しあっという間に朝が訪れるのだが、今日だけは夜が長く感じた。
そのせいなのか。白龍は夜明けまであと四半刻という時間になって、妙な夢をみた。
――白龍、なあ白龍。起きてくれよ。俺、なんか変なんだ。
体が妙に重かった。夢だから仕方ないんだろうが、四肢がうまく動かせない。まるで重たい水の中で身動きが取れないような感触である。
――どうしたらいいんだ、これ。なあ、どうしたら治るか教えてくれよ。
泣き縋る声を耳にした白龍は重たい目蓋をなんとか抉じ開けた。眼下に広がるのはつい昨日出会ったばかりの男の、泣き腫らした顔であった。
「これは、夢か?」
「夢なんかじゃねーよ! 寝ぼけたこと言ってねえで、コレどうにかしてくれよ!」
椅子に寝そべっていた白龍の真上、腹のあたりに、何故かジュダルが跨っていた。体にかけていた筈の毛布は剥ぎ取られており、床に落ちている。上手く身動きが取れなかったのは単に彼が乗っかっていて、その重さのせいだろう。
「なんだ、腹でも下したか」
「ちげえよ。同じシモでも、こっちのほう……」
彼は穿いていた寝間着の下衣を引っ張って、膨らみきった股座を押し付けてきた。
「おま……」
「そっそんな顔すんじゃねー! 俺だってなぁ、別に好きでこんなことしてるわけじゃ……」
尻すぼみになってゆく声と泣いた表情で何となく状況を察した白龍は上体を俄かに起こし、一応事情を聞いてみることにした。肘で支えつつ体を起こすと、ジュダルは目を見開いて白龍の肩を掴んだ。
「人間にも発情期があんのか!?」
「いや、とくには……ないと思う……」
「じゃあなんで急にこんなことになんだよ!」
人間は社会性のある生き物だ。決まった周期で発情するのではなく、その時の感情の昂ぶりや雰囲気、場面など、要は外的要因でそういう気分になることが多い。
だが偶に体の誤作動で、何てことない時にも体が勝手に臨戦態勢に入ることがある。これは本人の意思があるないに拘わらず起きる生理現象だ。人間の男とは不思議な生き物である。
「ご、誤作動……?」
「疲れが溜まったりするとスイッチが入る時がある。まあ仕方のないことだ」
「白龍もそうなるのか?」
「……」
敢えて答えないまま白龍は床に落ちた毛布を拾い、いい加減ジュダルを退かそうとした。いつまでも腹に跨られていては内臓が苦しいのである。あと、目の前に誤作動とはいえ発情している同性が存在するというのは、何というか居心地悪い。あまり心地いい気はしない。
「ど、どうしたら治るんだこれ。この時間に女探せってか?」
「……頭から冷水を浴びるか、擦って出せばいい」
「んだよそれ」
猫は納得いかない面持ちで首を傾げていた。
さすがは猫、必要最低限の生殖知識は持ち合わせているらしい。しかし相手はあくまで元野生動物。人間のそれとは少々価値観が異なるようで、そんなことよりつがいになる女を探すほうが、なんてことを言う始末だ。
「今のお前には女を宛がうより自分で処理したほうが最善だ」
「自分で処理?」
「少し待て。この部屋に人体の機能についての書物があった気がするから」
「なんで本読みなんだよ、白龍が教えてくれたほうが早いだろ!」
「な……」
真後ろから何やら喚き始めた男を置いといて、白龍は本棚の背表紙を睨みつけた。人体の機能、とくに生殖機能についてもきちんと記されている本が確かあった筈。日付を既に跨いでいた今の時間に書物倉庫へ忍び込む勇気はなかった。
「だいたい、なんで俺がそんなことまで教えないといけないんだ。勘弁してくれ」
「んだよ。別に減るモンでもねーだろ」
「俺の気持ちが追いつかない」
ようやく心当たりがある背表紙を見つけた白龍は、その本を手に取って目次を開いた。該当箇所の頁を見つけて早速捲ると、成程。男性の性機能、おもに性器の機能について事細かに記されてあった。
白龍ですらその本にそんなことが記されてあると知らなかったので少々面食らいつつ、頁を開いた状態で何も知らない男に手渡した。
「ほら、ここ読め」
「うーん、なんて読むんだ?」
「まさか字が読めないのか」
「難しい字は読めねー」
そういえばこいつは猫だった。どうやら店の看板の文字くらいなら判別はつくらしいが、さすがに読書の経験まではなかった。長い文章を読む経験など、無論ないに決まってる。
「文字が読めなくても図解がある。これなら分かるだろ」
「おお……」
男はその図を至近距離でまじまじと見つつ、成程、と呟いていた。
「手で握って擦るのか」
「ま、まあ」
「なんだ、簡単じゃねーかよ。なんで普通に説明してくれねえの」
「なんでってお前……」
同性の男、しかも自分とさして見た目の年齢は変わらなさそうな奴に、どうして自慰の仕方を言葉で説明せねばならないのだ。手で擦れば出る、と言えば易いが、きっと奴はそれだけでは理解しない。
「あれか、白龍はやったことないから分かんないのか!」
「な、なんでそうなる」
「じゃあやったことあんのか」
「いちいち煩いな、さっさと厠に行ってこい!」
彼の手から男性器の断面図が描かれている本を奪い取り、さっさと本棚に戻しておいた。彼は恥ずかしげも躊躇いもなくまじまじと見つめていた頁だが、白龍にとっては気まずさしかない。
「厠? これは小便じゃねーだろ」
「人前でするものじゃないんだ。いい加減分かれよ」
「白龍なら別にいいだろ」
「いや、良くない良くない」
男はあろうことかそんなことを呟いたのち、その場で下衣を寛げ始めたのだ。
「だって俺初めてで分かんねーもん。白龍はやったことあるんだろ? なら教えてくれよ」
「さっきの本を貸してやるから厠に行け」
「メンドくせーよ。外はさみいし、厠にまで行ったらまた道に迷うかもしれねえ」
ぶつぶつと文句を垂れる男は椅子に腰かけ、下半身を露出した状態で自身の性器を興味深そうに見つめていた。そして俄かに勃ち上がっていたそれにおそるおそる触れて、感触や温度などを確かめる動きをする。
人間の性器など初めて目にするんだろう。充血して膨らんだ状態はこうなるんだ、と驚いた様子はまさに無邪気な子供だ。だからこそ白龍は居た堪れない気分になってくる。
「じゃあ俺が席を外す」
「えっヤダ。駄目だって白龍。教えてくれよ。これ、どうしたらいいんだ?」
根元をきゅ、と握ったまま硬直する男は助けを乞うてきた。
まさか白龍が手本を見せるわけにもいかない。じゃあどうしろと言うのか。
「教えてくれよ白龍、おれ……」
ねこだからわかんないし。
舌足らずな響きが妙に熱を孕んでいた。白龍はぎょっとしつつ彼の顔を見た。
「これで合ってる……?」
「……あー……」
根元のあたりを小刻みに行き来する仕草を見遣って、思わず閉口していた。
あの調子ではいくら時間をかけても、出したくても出せない状態が続くだろう。同じ男としても想像するだけで居た堪れないし、なんだか可哀想だ。
「……一旦そこ座れ」
白龍が指さしたのは二人掛けの長椅子だ。彼は言われるがままに座って、きょとんとした面持ちで白龍の顔を見上げる。
「白龍?」
「あー……えっと、さっきの続き……」
そう声をかけると彼は右手を下半身に這わせて、ぎこちなく自慰の続きを始めた。釈然としない表情はそのままで、恥じらいなどは一切見当たらない。
白龍はそんな態度を見遣ってから咳払いしたのち、空いている隣に腰かけた。
「……?」
「いちいち俺の顔を見るな」
こちらを揶揄ってるわけじゃないらしいが、だからこそやりづらくて仕方ない。
白龍の気など微塵も知らない男が、無知を晒して色違いの瞳を見つめた。白龍は長い溜息を吐きつつ、どう説明すればよいものかと長考していた。