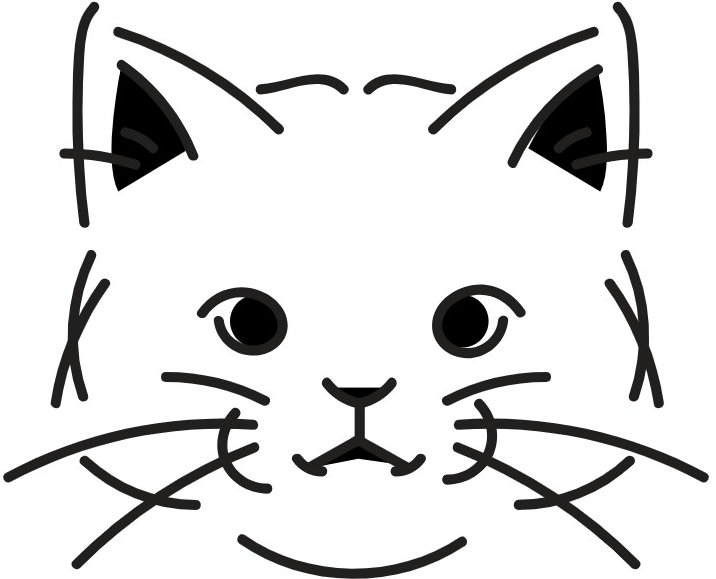
猫のいる暮らし 1
あれはとくに仕事が忙しい日だったように思う。
白龍は深夜までかかりっきりだった書類整理をようやく終え、執務室の戸締まりをしていた。窓掛け布の向こう側を覗くとまん丸の月が夜空にぼんやりと浮かび、その周囲を眩い星屑たちが囲っている。真下に視線を移すと静まり返った城下の景色が一望できた。
誰もが寝静まる時分だった。夜の帳はとうに下ろされ、人間も動物も穏やかな寝息を立てているような頃。驚くほどの静けさに満ちたこの国は昼間の喧騒とは程遠く、またこの空間にも自分一人しか残っていない。
先に仕事を終えた仲間たちの机を、白龍はじっくりと見分して回った。みな一様に早々と帰ってしまったが、果たして仕事の進み具合は如何ほどか。
「……陛下、これは……」
皇帝陛下の机上には、提出期限が先週までとなっている書類が残っていた。幸いにも国外向けの重要書類ではなく、文官たちからの請願書や稟議書の類であったものの。
「明日、早急に対処してもらおう」
書類を机の真ん中、一番見やすい位置に置き直して、朝一番に目を通してもらおうか。ついでに書類の管理方法についても今一度、考え直す必要がある。
他の者、たとえば白瑛や黄夏文の机は整理整頓が行き届いており、まるで手本のような美しさだった。やり残している仕事は一切見当たらない。二人の仕事術を皇帝陛下にも授けるべきだと、改めて思わせられる。
執務室の扉の鍵を閉じ、息を吐いた。自分の息遣いしか響かない廊下はちらほら明かりが点いているが、人影は見当たらない。今ここで誰かに遭遇するとしたら見回りの警備員くらいだろう。
白龍はやり残した仕事の文献や書類を小脇に抱えて、静かな回廊へ歩を進めた。
幼い頃は夜の宮殿が妙に不気味で、よく姉の腕にしがみついていたように思う。お化けが出ると泣きべそをかきながら散々迷惑と面倒をかけてしまった。今でこそ夜の宮中にさしたる恐怖心はないが、幼子なら怖がるのも無理はないかもしれない。
入り組んだ廊下の道はところどころ腐食が進んでいる。歩くたびミシミシと軋む音がするし、天井の飾り彫りには所々に蜘蛛の巣が見える。隣接する中庭や坪庭には鬱蒼と茂った草木が見え、夜は明かりが無いぶん少し不気味だ。
何より道が入り組んでいるせいで、先を見ても真っ暗なのだ。今晩は月が明るいから足元が見やすいが、曇天の夜はさらに視界が暗く、歩き回るのも困難になる。
夜間に巡回したり用のある者の為に、目印となる光源を壁に設置すべきだろうか。ついでに床板の張り替え、天井の念入りな掃除も近々要請したほうがいいかもしれない。
そんな考え事を巡らせていた折だ。
真っ暗な道の向こう側から、誰かの声がした。
「……?」
妖や幽霊の類は恐れるに足らない。白龍はもっと強靭で凶悪な敵と幾度も交戦し、時には命の危機に晒されながらも勝利してきた。だから居るか居ないかも分からない眉唾物の存在に、いちいち怯えるようなことはない、のだが。
「何の声だ……?」
思わず一瞬だけ足を止めていた。別に怖いわけじゃない。声のような音に耳を澄ます為だ。息を潜めて、その音の正体を探るのである。
「……人の声?」
それは赤子の泣き声にも似ていた。低く唸るような動物の声とは対照的な、甲高い声。しかし叫び声とも異なる。どちらかと言えば、悲しみや寂しさの滲むような声色だ。
「おい、そこに誰か居るのか!」
それとなく大声を上げながら早足で音源のほうに歩み寄ってみた。ここまできたら自分の目で確かめないと気が済まない。忍び寄っていた筈の疲労感や睡魔はとうに吹き飛び、今は目の前の事象が気になって仕方がないのだ。
「誰か居るなら返事をしろ!」
叫んでみるが返事はない。むしろ泣き声の音量が増して、頻度が多くなった。音源に近づいているから、だろうか。
いくつかの曲がり角を曲がったり引き返したり分かれ道で迷ったりしつつ、白龍は早足で歩を進めた。辿り着いたのは宮中で一番広い中庭に続く階段の傍だった。
月明りを頼りに周囲を見回してみるが人影は無かった。じゃあ何の声なのだろう。ここまで近くに来たのに、未だに声の正体が何なのか釈然としない。
ナーン、ナーン、という不思議な声だった。人ではないのかもしれない。一定の高さで何度も何度も鳴き続けている。ということは動物か何かだろうか。
「一体何の声なんだ」
中庭への階段を下りようとして、段差の位置を確認した時だ。
そこでふと目に留まった。白龍は足を止めて、その場にすぐさましゃがみ込んだ。
「……猫?」
階段の段差の影になっていて、真上に立っていたら到底見えない位置に居た。真っ黒の毛玉は三角形の大きな耳が生えていたので、何となく猫だと思ったのだ。
その予想は的中しており、胴体を持ち上げると紅蓮のアーモンドアイがこちらをじっと見つめてきた。いや、見つめるというより睨むと表現するほうが相応しいか。ずいぶんと目つきの悪い猫だと思った。
「どこから入ってきたんだ、お前」
もちろん人間の言葉で返事が寄越される筈がない。真っ黒の奴はナーン、と気だるげな鳴き声を寄越すのみだ。
先ほどから廊下の向こう側まで聞こえるほどの音量で鳴き続けていた犯人はこいつだったようだ。妖や幽霊の類でなくて良かった。白嶺宮に妙な怪談話が広まったら大変不名誉だろう。
「外に帰してやろう」
そう言いながら脇腹を抱えた時だ。黒猫は猛烈に暴れて、にゃうにゃうと唸り始めたのである。三角形の耳は外側にピンと尖り、細長い尻尾が大きく膨らむ。
「なんで怒るんだ。抱っこは苦手か」
猫の抱え方など知らないから適当に持ち上げたのが悪かったんだろうか。小脇に抱えていた書類の束を一旦廊下の端に置いて、猫を両腕の中に収めた。まるで赤子のようにすっぽり収まるそいつは目を丸くし、不思議そうな表情をしている。
「ほら、帰るぞ」
そして足を踏み出したときだ。猫は再び暴れ出し、胸元を蹴り上げて腕から飛び出そうとする。腕を引っ掻かれそうになったので思わず手を離すと、そいつは軽やかに飛び跳ねて床に着地してみせた。
さすがは猫だ。その身のこなしは賞賛に値するが、それ以外の挙動は褒められない。
「なんでだ。帰るのが嫌か」
しゃがんで猫と視線を合わせると、そいつは返事でもするみたいにナーン、と鳴いていた。
猫は気まぐれとも言う。たまたま今がそういう気分じゃないだけ、なのかもしれない。
「うちは動物を飼わない主義だ。馬は足になるから厩舎で飼育しているが、猫は生活の足しにならん」
「ナーン」
「今晩はもう時間も遅いから見逃してやるが、明日には追い出すぞ」
「ナーン」
じと、と胡乱な瞳が見上げてくる。なんともふてぶてしい、図々しい猫である。
というよりこいつは猫らしくない。あまり詳しくはないが、猫と言えばもっと愛らしくて主人に気ままに寄り添う愛玩動物ではなかったか。こいつはどちらかと言えば……
「人間の言うことなんか聞きたくないって顔だな」
「ナーン」
まるで人語を理解しているかのような風貌である。奇妙な猫だ。
日中は正門や裏門が開いているし、それ以外の壁面の隙間から動物の一匹や二匹、入り込むのはそう難しい話じゃない。むしろ今まで動物が入り込んだという話を聞いたことがなかったから意外なくらいだ。
「飯はやらん。外に出て、どこかで貰ってこい。いいな」
宮中で出される食事は国民の血税で賄われている。それをこんな薄汚い野良猫に分け与えるのは道理に反しているだろう。動物愛護の精神も行き過ぎるのは良くない。
しかし、野良猫というわりには毛並みはやたらと良いように見える。比較したことはないが、家猫とさして変わらない毛艶だ。毛づくろいが相当上手いか、誰かに世話をされているのかもしれない。
胴体は少し細いんだろうか。持ち上げた際に思いのほか軽かったのと、観察する限り腹周りは垂れていない。太りにくい種類か、食べ物にありつけず痩せ細っているんだろう。
だが可哀想だとは思わない。この世は良くも悪くも弱肉強食だ。困っている人に手を差し伸べるのは当然のことだが、野良猫にまで手を貸してやれるほどあいにくこちらは暇じゃない。
「道草を食ってしまった。そろそろ帰るとしよう」
白龍は廊下の端に寄せていた書類の束を再び抱えて、元来た道を歩き出した。
明日も早い時間から仕事が始まる。部屋に戻ってから書類の整理を少しだけ進めて、すぐに就寝しないといけない。
そういう段取りをしていた時に、ふと足元に違和感を覚えた。
「……お前な」
足元に纏わりつく影に気づかないほうがどうかしている。今晩は月が明るい夜だ。廊下に差し込む影の形、輪郭は明瞭で、だから四つ足の小動物が己の傍をうろちょろしているのはその姿を見なくとも分かった。
猫は影踏みでもするみたいに白龍の周囲をうろうろとついて回っていた。そして立ち止まった白龍の足元にすり寄って、再びナーン、と鳴き声を上げてみせた。
「いい加減にしろ。かわい子ぶるな」
白龍はその場に屈んで猫の首元を掴んだ。そして少し遠い場所に置いたのち、再び私室へ向けて歩き出した。
だが、すぐに分かってしまう。この廊下は老朽化が進み、歩くたびに木板が軋む音が鳴るのである。
それは猫の足とて同様らしい。ついでに爪が床を蹴る音も鳴るから、自分の斜め後ろに猫が居るんだと振り返るより先に分かってしまう。
だから白龍は振り向きざまに、猫に向かって叫んでいた。
「いい加減にしろ! 何度も言わせるな、俺は動物は飼わん!」
静寂に包まれていた夜の空気を揺さぶる白龍の声はその場に大きく響き渡った。その迫力にさすがの猫も怖気づいたのか、びくりと体を震わせていた。
「ふう。ようやく分かったようだな」
猫はどことなく気落ちした様子で俯きがちになった。立っていた耳は垂れ下がり、ふわふわと気ままに揺れていた尻尾はぺたりと力を無くしている。分かり易く落ち込んだ態度に白龍は少々面食らったが、咳払いをひとつだけした後は、既に歩を進めようとしていた。
白龍は一度も振り返らず私室を目指した。先ほどまでしつこいほど聞こえてきた妙な足音はもう聞こえなくなっていた。胸を撫で下ろし、明日の仕事の段取りについて歩きながら思案した。
私室に辿り着き、寝支度を終える頃には猫との遭遇という出来事すらすっかり忘れていた。時間にすれば四半刻にもならない、小さな小さな出来事だ。丸一日忙殺されっぱなしだった白龍にとっては些事である。
だから寝台に体を預けたのち、脇のあたりに擽ったい感触を覚えた瞬間。白龍はその場で素っ頓狂な声を上げた。
「きっ貴様……!」
その手触りは一度覚えたらすぐに思い出すであろう。ふわふわした柔らかい猫毛、美しい毛並み、真っ黒の艶やかな色合い。
何故か先ほど撒いたはずの黒猫が、白龍の寝床に滑り込んでいたのである。
「いつの間に……俺の後をついて歩いてきたのか!?」
「ナーン」
猫はその場でしゃがみ込んで、丸まり、尻尾を体に巻き付けて、いかにも寝る体制に入っていた。
「おいっ! 俺の寝台だ、お前の場所じゃない。あと出て行け、即刻!」
野良猫はどんな病原体や虫を持ち込んでくるか分からない。不衛生極まりない体で清潔な寝台を汚されたら非常に困るし、既にこの時点で白龍の寝る場所は汚染されたも同然だった。
白龍は猫を掴み上げて外に放り出そうとしたが、猫も猫で猛抵抗し出した。にゃうにゃうと唸り声を上げて、白龍の手に噛みついたり爪で引っ掻こうとしたのだ。
「噛むのだけは止めろ。どんな病気を移されるか分かったもんじゃない」
とにかく野生の動物は危険である。妙な感染症にでも罹ったら厄介だ。
そして白龍が噛むのは止めろ、と言った途端だ。猫は皮膚を突き破ろうとした歯を引っ込めて、代わりに噛もうとした部分を舐め始めたのである。
「そ、それは擽ったいから止めろ」
ざらざらした舌の表面が肌の表面を撫で上げて、痛いようなむず痒いような、妙な感覚を覚えた。しかし猫は相も変わらず言うことを聞かない。
「変な猫だな。俺の言葉が分かるのか? いや、まさかな」
生ぬるい舌の温度や掴んでいた胴体の温もりで、この猫も生きているのだと実感してしまう。真っ黒な毛で覆われた顔を覗き込むと、向こうも不思議そうな目をしてこちらを見つめ返してきた。大きな紅蓮の瞳が見開かれて、瞳孔が広がる。
「どうしても俺の寝台で寝たいのか?」
「ナーン」
「そうか。なら、それ相応の準備をしてもらわんと」
「ナーン……?」
猫は身じろぎもせず白龍の両手に収まっていた。この時までは、だ。
「お前は不潔だ。どこから来たかも分からん野生動物を寝室に招き入れたくない」
「ナーン……」
「だから、今から風呂に入れる」
白龍は一旦猫を床に置いてから、水差しの中身をすべて桶に移し替えた。朝の洗顔用に取っておいたのだが、こうなれば予定変更だ。就寝時間はますます後ろ倒しになるだろうが、頑固な猫が寝床を占領しようとするから仕方ない。
洗顔用の石鹸を泡立てて、濡れたままの手で猫の体を掴み上げた。猫は俄かに動揺していたが、今は言うことを聞いてもらうしかない。
泡だらけの桶に猫を放り込んで、体表面すべてに泡を塗りたくった。猫は驚いた様子で大暴れしたが羽交い締めにし、足先から尻尾、顔や耳の中まで綺麗に泡をつけた。
「こら、暴れるな。大人しく洗われてろ。言うことを聞かないと追い出すからな」
白龍がそう告げると、そいつは途端に大人しくなってされるがままとなった。
やはりこいつ、人の言葉を解してるんじゃないか。そんな疑念が白龍の中に生まれたが、直後、猫がするりと腕から逃げ出したのである。
「この馬鹿! まだ洗ってる途中なのに……!」
白龍はそう叫んだが、時すでに遅しだ。黒猫は真っ白の泡を全身に纏いながら軽やかに飛び跳ねて、寝台に潜り込んでしまったのである。これでは猫を洗ったところで寝台で寝ることは叶わないだろう。敷き布と掛け布団を全て取り替えて洗わねばなるまい。
「仕事を増やすなよ、まったく……」
すべてを諦めた白龍は怒る気力もなくなり、泡だらけの手で寝台に潜り込んだ猫を取り出した。もうこうなったらいくら汚れても同じだ。
猫を再び桶に放り込んで全身隅々を泡で洗ったあと、泡塗れの猫を一旦外に連れ出した。泡を洗い流す必要があるわけだが、部屋の中じゃ到底出来ないと判断したのだ。今度は床が水浸しになって、寝る場所がいよいよ無くなってしまう。
水場で桶に水を汲み、泡を漱いでやった。猫はぶるぶると体を震わせたあと全身の水を払う動きをしたが、泡はまだ残っている。再び水を掛けて、また体を震わせて。そういうやり取りを何度か繰り返したあと、白龍は水浸しの猫を担いで部屋に戻った。
床を水浸しにされるのは良くないから、部屋の出入り口付近に猫を置いたのだが。そいつは白龍の嫌がることを的確に、正確に判断しているらしい。嫌がらせかのように部屋中を駆け回った。
「こんの馬鹿猫! 俺の部屋を荒らすな!」
水浸しの体で再び寝台に潜り込んだのを見計らい、手拭いを両手に携えた白龍が猫を羽交い締めにした。
「ちゃんと体を拭いてからだ。あと寝台は汚れてるからもう入るな」
「ナーン」
猫は長いひげを震わせて、手拭いに顔を擦り付けた。まるで甘えるかのような仕草である。今までなかった愛らしい態度に白龍は暫し面食らったが、気にせず事務的に体を拭いてやった。
泡だらけの桶を外の水場で洗い流し、部屋に戻ってから床の濡れた部分を拭く。そして皺くちゃになった布団や敷き布は寝台の端に寄せて、明日の朝に纏めて洗濯することにする。
そうやって後片付けを終える頃には夜中の一時を回っていて、白龍は盛大な溜息を吐いた。
「お前のせいで俺は寝不足確定だ。どうしてくれる」
「ナーン」
白龍があくせく働いている間、猫はというと。白龍の言いつけどおり寝台には飛び乗らず、乾いた床の上でじっと座り込んで待っていた。何なら寝てくれたほうが楽なのだが、猫は白龍の動きに興味津々なようで、右往左往する白龍の動きに合わせて首を動かしていた。
そしてようやく後片付けもひと段落ついた頃だ。寝る場所に困った白龍は迫りくる睡魔、そして翌日の仕事の状況とを天秤にかけ、長椅子で横になって眠ることにした。
まず壁収納から冬用の分厚い毛布を取り出した。そして汚れていない枕を後頭部に敷き、椅子の座面に仰向けで寝そべった。風邪をひかぬよう毛布を体に被せて目を瞑る。寝返りは打てないが眠れないことはない。一晩の辛抱なら何てことはないと判断した。
なんせ少し前までの、戦争に明け暮れていた時代は野営は当たり前だったのだ。上着を掛布団代わりにして寝袋に寝そべり、深夜は見回りの為に交代で寝起きする。気候や天気にも左右されるがとても休んだ気はしない。
当時の野営に比べたら極楽だ。雨風を凌げる屋根があって、毛布があって、椅子の座面とは言えど柔らかい。目を瞑ると睡魔が瞼に覆い被さって、すぐに気が遠くなる。
「ん……」
体の上に重たい感触がした。そいつは体の上、おもに腹回りをうろうろと毛布の上から踏みつけたのち、ぽすんとしゃがみ込んだらしい。重さにすれば三キロ程度だろうか。
「図々しい奴だな……」
多少は身ぎれいになったから体に乗ることくらいは許してやろうか。
というより、今の白龍には猫に抗議する気力や体力は残っていなかった。なので猫の好きにさせることにしたのである。
別に気を許したわけじゃない。明日の朝には即刻部屋から追い出し、宮中の外へ逃がしてやるつもりだ。善良な市民の誰かに引き取られるほうがこの猫にとっても良いだろう。幸いなことにこいつは人懐っこく、憎たらしいが愛嬌はある。新しい家族に迎え入れられたらすぐに馴染めるだろう。
そういうことを思ったのち、意識を手放した。程よい重みは安眠の妨げどころか助けにもなり、白龍は朝までぐっすり熟睡できた。
そう、熟睡できたのだ。眠り過ぎてしまうくらいには。
目を覚ました理由は体にかかる謎の重みのせいだ。眠る直前、腹のあたりに猫に飛び乗られた。そのせいだろうか。
しかし猫にしては重すぎる気もする。あの成猫は痩せていて、せいぜい三キロと少し程度しかないと思われた。だが今白龍の体感している重みは三キロなんかじゃ通用しない、何倍もの圧力がかかっている。重すぎて内臓が苦しいくらいだ。
おそるおそる目を開けた。まずは格子状の見知った天井。
それから、知らない全裸の男が居た。
「だっ誰だこの変態!」
「うおっ起きた! 起きたぞこいつ!」
そいつは楽しそうにそう叫んで、にこにこと笑顔を振りまいている。何が面白いんだろうか。
赤い瞳を縁取る真っ黒の睫毛、それから色白の肌に痩せ細った四肢と、漆黒の長毛。鮮やかすぎるコントラストがやけに目につく。それにこの色の取り合わせはどこかで見た覚えがある。
「何? そんなに俺が変?」
「……変、どころの騒ぎではない」
男は無邪気に微笑んでいた。頭が動くたびに揺れる毛先が手足を擽る。その黒髪は腰よりもっと長いと思われた。
上体だけを起こすと、今置かれている状況がよく見渡せた。白龍の腹のあたりに男が跨った状態で馬乗りになっていたのである。悪夢のような光景だ。これは夢の続きで、自分はまだ眠っているんだろうか。そう信じたいほどに酷い景色だった。
「出て行け痴れ者! おい誰か、誰か居ないのか!」
「そんな大声出さなくても聞こえてるぜ?」
「貴様と話したいんじゃない! さっさとそこを退け変態!」
肩を掴んで床に下ろそうとしたら、そいつは呆気なく体勢が傾き、床に尻餅をついていた。いってぇ、何すんだよ! という叫び声は一旦無視し、すぐさま部屋の出口を目指す。廊下を巡回する家臣を呼び止めて、この変態を突き出してやらねば。これ以上同じ空間に居たら何をされるか分からないからだ。
そして白龍が部屋の扉を開け放った、その瞬間である。
「殿下! どうなさったんですか、こんなお時間ですよ!」
「夏黄文?」
今度は部屋に飛び込む勢いで、廊下のすぐ傍にいた夏黄文が叫んでいた。しかも叫んでいるのは彼だけじゃない。その隣には顰め面をした白瑛と、困ったような、心配しているような表情を浮かべる文官たちが勢ぞろいしていた。
一体これは何の騒ぎだ。もしやあの男、深夜に何か宮中でやらかしたのか?
そう思って白龍は真後ろを振り返り、部屋を見回した。
同時に、たまたま目に入ってしまったのだ。始業時間を大幅に超えた時刻を示す時計に。九時から会議が始まる予定だったが、現在は十時前だった。
「先ほどから何度も呼び掛けていたのですが返事がなく……強硬手段で今から部屋に突入しようかと相談していたところでありました」
「な……」
「貴方がこんな遅くまで寝坊するなんて、何かあったの?」
反応は三者三様だ。心配する者、苛立っている者、呆れている者。その全員が白龍からの言葉を待っている。
「皆の者、すまない。俺が粗相を働いたせいで」
「謝るのは一旦後回しよ。それより身支度を、それと今後の段取りについて考えて頂戴」
「今朝の会議の議題は殿下がご提案されるということで、殿下抜きでは進行できないのであります」
皆はすっかり消沈した白龍を必要以上に責め立てる気にもならないのだろう。それに普段の勤務態度は非の付け所がない。一度や二度の失態くらい、人間なら誰でも犯すものだ。その場に集った文官たちは溜飲を下げ、納得した面持ちで頷いてみせた。
「会議は午後から行わせてくれ。今は一旦、通常の公務に励むとしよう」
「白龍はその前に顔を洗ってきて、寝癖も直してね」
「はい、あね……白瑛殿下」
白龍が皆の厚意に感謝と謝罪の意を込めて、深々と一礼した。
直後、真後ろから聞き馴染みのない声が鼓膜を劈いた。
「へー、お前の名前ハクリュウっていうんだ」
その声の主は今朝しがた、白龍の胴体に跨っていた謎の人物であった。
そいつは部屋の出口で立ち塞がる白龍の背後から現れ、廊下に並ぶ面々に興味津々で視線を注いでいた。
「な、何奴……」
「一体どちら様なの」
「というかこの男、素っ裸だぞ」
「おい、白龍殿下の部屋から妙な男が」
「白龍殿下の部屋から?」
「お知り合いなのかしら」
「いや、名前も知らないようだったが……」
勿論彼らにも面識はない。どう見ても不審者なのだが、白龍の部屋から出てきたということもあって迂闊に不審者呼ばわりも出来ない、という微妙な状況である。
「おい出てくるな変質者! 事態がややこしくなるだろ!」
「白龍殿下が大寝坊したのってまさか」
「ちょっと、止めてくださいよ。ご本人の目の前で」
「じゃあなんで素っ裸の男が何食わぬ顔で出てくるんだ」
彼らの憶測はご尤もだ。白龍だって彼らと同じ状況なら、同じ予想をしてしまうに違いない。だからこそ白龍は声を大にし、この場に生じている疑惑を否定せねばならなかった。
「ちっ違う! 俺だってこんな奴知らない! 朝起きたら急に現れてて……きっと不法侵入だ!」
「急にい? 昨日は一緒に寝たじゃねーか」
「寝てない! 俺が弁明してるのに邪魔するな! というか先に服を着ろ!」
周囲は呆気に取られて謎の男と白龍の舌戦を見守っている。いや、巻き込まれたくないので黙っている、と言おうか。
「あったけー寝床だけじゃなく風呂にも入れさせてくれてさ。至れり尽くせりだったじゃん」
「……風呂?」
白龍は目が点になった。
なんせ昨晩の記憶では、風呂に入れさせてやったのは野良の黒猫だったからだ。こんな大男の入浴介助など、してやった覚えがない。
「俺が世話したのは黒猫だ。お前みたいな男は」
「だから、それが俺だって!」
「ん……?」
何を言ってるんだこいつは。それは白龍だけじゃなく周囲の者共も同じ気持ちを無言で共有しており、同じような視線を男に向けた。
「寝床を泡だらけにして、床を水浸しにしちまったろ? それが俺。ハクリュウが世話してくれたじゃねーか」
「だから俺が世話したのは黒猫で……」
「もしや猫が化けていたのでは?」
鶴の一声、もとい夏黄文の一声が響くと、白龍の周りには困惑したようなざわめきが起きた。
「猫が人間に化けていた? まさか怪談話でもあるまいし」
「しかしそのような伝承は極東平原に古くから残っております。あながちあり得ぬ話でも……」
化け猫が己の前に現れ、翌朝人間になっていただと?
そんなバカげた話をすんなり信じるほど白龍は子供じゃない。しかし目の前には化学や物理法則では説明しようがない現象が起きている。これを怪奇と呼ばずになんと説明できようか。
納得がいかない面持ちのまま、白龍は己を黒猫だと名乗る謎の男に改めて向き直った。
「お前、本当に化け猫なのか」
「化け猫? 何のことか分かんねーけど、俺はただお前と友達になりたくて」
「……友達」
一同はその単語を耳にするや否や押し黙った。なんだか場の流れが急速にあちらに有利に働いている気がする。
「そ。小汚い野良の俺を一晩面倒みてくれた人間と、一度話をしてみたくてさ。猫の俺は考え事しながらハクリュウの腹の上で眠ったワケ」
「……」
「そしたら夢に、こう、白っぽいデカい巨人が現れて……」
男は両手を広げて、これくらい、と表現してみせた。
「マギたるお前の願いを叶えてやろうって言われて」
「マギ……?」
「そんで、なんか不思議な力でデッカい人間になれたんだぜ!」
さっぱり意味が分からない。不思議な夢をみた、という顛末なのは理解できる。だがそこから先、人間になれたという理屈は意味不明だ。
「そいつの名前は、確かウーゴ……だっけな……」
「で、そなたは夢をみて人間の体を手に入れたと?」
「そ!」
夏黄文の訝し気な問いかけに、男は意気揚々と相槌を打った。朗らかな声は場にそぐわない明るいもので、周囲はますます彼に疑いの目を向けた。
どうやらこいつは本当に不法侵入をしでかして、頭のおかしい振りをしているんじゃないか。今回はたまたま無傷だったが、白龍は下手をすれば寝首を?かれていたかもしれない。そんな危険と隣り合わせの状況で、猫に化けていました、というイカれた弁解をされても信じられる筈がないのだ。
「本当だって、信じてくれよ! ハクリュウ、お前は信じてくれるよなぁ」
「は……?」
赤い目が潤む様子を目の当たりにしつつ、白龍は返答を言い淀んだ。
「昨晩遅くに俺が庭の階段の影で動けなくなってるのを、ハクリュウが助けてくれたろ?」
「動けなくなっていた?」
「あの晩は寒くて、腹も減って、力が出なかったんだよ。だから俺は親切にしてくれた人間についていこうとした。まあ、怒られちまったけど」
「……」
「でもそのあとはこっそりついてって、部屋に入り込んだんだ。暗闇だと体を隠せる黒猫で良かったぜ」
「……」
ここまで話していて、白龍は違和感を如実に覚えていた。
こいつ、本当にあの黒猫なんじゃないか? でないと昨晩の出来事をここまで詳細に、正確に話せる筈がない。
「お前まさか、本当に」
「もっと話してやろうか? 昨晩の出来事を順番に」
壁に凭れかかる男はどこか強気な口調で言い放った。それもその筈だろう。彼が本当にあの黒猫だとしたら、自身の主張を通すためにどんな話でも繰り広げられる。
「白龍殿下。奴の話は本当なのでありますか?」
「ああ……確かに俺は遅い時間まで黒猫の世話をしていた」
「そういえば深夜、誰かが水場で洗濯をしていたわね」
白瑛が思い出したように口を開いた。
「あれは洗濯ではなく猫を洗っていました。野良は不潔ですからね」
「不潔って言うなよ。もう綺麗だし!」
男は自身の胸を叩き、自信満々に述べてみせた。
「猫ならしょうがないのかもしれませんが、お召し物はきちんとしなさい。公衆の場で、恥ずかしいですよ」
白瑛が自身の羽織っていた上着を男に手渡そうとするので、慌てて白龍が遮った。
「姉上、お気遣い有難う御座います。ですがさすがに女性のお召し物を、こいつが身に着けるのは」
相手は全裸の青年男性である。
「俺の衣服を渡すようにします。……おい黒猫、部屋に戻れ。その恥ずかしい格好をどうにかするぞ」
白龍は男の長い髪を掴み、部屋の扉を一旦閉じて室内の奥へと引きずった。
「何すんだよ、いてーだろ!」
「猫なら運べたが人間は無理だ」
「あーそっか。今の俺ってデカいもんなぁ」
男は自身の体をまじまじと見つめたあと、妙に納得のいった面持ちを浮かべている。自分が人間であるという事実にまだ慣れていない、のかもしれない。変な話ではあるが。
とはいえだ。身元不明の不審者にまさか一張羅を貸し出すわけにもいかない。金目の物を貸し与えたらそれを持ち逃げして質屋に売り飛ばされるかもしれないからだ。白龍は黒猫の存在自体を未だ信用していないのである。勿論彼の眉唾物の証言にもだ。
「何この変な服」
だから貸したのは黒い薄手の羽織り物と下穿き、それから草履だけだ。これなら売り飛ばしても大した金額にはならない。
だが白龍の思惑を他所に、黒猫はぶうぶうと文句を垂れた。
「外に居てた奴らはもっとヒラヒラしてただろ」
「お前にそんな上等な物は不要だ」
「せっかく人間になれたんだしお洒落くらいさせてくれよ」
「なら働いて、稼いで、自分で買え」
人間の体を手に入れた彼に待ち受けるのは国民、一個人としての義務や責任ばかりだ。何も祈ってまで人間にならなくても、自由気ままな猫としての余生を送るほうがある意味有意義だろう。野良は苦労が多そうだが家猫なら将来安泰である。
「メンドくせーよ、俺はお前と友達になりたいだけなのに」
「自分のことを自分で出来ない奴とは友達になりたくない」
「な、なら……」
黒猫は白龍に縋るような眼差しで、こう述べたのである。
「俺、どうやったらハクリュウと友達になれる?」
そんなもの、他人に答えを聞いているようじゃ上手くはいかないだろう。
少なくともこいつは人の体を得て一日も経っていない。他人の情緒を解する能を持たないだろうし、説明しても無駄骨を折るだけだ。だとしたら自分から言える答えはひとつ。
「お前みたいな訳の分からない奴と友達になんかなりたくない」
「な……」
「分かったならとっとと仕事を見つけて働いてこい。自分の飯の種も準備できないくせに人間を名乗るな」
「ハクリュウの鬼! 人でなし! 薄情者!」
少なくともお前よりはまともな人間なつもりだ、と言い返そうとしたが、黙っておいた。
白龍は敢えて何も言わず、泣きべそをかき続ける男をただただ遠目に見つめるだけだった。