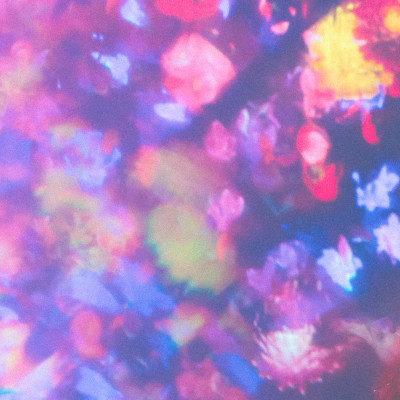
これをよすがとする 一話
視界が揺れるほどの拍手と歓声、色鮮やかな眺望と、集う人々の明るい表情。肩が触れて思わず振り向くと、隣のそいつも自分と同じ顔をしてこちらを見つめていた。その間わずか一秒にも満たなかった。満たなかったが、喜色の滲んだ緑はしっかりと脳裏に刻まれていた。カメラのシャッターが切られたように鮮明に、色彩豊かに、褪せない景色として記憶の引き出しの奥に仕舞われる。恐らく一生忘れることができないだろう。それくらい自分にとっては鮮烈で印象深い情景だった。
騎士の叙任式は国を挙げて盛大に行われる行事のひとつだ。宮中の人間は当然として、軍部からも大勢が招集され、関係各所から人が集まる。大袈裟な報道も後押しして、国中はちょっとしたお祝いムードに包まれるのだ。二人の固い決意の証明と契が交わされる瞬間を、周囲は当事者らより祝ってくれる。
ブリタニア家皇族の特権のひとつして、副総督以上の任を与えられた者は軍部からひとり、騎士を任命できる権利が付与される。騎士は命を賭してでも主人を護る義務があるし、主人も騎士に全幅の信頼を預ける必要がある。持ちつ持たれつの関係で成り立つ専任騎士制度は、ゆえに拝される者にとって栄誉あることだった。
永遠の忠誠を誓い、その身が滅びようと主人に尽くすことを約束する。その文言は呆れるほど仰々しく非現実的で、不確定要素も孕んでいる。
実際ひとは、ひとりで死ぬことのほうが多い。たくさんの人に囲まれ、見守られながら安らかに逝くというのは基本、寿命を全うした老人にしか訪れない最期だ。最後まで添い遂げてくれるのはせいぜい呼吸器か点滴のチューブか、看護師や医者くらいだろう。
読み上げられる条文、騎士侯としての心構えを記したそれらは全く持って非合理的だ。時代にそぐわないし、現代の価値観や死生観から剥離している。騎士の行動規範とやらは毎年刷新されるわけでもなく、この国が興った時代から代々受け継ぎ、語り継がれてきた。古めかしい文章や口語から察するに、それが書かれた頃というのは数百年ほど遡るだろうか。
とかく自分が思うのは、この古ぼけた伝承のような堅苦しい経典を一言一句、この男が真に受けてしまうのではないか、という懸念だ。高尚でご立派なのは構わないが、命を懸けてまで守れと自分の口からはとても言えない。言いたくない。相手にも生きてほしいからだ。信頼はするし背中も預けるが、死ぬな。これだけの信頼を置く人間に死なれては困ると、騎士には今日という日を迎えるまで何度も説いてきた。
「まさに騎士になろうとする者に、真理を守るべし、公教会、孤児と寡婦、祈りかつ働く人々すべてを守護すべし」
彼は佩刀していた剣を両の手で、壇上に立つ自分に手渡した。磨き上げられた刀身は銀色に鈍く光り、紅色の緞帳を鮮やかに映す。
「彼が、教会、寡婦、孤児、あるいは異教徒の暴虐に逆らい神に奉仕するすべての者の保護者かつ守護者となるように」
足元で跪く男は俯いたまま、唱えられる文言を黙って聞いていた。
受け取った長剣の平で、男の肩を三度打つ。いわゆる刀礼の儀は主君が騎士として認めるために必要なのだという。
古くから存在するらしいこの儀式は、もともとは単なる通過儀礼でしかなかったようだ。しかし皇歴1200年代にもなるとフランスでは様式が確立、洗練されてゆき、1400年代にドイツへ伝わった際は”首打ち”が採用された。そうして時代を超えた現在。道徳的、宗教的な形式が整備されるにつれ儀式はより厳かに、盛大に催されるようになった。
「汝、民を守る盾となり、君主の敵を討つ矛となれ」
「……」
差し向けられた剣の刃先に、彼は恭しく口付けを落とす。鈍色の刃に艶やかな肌の光が灯る。
「汝を我が騎士に任命する」
剣は再び彼の手に渡され、腰帯に備えられた鞘に収まる。絨毯につけていた膝を崩し男が立ち上がると、一斉に拍手が巻き起こった。すらりと伸びた背に緊張の糸が走るのがよく見えた。おもむろに肩を叩いて顔色を窺うと存外、彼は晴れやかな面持ちであった。
四方八方から炊かれるフラッシュライトが目に眩しい。歓声と拍手はなかなか鳴り止まないし、そこかしこではすでに乾杯を済ませた来賓者らが祝宴を始めていた。
重々しく堅苦しい儀式の時間はもう終わりだ。あとは心ゆくまで食べて飲んで、音楽に合わせて騒ぐだけだ。堰を切ったように喧騒に包まれる広間は、人々の話し声で飽和しきっていた。
「……命を捧げよとは言わないんだね」
「俺に一人で野垂れ死ねと?」
「後任が見つかるまでは頑張ってよ」
「そんなの、思いつきもしない」
呆れるように言葉を零すと、男は可笑しそうにくすりと笑った。周囲に聞こえない声量で、二人はこっそりと耳打ちしあった。
全身全霊で主人を護れ。でもお前は死ぬな。それは相反するようでいて、実は両立できる願いではないかと考えていた。とくに彼のような、死に急ぐような人間にはとくに効き目があるのでは、と。
お前が居ないと俺はどうすればいい。そう訴えるように見つめると、彼は困ったように眉を下げた。
「ちょっと憧れたんだけどな」
「言葉の鎖で繋がれることに?」
「嫌な言い方」
彼は歯を見せて笑った。
「……ルルーシュなら鎖でも呪いでも、喜んで受け入れるんだけどな。そういう覚悟だった」
「勘違いするな。これはスザクから俺に対する誓いだ。それを俺は受け入れた。叙任式というのは、そういう意味の儀式だ」
「うん」
「俺の矛であると同時に、自分の命を省みることも忘れるな」
「誓うよ」
儚げな色を湛えた緑は瞬いて、ゆっくり頷いた。空虚な響きはすぐに喧騒にかき消されてしまって、もう思い出すこともできない。どこか憂いを帯びた切ない表情だけが、その時の彼の心情に触れる唯一の手がかりであった。